相続した不動産売却時にかかる税金は?節税になる特例の解説や計算例も!

本記事では、相続した不動産売却時にかかる税金の種類や税金を抑える特例について解説します。また、実際にいくらかかるのかシミュレーションもおこなうため、ご自身の場合に当てはめて計算してみてください。
記事の目次
相続した不動産売却時にかかる税金

相続した不動産を売却する際にかかる税金には、大きく4種類あります。どういうタイミングで何のために払うのか、それぞれ見ていきましょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権や抵当権などの権利を登記する際にかかる税金です。被相続人(遺産を残して亡くなった方)の名義では不動産を売却できないため、被相続人から相続人に所有権を移す必要があります。その際にかかる登録免許税は次の式で求められます。
不動産価格×0.4%
また、相続した不動産を売却した際には、買主に所有権が移るため、再度登録免許税がかかります。しかし、この時は買主が負担するのが一般的です。
なお住宅ローンが完済できていれば、抵当権を抹消して売却することになります。抵当権抹消にあたっての登録免許税は、1つの不動産につき1,000円となっています。土地と住宅の抵当権を抹消する際にはそれぞれ1,000円ずつかかり、合わせて2,000円となることを理解しておきましょう。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書など決済の取引で交わされる書類に貼付する税金です。相続した不動産を売却する際には、売買契約書に貼付が必要となります。印紙税は契約金額によって異なり、具体的な金額は下表のとおりです。
| 不動産売買契約書 | 本来の印紙税 | 軽減後の印紙税 (2024年3月31日までに作成されるもの) |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
例えば、相続した不動産を3,500万円で売却した場合には、1万円(本来なら2万円)となります。2024年(令和6)年3月31日までに作成されるものには軽減措置が適用されます。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産の売却によって得た利益に対して課税される税金です。次の計算式で譲渡所得は求められます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
収入金額とは、相続した不動産の売却価格です。取得費とは、その不動産を取得するのにかかった費用のことです。例えば、不動産の購入代金や取得時の仲介手数料、登録免許税などです。相続した不動産の場合、書類が残っておらず、いくらかわからない場合もあるでしょう。その際は収入金額の5%を取得費として計算します。
譲渡費用とは、相続した不動産を売却した際にかかった費用のことです。例えば、売却時の仲介手数料や印紙税、建物の取り壊し費用などが該当します。
上記の式で求めた譲渡所得に対して、不動産の所有期間に応じた税率をかけます。所有期間が5年以下であれば30%、5年超であれば15%です。
住民税
相続した不動産を売却した際には、譲渡所得に応じて住民税も課税されます。こちらも所有期間に応じて税率が異なっており、5年以下であれば9%、5年超であれば5%です。
また、住民税だけでなく、復興特別所得税も加算されます。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために設けられたもので、2037(令和19)年12月31日までの間に生ずる所得について徴収されます。所有期間に応じて税率が異なり、5年以下であれば0.63%、5年超であれば0.315%です。
相続した不動産売却時の税金を抑える特例
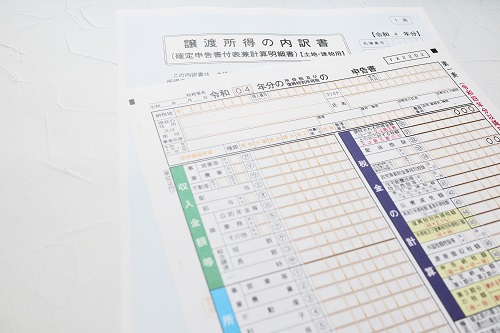
相続した不動産を売却する際に利用できる、税金を抑えるための特例があります。節税につながるため、どういったものがあるかよく確認しておきましょう。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
自己居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるものです。しかし、「自己居住用財産」とあるように、自分が住んでいる必要があります。そのため、亡くなった両親と一緒に住んでいた場合などが適用となります。他にも要件があるため、確認しておきましょう。
特例の適用を受けるための要件
- 自分が住んでいる住宅を売る、もしくは住宅とともに土地や借地権を売ること
なお、住んでいた住宅や土地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること - 売却した年の前年および前々年にこの特例や「マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」を受けていないこと
- 売却した年、前年、前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと
- 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと
特別控除を適用し、譲渡所得が0円となった場合でも確定申告は必要となります。忘れず申請するようにしましょう。
参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例
相続で取得した住宅や土地を売却した際に、要件にあてはまる場合は譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。この特例の適用を受ける際には、次の要件を満たしている必要があります。
特例の適用を受けるための要件
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続開始があった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売ること
- 売却価格が1億円以下であること
区分所有建物とは、独立した2つ以上の部屋があり、それぞれの部屋が所有権の対象になっている建物を指します。具体的には分譲マンションが該当します。
また、2024(令和6)年1月1日に売却をおこない、相続人の人数が3人以上である場合の控除額は2,000万円までとなります。
参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
取得費加算の特例
相続した際に相続税を払った方もいるでしょう。「また税金を払うのか」と思われるかもしれませんが、その際に利用できるのが、取得費加算の特例です。相続によって取得した土地や建物の財産を一定期間内に売却した場合に、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できます。適用を受けるための要件は次のとおりです。
特例の適用を受けるための要件
- 相続により財産を取得した者であること
- 財産を取得した人に相続税が課税されていること
- 財産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること
なお、相続税の申告期限は、相続の開始があった翌日から10カ月となります。取得費に加算できるため、譲渡所得が減り、結果として譲渡所得税も抑えられます。
参考:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
相続した不動産売却時の税金シミュレーション

どういった税金があるのかを見てきましたが、気になるのは実際にいくらかかるのかという部分でしょう。本章では、具体例を挙げながらシミュレーションしてみます。
<条件>
固定資産税評価額 土地:2,000万円 建物:3,000万円
売却価格 土地:4,000万円 建物:2,000万円
取得費用 土地:1,000万円 建物:3,000万円
取得時の経費 300万円
譲渡費用 500万円
所有期間 20年
建物の構造:木造
登録免許税
まず、相続した際にかかる登録免許税を計算しましょう。土地と建物それぞれで計算し、合計します。今回の場合、次の計算式となります。
土地 2,000万円×0.4%=8万円
建物 3,000万円×0.4%=12万円
登録免許税の合計 8万円+12万円=20万円
先述したように、現在、相続した土地の登録免許税は免税されていますが、ここでは課税されたと仮定します。
印紙税
次に、不動産の売買契約時にかかる印紙税を計算しましょう。今回は売却価格が6,000万円のため、6万円となります。(軽減措置適用時は3万円です)
譲渡所得税
譲渡所得を計算しましょう。建物は年数が経つと価値が下がるため、その分を引く必要があります。この引く分を減価償却費といい、取得費から引かなければなりません。計算式は次のとおりです。
取得費×90%×償却率×経過年数
償却率は、建物が何でできているかによって異なります。木造の場合は0.031となります。償却率の詳細は「国税庁のホームページ」でご確認ください。条件を当てはめて計算してみると次のようになります。
建物の減価償却費
3,000万円×90%×0.031×20年=1,674万円
建物の取得費
3,000万円ー1,674万円=1,326万円
取得費の総額
1,000万円+1,326万円+300万円+20万円=2,646万円
譲渡所得
6,000万円ー(2,646万円+500万円)=2,854万円
譲渡所得税
2,854万円×20.315%=579万7,000円
登録免許税、譲渡所得税、印紙税の合計
20万円+579万7,000円+6万円=605万7,000円
この条件で相続した不動産を売却する際は、605万7,000円の税金がかかることになります。
登録免許税は相続登記の際に納めていますが、取得費に加算できるため、忘れないようにしましょう。
譲渡所得を申告する際の注意点

相続した不動産の売却時には税金がかかりますが、特例を利用すると抑えられる可能性があることを解説してきました。本章では、譲渡所得を申告する際の注意点を解説します。
併用できない特例制度がある
相続した不動産を売却する場合、併用できるものと併用できないものがあります。また、控除できる上限額が決まっているものもあります。例えば、先ほど紹介した「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「取得費加算の特例」は併用できません。
また「自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は併用が可能です。しかし、同一年内に使用する場合は、合わせて3,000万円が最大控除額となります。合わせて6,000万円控除できるわけではないため、注意しましょう。
どうすれば控除額を最大にできるか、よくシミュレーションしましょう。
所有期間は被相続人が取得した期間から考える
譲渡所得税を計算する際、所有期間によって税率が大きく異なります。この所有期間は、相続時からではなく、被相続人が取得した日から計算することを覚えておきましょう。そのため、相続して間がなくても、被相続人が所有していた期間が5年超であれば、長期譲渡所得として計算します。
相続した不動産売却時の税金に関するよくある質問
相続した不動産を売却した際にかかる税金に関して、よくある質問をまとめてみました。
相続した不動産の売却は3年以内がいい?
今回解説した「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」「取得費加算の特例」で、どちらも3年という数字が出てきます。これらの適用を受けたいのであれば、3年以内に売却するのがいいでしょう。
例えば、先ほどシミュレーションした条件で、「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」を適用した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できるため、譲渡所得は0円となり、節税できた金額は579万7,000円となります。条件によっても異なりますが、控除できる金額が大きいことは間違いありません。
相続した不動産売却時にかかった税金はいつ納める?
登録免許税は相続した際に、印紙税は売買契約時にかかります。相続した不動産を売却した場合の譲渡所得税は、売却した年の翌年2月16日〜3月15日までに納める必要があります。譲渡所得税は所得税の一種であり、その年の所得に対して課税されるため、確定申告で申告します。譲渡所得税の納付期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが科せられます。
相続した不動産を売却したら確定申告が必要?
相続した不動産を売却し、利益が発生したら確定申告が必要となります。また、譲渡所得が発生しない場合でも、特例の適用を受けるのであれば申告が必要です。忘れずに申告するようにしましょう。
まとめ
今回は、相続した不動産売却時にかかる税金について解説しました。譲渡所得税は高額になる可能性もありますが、特例が適用できれば大きく税金を抑えられます。どういう特例があるか、要件は何かを確認しておきましょう。また、不明点がある場合には税理士や税務署の職員などに問い合わせましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





