20代の貯金はいくらあれば安心?備えたいライフイベントと相場もご紹介!

そこで今回は、20代の収入や貯金事情をはじめ、なるべく貯めておきたい金額の目安などについて解説していきます。
記事の目次
20代の平均年収は?

はじめに、20代における収入額の相場から簡単に見ていきましょう。厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査の概況(PDF)」によれば、20代の平均年収は、次のようになっています。
| 男女計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 20歳~24歳 | 224.6万円 | 229.3万円 | 219.6万円 |
| 25歳~29歳 | 258.3万円 | 267.8万円 | 245.8万円 |
上記では20代の前半と後半に分かれたデータとなっていますが、双方をあわせて計算した平均値は、241.45万円。つまり、20代の平均年収は240万円前後です。
20代の平均貯金額は75万円

金融広報中央委員会「(参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯]令和5年調査結果」では、20代の預金額平均は75万円(20代を世帯主とする場合)。これは実際に金融機関などで貯めている金額で、株式や保険などの資産は含みません。
収入やライフスタイル、生活環境などは人によって異なるので、無理しない程度に貯金ができるように意識してみましょう。
20代の貯金はいくらあれば安心?
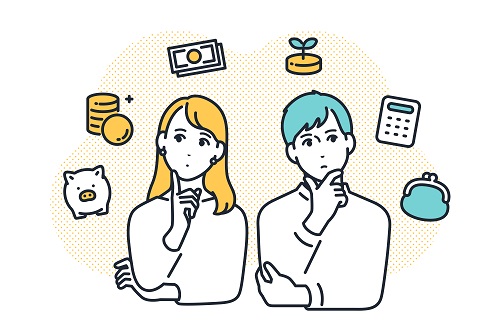
では実際に、どの程度の貯金があれば安心なのか、具体的な金額を見てみましょう。必要な生活費のシミュレーションも交えながら、どれくらいの貯金額が基準となるのか、詳しく解説していきます。
貯金額の目安は生活費半年~1年分
事故や病気といった、想定外の事態や突発的なトラブルなどが起きる可能性を考えた場合。急な出費や収入の減少などに対応するためには、実際にかかる生活費の半年から1年分くらいの貯金があると、万が一の備えになるとされています。では具体的に、20代で必要な毎月の生活費は、どの程度になるのでしょうか。
総務省統計局の「令和5年 家計調査 家計収支編」によれば、若年層の単身世帯(34歳以下)における、毎月の平均出費額は次のようになっています。
| 項目 | 毎月の平均出費額 |
|---|---|
| 住居費(家賃など) | 3万6,954円 |
| 食費 | 3万8,666円 |
| 水道光熱費 | 1万119円 |
| 日用品全般 | 4,482円 |
| 被服費 | 6,561円 |
| 医療費 | 5,019円 |
| 交通費 | 7,729円 |
| 自動車関係費 | 8,252円 |
| 通信費 | 5,421円 |
| 娯楽費(趣味代など) | 2万2,342円 |
| 交際費 | 1万83円 |
| その他(嗜好品・美容代) | 1万3,920円 |
| 合計 | 16万9,548円 |
上記の諸経費を合計すると、1カ月ごとの生活費は16万9,548円。大体の目安としては、毎月約17万円の生活費がかかる計算になります。
ここから算出してみると、20代の貯金額の理想としては、次のとおりです。
- 約17万円(毎月の生活費)×6カ月 ~ 12カ月 = 102万円 ~ 204万円
あくまで参考にはなりますが、大まかには100万円~200万円前後の貯金があると、何かあった場合にも安心できるでしょう。
20代の毎月の貯金額の目安は?

ここまでに見てきたように、ある程度の蓄えをつくっておくためには、毎月の収入をコツコツと貯めていくのが基本です。ちなみに毎月の貯金額としては、月収の1割~2割とするのが一般的。先ほども出てきた20代の平均年収から換算してみると、次のようなイメージになります。
約240万円(20代の平均年収)÷ 12カ月 = 約20万円(平均月収)
約20万円(平均月収)× 0.1 ~ 0.2 =2万円 ~4万円
平均的に考えて、毎月少なくとも2万円~4万円ほどは貯金できるのがベストです。例えば25歳から貯金をスタートしたとして、仮に毎月3万円を貯めていく場合、30歳までには以下の金額になることが想定できます。
3万円(毎月の貯金額)× 12カ月 = 36万円(年間貯金額)
36万円(年間貯金額)×5年(25歳から30歳)= 180万円
もちろん個々の収入額によって、毎月貯金に回せる金額は変わってきます。とはいえ月収の1割~2割ずつ貯めるだけでも、年々まとまった貯金額になるでしょう。あくまで目安ではありますが、毎月の目標貯金額を決める際などには、参考にしてみてください。
20代から無理なく貯金するコツは?

いざ貯金をはじめてみようと思っても、実際には何から手をつけたらいいのか、悩んでしまうこともあるかもしれません。では20代から着実に貯金していくための方法として、知っておきたいコツをご紹介していきます。
貯金用の口座を開設する
「毎月の給与から余った分だけ貯めていこう」と考えていると、結局のところ毎月の収入を使い切ってしまい、なかなか余剰が出ないケースも少なくありません。確実にお金を貯めるには、あらかじめ貯金額は別にしておき、その差し引いた分でやりくりするのがおすすめです。こうした先取り貯金にあると便利なのが貯金専用の銀行口座で、開設するだけなら手数料などもかかりません。また銀行に預けておけば、多少なりとも預金金利がプラスになります。自分のなかで、使える生活費の制限を設けるためにも、貯金用の口座をつくっておくとよいでしょう。
家計簿をつける
家計簿をつけて、毎月の収支を記録していくことで、何にどれくらいの費用がかかっているのか明確にできます。例えば「毎月この部分で費用がかさんでいる」などの状況がわかれば、使い方を見直して節約するのも可能。もし目標の貯金ができなかった月があったら、家計簿をチェックして原因を見つけることもできるでしょう。自分自身で家計の流れを把握しておくことで、生活費をしっかりと管理して貯金額を増やせる効果が見込めます。
資産運用をはじめる
資産運用とは、使わずに貯めてあるお金を投資に回して、収益を出して貯蓄を増やしていくものです。20代の若いうちからはじめることで、その分長期的な運用につながり、より大きな資産を生み出しやすいメリットがあります。もし金銭的に余裕があって、いくらか投資に回してもまとまった貯金額が残せそうな場合には、効率的にお金を増やせる資産運用も検討してみましょう。
財形貯蓄をはじめる
財形貯蓄とは、勤務先からの給与やボーナスの天引きにより、自動的に貯金を積み立てる社内制度です。もし会社の福利厚生で財形貯蓄があれば、貯金に向けて活用する方法も考えられます。財形貯蓄なら、給与やボーナスが支払われる時点ですでに貯金分が差し引かれているため、毎月必ず一定額のお金を貯めることが可能。ちなみに貯金額の払い出しについては、財形貯蓄の種類や会社の規定などによって異なるので、まずは一度勤務先に相談してみましょう。
銀行の自動積み立てを活用する
各銀行では、預金口座から自動的に決まった金額を引き落として、お金の積み立てをできるサービスをおこなっています。毎月必ず、貯金したい分は定期預金として振替がされるので、特別な手間もなく確実にお金を貯めることが可能。自分で管理するのが苦手な方は、銀行の自動積み立てサービスを使ってみるのもおすすめです。
20代で備えたいライフイベントと相場は?
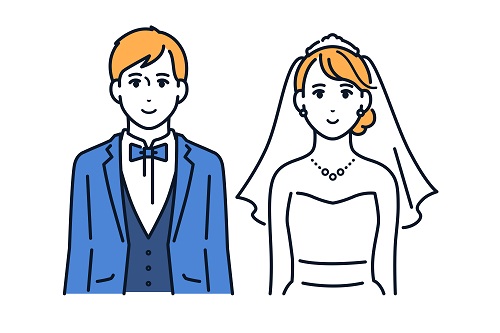
さまざまなライフイベントを迎える際には、大きな出費をともなうことが多くあります。もちろん個人差はありますが、20代のうちに、何かしらのライフイベントに向けた費用が必要となる可能性も。貯金を考える際には、次のような費用も考慮しながら、自分自身としてどれくらいお金を貯めるべきなのか検討してみましょう。
結婚費用
カップルの考え方によっても異なりますが、結婚は人生の一大イベントでもあり、さまざまな費用が発生するのが一般的です。また自分自身の結婚だけでなく、親族・職場の同僚・友人などが結婚する場合には、ご祝儀を用意するケースも想定されます。では実際に、結婚にともなってどのような費用が必要なのか、具体的なイメージを見ていきましょう。不動産情報サイト アットホームが実施した独自のアンケート調査では、次のようなデータが出ています。
| 結婚時に必要なおもな費用 | 金額 |
|---|---|
| 結婚指輪 | 約36万円 |
| 結婚式 | 約214万円 |
| 新婚旅行 | 約60万円 |
| 新生活の準備費(必要な家具・家電など) | 約78万円 |
| 合計 | 約388万円 |
<アンケート調査> 結婚にかかった費用について教えてください(調査時期/2022年12月/回答サンプル数:542)
合計すると、全体で約388万円かかる計算になります。なかには結婚式や新婚旅行などは省くパターンも見られますが、もし一通りのイベントをするのであれば、上記のような費用が必要になる点は頭に入れておきましょう。
ちなみに一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)がおこなった「祝儀(結婚祝い)等に関するアンケート調査(令和5年度)」では、ご祝儀の平均額として、以下のような結果となっています。
| 結婚祝いの相手 | ご祝儀額 |
|---|---|
| 兄弟、姉妹 | 約6万円 |
| 従兄弟、従姉妹 | 約3万5,000円 |
| 甥、姪 | 約8万円 |
| 職場の同僚 | 約3万2,000円 |
| 職場の部下(自身が上司) | 約3万8,000円 |
| 職場の上司(自身が部下) | 約3万5,000円 |
| 友人 | 約3万円 |
新郎新婦との関係性にもよりますが、一部の親族を除けば、ご祝儀の相場としては3万円前後になるのが一般的です。
出産費用
20代で子どもを産んで育てるためには、まずは出産に向けた費用を想定しておく必要があります。ちなみに厚生労働省の「出産費用の見える化等について(PDF)」では、出産費用の平均額として、次のようなデータが出ています。
| 受診機関の種類 | 平均額 |
|---|---|
| 全施設 | 46万8,756円 |
| 公的病院 | 42万482円 |
| 私的病院 | 49万203円 |
| 診療所(助産所など) | 48万2,374円 |
ただし健康保険や国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金として50万円が支給されます。そのため一般的な出産であれば、出産育児一時金でカバーすることも可能です。
ただし出産にともなって、ベビー用品の購入費用など、赤ちゃんを迎えるための準備費用も考えておかなければなりません。もちろん詳しい金額は家庭によって異なりますが、数十万円はかかると思っておいたほうが無難。出産育児一時金で補てんできる部分もありますが、やはり各家庭でも50万円ほどは用意しておくと安心でしょう。
またこちらも自身の出産のみでなく、家族や友人への出産祝いが必要になるケースもあります。出産した方との関係性によっても異なりますが、以下の金額が一般的。連名で贈る場合には、一人あたり1,000円といわれています。
| 出産祝いの相手 | ご祝儀額 |
|---|---|
| 兄弟、姉妹 | 約1万円~5万円 |
| 従兄弟、従姉妹 | 約1万円~2万円 |
| 親族 | 約1万円~3万円 |
| 甥、姪 | 約5,000円~1万円 |
| 職場の同僚・部下 | 約1,000円~5,000円 |
| 職場の上司・先輩 | 約5,000円~1万円 |
| 友人 | 約3,000円~1万円 |
| 知人(近隣の人など) | 約3,000円 |
教育費用
すべて20代のうちに必要となるわけではありませんが、子どもを出産して育てていくにあたっては、教育費用も含めて貯金額を考える必要があります。なお文部科学省がおこなった「令和3年度子供の学習費調査」では、子どもの通園・通学にかかる平均費用として、次のようなデータが出ています。
| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 (全日制) |
|
|---|---|---|---|---|
| 公 立 |
16万5,126円 | 35万2,566円 | 53万8,799円 | 51万2,971円 |
| 私 立 |
30万8,909円 | 166万6,949円 | 143万6,353円 | 105万4,444円 |
仮に高校まですべて公立に通ったとしても、少なくとも156万9,462円はかかる計算になります。
さらに大学に通うことを検討するのであれば、その進学費用も検討しておかなければなりません。ちなみに日本政策金融公庫の「令和3年度 教育費負担の実態調査結果(PDF)」では、大学進学費用の平均値として、次のような結果を発表しています。
| 私立大学(理系) | 私立大学(文系) | 国公立 大学 |
|
|---|---|---|---|
| 入学費用 | 88.8万円 | 81.8万円 | 67.2万円 |
| 1年間の在学費用 | 183.2万円 | 152.0万円 | 103.5万円 |
例えば私大の理系学部に4年間通うなら、進学費用は合計して821.6万円。国公立大学でも、481.2万円はかかるのが一般的です。
加えて、もし学習塾などを利用するのであれば、当然ながら必要な教育費用は増えます。総合的に考えると、子どもの教育費用としては、少なくとも1,000万円程度はかかる見込みといえます。
住宅購入費用
もし20代でマイホームを検討するのであれば、その購入費用も検討しておく必要があります。なお国土交通省が発表している「令和4年度 住宅市場動向調査報告書(PDF)」によるとマイホーム取得にともなう平均費用は、次のとおりです。
| 住宅の種類 | 平均額 |
|---|---|
| 新築注文住宅(土地購入費含む) | 5,436 万円 |
| 分譲一戸建て住宅 | 4,214 万円 |
| 分譲集合住宅 | 5,279 万円 |
| 中古一戸建て | 3,340 万円 |
| 中古集合住宅 | 2,941 万円 |
一般的には住宅ローンを組んで、毎月少しずつ返済することになります。当然ながら20代の若いうちから返済できれば、早く住宅ローンが完了するのもメリット。上記の相場を参考にしながら、毎月いくらずつ返せば何歳で完済できるのか、一度シミュレーションしてみるとよいでしょう。
20代で貯金をする時の注意点

20代からの貯金で意識したいのは、決して無理はしないことです。20代の若いうちだからこそ、貯金ができる期間は長くなるので、あまり必死になりすぎなくても心配はいりません。長い時間をかけて少しずつでもコツコツ貯めていけば、まとまった金額になります。
また特に20代のうちは、まだあまり給与が高くないケースも多いでしょう。そうしたなかで、「月収の○%は絶対に貯金する」などのルールを固めてしまうと、我慢や節約の負担が大きくなってしまうことも。そして結局はストレス感やプレッシャーなどから貯金が続かず、逆に大きな出費につながってしまい、お金を貯めた意味がなくなってしまう可能性もあります。
例えば、節約のために必要以上に光熱費や食費を削って体調を崩してしまうと、高額な医療費がかかってしまう危険性も。また交際費を削りすぎて、人間関係などに支障が出てしまう可能性もあります。貯金額を確保するために必要な経費まで削るようなことは避けましょう。
せっかく早いうちから貯金をはじめても、頑張りすぎた結果、お金だけでなく交友関係や健康など、大切なものをなくしてしまっては本末転倒です。20代の若いうちだからこそ、なるべく固く考えすぎずに心に余裕を持って、状況を見ながら柔軟に貯金ができるようにしましょう。
20代の貯金に関してよくある質問

ここからは、20代の貯金に向けて、整理しておきたい基本的なポイントをまとめていきます。
20代の貯金はいくらあれば安心?
20代のうちに貯めておきたい金額の目安は、毎月かかる生活費の半年~1年分程度です。仮に毎月17万円(全国平均)の生活費がかかっている場合には、102万円~204万円が相場となります。
毎月の貯金額の目安は?
20代の毎月の貯金額としては、月収の1割~2割程度が適切とされています。例えば年収240万円(全国平均)とすれば、月収は20万円となるので、月ごとに2万円~4万円の貯金ができると安心です。
上手に貯金するコツは?
まずは貯金額の目標を決めて、毎月使える生活費と切り分けながら貯めていきましょう。例えば、貯金用口座をつくったり、財形貯蓄や銀行の自動積み立てサービスを活用したりする方法があります。また余裕があれば資産運用をするのもおすすめ。さらにしっかりと節約を考えるなら、家計簿をつけて収支の記録をするのも効果的です。
まとめ
20代では貯金を具体的に考える機会も少ないかもしれません。しかし、この先に何があるかはわかりませんし、時には予想外の大きな出費が発生することも。将来設計だけでなく、万が一の事態に備える意味でも、20代の早いうちから貯金をしておくのがベストです。もし節約して貯金を増やしたいのであれば、生活費の見直しをするのもおすすめ。例えば、固定費として大きくなりやすい家賃を削るだけでも、より貯金はしやすくなります。ぜひ本記事も参考にしながら、自分にとっての安心につながる貯金をつくっていきましょう。
物件を探す









