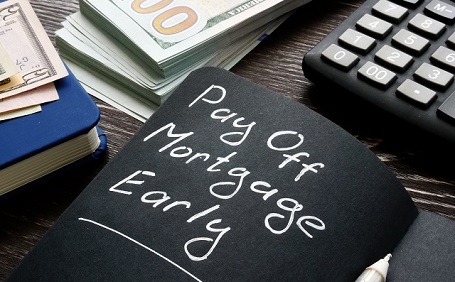住宅ローン控除はいつまで受けられる?適用期間や2024年以降の動きを解説

そこで本記事では、住宅ローン控除の基礎知識をおさらいし、2024(令和6)年度の税制改正での変更点や手続きの方法などを解説します。知らなかったと後悔することのないよう、常に最新の情報を得るようにしましょう。
記事の目次
住宅ローン控除の基礎知識
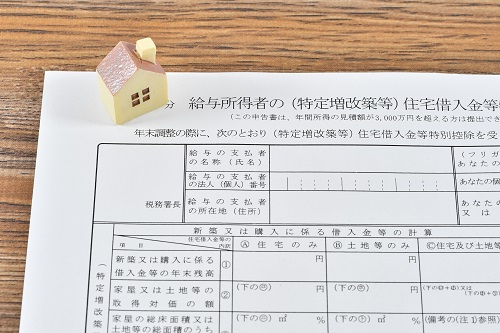
まずは、住宅ローン控除とはどのような制度なのかを押さえておきましょう。住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して家を購入したあと、一定期間、毎年年末時点の住宅ローン残高に0.7%をかけた割合が所得税から控除される制度です。所得税から引き切れなかった場合は、9万7,500円を上限として住民税から控除されます。税金が抑えられるため、結果として住宅購入の負担が軽減されます。
令和6年度税制改正での住宅ローン控除の変更点
2024(令和6)年度の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して住宅ローン控除の拡充がおこなわれました。これは、少子高齢化が進み、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅購入意欲が低下していることを受け、住宅購入をあと押しするものです。また、都市部を中心に住宅価格が上昇していることも改正された要因となっています。他にも、温室効果ガスの削減目標を達成すべく、省エネ性能を備えた住宅の普及を図るために改正がおこなわれました。具体的にどのような点が変更されたのかを見ていきましょう。
借入限度額
2024(令和6)年度の税制改正では、住宅ローン控除の借入限度額が変更されました。具体的には下表のとおりです。
| 区分 | 2023 (令和5)年 | 2024年 (令和6)年〜 2025 (令和7)年 |
控除期間 | |
|---|---|---|---|---|
|
新 築 住 宅 ・ 買 取 再 販 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 |
【改定】 4,500万円 子育て・若者夫婦 世帯5,000万円 (※1) |
13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
【改定】 3,500万円 子育て・若者夫婦 世帯4,500万円 (※1) |
||
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
【改定】 3,000万円 子育て・若者夫婦 世帯4,000万円 (※1) |
||
| その他住宅 | 3,000万円 |
【改定】 0円 (※2) |
10年 | |
|
既 存 住 宅 |
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 10年 | |
| その他住宅 | 2,000万円 | |||
出典:国土交通省「住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税)別紙1」
(※1) 2024年入居の場合、子育て世帯(19歳未満の子どものいる世帯)と若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)は、以前の水準の借入限度額が認められています。
(※2) 2023(令和5)年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024(令和6)年6月30日までに建築されたものは除きます。もし前述の期間に建築されている場合は、既存住宅のその他住宅と同じ取り扱い(借入限度額が2,000万円、控除期間10年)になります。
子育て・若者夫婦世帯の支援を強化するため、他の世帯と比較して借入限度額が500万円〜1,000万円高く設定されました。例えば、子育て世帯が2025年に長期優良住宅を購入すると、借入限度額5,000万円に対して住宅ローン控除が受けられます。もし年末時点での住宅ローン残高が4,800万円だった場合、33万6,000円が所得税や住民税から控除されます。
床面積要件
床面積要件も、2024(令和6)年度の税制改正で変更された点の1つです。住宅ローン控除を受けるためには、住宅の床面積が50平方メートル以上必要でした。しかし、現在は新築住宅で2024年末までに建築確認がおこなわれた場合は、40平方メートル以上あれば住宅ローン控除を受けられます。なお、これには所得要件が設けられており、所得が1,000万円以下の場合に限られる点に注意しましょう。
住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除を受けるためには、一定の要件を満たさなければなりません。また、新築や中古など、購入する住宅の種類によっても異なります。本章では、住宅別に住宅ローン控除の適用条件を解説します。
新築・買取再販住宅の場合
まずは新築住宅の適用条件を見ていきましょう。
- 家を新築した日または購入した日から6カ月以内に住んでいる
- 住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで住んでいる
- 年間の合計所得が2,000万円以下である
- 住宅の床面積が50平方メートル以上、かつ床面積の2分の1以上を居住用にしている
(住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満、かつ床面積の2分の1以上が居住用であれば合計所得が1,000万円以下でも可) - 住宅ローンの返済期間が10年以上である
- 譲渡所得の課税の特例を受けていない
- 生計を一つにする親族や特別な関係のある者からの取得でない
- 贈与による取得でない
出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
次に、買取再販住宅の適用条件を見ていきましょう。なお、買取再販住宅とは、不動産会社が中古住宅を買い取り、リフォームやリノベーションをおこなって販売する住宅のことです。
- 新築された日から10年を経過した住宅である
- 特定増改築の工事がおこなわれている
- 特定増改築の工事にかかった費用が建物価格に対し20%以上(300万円を超える場合には300万円以上)であること
- 宅地建物取引業者が取得した日から2年以内に購入している
出典:国税庁「No.1211-2 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
なお、特定増改築の工事内容としては、バリアフリー改修や省エネ改修、耐震改修などが挙げられます。
中古住宅の場合
中古住宅の場合は、先ほど解説した新築住宅の適用条件に加え、次のいずれかの条件を満たさなければなりません。
- 1982年1月1日以降に建築された
- 現行の耐震基準に適合している
以前は、耐火住宅は築25年以内、非耐火住宅は築20年以内と、築年数の要件が設定されていました。しかし、空き家問題が深刻化していることから、中古住宅の取引を促進させるため、2022(令和4)年度の税制改正で築年数の要件は撤廃されています。
リフォーム・増築住宅の場合
最後に、住宅をリフォームや増改築した場合の要件を見ていきましょう。
- 住宅の増改築した日から6カ月以内に住んでいる
- 住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで住んでいる
- 年間の合計所得が2,000万円以下である
- 増改築したあとの住宅の床面積が50平方メートル以上、かつ床面積の2分の1以上を居住用にしている
- 住宅ローンの返済期間が10年以上である
- 譲渡所得の課税の特例を受けていない
- 増改築の工事にかかった費用が100万円を超えており、2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用である
出典:国税庁「No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
なお、リフォームや増改築した場合の、住宅ローン控除を受けられる借入限度額は2,000万円、適用期間は10年となります。新築や中古住宅と異なる点に注意しましょう。
住宅ローン控除はいつまで受けられる?

住宅ローン控除の制度改正は頻繁におこなわれており、入居した年が1年違うだけで借入限度額や適用期間が異なることもあります。そこで本章では、住宅ローン控除の適用期間はいつまでなのか、制度はいつまで継続されるのかを解説します。
住宅ローン控除の適用期間はいつまで?
住宅ローン控除の適用期間は、新築か中古か、または住宅の性能によって異なります。下表に住宅の区分別で控除期間をまとめました。なお、これは2024年、もしくは2025年に住み始めた場合です。
| 区分 | 控除期間 | |
|---|---|---|
| 新築住宅 買取再販住宅 |
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
13年 |
| その他住宅 | 10年 | |
| 中古住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
10年 |
| その他住宅 |
住宅ローン控除の制度はいつまで?
現行の住宅ローン控除の制度は、2025年12月31日までに住み始めた場合に適用されます。国土交通省の「令和7年度国土交通省税制改正要望事項」によると、2024(令和6)年度税制改正で変更された点は、2026(令和7)年度も引き続いて実施される予定です。2026年以降、住宅ローン控除の制度が継続されるか、公式発表はありません。
しかし、住宅ローン控除の制度の歴史は古く、1972年に住宅取得控除という形で始まりました。50年以上にわたって続いてきた制度であり、突然終了することは考えにくいでしょう。ただし、控除率が引き下げられたり、省エネ性能がなければ控除を受けられないなど、内容は厳しくなりつつあります。毎年12月中旬ごろに与党から「税制改正大綱」が発表され、その後各省庁から詳しい解説資料が公表されます。日頃からアンテナを張り、最新情報を入手するようにしましょう。
住宅ローン控除の制度が終わるとどうなる?
住宅ローン控除の適用期間が終わるとどうなるのでしょうか。住宅ローン控除の適用がなくなると、これまで税金から引かれていた控除額がなくなります。そのため、還付金が少なくなったり、場合によっては追徴となる可能性も。所得税から引き切れず、住民税からも控除されていた場合は、住民税額が増えることになります。
具体的に、住宅ローン控除適用の有無で税金がどう変化するのかを見てみましょう。
<条件>
- 年収:700万円
- 年末時点でのローン残高:2,000万円
- 住宅:長期優良住宅
この場合、住宅ローン控除を受ける前の所得税の金額は30万6,500円で、以下のように算出できます。
給与所得控除
700万円×10%+110万円=180万円
社会保険料控除(15%と仮定)
700万円×15%=105万円
基礎控除:48万円
課税所得額 700万円ー180万円ー105万円ー48万円=367万円
367万円×20%ー42万7,500円=30万6,500円
住宅ローン控除で受けられる控除額は14万円のため、最終的な所得税の金額は16万6,500円です。もし、年収が同じで住宅ローン控除の適用がなくなった場合、この14万円分、税金の負担が増えることになります。
住宅ローン控除を受けるための手続きと必要書類

住宅ローン控除を受けるためには、必要書類を提出し、所定の手続きをおこなわなければなりません。本章では、手続きの方法と必要書類を解説します。
1年目の手続きと必要書類
住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅を取得した翌年に確定申告をおこなう必要があります。確定申告が必要な理由は、住宅ローン控除の適用条件を満たしているか、税務署からの確認を受けなければならないためです。確定申告では、次の書類を提出します。
| 必要書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書 | 国税庁のホームページ・税務署 |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁のホームページ・税務署 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 住宅ローンを借り入れている金融機関から郵送 |
| 登記事項証明書 | 法務局・登記ねっと (オンライン) |
| 工事請負契約書または売買契約書の写し | 不動産を購入・工事施工した不動産会社や建築会社 (購入や建築の際に入手済み) |
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
| 本人確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類) | 市区町村役場 |
| (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合) 認定通知書の写し |
不動産を購入・工事施工した不動産会社や建築会社 |
不明点や疑問点がある場合はそのままにせず、税務署や不動産会社などに確認しましょう。

- 【初年度】住宅ローン控除の確定申告の手続きは?必要書類や手順を解説!
- 住宅を購入したあと、忘れてはならない手続きがあります。それは住宅ローン控除を受けるための確定申告です。確定申告をすると
続きを読む

2年目以降の手続きと必要書類
会社員の場合、2年目以降は確定申告をする必要はありません。年末調整で住宅ローン控除を受ける手続きが可能です。次の2つの書類を勤務先に提出しましょう。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
個人事業主の方は、1年目と同様、確定申告をしなければなりません。ただし、必要書類は1年目と比較して少なくなるため、負担は軽減されるでしょう。
住宅ローン控除を受ける際の注意点

住宅ローン控除を受ける際、2つの注意点があります。場合によっては、別の制度を利用したほうが税制上、優遇を受けられる可能性もあります。後悔しないためにも、よく理解しておきましょう。
併用できない控除がある
住宅ローン控除を受ける際、併用できない控除がある点に注意しましょう。併用できない控除は次の3つです。
- 3,000万円の特別控除
- 10年超所有軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
いずれも自宅を売却したあとに利用できる控除です。しかし、自宅を売却したあとに住宅ローンを利用して新たに住宅を購入した場合、これら3つの控除と住宅ローン控除の併用はできません。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除とは、自宅を売却した際、売却益から最高3,000万円までを控除できる制度。売却益に対してかかる譲渡所得税を抑えられます。
10年超所有軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例とは、10年超所有していた自宅を売却した時に、譲渡所得税の税率が低くなる制度。通常、所有期間が5年を超える自宅を売却した際、長期譲渡所得として税率が20.315%となります。しかし、この特例を適用すると、売却益が6,000万円以下の部分について、税率が14.21%まで軽減されます。
特定の居住用財産の買換え特例
特定の居住用財産の買換え特例とは、はじめの住宅の売却時には、売却益に対して課税はおこなわず、新しく購入した住宅を売却する際に課税されるもの。例えば、最初に自宅を売却した時の売却益が3,000万円だったとしましょう。通常であれば、この3,000万円に対して課税されます。しかし、特定の居住用財産の買換え特例では、この時点では課税されません。
次に、5,000万円で自宅を買い換え、7,000万円で売却した場合、売却益の2,000万円に対して課税がおこなわれます。この時、最初に売却した際の売却益3,000万円と合わせ、売却益の合計5,000万円に対して課税されるというものです。
住宅ローン控除か、3つのいずれかの控除を受けるか、どちらが有利かは条件によって異なります。税理士などの専門家に相談し、慎重に判断しましょう。
住宅ローンの返済期間10年未満は利用できない
住宅ローン控除を受けるためには、ローンの返済期間が10年以上必要です。例えば、繰り上げ返済をおこなった結果ローンの返済期間が10年未満になった場合、控除が受けられません。そのため、控除の適用期間中に繰り上げ返済をおこなう場合は、事前にシミュレーションをし、返済金額や時期を検討しましょう。
まとめ
本記事では、住宅ローン控除はいつまで受けられるのかを解説しました。控除の適用期間は入居した年や住宅の性能によって異なります。省エネ性能のある住宅を普及させるため、住宅ローン控除の適用要件にも盛り込まれており、要件を満たしていない場合は10年となります。2024年12月時点で、2026年以降、住宅ローン控除の制度が継続されるか、公式発表はありません。しかし、50年以上続いてきた制度であることを考えると、突然終了するとは考えにくいでしょう。ただし、控除を受けるための要件や内容は厳しいものになりつつあります。住宅の購入を検討している方やすでに住宅ローン控除の適用を受けている方は、常に最新の情報を得るようにしましょう。
物件を探す

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ