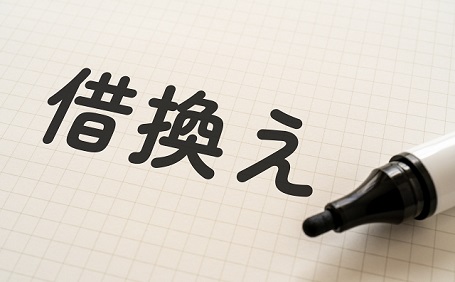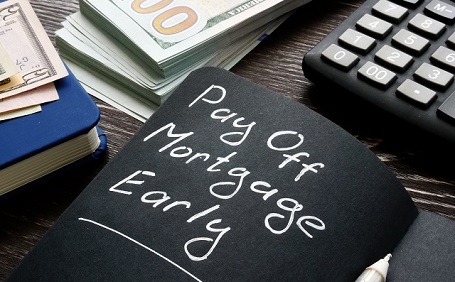住宅ローンの金利の引き下げ交渉を成功させるには?ポイントと引き下げられなかった場合の対処法を解説

金融機関と交渉すれば、住宅ローンの金利を引き下げられる可能性があります。しかし、必ずしも成功するわけではありません。そこで本記事では、住宅ローンの金利引き下げを成功させるためのポイントをご紹介。金利を引き下げられなかった場合の対処法や交渉の具体的な流れと注意点もあわせて解説します。
記事の目次
住宅ローンの金利は引き下げ交渉ができる

住宅ローンの金利は引き下げるように交渉が可能です。引き下げ交渉ができる主な金融機関の種類は以下のとおりです。
- メガバンク
- 地方銀行
- ネット銀行
- 信用金庫
金融機関が金利の引き下げに応じてくれる理由の一つは他の金融機関への借り換えを防ぐためです。
住宅ローンは長期の返済を前提に組まれることが多いため、金融機関は長期間に渡って金利収入を得られます。しかし、融資している顧客が借り換えを選択すると、得られるはずだった金利収入を失ってしまいます。
金利を引き下げれば金融機関の金利収入は減少しますが、顧客の流出を防げるのであれば、金利の引き下げに応じてくれる可能性はあるでしょう。
実際に住宅ローンの金利の引き下げに応じる金融機関も増えており、金利の引き下げに関する条件を提示している金融機関もあります。住宅ローンを借り入れている金融機関の金利引き下げ条件を確認しましょう。
ただし、「フラット35」を利用している場合は金利引き下げの交渉ができません。フラット35は、民間金融機関と「独立行政法人住宅金融支援機構」が提携して提供することから、融資条件を個別に変更できない仕組みになっているためです。フラット35を契約している方で金利を引き下げたい場合は、交渉ではなく借り換えを検討しましょう。
住宅ローンの金利引き下げ交渉を成功させるためのポイント

住宅ローンの金利引き下げ交渉を成功させるためのポイントは、以下のとおりです。
- 交渉前に必要な情報を収集する
- 返済能力の高さをアピールする
- 他の金融機関への借り換えを交渉材料にする
- 金利の引き下げ目標を決定する
- 引き下げ交渉をおこなう時期に気を付ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
交渉前に必要な情報を収集する
金利の引き下げ交渉では、交渉に必要な情報の事前準備が重要です。引き下げ交渉をおこなう前にやっておきたい準備を以下にまとめました。
- 金利の優遇条件を確認する
- 現在の金利と他の金融機関の相場を比較する
- 他の金融機関で借り換えの仮審査を受ける
まず、契約している金融機関の金利の優遇条件を確認します。具体的な条件を把握してアピールすれば交渉時に有効です。
次に、現在の金利と他の金融機関を含めた金利の相場を比較します。他の金融機関と比較して、金利が割高であることを示すと、引き下げの余地が生まれるでしょう。
最後に、住宅ローンの金利引き下げ交渉で有効な方法が、他の金融機関への借り換えを交渉材料にすることです。交渉前に他の金融機関で借り換えの仮審査を受けて、審査結果を持ち込めば説得力のある交渉材料になります。
返済能力の高さをアピールする
金利の引き下げ交渉では、返済能力の高さも重視されます。例えば、現在の資産状況がわかる資料を持参して、十分に資産があると判断されれば交渉で有利に働きます。事前に住宅ローンを契約している金融機関に預金を預けていれば、より効果的でしょう。
住宅ローンを契約した当時よりも年収が増加している場合は、源泉徴収票など収入がわかる書類を持参します。返済能力の高さをアピールして、金融機関にとって優良な顧客であることを示すと、引き下げ交渉を進めやすくなります。
他の金融機関への借り換えを交渉材料にする
金融機関が金利の引き下げに応じる大きな理由は、他の金融機関への借り換えによる顧客の流出を防止するためです。そのため、他の金融機関への借り換えは、特に有効な交渉材料になります。
他の金融機関の方が住宅ローンの総返済額が安くなるなどの具体例がある場合、現在取引をしている金融機関は引き止めるために、金利の引き下げを提案する可能性あるでしょう。事前に他の金融機関で仮審査を受け、交渉の際に審査結果を用意すると説得力が増します。
金利の引き下げ目標を決定する
金利の引き下げ目標がない状態で、漠然と金利を下げるように交渉しても思うように進みません。引き下げ目標の基準は以下の2点が考えられます。
- 借り換え候補の金融機関の金利
- 契約している金融機関が公開している優遇金利
それぞれ詳しく解説します。
まずは、「借り換え候補の金融機関の金利」を金利の引き下げ目標を設定するケース。例えば、現在の金利が2.0%で、借り換え候補の金融機関の金利が0.9%の場合に、1.1%の引き下げを求めるケースは、借り換えのわかりやすい交渉方法といえるでしょう。
次に、「契約している金融機関の優遇金利」と現在の金利を比較して差がある場合は、その差分の引き下げを目標とするのも有効でしょう。例えば、現在の金利が優遇金利と1.5%の差がある場合は1.5%の引き下げが目標になります。
引き下げを交渉する際、金融機関から引き下げの具体的な数字を求められることが自然です。明確に決まっていない場合は、金融機関に下げ幅を委ねる展開になるため、あまり下がらないケースも。交渉の際は具体的な数字を決めておくことが重要です。また、もし目標通りの下げ幅にならない場合の妥協点も検討しましょう。希望の引き下げ幅と合わせて、最低でもどの程度の引き下げが望ましいのかも考えておくのがおすすめです。
引き下げ交渉をおこなう時期に気を付ける
引き下げの交渉には効果的と考えられる時期が存在します。金融機関によっては住宅ローンの融資目標額を設定しており、決算期の目標達成が求められます。多くの金融機関の決算期である3月と9月は目標達成のために、顧客流出を恐れて金利の引き下げ交渉が有利に進む可能性があります。
ただし、決算期は従業員が忙しくなるため、金融機関によっては交渉の時間を取ってもらえないかもしれません。時期に関しては必ずしも有利になるわけではなく、時期を待つよりも早く交渉を開始したほうが金利の引き下げ時期が早まって、総返済額が少なくなる場合もあります。
住宅ローンの金利引き下げ交渉の方法と具体的な流れ

住宅ローンの金利引き下げ交渉の方法と、具体的な流れは以下のとおりです。
- ステップ1金融機関の窓口に連絡する
- ステップ2金利の引き下げに有効な条件を提示する
- ステップ3交渉結果からその後の対応を検討する
それぞれ詳しく解説します。
ステップ1.金融機関の窓口に連絡する
交渉を始めるには、金融機関の住宅ローンを担当する窓口に連絡し、「金利の引き下げの相談をしたい」と伝えましょう。住宅ローン契約の際にやり取りをした担当者と連絡がつく場合は、同じ担当者に連絡すれば交渉までスムーズに進みやすくなります。
ステップ2.金利の引き下げに有効な条件を提示する
実際に交渉を始める際には、上記で解説した引き下げに有効な条件を提示します。交渉では条件を一方的に提示するだけでなく、事前に相手からの質問や提案を想定したうえで交渉に臨みましょう。すぐに答えることが難しい質問・提案をされた場合は保留しても問題ありません。
ステップ3.交渉結果からその後の対応を検討する
交渉の結果、こちらが提案した金利の引き下げに応じたのであれば、交渉は成功です。しかし、交渉がまとまらなかった場合は、その後の対応を検討することになります。交渉を続けることで納得のいく金利まで引き下げられる手ごたえがあった場合は、再び交渉をおこないましょう。
ただし、これ以上の交渉を続けても金利の引き下げを期待できない場合は、その後の対応を検討します。
住宅ローンの金利を引き下げられなかった場合の対処法

住宅ローンの金利を引き下げられなかった場合の対処法は、以下のとおりです。
- 金利タイプを変更する
- 他の金融機関に借り換える
- 繰り上げ返済も検討する
- 家計の見直しと資金計画を再検討する
- 時間をあけて再交渉をおこなう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
金利タイプを変更する
金利の引き下げ交渉、借り換え以外の方法で金利を安くするには、同じ金融機関で住宅ローンの金利タイプを変更しましょう。住宅ローンの金利タイプは、大きく分けて2つあります。
- 固定金利:あらかじめ定められた期間の金利が固定されている
- 変動金利:一定期間ごとに金利が見直される
現在が固定金利であれば変動金利、変動金利であれば固定金利に変えることで、金利を引き下げられる可能性があります。ただし、金利タイプの変更も金融機関によっては認められない場合もあるため、必ずしもできるわけではありません。また、金利タイプを変更することで金利が引き上がり、総返済額が上昇するケースもあります。
他の金融機関に借り換える
住宅ローンの金利の引き下げで交渉と同様に効果的な方法は、他の金融機関への借り換えです。借り換えを材料に交渉がまとまらない場合は、借り換えることも選択肢の一つです。ただし、借り換えには諸費用がかかるため、金利の引き下げ幅によっては諸費用が上回る場合もあることに注意しましょう。
繰り上げ返済も検討する
上記の金利タイプの変更・金融機関への借り換えを検討して、金利が引き下がらない場合は総返済額を抑える他のアプローチにも注目しましょう。総返済額を減らす方法には、「繰り上げ返済」があります。繰り上げ返済とは、通常の返済とは別に住宅ローンの元金の一部または全額を返済する方法です。
繰り上げ返済によって住宅ローンの返済期間が短縮されると、支払う利息が抑えられるため、金利の引き下げ以外で総返済額の減少が期待できます。
家計の見直しと資金計画を再検討する
金利の引き下げができず、住宅ローンの返済が難しい場合は、返済計画を見直しましょう。例えば、家計の支出を見直して無駄な出費を削減し、住宅ローンの返済資金を確保すれば返済の負担が減少します。資金計画も再検討したうえで、長期的に返済を続けられる返済計画を考えます。
思うように金利の引き下げ交渉ができなかった場合は、それ以外で住宅ローンの返済負担を減らす方法を総合的に実施しましょう。
時間をあけて再交渉をおこなう
上記でご紹介した対処法を検討してもなお金利の引き下げが望ましい場合は、時間をあけて再交渉をおこなうと、金利を引き下げられるかもしれません。なぜなら、住宅ローンの金利事情は時間が経てば変化するためです。
また、住宅ローンの契約者の預金、年収などが上昇すれば、交渉の結果が変わる可能性があります。今は失敗に思える交渉結果であっても、時間を置いての再交渉も検討してみましょう。
住宅ローンの金利引き下げ交渉の注意点

住宅ローンの金利引き下げ交渉の注意点は以下のとおりです。
- 信用情報に傷を付けないようにする
- 当初固定金利のリスクを把握する
- 見込まれる総返済額を計算する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
信用情報に傷を付けないようにする
金利引き下げ交渉では、金融機関から再審査を受けるため、返済の遅延などによって信用情報に傷があると不利です。また、金利引き下げ交渉によって優遇金利が適用されたあとも、返済を遅延すると適用されていた優遇金利が取り消される場合もあります。
信用情報に傷が付くことは金利の引き下げ交渉の前後においてリスクがあるため、ローンの返済、クレジットカード・カードローンの支払いなどで延滞しないように心がけましょう。
当初固定金利のリスクを把握する
金融機関と交渉の最中に、金融機関側から「当初固定金利」を提案される可能性がありますが、金利だけを確認して合意しないように気を付けましょう。当初固定金利は、返済開始から一定期間が固定金利で、固定金利期間終了後は原則として変動金利になります。
固定金利である一定期間においては金利が引き下げられるため、期間中の返済額は減少する仕組みです。しかし、変動金利に切り替わると金利が大きく上昇する場合があり、最悪の場合は金利の引き下げを交渉する前よりも総返済額が増える可能性もあります。
当初固定金利を提案された場合は、金利の数値以外の条件を確認して、適切な返済計画を立てられるかを検討してから合意するようにしましょう。
見込まれる総返済額を計算する
住宅ローンの金利引き下げ交渉をおこなうにあたって、見込まれる総返済額を計算してみましょう。以下に計算例をまとめました。
現在の住宅ローンの返済状況
- 住宅ローンの借入金:5,000万円
- 金利:2.0%(全期間固定)
- 返済期間:30年
- 返済方式:元利均等方式
金利引き下げ後の住宅ローンの返済状況
- 住宅ローンの借入金:5,000万円
- 金利:0.9%(全期間固定)
- 返済期間:30年
- 返済方式:元利均等方式
| 現在 | 金利引き下げ後 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 18万4,809円 | 15万8,533円 | 2万6,276円 |
| 総返済額 | 6,653万1,359円 | 5,707万1,836円 | 945万9,523円 |
| 利息分 | 1,653万1,359円 | 707万1,836円 | 945万9,523円 |
事前に引き下げ交渉の目標とする金利で計算をおこないましょう。交渉中に相手から別の金利を提案された場合も、総返済額を計算して金利の引き下げ効果を比較しながら、提案を受けるかを検討します。
まとめ
今回は、住宅ローンの金利引き上げ交渉のポイントと、引き下げられなかった場合の対処法について解説しました。住宅ローンの金利引き下げ交渉は、事前の徹底した情報収集と事前準備が成功の鍵になります。交渉の際には、他金融機関での仮審査結果や市場金利の比較、返済能力の証明資料など、説得力ある交渉材料を揃えましょう。
交渉がうまくいかない場合は、金利タイプの変更、借り換えなど、交渉以外の金利の引き下げを検討します。また、金利を引き下げる他にも繰り上げ返済、家計の見直しなど、多様な対策を検討することで、返済負担の軽減が見込めるでしょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ