財形貯蓄とは?メリット・デメリットや活用方法についてわかりやすく解説

資産形成の一つとして挙げられるのが「財形貯蓄制度」です。今回は、住宅購入資金や老後資金などまとまったお金の準備に活用できる財形貯蓄制度についての説明やメリット・デメリット、活用方法をわかりやすく解説します。
記事の目次
財形貯蓄とは?

財形貯蓄とは、会社が従業員の給与やボーナスから一定額を天引きしておこなう貯蓄制度のことです。
住宅購入や子どもの進学、老後資金の準備など、従業員のライフイベントで必要となる資金作りを会社が支援します。勤め先が財形貯蓄制度を導入している場合に利用できます。
財形貯蓄制度は3種類ある
財形貯蓄制度には、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類があります。
それぞれの内容や違いは以下のとおりです。
| 一般財形貯蓄 | 財形住宅貯蓄 | 財形年金貯蓄 | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 財形貯蓄制度のある企業で働く従業員 | 財形貯蓄制度のある企業で働く、満55歳未満の従業員 | 財形貯蓄制度のある企業で働く、満55歳未満の従業員 |
| 利用目的 | 自由 | 住宅の建築・購入・リフォームに必要な資金の準備 | 老後資金の準備 |
| 積立期間 | 原則3年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
| 払い戻し 時期・回数 |
貯蓄開始から1年経過後、いつでも払い出し可能 払い出し回数に制限なし |
住宅取得前(一部)、住宅取得後に払い出し リフォーム前(一部)、リフォーム後に払い出し 払い出し回数は1回もしくは2回 |
満60歳以降に5年以上20年以内で年金として払い出し (保険商品は終身受け取り可) |
| 非課税措置 | なし | 財形年金貯蓄と合わせて、預貯金または保険の払込額550万円までの利子が非課税 | 財形住宅貯蓄と合わせて、預貯金は550万円まで、保険の払込額は385万円までの利子が非課税 |
| 積立商品の 種類 |
預貯金、有価証券、生命保険、損害保険など | 預貯金、有価証券、生命保険、損害保険など | 預貯金、有価証券、生命保険、損害保険、郵便年金など |
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は1人1契約までですが、一般財形貯蓄は1人で複数契約することも可能です。また、3種類とも他の財形貯蓄と併用できます。
いずれも毎月の給与からの天引きですが、ボーナスからの天引きも可能です。ただし、財形貯蓄は定期的に積み立てていく必要があります。
では、それぞれの財形貯蓄を詳しく解説していきます。
一般財形貯蓄
一般財形貯蓄は、利用目的が自由な貯蓄制度です。非課税措置はありませんが、貯蓄開始から1年経てばいつでも払い出しができるので、ライフイベントでまとまった費用が必要になった時に活用できます。
3年以上は積立を続けることが条件ですが、1人で複数の契約が可能で、積立限度額は設定されていません。
ただし、生命保険は払込額が3,000万円まで、郵便貯金は積み立てが1,300万円までと制限が設けられているケースがあるので注意しましょう。
以下は、一般財形貯蓄の利用目的の一例です。
- 結婚
- 引越し
- 車の購入
- 海外旅行
- 医療費
- 教育費
財形住宅貯蓄
財形住宅貯蓄は、住宅の建築・購入・リフォームに必要な資金を準備するために利用できる貯蓄制度です。
財形年金貯蓄と合わせて550万円までは利子が非課税になります。ただし、住宅以外の目的で払い出しをすると非課税措置が受けられなくなる場合があります。
財形住宅貯蓄を利用できるのは満55歳未満の人で、5年以上の積み立てが必要です。
また、払い出しも住宅取得やリフォーム前後2回までとなっているため、利用の際は条件の詳細をよく確認しておきましょう。
財形住宅貯蓄を利用できる条件
財形住宅貯蓄で建築・購入・リフォームする住宅は、以下の条件を満たす必要があります。
| 新築住宅を建設・ 購入する場合 |
・床面積が50平方メートル以上であること
(2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅は40平方メートル以上から対象となる)
・従業員本人の所有・居住する住宅であること
|
|---|---|
| 中古住宅を 購入する場合 |
・床面積が50平方メートル以上であること
・1982年1月1日以後に建築された住宅であることもしくは一定の耐震基準を満たしていること
|
| リフォーム する場合 |
・工事後の床面積が50平方メートル以上あること
・工事費用総額が75万円を超えていること
・リフォーム後に従業員本人が住宅に住むこと
|
財形住宅貯蓄は住宅の建築・購入・リフォームの資金として利用することで非課税措置を受けられますが、それ以外の目的で払い出しをすると、課税対象となります。
この場合、預貯金は払い出しをした月から5年をさかのぼって課税されます。保険商品は解約時に全期間の利子に課税されるので注意しましょう。
ただし、災害や疾病などやむを得ない事情がある時は、非課税で払い出しができる特例があります。
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄は、老後資金を準備するための貯蓄制度です。
利用できるのは満55歳未満の従業員ですが、給与天引きで貯められるので、比較的早い時期から確実に老後資金の準備をはじめられるでしょう。
預貯金は財形住宅貯蓄と合わせて550万円まで、保険商品の場合は払込額が385万円までは利子が非課税になります。
受け取り方法は年金のみで、一括で払い出せません。年金以外での払い出しは非課税措置が受けられなくなるので注意しましょう。
ただし、災害に遭ったり、病気になったりした場合など一定の条件を満たす払い出しは利子が非課税になる特例があります。
財形貯蓄制度のメリット
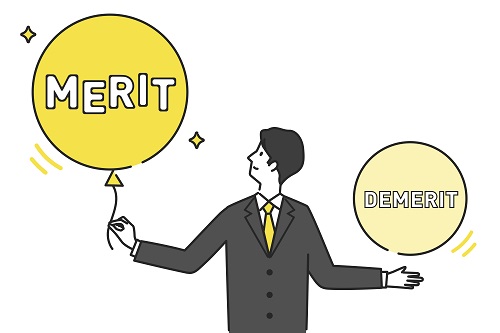
財形貯蓄制度には5つのメリットがあります。どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
自動的に貯蓄ができる
財形貯蓄のメリットは、給与やボーナスからの天引きで積み立てができる点です。貯蓄口座にお金を移動させる手間がなく、自動的にお金が貯まっていきます。
手元にお金があるとつい使ってしまいがちな人や、自分でお金を移動させるのが面倒な人に向いている貯蓄方法です。
ライフイベントに備えた資産形成ができる
結婚や子どもの進学、住宅購入、車の購入、老後資金など、ライフイベントではまとまった資金が必要になります。そんな時に備えて、財形貯蓄は資産形成の手段として利用可能です。
給与天引きでお金が確実に貯まるので、一般財形貯蓄は教育費の準備のように、まとまった資金作りに有効。財形住宅貯蓄は住宅購入の頭金として、財形年金貯蓄は老後資金の準備として活用できるでしょう。
利子が非課税になる
通常の預貯金や保険金などで得られる利子には20.315%の税金がかかります。
しかし、財形住宅貯蓄では、財形年金貯蓄と合わせて預貯金と保険の払込額が550万円までの利子が非課税になります。
また、財形年金貯蓄では、財形住宅貯蓄と合わせて預貯金は550万円まで、保険の払込額は385万円までの利子が非課税です。
住宅ローンの負担を減らすことができる
財形住宅貯蓄を利用すれば住宅購入の頭金を貯められるので、住宅ローンの借入金額を減らせるでしょう。また、財形貯蓄制度の利用者は「財形持家転貸融資」が利用できます。
財形持家転貸融資とは、財形貯蓄制度を利用している従業員のための住宅ローンです。比較的低利で利用でき、子育て世帯や中小企業の従業員は金利優遇措置を受けられる場合があります。
給付金を受け取ることができる
勤め先が「財形給付金制度」や「財形基金制度」を実施している場合、財形貯蓄を利用する従業員は7年ごとに財形給付金または基金給付金を受け取れます。
財形給付金制度とは、従業員1人につき10万円を上限に拠出し、7年経過ごとに財形給付金として従業員に支給する制度です。
財形基金制度も、従業員1人につき10万円を上限に拠出することで、7年経過ごとに基金給付金を従業員に支給する制度になります。
また、従業員が受け取る財形給付金と基金給付金は所得扱いになりますが、一時所得となるため、50万円までは非課税です。
財形貯蓄制度のデメリット
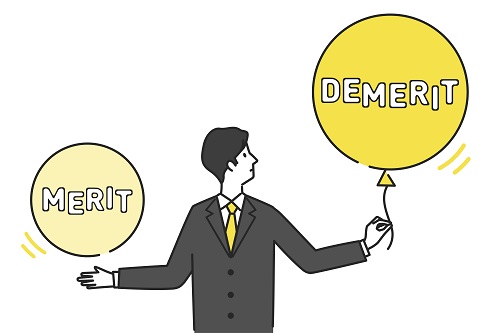
財形貯蓄制度には6つのデメリットがあるので注意が必要です。どのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。
勤め先によっては利用できない
財形貯蓄は、勤め先が財形貯蓄制度を導入していないと利用できません。自分の勤め先は制度を導入しているかどうか確認してみましょう。
目的以外のために引き出すと非課税にならない
一般財形貯蓄には非課税措置はありませんが、利用目的が自由なので、1年を経過すれば自由に引き出せます。
しかし、財形住宅貯蓄は住宅の建築・購入リフォーム資金として、財形年金貯蓄は老後資金として使用することで非課税措置を受けられます。そのため、住宅資金や老後資金以外の目的で払い出しをすると非課税措置を受けられません。
また、財形住宅貯蓄は対象となる住宅やリフォーム工事の条件や費用の範囲が定められています。
加えて、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は非課税で払い出す場合、法令で定められた方法による「適格払い出し」の条件を満たす必要があります。
利用の際は、事前に内容や条件をよく確認しておきましょう。
利率が低いと非課税の恩恵を受けにくい
現時点では、預貯金は超低金利となっています。非課税措置を受けられても、非課税対象となる税額が少ないため、非課税の恩恵を受けにくい状況です。
ただ、2024年3月19日に日本銀行がマイナス金利の解除を決定したことから、メガバンクや地方銀行が普通預金金利の引き上げを発表しました。
場合によっては、超低金利時代よりも非課税の恩恵を受けられるようになるかもしれません。
他の財形貯蓄に変えられない
一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の3つは併用することが可能です。
しかし、一般財形貯蓄は3年以上、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は5年以上積み立てを続ける必要があります。
そのため、規定の期間を経過するまでは、他の財形貯蓄に切り替えられません。
所得控除がない
財形貯蓄は給与天引きで毎月お金を積み立てていきます。しかし、積立金は所得控除にはなりません。
一方で、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」も毎月掛金を積み立てていきますが、こちらは掛金全額が所得控除の対象になります。
財形年金貯蓄とiDeCoはどちらも老後資金を準備するためのものです。非課税措置はありますが、所得控除の扱いが異なる点は留意しておきましょう。
商品によっては元本割れの可能性がある
財形貯蓄で利用できる商品のなかには、株式投資信託など日々値動きがある金融商品が含まれています。よって、場合によっては元本割れになる可能性がある点は留意しておきましょう。
財形貯蓄はマイホーム購入時の負担を減らせる?

財形貯蓄はマイホームを購入する際の頭金を準備するのに活用できます。頭金を準備できれば住宅ローンの借入金額を減らせるので、家計の負担を軽減できるでしょう。
なかでも財形住宅貯蓄はマイホームの建築や購入のための資金を貯めることが可能です。550万円までは非課税となる(ただし、財形年金貯蓄と合算して550万円)のでお得です。
また、給与天から引きで積み立てていくので、頭金を貯めやすいでしょう。
財形貯蓄で積み立てたお金を頭金にする
ここでは、財形貯蓄で貯めたお金を頭金としてマイホームを購入する際のシミュレーションを、頭金なしの場合と比較しながらご紹介します。
【条件】
- 物件価格:4,000万円
- 頭金:500万円
- 住宅ローン金利:全期間固定金利 年1.84%
- 返済期間:35年
- 返済方法:元利均等返済
- ボーナス払いなし
参考:フラット35「借入希望金額から返済額を計算」
| 頭金なしの場合 | 頭金500万円の場合 | |
|---|---|---|
| 価格 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 頭金 | 0円 | 500万円 |
| 住宅ローン借入額 | 4,000万円 | 3,500万円 |
| 毎月の返済額 | 13万円 | 11.4万円 |
| 総返済額 | 5,429万円 | 4,750万円 |
| 総支払利息 | 1,429万円 | 1,250万円 |
| 頭金を含めた 総支払額 |
5,429万円 | 5,250万円 |
同じ物件価格の住宅購入でも、頭金を準備できれば借入額を減らせます。その結果、支払わなければならない利息分が減るので、月々の返済額や総返済額も減らせます。
つまり、住宅購入では頭金があれば家計の負担を軽減できるでしょう。その際、非課税措置のある財形住宅貯蓄を利用すれば、550万円までは税金の負担もなくなります。
勤め先が財形貯蓄制度を実施しているなら、頭金作りとして活用しましょう。
財形持家転貸融資を利用する
勤め先が財形貯蓄制度を実施していて「財形持家転貸融資」を導入している場合、住宅の建築・購入・リフォーム費用を低利で借り入れられます。
財形持家転貸融資とは財形貯蓄の利用者が借り入れできる住宅ローンです。財形貯蓄残高の10倍以内(最高4,000万円まで)、かつ、原則かかる費用の90%以内の借り入れが可能です。
ただし、財形持家転貸融資を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
【利用条件】
- 一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄のいずれかを1年以上続けている
- 財形貯蓄残高が50万円以上ある
- 自分が取得・居住する住宅の建築・購入・リフォームである
- 借入申込日の2年前から財形貯蓄で積み立てをおこなっている
- 事業主から負担軽減措置を受けられる
- 申込日現在の年齢が70歳未満、完済時年齢が80歳までである
- 廃止前の財形持家分譲融資を受けていない
財形持家転貸融資の返済期間は最長35年で、融資利率は、2024年1月1日現在1.02%で、5年間固定金利制となっています。これは5年間の金利は固定され、5年経過ごとに金利が見直される制度です。
利用する前には、財形持家転貸融資の制度内容や利用条件の他、対象となる住宅や土地の条件も確認しましょう。
財形貯蓄制度に関するよくある質問
ここでは、財形貯蓄制度で多く寄せられる質問にお答えします。
財形貯蓄はいつでも引き出せる?
財形貯蓄はお金を引き出せるタイミングが決まっています。
一般財形貯蓄は、貯蓄開始から1年間は引き出せませんが、1年を過ぎたらいつでも自由に引き出すことが可能です。
ただし、財形住宅貯蓄は住宅の建築または購入の前後2回まで、リフォームの場合は工事の前後2回と回数が決められています。
また、財形年金貯蓄は60歳以降、5年以上20年以内の年金でしか受け取ることができないので注意しましょう。
引越し費用にも使うことはできる?

一般財形貯蓄なら利用目的が自由なので、引越し費用として利用できます。
引越しでは荷物の運搬費用の他、新居で使う家具家電やカーテンの購入などお金が必要になるので、一般財形貯蓄は非常に役立つでしょう。
財形貯蓄制度以外の資産形成の方法は?
資産形成の方法は財形貯蓄制度だけではありません。
「NISA」はNISA口座で購入した金融商品から得た運用益が非課税になります。また、2024年1月からはNISAの制度が改正されて、年間の非課税投資枠が拡大し、非課税期間が無期限になるなど、資産形成として利用しやすくなりました。
また、一括投資の「成長投資枠」と、投資信託で積立投資をする「つみたて投資枠」は併用できるようになっています。
その他、老後資金の準備方法としては「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。勤め先が企業型確定拠出年金を実施していれば、これも資産形成に活かせます。
貯蓄額が550万円超えたらどうなる?
財形貯蓄では生命保険の払込保険料と郵便貯金以外は、積立限度額はありません。
ただし、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、この2つの貯蓄残高の合計が550万円を超えた場合、超えた分の利子は課税されます。
なお、一般財形貯蓄は貯蓄額に関係なく利子に課税されるので留意しておきましょう。
育児休業中は財形貯蓄を休止できる?
非課税措置のある財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄ですが、原則これらは2年間中断すると非課税措置が受けられず、利子は課税対象になるため、2年以上育児休業を取得する場合、財形貯蓄を続けられませんでした。
そこで厚生労働省は、2015年4月から「育児休業等取得者の継続適用特例」を設けました。所定の手続きをすれば、子どもが3歳になるまで育児休業を取得しても、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の非課税措置が継続されます。
財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄を利用しながら育児休業を取得する際は、育児休業に入る前に勤め先を通じて忘れず手続きをしましょう。
退職したら財形貯蓄はどうなる?
会社を退職したら新たな積み立てができなくなり、財形貯蓄は解約することになります。ただ、退職後2年以内に再就職した場合、転職先でも財形貯蓄制度を実施していれば継続可能です。
まとめ

財形貯蓄は、給与やボーナスからの天引きで積み立てをおこなう貯蓄制度です。
利用目的が自由な「一般財形貯蓄」、住宅の建築・購入・リフォームの資金準備に利用できる「財形住宅貯蓄」、老妓資金の準備ができる「財形年金貯蓄」の3種類があります。
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は預貯金残高の合計が550万円までは利子が非課税に。
勤め先で財形貯蓄制度を導入しているのであれば、資産形成の手段として財形貯蓄を活用してみてはいかがでしょうか。
物件を探す






