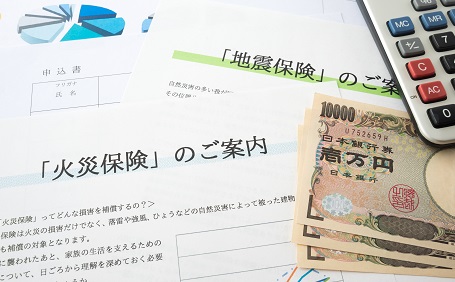地震が起きたらどうする?持ち物や逃げる場所、とるべき行動を解説

記事の目次
巨大地震とはどんな地震を呼ぶのか?

「巨大地震」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際にどのくらいの地震を巨大地震と呼ぶのでしょう。地震調査研究推進本部が定義する巨大地震とは、マグニチュード8程度以上の大きな地震とされています。マグニチュード8程度の地震の例として、近年では東日本大震災がマグニチュード9.0と最大値を観測しています。
1995年に起きた阪神淡路大震災では、マグニチュードは7.3、2024年元日に起きた能登半島地震のマグニチュードは7.6でした。
南海トラフ巨大地震は必ず起きる

政府の地震調査委員会は2024年1月に、南海トラフ周辺で発生するマグニチュード8.0~9.0の巨大地震の発生確率を次のように発表しています。
- 10年以内では30%程度
- 30年以内では70~80%程度
- 50年以内では90%程度もしくはそれ以上
この予測を見て、「10年は安心ということだ」と考えてはいけません。10年以内というのは、今日かもしれませんし明日かもしれないのです。そして、30%は確率の数字であり、0%でない限り巨大地震はいつ起きてもおかしくない状況にあります。
また、首都直下地震は2020年1月24日時点で、今後30年以内に70%の確率で発生すると発表されています。マグニチュードは7.0程度とされているため、巨大地震とは呼ばれていません。しかし、高速道路が倒壊した阪神淡路大震災でもマグニチュードは7.3ですから、巨大地震でないにしろ、首都直下地震も不安材料になるのは間違いないでしょう。
地震が起きたらどうする?

近年では防災意識が高まっており、地震が起きたらどのように行動するか知っている方は多いでしょう。とはいっても、時系列ごとに何をすべきか説明できる方が少ないのも事実です。そこで改めて、地震が起きた際にとるべき行動を確認してみましょう。
地震発生直後にすべきこと
- 丈夫なテーブルの下に隠れる
- 使用中のガスコンロやストーブを消す
- ドアや窓を開け逃げ道を確保する
- 窓の大きなオフィスビルでは窓から離れる
- スーパーなどはレジ付近や生鮮食品売り場に逃げる
- 外出時にはブロック塀や自動販売機から離れる
- カバンなどで落下物から頭を守る
- 電車乗車中なら急ブレーキに備える
建物内にいる時に地震が起きたら、机など丈夫なテーブルの下に隠れることは多くの方が知っているでしょう。ただ、オフィスなら机の下に、体全体が完全に隠れないといけません。その理由は、複合機などのOA機器が揺れによって襲ってくるからです。特に高層階なら震度が低くても大きな揺れをともなうため、OA機器は凶器となります。
また、スーパーなどではレジ周りは棚がなく比較的安全ですし、生鮮食品売り場も高い棚はありませんから緊急の避難場所に適しています。それぞれの行動を普段からイメージしておくと、急な地震にも対応できます。
揺れが収まったらすべきこと
- 出火があれば消火をする
- 家族やペットの安全を確認する
- スリッパや靴を履く
- ガスの元栓を閉めブレーカーを落とす
- 非常持ち出し袋を持つ
- 家屋倒壊の可能性がある場合は避難する
- 住宅内の被害状況を確認する
- 海や川の近くにいるならすぐに離れる
- オフィスでは階段を使って避難する
地震の揺れが収まったら住宅内の被害状況を確認して、状況によって対応を決めましょう。最近では都市ガスやLPガスはマイコンメーターが導入されており、震度5以上の地震発生時には自動でガスを遮断します。そのため、震度5以上の揺れが起きたら、ガスコンロで調理中でも火は消えます。
しかし、震度3~4では自動で遮断されないため、揺れによってキッチンペーパーなどがガスコンロに落ちて出火するかもしれません。そのため、キッチンに消火器を準備していれば安心です。
また、住宅に損傷があり一時的に住めない状況にあれば、非常持ち出し袋を持って近くの避難所に避難しましょう。避難の際にはガスコンロの元栓を閉めて、配電盤のメインブレーカーを落としてから避難します。
大きな揺れでなくても地震があれば、海や川の近くから離れないといけません。オフィスでは避難マニュアルに従って避難しますが、どんなに高層階でもエレベーターでなく階段での避難が必須です。
【場所別】地震が起きたらどこに逃げる?
地震が起きた際には、身の安全の確保が最優先です。そのため、危険リスクのない、または少ない場所に逃げることが大切です。ここでは地震が起きた際に、自分がいた場所別の逃げ方について解説します。
家にいる時

自宅のキッチン付近にいたなら、ダイニングテーブルの下に隠れます。それ以外の場所なら、何も落ちてこない、倒れてこない、飛んでこない場所に逃げましょう。例えば、ベッドルームには背の高い家具を置かずベッドだけにしておけば、地震時にはベッドルームに逃げ込めば身を守れます。
その後は、住宅内の被害状況を確認して自宅に残るか、避難所に避難するかを判断します。家にいる時の地震では、大型家具などの転倒から身を守るのは当然ですが、割れた食器やガラスなどでケガをしないことも重要です。
外にいる時

外にいる時に地震が起きたら、すぐにブロック塀や自動販売機から離れます。ただ、急に道路の真ん中に飛び出すと車にひかれる可能性もあるため、道路状況はよく確認しましょう。しかし、この判断は難しく状況に応じて対応するしかありません。
高い建物がある場所ならカバンなどで頭を守りながら、公園などの広い場所に逃げましょう。ただし、揺れているなかの移動は控えて、揺れが収まってから道路状況を確認して公園などに避難します。地震の揺れで道路が陥没したり割れたりしますし、液状化が起きると非常に危険です。
地下街にいる時
地下街にいる時に地震が起きたら、柱や壁のそばで揺れが収まるまで待ちます。停電になっても慌てず、非常照明灯がつくまで落ち着いて待ちましょう。慌てて非常口や階段にいくと、人が殺到してしまい逆に危険です。
地下街では60m間隔で非常口が設置されているので、揺れが収まってから近くの非常口から慌てずに順番に避難します。避難時は壁に沿って脱出すると安全です。
商業施設にいる時
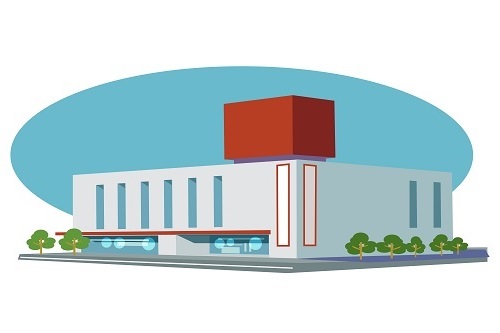
スーパーやデパート、コンビニなどの商業施設にいる時に地震が起きたら、陳列棚のある場所からすぐに離れてください。逃げ場所としてはスーパーやコンビニではレジ横、デパートならエレベーターホールがよいでしょう。それ以外でも、高いショーケースや陳列棚、天井のシャンデリアなどがなければ大丈夫です。揺れが収まったら、コンビニや小さなスーパーでは自己判断で店舗を出ることとなりますが、大きなスーパーやデパートでは従業員の指示に従って行動します。
職場にいる時
職場にいる時なら、コピー機や複合機の移動に巻き込まれないよう、机の下にスッポリ身体が収まるよう隠れます。また、窓際にいるなら確実に窓から離れないと、窓ガラスが割れて大ケガをしたり外に転落したりするかもしれません。
最近ではフリーアドレスで、専用の机のないオフィスも増えてきました。この場合でも、作業用の机はあるはずなので、パソコンなどで頭を守りながら机の下に避難します。
揺れが収まったら、防災担当の職員の指示に従って避難行動を開始しましょう。オフィスビルでは勝手な行動が災害リスクを高めてしまうため、必ず責任者の指示に従うことが重要です。
学校にいる時
学校の教室にいた時に地震が起きたら、自分の机の下に隠れます。廊下にいたなら窓から離れて、階段の踊り場など広いスペースまで逃げましょう。
運動場にいる場合には校舎から離れ、運動場の真ん中付近まで逃げて、揺れが収まるまでしゃがんだ体制で待ちます。その後は、教職員の指示に従って避難行動に移ってください。
山や海にいる時

海にいる時は揺れが収まるまでは、砂浜などで待機します。海水浴シーズンで海の家などにいる場合は、砂浜まで逃げましょう。砂浜では倒れてくるものや落ちてくるものがないので、とりあえずは安全です。揺れが収まったら、津波が襲ってくる可能性があるためすぐに近くの高台まで避難します。
山にいた時は状況によって異なりますが、崖や登山道から滑落しないよう木にしがみつくかその場にしゃがみ込みます。揺れが収まったら、登るのは止めてすぐに下山を開始しましょう。
エレベーターにいる時

エレベーターに乗っている時に地震が起きると、動揺してしまうかもしれません。しかし、まずはすべての階のボタンを押してみてください。最寄りの階でエレベーターを降りて、エレベーターホールで揺れが収まるまで待機しましょう。
揺れが収まったら、階段を使って下の階に避難します。万が一閉じ込められても慌てずに、非常ベルや非常電話で管理会社と連絡し合い救助を待ちましょう。狭い空間に閉じ込められるとパニックに陥りやすいので、エレベーターでの避難方法を知っておくと少しは落ち着いて行動できます。
地震が起きたときに自分がいる場所によって、とるべき行動が変わります。しかし、どこにいても変わらないのは、慌てずに自分の身を守ることです。ここでは自分のいる場所別に、どこに逃げるのがベストなのか、逃げ方などもご紹介しました。ぜひ、地震発生時の避難行動の参考にしてください。
地震発生後の注意点

せっかく地震の揺れから身を守っても、その後に間違った行動をすると命を落とすリスクもあります。また、地震災害では多くの方が被災するので、お互いを思いやる気持ちも大切です。そこで、ここでは地震発生後に注意すべき項目をご紹介します。
慌てて外に飛び出さない
地震の揺れが収まったからと、慌てて外に飛び出すのはよくありません。地震発生後は道路や建物がどのような状況になっているか、しっかり確認して行動しないと危険です。
例えば、液状化で道路が沈下していれば、外に出た途端に沈下した道路に落ちてしまいます。また、破損した建物から落ちてくる看板やガラスなどで、ケガだけでなく命を落とすリスクもあるからです。そのため、建物内から外へ出るときは、外部の状況をしっかり把握したうえで、カバンなどで頭を守りながら建物外へ出るようにしましょう。
電話はなるべく使わない
地震発生後には救急や警察への通報、役所などへの問い合わせ、安否確認などにより、一般の電話回線がパンク状態になります。そのため、自分が無事であることを知らせるなら、災害伝言ダイヤルや災害伝言板(Web171)を利用しましょう。
NTT西日本・東日本では、地震など災害が発生した際に電話回線を利用しなくても安否確認がおこなえるサービスを提供しています。地震発生後に使い方がわからないと困るため、次の日時に体験できるのでぜひ利用して使い方をマスターしておきましょう。
- 毎月1日および15日 00:00~24:00
- 正月三カ日(1月1日00:00~1月3日24:00)
- 防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00)
- 防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00)
また、au・docomo・Softbank各社も災害用伝言ダイヤルを提供するので、地震発生直後は安否確認の電話は控えてこれらのサービスを利用してください。
ラジオで情報収集をする
近年では、スマホでもラジオを聴けるアプリが登場しています。そのため、地震発生後に学校のグラウンドに避難していても、ラジオで情報収集が可能です。公共性の高いラジオなら、信頼度の高い情報を得られるため、情報収取には最適なアイテムといえます。
SNSなどのデマに惑わされない
先のラジオでの情報収集に関連しますが、スマホが普及したことで、災害時にSNSで情報を得る方も多くなっています。しかし、SNSでは偽情報が発信される可能性も高く、特にX(旧Twitter)での情報収集は今後注意しないといけません。
現在はX(旧Twitter)での投稿も、インプレッションによって収益を得られるようになりました。そのため収益を得るためだけに、嘘の情報を流しインプレッションを稼ぐ悪質な存在も増えています。しかも、日本からでなく遠い海外から発信される虚偽投稿も目立ち、信頼性が低くなっています。情報は投稿日時や背景、発信元などよく注意して利用しましょう。
二次被害に注意
地震発生後には、二次災害にも注意しないといけません。二次災害とは地震の揺れから避難できたのに、その他の要因によって地震以外の災害に遭遇してしまうことを指します。これまでの地震による二次災害として分かりやすいのは、エコノミークラス症候群や火災、ライフラインの遮断でしょう。
2016年に発生した熊本地震では車中泊する方も多く、エコノミークラス症候群によって死亡した方も少なくありませんでした。エコノミークラス症候群は身体を動かさないことが要因で起きる症状で、長期に渡る車中泊で足を動かすことが極端に少なくなり引き起こされます。
また、1995年に起きた阪神淡路大震災では、地震後に大規模な火災が発生し多くの家屋が焼失し死者も出ています。さらに、能登半島地震で起きているように、ライフラインの遮断は大きな二次災害につながります。水道が使えないため、トイレ・お風呂はもちろん、掃除さえもできずに健康的な生活ができない地域も多く存在しています。長期的な停電が起きると冷蔵庫が使えないことから、食材の保存ができなくなります。
このように、地震発生後に起きる二次災害は、せっかく助かった命を危険にさらす高いリスクがあります。そのため、エコノミークラス症候群など自分で対応可能な部分は、しっかりと対策をしておきましょう。
地震が起きる前に備えておきたい持ち物は?

ここで、地震が起きる前に備えておきたい持ち物をご紹介しましょう。基本セットとして以下のグッズを揃えておけば、突然起きる地震災害から避難する際に便利です。
- 飲料水
- 栄養補助食品・レトルト食品(すぐに食べられるもの)
- 現金類
- 照明(懐中電灯、ライト)
- モバイルバッテリー
- マスク
- タオル
- ブランケット(ひざかけ)
- ティッシュ・ウェットシート・ボディシート
- 歯ブラシ・歯磨き粉
- 軍手
- 救急セット
- 生理用品
この他にも、乳児がいる家庭では液体ミルクや哺乳瓶の取り換え用乳首、オムツなどをプラスすると安心です。その他、小さなお子さんや高齢者の方、介護を要する方など家庭の状況によって、必要なアイテムをプラスするとよいでしょう。
災害時に有効な防災グッズを詳しく解説した、次の関連記事も併せてご覧いただくと、地震時に必要な持ち物がより充実します。
家でできる地震対策

いつ起きるか分からない地震に対して、家でできる対策をご紹介します。
地震に強い家・エリアに住む
地震に強い家とは耐震等級1以上の住宅であり、震度6~7程度相当の地震が起きても倒壊・崩壊しない強度を誇ります。基本的に1981年以降に建築された住宅であれば、耐震等級1以上となります。
では、それ以前の建物はどうすればいいのかというと、耐震診断と耐震改修が推奨されています。国土交通省では「令和12年までに耐震性が不十分な住宅、令和7年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消する」ことを目標に、住宅の所有者に対してさまざまな耐震化の支援制度を提供しています。この制度を活用して、地震に強い家に改修しましょう。
また、地震に強いエリアに住むこともよいアイデアです。地震に強いエリアとは「ゆれやすさマップ」を見れば、大きな地震が起きた際に自分が住むエリアの震度を知ることができます。例えば、震度7のエリアと震度5弱のエリアでは、もちろん震度5弱のエリアの方が危険度は低くなります。
また、土砂災害ハザードマップを確認すれば、土砂災害被害のないエリアに住むことが可能です。津波ハザードマップを確認すれば、海溝型地震による津波被害のないエリアに住むことができます。引越しや転居のタイミングで、各ハザードマップを確認して災害危険度が低いエリアに移り住むことで安全性を高められます。
家具が転倒しないよう固定する
いくら地震に強い家でも、それは住宅そのものが強いのであって、住宅の中は自分で地震に強い環境にしないといけません。特に大型家具や、電化製品の転倒防止は必須です。
阪神淡路大震災での死亡原因の多くが、家具の転倒による圧死、または逃げ遅れでした。そのため、食器棚や冷蔵庫などは転倒防止器具によって、地震の揺れでも転倒しないようしっかり固定することが重要です。
最近ではさまざまな転倒防止器具が販売されており、借家でも住宅に傷をつけることなく利用可能な器具もあります。特につっぱり棒のような転倒防止機器は安価で高性能です。製品によっては実証実験をおこない、震度7の揺れでも食器棚が倒れない転倒防止機器もあるので、活用して家具などをしっかり固定しましょう。
非常持ち出し袋を準備する
非常持ち出し袋の準備も重要です。中身は先にご紹介したグッズや、関連記事で取り上げている防災グッズを参考にしてください。ただ、非常持ち出し袋を準備していても、地震時に持ち出せないと意味がありません。家族の誰もが非常時に持ち出せる場所を決めておき、いざという時にサッと持ち出せる保管スペースの確保が大切です。
飲料や食品を備蓄する
飲料や食料の備蓄も家ごとに必要ですが、それほど大げさに考えなくても大丈夫です。ネットショップなどで販売される防災専用の備蓄食を購入すれば、5年以上の保存期間があるので長期間の備蓄が可能ですが、そこまでしなくても、普段の買い物のついでにレトルト食品や缶詰、パスタ、パックご飯、ペットボトルのミネラルウォーターなどを購入して備蓄すれば問題ありません。いずれも半年~1年の賞味期限があるので、備蓄に適しています。
ただし、備蓄は「ローリングストック」が基本となるため、3~6カ月程度で備蓄品を消費して新たな食材を備蓄するのがおすすめです。定期的に「消費→備蓄→消費」を繰り返すことで、いざという時に消費期限が切れていて食べられなかったり、備蓄すら忘れてどこに保管したかわからなくなるリスクが減ります。スーパーなどの日常の買い物で食材などを買い足して、簡単に楽しく備蓄をスタートさせましょう。
家族の安否確認方法を共有しておく
家族が学校や仕事に出かけている際に地震が起きれば、それぞれが個別に避難することとなります。自分の身の安全を確保すると、次に心配になるのは家族の安否です。しかし、災害時は電話回線がパンクしてしまうため、思うように連絡がとれないのが現実でしょう。そこで、利用したいのが先に紹介している災害伝言ダイヤルや災害伝言板(Web171)です。
また、個人が発信しているSNSでのコメント機能の利用や、災害時のみに表示される「LINE安否確認」を利用するなど、家族間でどのような連絡方法を利用するか相談して確認方法を共有しておきましょう。先にご紹介したように、災害伝言板などは実際に体験できる日時があるため、家族全員で体験しておけば安否確認方法が確実なものになるはずです。
避難経路・避難場所を確認しておく
ハザードマップで地震時の避難場所や避難所を確認したら、自宅や職場、学校など、さまざまシーンで地震が起きたと仮定して、目的の避難所までのルートを実際に歩いておきましょう。避難時は徒歩避難が原則ですが、最近では自転車を使った避難も推奨されています。そのため、通勤や通学で自転車利用しているなら、自転車で実際に避難所までのルートを走ってみるとよいでしょう。
途中で階段や急な登り坂があれば、自転車での避難が難しくなるため、ルートを変えるか自転車をその場で乗り捨てて徒歩避難に切り替えるかの判断が可能です。また、徒歩避難時でもどのくらい避難に時間と体力が必要か分かるため、非常持ち出し袋の内容の検討もおこなえます。
地域の危険個所を把握しておく
先の避難所までのルートを確認しておくことに関連しますが、地域の危険な場所を把握するのも重要です。例えば、避難所までに細い道の両側に背丈よりも高いブロック塀がある道は、利用してはダメなルートです。また、津波ハザードマップにて地震による津波の影響がある地域も、ルートから外す必要があります。このように、地域の危険個所を調査して把握しておけば、安全な避難ルートの選定に役立ちます。
避難訓練に参加する
職場や地域で開催される避難訓練には、できるだけ参加しておきましょう。職場の避難訓練は半強制的になるため、ほとんどの方が参加するはずです。半強制的であっても参加しておけば、どのように避難するのか体験できるため、「机の下にスニーカーを用意しておこう」などの啓発につながります。
地域の防災訓練では普段顔を合わさない近隣住民と、コミュニケーションがとれるよい機会です。高齢者の方との避難方法や公民館に用意してある備蓄品の確認もできるため、避難時に準備しておけばよいグッズの検討もできて有意義です。
ここまででご紹介した家でできる地震対策は、少なくともおこなっておくべき対策です。何の対策も講じていなければ、突然地震が起きると慌ててしまい大切なものを失うかもしれません。1人ひとりの小さな対策が大きな効果を生み出す結果となるため、ぜひ実践しておきましょう。
この記事のまとめ
今回は地震が起きた際の持ち物や逃げる場所、とるべき行動を詳しく解説してきました。すでに知っている内容もあったかもしれませんが、思い出すことでイメージが確実なものとなります。記事内でご紹介している地震時に取るべき行動や、避難場所や避難所の確認、防災グッズや備蓄などを参考にしていただき、ぜひ実践してください。以下に、ポイントをまとめましたので改めて確認しておきましょう。
地震が起きたらどうすればいい?
地震が起きたら、身の安全を確保することが最優先です。家庭や職場、学校のなかならダイニングテーブルや机の下に隠れましょう。外にいるなら、カバンなどで頭を守りブロック塀や自動販売機から離れます。その場の状況に応じて、命が助かる行動が重要です。
地震が起きたら気をつけることは?
地震が発生した際に気を付けることは、とにかく落ち着いて行動することです。SNSなどのデマに惑わされないように、情報は信頼性のある発信源から取得します。地震後に二次災害となる、エコノミークラス症候群などへの対策は重要です。
地震が起きたらどこに逃げる?
地震が起きた際には揺れが収まるまで安全な場所で待機して、地震に対応した避難場所や避難所に避難します。海や川の中や近くにいるなら、津波の恐れがあるためすぐに近くの高台へ逃げましょう。
南海トラフ巨大地震の発生率は、10年以内で30%程度、30年以内では70~80%程度と公表されています。つまり、いつ大きな地震が起きてもおかしくない状況です。2024年に入ってすぐに能登半島地震が発生し、千葉県周辺の地震など多くの地震が発生しています。そんな状況にあるなかで、地震に対しては個人で対応するケースが多くなります。いつどこで巨大地震が起こっても冷静に対応できるように、日頃の準備を徹底しましょう。
物件を探す