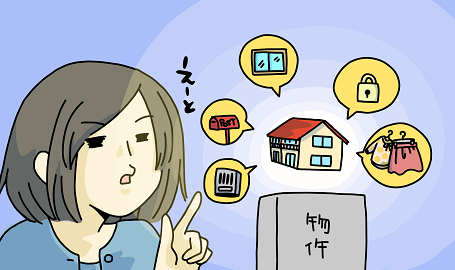高校生でも一人暮らしできる?賃貸契約の手順と方法、お部屋選びのポイントを紹介

記事の目次
高校生でも一人暮らしはできる?

未成年の高校生でも、部屋を借りて一人暮らしすることは可能です。ただし、そのためには親の同意と承認が必要になります。なぜなら、未成年者が賃貸借契約を結ぶには、親権者の同意が必要と法律で定められているから。賃貸物件を借りるには、大人であっても入居審査があり、「この人には家賃の支払い能力があるか?」「継続して支払う収入があるか?」などを見られます。さらに、保証人が必要となる場合もあるでしょう。高校生の場合、同意してもらうのも保証人になってもらうのも、ほとんどの場合が親になります。
18歳以上であれば親の同意なしで一人暮らしが可能
2022年4月から、成人年齢が18歳に引き下げられました。そのため法律上では、高校生であっても18歳になったら親の同意なく、単独で賃貸借契約を結ぶことが可能です。ただし、実際のところ、これは現実的ではありません。
30歳になっても40歳になっても、部屋を借りる際には「勤め先」「月収」「勤務歴」などさまざまなことを聞かれます。これは、その相手に部屋を貸しても大丈夫かどうかを調べるためです。
高校生で、親の同意も保証人もなく、この審査に通ることは難しいでしょう。そのため、親と話し合うのが一番の早道。難しければ卒業して職に就き、自分で収入を得られるようになってから一人暮らしに挑戦しましょう。
公立の高校だと一人暮らしができない
親の同意があったとしても、全日制の公立高校の場合、入学の必須条件に「保護者と本人が、高校のある都道府県の同住所に居住していること」といった記載があることが多いでしょう。東京都教育委員会は「都外から東京都の高校に通うことができるか?」という質問に対して、「入学日までに保護者とともに東京都に転入し、その後も住み続けるのであれば可能」と応えています。
定時制の場合、本人のみが高校のある都道府県に住んでいれば、志願者の資格を得られるところもあります。自分の住んでいる地域ではどうなのか、気になる人は都道府県の教育委員会または教育局などに問い合わせてみてください。
18歳未満で一人暮らししている人は全国で約8,000人

2020年(令和2年)におこなわれた「国勢調査」によると、18歳未満の単身世帯の数は、7,995世帯となりました。そのうちのすべてが高校生というわけではありませんが、一人暮らしをしながら高校に通っている学生さんも少なからずいることがわかります。
高校生で一人暮らしをする理由は、進学したい学校が他県の場合や、親の転勤が決まり家族で引越しすることが決まったが、自分だけ地元に残り現在通っている高校を卒業したいなど、人によってさまざまです。
高校生がお部屋を借りるために必要なこと

部屋を借りるまでの一般的な流れは、高校生であっても通常と変わりません。部屋探しのポータルサイトなどで場所・賃料・初期費用などの条件から物件を探し、不動産会社に連絡してみましょう。あるいは、住みたいエリアの近くにある不動産会社に足を運び、部屋探しの条件を伝えます。そして、住みたい部屋が見つかったら、実際の部屋に案内してもらって内見。気に入ったら申し込み、そこから貸主側で入居審査がおこなわれます。審査にかかる時間はおよそ2週間。無事に審査が通ったら、住む物件の重要事項説明を受けたのちに、契約に必要な金銭を支払うという流れです。
親と子どもが一緒に契約をする
未成年は親権者の同意がないと、賃貸契約をすることができません。たとえ高校生本人が「この部屋に住みたい」と決めたとしても、親が同意しなかった場合、その部屋を借りることはできません。そのため、高校生だけで内見(実際に部屋を見学すること)させてくれる不動産会社は少ないでしょう。物件探しの時点から、親と一緒におこなうことが理想です。
生活費の支払いを誰がどのくらいするのか話し合う
15歳になって最初の3月31日を過ぎると、高校生でもアルバイトをすることができます。とはいえ、高校生のアルバイトで月々の家賃と生活費のすべてを支払うのは無理があるでしょう。家賃の一部を自分で働いたアルバイト代から支払うのか、親が全額支払うのか、最初に家族で決めておくことが大切です。
生活費がどのくらいかかるのかを把握しておく

一人暮らしに必要な費用は、家賃だけではありません。毎日の食費も必要ですし、電気・ガス・水道などの光熱費もかかります。実際に生活するための費用は月々どのくらいかかるのか、一般的な例をあげてざっくりとご紹介しましょう。
まず、生活費として毎月かかってくるお金には、家賃・水道光熱費・通信費・食費などがあります。政府統計の「1世帯当たり1か月間の収入と支出(単身世帯)2024年度調査」による単身世帯の平均的な支出は、家賃を除くと以下のようになっています。
| 用途 | 1カ月あたりの支出 |
|---|---|
| 食料 | 43,941円 |
| 電気代 | 6,756円 |
| ガス代 | 3,056円 |
| 水道代 | 2,282円 |
| 通信費 | 6,379円 |
| 合計 | 62,414円 |
出典:政府統計「1世帯当たり1か月間の収入と支出(単身世帯)2024年度調査」
これだけで6万2,414円ですから、仮に家賃5万円とすると合計は11万円超え。他にも洋服や美容室などのファッションにかける費用、遊びに行くときの娯楽費、急な病気の際の医療費なども必要です。
また、月々にかかる費用以外に、一人暮らしを始めるにあたって揃えないといけないものもあります。冷蔵庫、洗濯機、コンロ、レンジなどの家電製品、棚や収納のための家具、寝るための寝具、食器や調理器具なども必要でしょう。必要最低限のものを選び、リサイクルショップや100円均一ショップなどを利用したとしても、新たにすべて揃えれば最低10万円程度はかかるでしょう。これに加え、さらに引越し代も発生します。
政府統計には単身世帯のなかに勤労者も含まれているので、年齢も近い大学生の例のほうが参考になるかもしれません。こちらの記事もあわせて参考にしてみてください!
大学進学や就職も見据えておく
高校生の場合、卒業後の進路についても考える必要があります。学業と家事、生活を支えるためのアルバイトと、日々を過ごしていくだけで精一杯ではないでしょうか。そのうえで、大学進学や就職に向けて備えられるのかどうか、将来のこともよく考えましょう。
高校生が住むお部屋探しのポイント

セキュリティ性の高い部屋を選ぶ
親元を離れての初めての一人暮らしは、些細なことにも不安がつきまといます。そのため、できるだけセキュリティ性能の高い部屋を選ぶと安心できるでしょう。泥棒や不審者に入られにくいオートロック付き、訪問者を離れた場所から確認できるモニター付きインターホンなどがある物件は、セキュリティや防犯対策をした物件といえます。部屋の階数は1階より2階のほうが外から侵入しにくく、4階以上になると格段に外からの侵入を防げて安心です。さらに、窓の周りを囲む塀などがなければ、周りからの目が犯行を防いでくれます。
周辺の治安や環境、施設を確認する
建物自体のセキュリティはもちろん、周りの治安もチェックポイントのひとつです。初めて一人暮らしをするときは、できれば朝・夜の両方を見ておくことをオススメします。朝はゴミ出しの様子で、周辺住民の質がわかるといいます。夜は最寄りの駅やバス停、スーパーなどから家までの道のりの明るさや人通りの多さをチェック。不安なところがないか確認しましょう。
近くに歓楽街などがあるところは、たとえ人通りが多くても、あまり治安がよいとはいえません。逆に、学校や警察署が近くにあると周りの目が守ってくれますし、24時間営業のお店があれば、いざというときに駆け込めて安心です。
いざというときに頼れる人が多い場所にする
健康なときは問題なく過ごせていても、いざ病気になったり、トラブルに巻き込まれたりしたときに、一人暮らしだととても不安になります。家族や親戚、仲のいい友達が近くにいるところに住んでいれば、いざというときにすぐに頼ることができて安心です。頼れる人が思いつかないときは、近くの病院や交番の場所、緊急避難場所などを把握しておき、非常時に備えて防災食・防災グッズなども準備しておきましょう。
通学しやすい場所を選ぶ
予算の都合などもありますが、できるだけ通学が便利な場所を選びましょう。通学に不便な場所を選んでしまうと、行き帰りするだけで時間も体力・気力も奪われてしまいます。さらにアルバイトをするつもりであれば、余計に生活時間が奪われてしまうでしょう。通学しやすい場所を選び、きちんと学校に行ける環境に身を置くことも大切です。
高校生の一人暮らしはトラブルに注意

病気やケガ
一人暮らしで病気やケガをしたとき、親に心配をかけたくないからと黙っているケースは多いようです。しかし、きちんと知らせるようにしましょう。万が一、意識がなくなったときなどに病気やケガの通院歴を保護者が把握していないと、病院側で最適な治療をしてもらえない可能性があります。もし、近くに親戚が住んでいる場合などは、万が一の場合に連携できるように前もって相談しておいてください。
金銭関係
本来なら高校生活は、学業や部活に専念して過ごすのが理想でしょう。そのため、一人暮らしにかかる費用、家賃や生活費などは、できる限り親が支援してあげたほうがいいかもしれません。高校生のアルバイト代だけで、生活費のすべてを賄うのは困難です。保護者は、お子さんの一人暮らしの生活費を支援するだけの金銭的余裕があるかどうかを考え、計画しておくことも大切です。
最近では、若年層を狙った特殊詐欺も増えています。オンラインゲームやSNSで知り合って高額なバイトに誘われ、お小遣い欲しさに犯罪に巻き込まれるといったトラブルも増えているので注意が必要です。
学業との両立
一人暮らしでは干渉してくる周りの目がなくなり、つい羽を伸ばしがちです。一緒に住んでいるときは、子どもが日々きちんと勉強しているかを確認できますが、離れているとそうはいきません。前期・後期の中間テストと期末テスト、学期始めの実力テストの結果は、必ず見せるように約束しておくとよいでしょう。著しい学力の低下があった場合は、その原因を話し合って対策しましょう。
食生活の偏り
実際に一人で暮らしてみると、毎日何もせずごはんが食べられていたことのありがたさに気づきます。「もともと料理を作るのが好き」「一人暮らしを機に料理がしたかった」という人は別ですが、料理の苦手な人は毎日手軽なインスタント食品やカップラーメンばかりの食事になりがちです。10代は、体も心も大きく成長する時期。健康な体を作り、すこやかな心を育むためには、毎日のバランスの取れた食事が大切です。毎日作るのが面倒な場合は、作り置きするなどしてなるべく栄養が偏らないようにしましょう。
人間関係
高校生の一人暮らしは、やはり珍しいケースです。友達を一度招待したつもりが、いつの間にか大勢が集まるたまり場になってしまうことも考えられます。その結果、自分の生活リズムが崩れてしまったり、悪い先輩が入り浸っていつの間にか犯罪に巻き込まれてしまったり。そういう可能性もゼロではありません。高校生の一人暮らしという特別な環境を利用しようとする人とは、少し距離をおいて付き合ったほうがいいかもしれません。親としては、最初にお子さんと「何時以降は他人を部屋に入れない」「一度に部屋にあげるのは何名まで」などの約束を交わし、20時になったらビデオ通話をするなどのルールを決めておくとよいでしょう。
不審者
高校生が一人で暮らしていると、周りからは少し目立つものです。親切な人が声をかけてくれることもあるかもしれませんが、なかには不審者や犯罪者、怪しい団体などがいるかもしれません。ドアの施錠はもちろん、インターフォンが鳴っても確かめてからドアを開ける、荷物は置き配にする、窓にミラーカーテンをかけるなどの対策をし、常にトラブルに備えておきましょう。
まとめ
高校生でも一人暮らしすることは可能です。しかし、18歳になったからとはいえ、社会的信用が高くなったわけではありません。そのため、高校生が一人で賃貸契約を結ぶことは難しいでしょう。また、生活するうえでも不安な点が多々あります。保護者はその点を踏まえて家賃や生活費を支援し、防犯対策や日々の生活管理に気を配っておきましょう。