賃貸物件で水漏れ!対処法は?費用は誰が払うの?
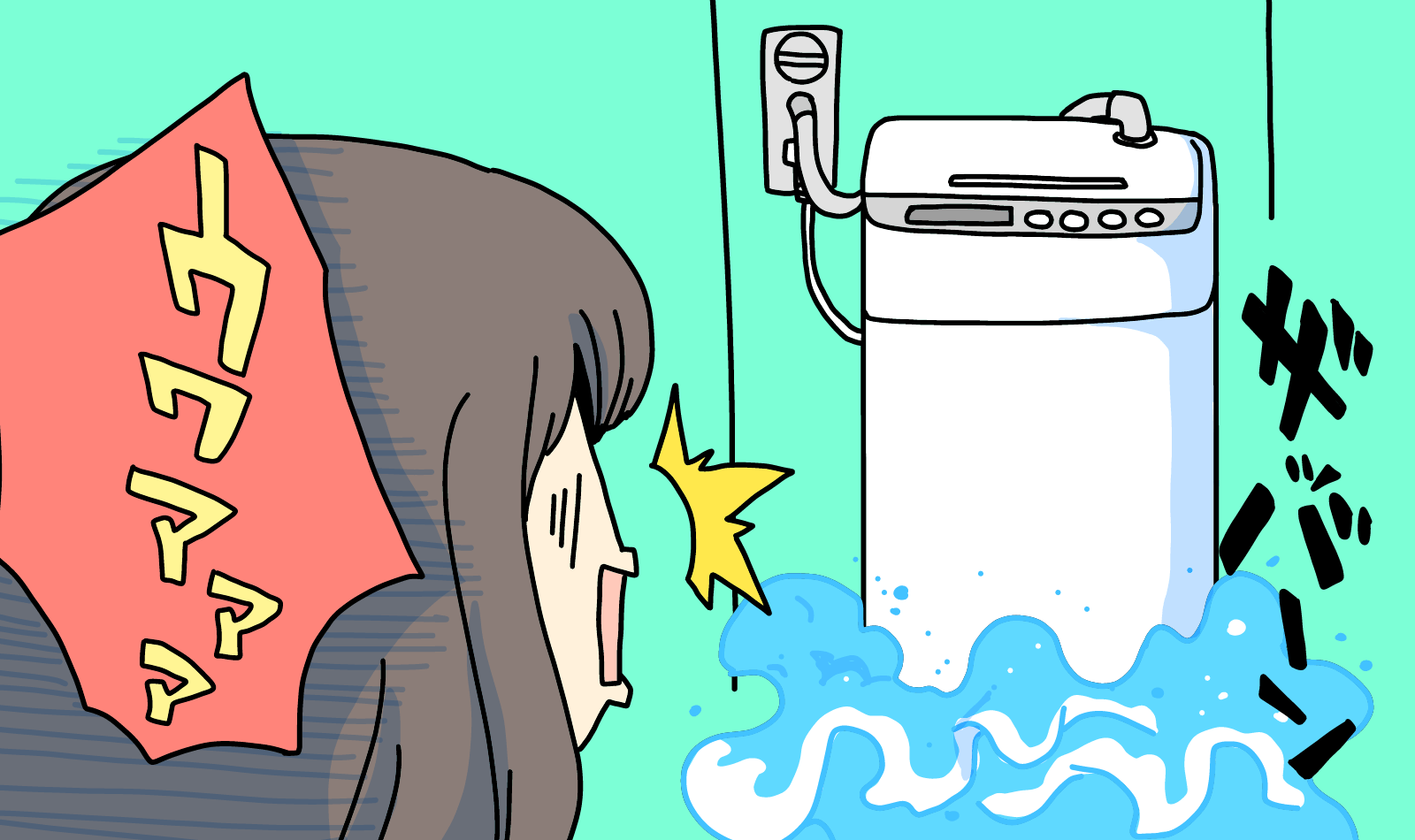
アパートやマンションのように複数の世帯が共に暮らす環境では、しばしば騒音トラブルが発生します。日々のストレスに繋がるほか、放っておくと裁判などに発展する恐れがありますので、深刻化する前に対処することが重要です。
この記事では、賃貸物件における「騒音トラブル」について、その原因と対処法、騒音トラブルを避けるための物件選びについて解説します。
記事の目次
集合住宅での騒音トラブルは、主に以下の4つの原因で起こります。
まず、1つ目の「季節的な要因」は、春や年末、新人歓迎会や忘年会の二次会を家で行い、夜通し部屋で騒ぐといった場合に起きる騒音です。特に学生が住んでいるようなアパートでは、4月に飲み会絡みの騒音トラブルが多発します。
2つ目は、新しい入居者によるマナー不足です。例えば、初めて賃貸物件に住む人が隣に引越してきたような場合が考えられます。今まで実家で暮らしてきた学生が一人暮らしを始め、実家にいるときと同じ感覚でテレビや音楽を大音量で聞くようなケースが該当します。
このようなケースでは、相手が近隣に迷惑をかけていることを理解していないことが多いので、早めに注意し賃貸物件のマナーを理解してもらうことが必要となります。
3つ目として、被害を受ける本人の感覚が原因となることもあります。騒音というのはある意味主観的な被害ですので、受ける側の捉え方次第で騒音と感じてしまうこともあります。
このケースは、自らが新しくアパートなどに引越した場合に起こることが多いものです。今まで閑静な住宅街で暮らしてきた方が小学校近くのアパートに引越し、昼間に学校から聞こえてくる子どもたちの声に悩む、といったケースが該当します。
周辺環境による騒音はしばらくすると慣れることも多いですが、どうしても耐えられない場合は再度引越す等の対策も考える必要があります。
4つ目は、設備・構造の要因です。木造や軽量鉄骨のアパートでは、鉄筋コンクリート造のマンションに比べて隣住戸の騒音被害を受けやすくなります。また、建物自体が老朽化している場合、玄関や室内建具の開閉音でトラブルになることもあります。さらには、隣住戸で使っている洗濯機の音が大きいような場合も騒音トラブルの原因となります。
では、具体的にどのようなケースで騒音トラブルは起きるのでしょうか。この章では、騒音トラブルでよくあるケースを6つに分けて紹介します。
夜間に洗濯や掃除を行うと、その音がトラブルになることがあります。土日にまとめて行うことや静音タイプの製品を買うことなどで対応しましょう。

テレビや音楽の音もトラブルになります。スピーカーの位置を変える、ヘッドホンを用いる等の対応で防ぐようにしてください。
楽器演奏の音もトラブルとなります。禁止事項に該当している物件もありますので、賃貸借契約書をよく確認するようにしましょう。
子どもが室内を走ったりする際の足音や騒ぎ声が問題となることもあります。お子さんがいる方は入居時に下階に必ず挨拶に行くなど、トラブルを未然に防ぐことも必要です。
怒鳴り声や喧嘩、しかりつける声は、騒音トラブルとなるだけでなく近隣住民に不安を与えます。自分ではなかなか気付きにくいポイントですが、度が過ぎると警察を呼ばれてしまう可能性もありますので、今一度注意してみましょう。
ペット可の物件では、ペットの鳴き声や足音が問題となることもあります。ペット禁止の物件ではそもそも「用法違反」であり、契約解除の理由になり得ます。
騒音トラブルに悩まされたときはどのように対処したら良いのでしょうか。この章では、その相談先について紹介します。
騒音トラブルが発生したときに真っ先に相談する相手は「管理会社」です。
トラブルが生じたら、まずは貸主や管理会社に相談しましょう。
もし貸主と管理会社が両方存在する場合は、まず管理会社に相談します。貸主が物件の管理を行っている場合は貸主に直接連絡することになりますので、有事の際の連絡先がどこになるのかを確認しておきましょう。
また、騒音トラブルは早く注意し常習化させないことが重要です。
例えば、夜中に隣住戸で飲み会の大騒ぎがあったときは、次の日には管理会社に伝え、早い段階で注意をしてもらうことがおすすめです。
管理会社の対応が悪く騒音トラブルが解消されない場合には、最終的に弁護士に介入してもらうようなケースもあります。
ただし、裁判になると解決まで長期化してしまうので、解決方法としては適切ではありません。裁判の証拠として騒音のデシベル数を測定され、それが許容範囲内と判定されてしまうと、何も解決できないことも考えられます。
その前段階で解決することが望ましいですが、もしも解決が見込めない場合は賃貸物件ですので、こちらから引越してしまうというのもひとつの策です。まずは管理会社(貸主)に相談するなど手順を踏んでいき、それでも改善の気配がないということであれば、思いつめ過ぎず新しい環境に目を向けてみてもよいかもしれません。
騒音問題において、自分が加害者になってしまうこともあります。この章では、自分が加害者になった際の対処法について解説します。
賃貸借契約書では、通常「禁止事項」が規定されています。禁止事項に反したときは賃貸借契約が解除となり、強制退去させられてしまうこともあります。
賃貸借契約書における典型的な禁止事項には、以下のようなものがあります。
大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと
一方で、騒音に関して賃貸借契約書に細かな規定を設け過ぎると生活に支障をきたす恐れがあることから、あえて騒音トラブルを解除事由としていない契約書も少なくありません。
その代わりに「入居のしおり」等を配り、入居者に共同生活のルールを認知させているケースもよくありますが、入居のしおりに違反するような行動を取った場合は掲示板への掲出やチラシで注意喚起されてしまうことがあるので、加害者にならないよう注意しましょう。
騒音トラブルは多くの場合、管理会社が仲裁に入ることで解決していきます。しかし、当事者間で揉めてしまった場合には相手に直接お詫びに行かなければいけないケースも考えられます。
お詫びの際には、話を遮らずに相手の話に耳を傾けるなど、余裕をもって対応するようにしてください。お詫びの際に再発防止策も伝えると印象が良くなります。
騒音トラブルを生じさせた場合は、再発防止に取り組むことが重要です。フローリングにカーペットを敷くことや、椅子の足にゴムカバーを付けること、テレビを壁から離したり、防音シートや吸音パネルで防音壁をつくるなど、ちょっとした工夫や簡単なDIYで防音対策を行うことができます。
また、扉をバタンと閉めず手を添えて閉めるなど、行動パターンを変えるだけでも騒音はかなり抑えることができます。
入居時の挨拶で子どもやペットがいることを伝えておくとクレームに繋がりにくくなります。
逆の立場だった場合、何も連絡なく騒音に悩まされるよりも、「なるべくご迷惑にならないように努めますが、もしかするとうるさくしてしまうかもしれません」と事前に声をかけられていたほうが安心できるのではないでしょうか。
相手の感じ方が違ってくるので、クレーム防止策として事前に挨拶し、伝えておきましょう。
ここまで、現在暮らしている物件での騒音トラブルについて解説してきました。
それでは、騒音トラブルを避けるために物件探しの段階でできることはあるのでしょうか? ここでは物件探しのポイントについて紹介します。
物件内覧時は、過去にトラブルがなかったかを確認するようにしてください。例えば「前の物件は騒音が嫌で出たのですが、この物件では騒音トラブルはないですか?」などと聞いてみると良いでしょう。
他の部屋にどんな入居者が多いかを聞いて見ることも有効です。学生や若い方が多かったり民泊に使われている部屋があったりする場合には、騒音トラブルが多い傾向があります。
騒音が気になるようであれば、鉄筋コンクリート造の物件を選ぶのがコツです。また、築年数が浅くサッシュの防音性能が高い物件も騒音トラブルは起きにくくなります。
最上階や角部屋などは比較的騒音の影響を受けにくくなります。ただし、小さな子どもがいる家庭は2階以上に住むと下階に音が伝わりやすくなってしまうこともありますので、心配であれば物件選びの際に不動産会社に相談しておきましょう。
一度、住民が帰宅している夜の時間に内見してみても良いかもしれません。日当たりや物件までの道のりの確認のために昼、音の伝わり方や物件での過ごし方をイメージするために夜、というかたちで二回内見すると理想的です。
トラブルが発生した場合は、ひとりで抱え込まず管理会社に相談することが大切です。
管理会社は住民のトラブルを解決するためにも存在しています。何かあっても直接相手に怒鳴り込むようなことは絶対にせず、管理会社に仲裁に入ってもらい、落ち着いて対処するようにしてください。
ここまで、賃貸物件の騒音トラブルについて解説してきました。
騒音トラブルにおいては、誰もが被害者にも加害者にもなり得ます。トラブルなく快適に暮らせるよう、共同生活のルールをしっかり守ることを心がけましょう。