賃貸物件で水漏れ!対処法は?費用は誰が払うの?
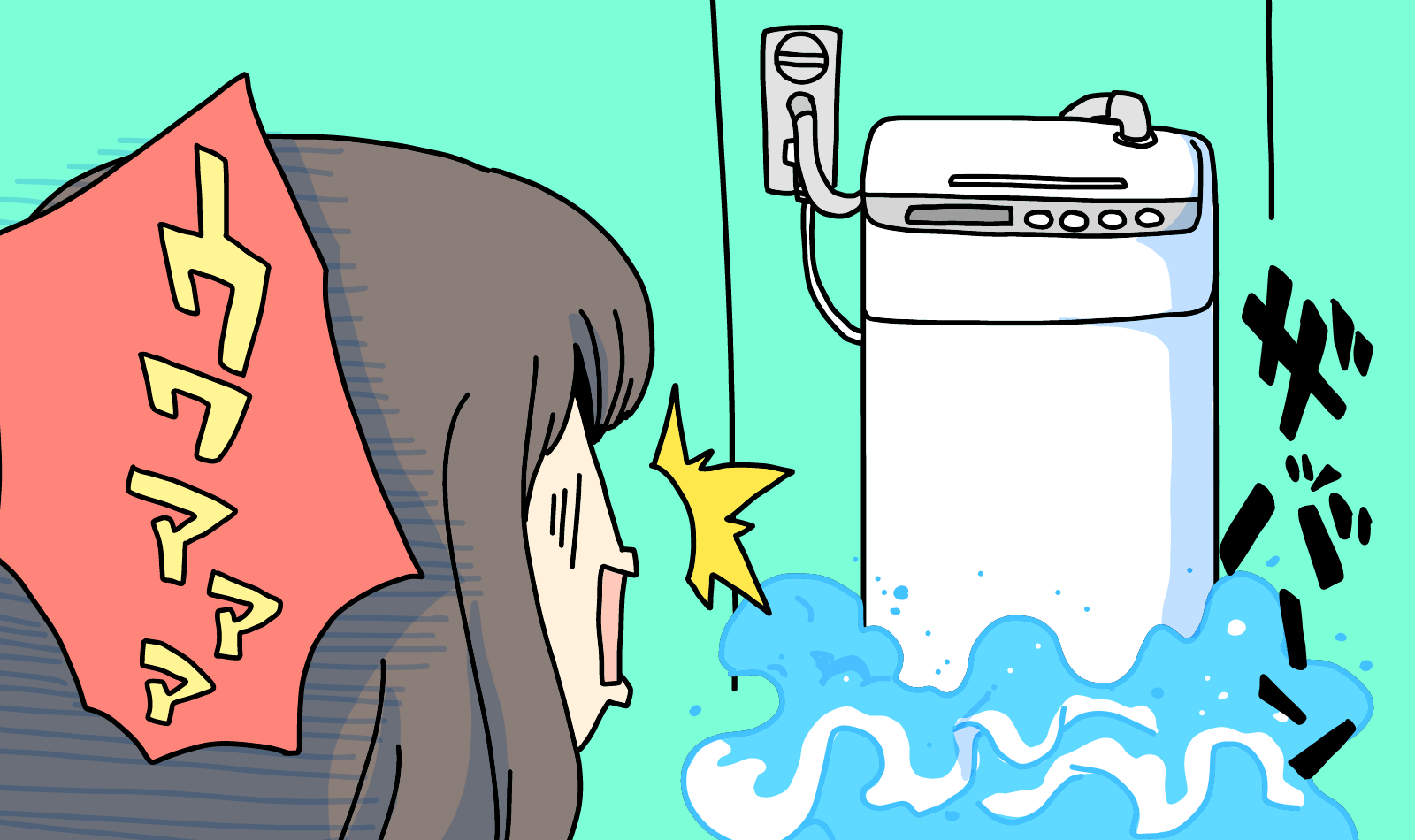
賃貸物件を借りる際、借主(部屋を借りている人)は「火災保険」に加入します。
借主が加入する火災保険は、基本的には「家財」であり、「建物」については貸主(部屋を貸している人)が火災保険をかけます。
いざというときのため、賃貸物件の借主も火災保険に関する知識は必要です。そこでこの記事では、「賃貸の火災保険」についてわかりやすく解説していきます。
記事の目次
木造住宅の多い日本では失火責任法という法律により、他人からのもらい火で家が焼けても、出火元に重大な過失がない限り、原因者に賠償請求ができないことになっています。
つまり、隣の部屋の住人や近隣住民の失火(過失によって起こした火事)が原因で家が焼けても「お金を払ってくれ」とは言えないということです。
そこで、自分の失火から資産を守るのと同時に、他人からの失火に対しても資産を守るために、火災保険に加入する必要があります。
火災保険の対象は、「建物」と「家財」の2つです。
このうち、建物に関しては貸主が加入し、家財に関しては借主が加入します。家財は、テレビや冷蔵庫といった家電製品から、リビングセットや洋服ダンスといった家具類、衣類などの建物内に収容されている生活用品全般が対象です。
なお、地震保険と火災保険は異なります。
地震保険とは、「地震保険に関する法律」により国と損害保険会社が共同で運営する保険です。地震保険のみ加入することはできず、地震保険に加入するには火災保険に加入することが前提となっています。
借主が入る火災保険には、「家財補償」の他、「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」も付けるのが一般的です。
家財補償とは、建物内の生活用品全般に対してかける火災保険です。
火災保険は、必ずしも火災に対する補償だけでなく、選択するオプションによって以下のような損害に対しても補償を受けることができます。
例えば、落雷の影響による過電流でパソコンが故障してしまった場合も家財補償の対象です。
ただし、補償範囲を増やしていけば、その分保険料は値上がりします。自分にとって適切な補償範囲で選ぶことをおすすめします。
火災保険は、燃えにくい構造の建物ほど保険料が低く、燃えやすい構造の建物ほど保険料が高くなる傾向にあります。
火災保険では、建物構造を以下の3つに分類しています。
| 構造 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|
| M構造 (マンション構造) |
保険料は最も安い | ||
| T構造 (耐火構造) |
保険料は標準的 | ||
| H構造 (非耐火構造) |
保険料は最も高い |
家財補償のみの場合、1年間の保険料の目安は以下の通りです。
| 構造 | 相場 | ||
|---|---|---|---|
| M構造 (マンション構造) |
2,000円~6,000円程度 | ||
| T構造 (耐火構造) |
4,000円~6,000円程度 | ||
| H構造 (非耐火構造) |
10,000円~15,000円程度 |
ただし、次節で紹介する「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」も付けると、年間保険料はプラス3,000円~5,000円程度アップします。
賃貸住宅の火災保険では、通常、借家人賠償責任保険にも加入します。借家人賠償責任保険とは、簡単に言うと「貸主に対する保険」です。
賃貸住宅では、例えば借主の煙草の消し忘れなど、故意または重大な過失が原因で、部屋や建物が焼損してしまうことがあります。 この場合、一旦は貸主の火災保険によって貸主は補償されますが、貸主に対して保険金を支払った保険会社が借主に損害賠償を請求してくることがあります。 この貸主側からの損害賠償請求に備えるのが、借家人賠償責任保険です。
賃貸住宅では、借家人賠償責任保険にも加入することが通常ですので、忘れずに加入するようにしましょう。
アパートやマンションでは、階下に水漏れの被害を与えてしまうことがあります。このような階下の水漏れの被害などに備えるのが、個人賠償責任保険です。
一戸建てのように独立している物件であれば加入は不要ですが、集合住宅を借りる場合には、個人賠償責任保険も加入します。
家財に関しては、各保険会社かける保険金額の目安を示しています。損保ジャパン日本興亜が示している家財の目安(https://www.sjnk.co.jp/kinsurance/habitation/sumai/house/pop1/)を示すと、以下の通りです。
| 家族構成 | 2名 大人のみ |
3名 大人2名 子ども1名 |
4名 大人2名 子ども2名 |
5名 大人2名 子ども3名 |
独身世帯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯主の 年齢 |
||||||
| 25歳前後 | 490万円 | 580万円 | 670万円 | 760万円 | 300万円 | |
| 30歳前後 | 700万円 | 790万円 | 880万円 | 970万円 | ||
| 35歳前後 | 920万円 | 1,000万円 | 1,090万円 | 1,180万円 | ||
| 40歳前後 | 1,130万円 | 1,220万円 | 1,310万円 | 1,390万円 | ||
| 45歳前後 | 1,340万円 | 1,430万円 | 1,520万円 | 1,610万円 | ||
| 50歳前後 (含以上) |
1,550万円 | 1,640万円 | 1,730万円 | 1,820万円 | ||
例えば、35歳前後の人で、大人2人子ども1人の家族構成であれば、1,000万円程度の家財を持っていることになります。家財保険を設定する際は、上記のような目安を参考にするのが一般的です。
火災保険の加入は義務ではありません。
ただし、火災保険は貸主のためではなく自分のために入るものです。自分を守るためにも、加入することをお勧めします。
失火責任法により他人からのもらい火で被害にあった場合でも、失火原因者に損害賠償を請求できないことになっています。
逆に自分が失火の原因となっても、重大な過失がない限り他人から損害賠償請求がされることはありません。
賃貸契約の際に、不動産会社から保険会社を紹介されます。
ただし、必ずしも不動産会社から紹介された保険会社に加入しなければならないわけではありません。
補償対象や範囲、金額などを確認して、自分に合った火災保険を選ぶことをおすすめします。
引越しをする場合、以前の住まいで火災保険に加入しているときは、そちらの火災保険の解約が必要です。
以前の火災保険が長期一括契約をしている場合、解約すると残存期間分の保険料が解約返戻金として戻ってきます。保険の解約は引越しによって自動で行われるものではないので、忘れずに自分で行うようにしてください。
借主が「故意または重大な過失」により出火させてしまった場合には、貸主に対して損害賠償責任を負います。理由としては、借主は善管注意義務と原状回復義務の2つの義務を負っているからです。
善管注意義務:貸主に対し賃貸住宅をしっかり管理しなければならない義務
原状回復義務:退去時に原状に回復して返還しなければならない義務
貸主への損害賠償は借家人賠償責任保険によって対処することになります。
火災保険は、借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険に加入していなければ、自分の家財のみが補償対象となります。
家財とは、建物内に収容されている生活用品全般です。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、美術品は明記物件として申込書に明記しないと保証されない場合があります。一方で、自動車や動植物、パソコン内のデータなどは補償対象とはなりません。
また、地震が原因で生じた火災の場合には、地震保険に入っていないと補償されないことになります。地震による延焼に備えるには、別途、地震保険の加入が必要です。
サラリーマンなどの給与所得者は、年末に年末調整を行います。年末調整では、各種保険料を所得から控除でき、所得税を節税することができます。
ただし、残念ながら火災保険だけでは所得控除の対象とはなりません。以前は火災保険も所得控除の対象でしたが、2007年1月1日以降は対象外となっています。
地震保険にも加入していると、地震保険の部分だけ年末調整で所得控除の対象とすることが可能です。地震保険の保険料はやや割高ですが、加入すれば所得控除の対象となるというメリットはあります。
火災保険に加入する際は、よくわからないまま保険に加入しないことが重要です。
例えば、明らかに家財が少ないのに標準的な家財の目安に基づいて保険金額を決めてしまうと、割高な保険に入ることになります。また、一戸建てやアパートの1階を借りるのに個人賠償責任保険も入ってしまうのはもったいない選択といえます。
さらにマンションの高層階の場合、台風や豪雨に対する水災や風災はあまり必要性が高くありません。
保険の範囲は十分に精査して、適切な内容の保険に入るようにしましょう。
保険は重複して保険に加入しないようにすることも必要です。
まず、引越し前の火災保険は解約することが基本となります。
また、オプションを選択する際、内容が重複するような保険も避けるようにしましょう。例えば火災保険の中には、地震による火災も保証してくれる地震火災費用特約があります。
地震火災費用特約は、地震による火災で火災保険金額の5%(上限300万円)を補償する保険で、地震保険とは異なります。
地震保険にも加入する場合には、内容が重複する地震火災費用特約は不要です。
オプションを選ぶ際は重複内容についてもしっかり確認した上で加入するようにしましょう。
ここまで、「賃貸住宅の火災保険」について解説してきました。
家を借りる際は、借主も家財の火災保険に入るのが基本です。内容をよく精査し、適切な範囲で保険に加入するようにしましょう。