不動産投資の利回りとは?表面利回りと実質利回りの違いを徹底解説
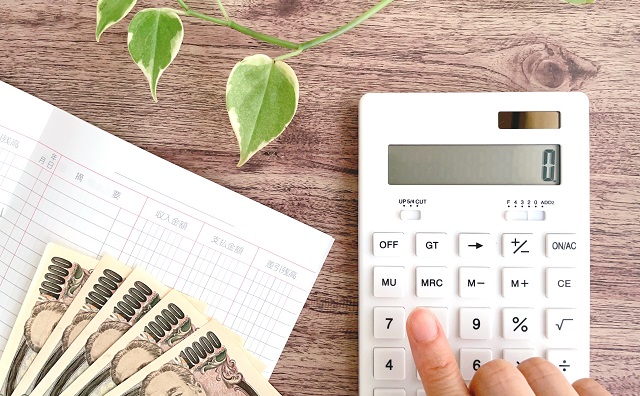
表面利回りは一見魅力的な数字を示すことがありますが、実際の収益性を正確に反映しているとは限りません。一方、実質利回りはさまざまな経費を考慮した、より現実的な収益指標のことです。
本記事では、表面利回りと実質利回りの特徴や計算方法などを詳しく解説します。不動産投資をこれから始める方は、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
利回りとは

不動産投資での利回りは、投資金額に対する収益の割合を示す重要な指標です。一般的に高い利回りが望ましいとされますが、実際にはそれほど単純ではありません。利回りにはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
ここでは、主に表面利回りと実質利回りの違い、想定利回りなどを詳しく解説します。それぞれの利回りの特徴を理解することで、より賢明な投資判断ができるでしょう。
表面利回りとは
表面利回りは、年間の家賃収入を物件価格で割った数値です。表面利回りは、不動産投資の世界でよく使われる指標の一つで、計算が簡単で直感的に理解しやすい点が大きな特徴です。
多くの不動産広告やポータルサイトでは、表面利回りの数値が使用されています。例えば、ある投資物件の表面利回りが8%、別の投資物件が6%だった場合、一見すると前者のほうが収益性が高いように見えないでしょうか?
しかし、表面利回りには大きな欠点があります。それは、税金や管理費、修繕費などの経費を一切考慮していないことです。そのため、現実的な収益性を反映しているとはいえません。投資判断をおこなう際には、表面利回りのデメリットを十分に理解しておく必要があります。
表面利回りの計算方法は以下のとおりです。
年間家賃収入 ÷ 物件購入費用 × 100 = 表面利回り(%)
計算方法はいたって簡単なので、計算が苦手な方でも計算しやすいでしょう。
実質利回りとは
実質利回りは、年間諸経費と物件購入時の諸経費を考慮に入れた、表面利回りよりも現実的な指標のことです。実質利回りは、実際の投資効率を知るうえで重要なポイントとなります。
実質利回りは、初期費用やランニングコストを含めて計算するため、投資家が手にする実際の収益を、より正確に把握が可能。例えば、固定資産税や管理費、修繕積立金、空室損失などのコストをすべて考慮に入れるので、より現実的な収益予測ができます。
ただし、実質利回りには課題も。一般的に公開されている情報は、表面利回りしか記載されていないことが多く、投資家自身が各種コストを調べて計算する必要があります。また、将来の修繕費用や空室率の予測は難しく、不確実性がともなうことも理解しておかなければなりません。
それでも、実質利回りを算出することで、投資物件の現実的な収益性を確認できるため、不動産投資の失敗リスクを減らせるでしょう。特に複数の投資物件を比較する際には、実質利回りを基準にすることで、より適切な投資物件の選択が可能になります。
実質利回りの計算方法は以下のとおりです。
(年間家賃収入 - 年間諸経費)÷(物件購入費用 + 物件購入時諸経費)× 100 = 実質利回り(%)
実質利回りの計算方法は、表面利回りの計算方法より複雑になりますが、一つひとつ確認しながらおこないましょう。
想定利回りとは
想定利回りは、投資物件が満室状態であることを前提に算出する利回りです。想定利回りは、投資物件の潜在的な収益性を示す指標として使用される点が特徴の一つ。
不動産広告や販促資料で使用されることもありますが、その場合、基本的には「想定」という文言が表記されます。これは、実際の運用では、必ずしもこの利回りを達成できるとは限らないことを表しています。
想定利回りの計算方法は以下のとおりです。
満室時の年間家賃収入 ÷ 物件購入費用 × 100 = 想定利回り(%)
想定利回りは、投資物件の収益性に関するポテンシャルを把握する際に役立ちますが、現実的な収益予測としては、役立たない可能性があります。それは、実際の運用では、空室期間や家賃の変動、予期せぬ修繕費用などが発生する可能性が高いためです。
投資家は、想定利回りを参考にしつつも、より詳細な見積もりをおこなうようにしましょう。例えば、平均的な空室率を考慮に入れた計算や、地域の賃貸市場動向を踏まえた予測をおこなうことで、より現実的な収益予測が可能になるでしょう。
不動産投資にかかるコスト

不動産投資には、物件購入費用以外にも、さまざまなコストが発生します。不動産投資にかかるコストは大きく分けて、初期費用とランニングコストの2種類です。
不動産投資における初期費用
初期費用には、不動産仲介手数料や司法書士への報酬料、登記費用、不動産投資ローン事務手数料、火災保険料、不動産取得税などが含まれます。初期費用は物件購入時に発生する費用で、合計すると物件価格の数%から10%程度になることも珍しくありません。
不動産投資におけるランニングコスト
ランニングコストは投資物件を保有し続ける限り、継続的に発生する費用です。例えば、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金、不動産投資ローンの利息など。ランニングコストは毎月または毎年発生し、収益に対して長期的に大きな影響を与えます。
特に注意が必要なのは、突発的な修繕やリフォームに備えた資金準備です。建物の経年劣化にともなう大規模修繕や、設備のメンテナンスなどは避けられません。上記の費用に備えて、十分な積立金や自己資金を用意しておくことが重要です。
また、空室期間中の収入減少も考慮に入れる必要があります。地域や物件タイプによって異なりますが、年間1〜2カ月程度の空室を想定しておくことが一般的。
上記のコストを事前に把握し、適切に管理することで、より安定した不動産投資が可能になります。他にも、コストを削減できる部分がないかを探ることで、収益性を向上させられるでしょう。
不動産投資で利回り評価をする際の注意点

不動産投資において利回りを評価する際には、いくつかの重要な注意点があります。
高利回りに惑わされない
高利回りが必ずしも優良物件を意味するわけではありません。魅力的な高利回りの裏には、さまざまな要因が隠れている可能性があります。
例えば、相場より高い家賃設定や安い物件価格には、築年数が古い、メンテナンス不良、エリア需要が低いなど、何らかの問題がある可能性が高いです。
また、一時的に高い家賃で入居者を集め、高利回りに見せかけ、実際は長期的な入居が見込めないケースも。
このような投資物件は、短期的には高い利回りを示すかもしれません。しかし、長期的には収益性が低下したり、大規模な修繕が必要になったりする可能性があります。そのため、利回りだけでなく、投資物件の質や立地、将来性なども含め、総合的に判断することが重要です。
利回りは時間とともに変動する
利回りは時間とともに変動することも、頭に入れておかなければなりません。建物の劣化や周辺環境の変化により、当初の高利回りが維持できない可能性があります。
例えば、新しい競合物件の登場や地域の人口減少などにより、家賃が下落したり、空室率が上昇したりする可能性があります。
上記のリスクに対処するためには、定期的なメンテナンスやリフォーム、適切な家賃設定などの対策を取ることが重要です。また、投資物件の魅力を維持・向上させるための投資も必要になるでしょう。
市場動向や経済情勢の変化をこまめにチェックする
市場動向や経済情勢の変化にも、注意を払う必要があります。金利の変動や税制の改正、不動産市場の状況なども、投資物件の利回りに影響を与える可能性があります。
市場動向や経済情勢をこまめにチェックし、何らかのトラブルが起きても、迅速に対応できるように準備を整えておきましょう。
実質利回りには統一された計算方法が存在しない
実質利回りは現実的な収益性を示すために重要ですが、課題もあります。それは、業界内で統一された計算方法が存在しないこと。
実質利回りの計算には、さまざまな要素を考慮する必要があります。例えば、投資家の属性(個人か法人か、資金調達方法など)や投資物件の情報(築年数、立地、設備の状態など)によって、考慮すべきコストや予測値が大きく変動します。
そのため、不動産会社が実質利回りを明確に提示することはとても難しいのです。仮に提示したとしても、計算の結果がすべての投資家に当てはまるわけではありません。
この課題に対処するためにも、投資家自身が自らの状況に応じて、実質利回りを算出する必要があります。自分に合わせた実質利回りを計算するためには、詳細な市場調査や投資物件の細かな分析、将来のコストや収入の予測などが必要です。
また、実質利回りの計算には、不確実な要素も多く含まれます。例えば、将来の空室率や家賃の変動、修繕費の発生タイミングなどは、正確に予測することが難しいもの。
それでも、可能な限り正確な実質利回りを算出することは、投資判断をおこなううえで重要です。表面利回りだけでなく、実質利回りもあわせて検討することで、より現実的な収益予測が可能になり、リスクの高い不動産投資を避けられるでしょう。
不動産投資における実質利回りの理想と最低基準

不動産投資における実質利回りの目安は、投資物件の種類や築年数によって異なります。ここからは、実質利回りの理想的な目安と最低基準を解説します。
新築物件の実質利回り
新築物件の場合、理想的な実質利回りは5%以上とされています。最低ラインは3%程度です。
上記は、不動産投資ローンの金利相場が2〜5%台であることが考慮されています。
不動産投資の基本的な原則として、不動産投資ローンの金利を上回る実質利回りを確保することが重要です。ただし、低金利融資を受けられる場合、最低ライン以下でも黒字化の可能性はあります。
中古物件の実質利回り
中古物件は通常、新築よりも高い実質利回りが期待できます。築年数が古い物件は購入価格が安いため、表面利回りは比較的高めです。しかし、築年数が古いほど、修繕箇所が多かったり、リフォーム費用がかかったりするため、実質利回りの面ではそれほど高くない傾向にあります。
一般的に、新築より1%程度高い実質利回りを想定し、理想は6%以上、最低ラインは4%程度とされます。
ただし、中古物件の利回りは投資物件ごとに大きく差があり、10〜20%を超えることもあるため、競合物件との比較が不可欠です。
不動産投資で実質利回りを低下させる要因

不動産投資において実質利回りを低下させる主な要因は以下の3つです。
旧耐震基準の投資物件
旧耐震基準とは、建築基準法が制定された1950年~1981年5月31日までに申請を受けた建物に適用された耐震基準のことです。震度5程度で、家屋が倒壊しないことを基準に、建物自重の20%にあたる震度でも建材が損傷を受けていないことが条件とされています。
しかし、1981年に法が改正され、新耐震基準が設けられました。新耐震基準では震度レベルが6~7に引き上げられています。
耐震工事には高額な費用がかかり、地震保険料も高くなります。保険料や工事費用は利回りを大きく圧迫する可能性があるため、投資物件に適用されている耐震基準を確認しておきましょう。
管理状態の悪さ
適切な管理がされていない投資物件は、修繕費用の増加や空室率の上昇につながるでしょう。修繕費用の増加や空室による家賃収入の減少は、収益を減少させ、実質利回りも低下させてしまいます。
立地条件の悪さ
交通の便が悪い場所や水害リスクの高い地域では、入居者の確保が困難なケースも。空室期間が長くなれば、その分だけ実質利回りは低下します。
不動産投資で高実質利回り物件を選定するポイント

高い実質利回りを実現するには、入居率の向上や家賃の上昇、経費の削減が重要なポイントです。ここからは、高い実質利回り物件を選ぶポイントを解説します。
賃貸需要の高いエリアを選ぶ
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会の「2023年住宅居住白書」によると、入居者が重視するポイントは賃料(48.0%)、周辺・生活環境(45.8%)、交通の利便性(38.5%)です。
これらを踏まえると、最寄り駅から徒歩10分以内で、近隣に公園や人気の商業施設がある地域は、賃貸需要が高いといえます。
人気設備が充実している
入居率向上と家賃上昇には、人気の設備の設置が重要です。高い魅力を持つ物件は、高い家賃で貸すことができたり、長い間の空室を防ぐことにもつながります。
不動産情報サイト アットホームの「不動産のプロに聞いた!「2024年上半期 問合せが増えた設備~購入編~」ランキング」によると、マンションでは駐車場、エレベーター、宅配ボックスが上位を占めました。
一方、一戸建てでは駐車場、トイレ2カ所以上、システムキッチンが人気でした。
マンション、一戸建てともに、駐車場が人気1位という結果に。ただし、設備の人気はトレンドにより変化するため、常に最新の情報を把握することが大切です。
適切な物件管理をおこなう
適切な物件管理をおこなうことも重要なポイントです。投資物件の管理に問題があると、入居者同士や管理会社と入居者トラブルが起きたり、騒音・害虫問題などが起きやすくなります。投資物件自体の管理だけではなく、トラブルが起きた際に迅速に対応できるかが重要でしょう。管理不備による退去を防ぐため、管理会社との連携を強化したり、必要に応じて管理会社を変えたりなど、対策を検討してみてください。
また、投資物件の購入後も利回りを上げる方法はあります。例えば、入居者の初期費用の負担を軽減させる方法です。敷金や礼金、初月家賃を減額することで、入居のハードルを下げ、入居率を向上させる効果が期待できるでしょう。
さらに、リフォームも効果的です。特に水回りの改善は、入居率アップに大きく貢献します。築古物件でも、きれいにリフォームされていれば、入居者の関心を引きやすくなるでしょう。上記の戦略を適切に組み合わせることで、不動産投資の実質利回りを向上させることが可能です。常に市場動向をチェックし、柔軟に対応することが成功の鍵となります。
まとめ
表面利回りと実質利回りは、不動産投資の収益性を評価するうえで欠かせない指標です。表面利回りは簡易的な目安として便利ですが、実際の投資判断には実質利回りも欠かせません。
経費や空室率、将来の修繕費用なども考慮した実質利回りを正確に算出することで、より現実的な投資計画を立てられるでしょう。
ただし、利回りだけでなく、投資物件の立地、将来性、市場動向なども総合的に判断することが重要。不動産投資の成功には、表面的な数字に惑わされることなく、実質的な収益性を見極める目を養うことが求められるのです。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







