公務員は不動産投資できる?副業でも問題ないとされる基準や注意点を解説

記事の目次
公務員は副業として不動産投資できる?

公務員は原則として副業が制限されています。国家公務員は、国家公務員法第96条第1項で次のように定められているからです。
そして、守るべき規則として、「私企業からの隔離」「他の事業または事務の関与制限」の2つが定められています。本章では、国家公務員と地方公務員に分けて守るべき規則を解説します。
私企業からの隔離
「私企業からの隔離」は国家公務員法第103条で定められています。どのような規定なのか、詳しく見てみましょう。
引用:国家公務員法第103条
国家公務員は国民のために働く立場であり、利益を追求する企業の役員の立場とは相反する関係にあるため、副業が制限されます。なお、制限がされているのは「営利企業の役員兼業」と「自営兼業」の2種類です。しかし、第2項では次のように定められています。
つまり、所属する機関の首長などに承認を得れば、副業は問題ありません。「自営兼業」の例として、不動産投資や農業などが挙げられます。
他の事業または事務の関与制限
「他の事業または事務の関与制限」は、国家公務員法の第104条で定められています。詳しく見ていきましょう。
引用:国家公務員法第104条
参考:内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について(概要)」(PDF)
営利企業などの従事制限
「営利企業などの従事制限」は、地方公務員法の第38条で定められています。内容は国家公務員法の第103条・第104条と同様です。地方公務員の「役員兼業」と「自営兼業」、「事業や事務に従事して報酬を得ること」を制限しています。
これまで見てきたように、公務員の方は国民のために働く立場であるため、副業が制限されています。ただし、禁止されているわけではなく、所属する機関の長の承認を得れば可能です。また、不動産投資においては、細かく基準が定められているため、次章で解説します。
公務員の不動産投資が副業として問題ないと判断される基準

公務員の方の副業は、国家公務員法や地方公務員法によって制限されています。また、不動産投資においては、国家公務員法で次の3つの基準が定められており、これらを満たすと副業にあたるとされます。つまり、本章で解説する基準以下であれば、副業にはあたりません。事前によく確認しておきましょう。
不動産投資の規模が5棟10室未満である
1つ目の基準は、不動産投資の規模が5棟10室未満であることです。これは人事院規則14-8により、副業にあたる基準が次のように定められているためです。
- 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること
- 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること
独立家屋とは一戸建てのことを指し、独立家屋以外の建物とはアパートやマンションのことを指します。上記の2つが同列とされていることから、アパートやマンションの2室を一戸建て1棟として計算します。例えば、不動産投資で一戸建てを3棟、マンションの4室を所有したとしましょう。マンションは一戸建てに換算すると2棟となり、合わせると5棟以上になるため、自営兼業となります。もし、アパートやマンションの9室のみの場合は副業にあたらないため、問題ありません。
不動産投資による収入が年間500万円未満である
不動産投資による収入が年間500万円未満であれば、副業にはあたりません。これも先ほどと同様、人事院規則14-8で次のように定められています。
つまり、家賃収入が年間500万円以上の場合、副業とみなされます。なおこの収入は、経費を引いた金額ではありません。例えば、家賃が月8万円のワンルームマンションを所有した場合をシミュレーションしてみましょう。
<1室あたりの年間の家賃収入>
8万円×12カ月=96万円
<5室所有した場合の年間の家賃収入>
96万円×5室=480万円
<6室所有した場合の年間の家賃収入>
96万円×6室=576万円
5室の場合は500万円を下回っていますが、6室の場合は超えてしまいました。この場合、6室所有すると副業とみなされてしまいます。
管理業務を委託している
公務員の方が不動産投資をおこなう際は、管理業務を委託しなければなりません。これは先述したように、職務の遂行に専念しなければならないと国家公務員法で定められているためです。さらに、人事院規則では次のように定められています。
公務員に不動産投資をおすすめする理由
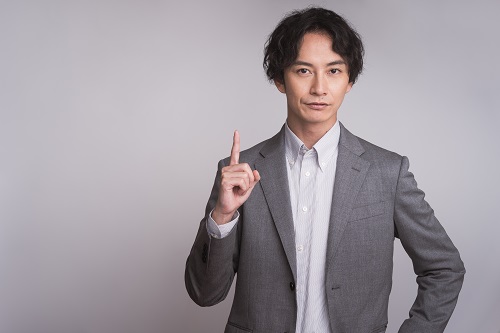
不動産投資は、基本的に不動産投資ローンを利用しておこないます。高額な借り入れですが、公務員の方はいろいろな面で有利になります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
不動産投資ローンの審査が通りやすい
不動産投資をおすすめする理由の一つ目は、公務員の方は不動産投資ローンの審査に通りやすい点です。公務員の方は民間企業と比べて、収入が安定しています。これは給与が規定に基づいて決められており、景気の影響を受けにくいからです。また、国家公務員法や地方公務員法によって、身分が保証されており、解雇される心配がありません。不動産投資ローンの審査では、借り手の返済能力を見るため、収入が安定している公務員の方は有利になるでしょう。
本業を妨げずに不労所得が得られる
本業を妨げることなく不労所得を得られる点も、公務員の方に不動産投資が推奨される理由の一つです。先述したように、公務員の方は職務に専念しなければならないため、本来であれば不動産投資はできません。しかし、管理業務を委託し、本業に専念できる環境を整えれば不動産投資をおこなうことが可能です。
不動産投資の管理業務は、主に以下の3つに分けられます。
- 賃貸仲介:入居者の募集や賃貸契約など、部屋を探している人と物件をマッチングさせる業務
- 入居者対応:家賃の回収やクレーム対応といった業務
- 建物管理:設備の管理・メンテナンスといった業務
本業をしながら、これらの管理業務を自分で担うのは難しいでしょう。しかし、信頼できる不動産管理会社に委託することで、本業に専念しつつ不労所得を得ることが可能です。
相続税対策になる
公務員の方に限った話ではありませんが、不動産投資は相続税対策になります。これは、不動産の相続税評価額が現金と比べて低く評価されるためです。例えば、現金5,000万円の場合、相続税評価額はそのまま5,000万円となります。しかし、不動産の相続税評価額は、土地は市場価格の80%程度、建物は市場価格の70%程度とされています。土地3,000万円、建物2,000万円を購入した場合の相続税評価額を見てみましょう。
<土地の相続税評価額>
3,000万円×80%=2,400万円
<建物の相続税評価額>
2,000万円×70%=1,400万円
<土地と建物の相続税評価額の合計>
2,400万円+1,400万円=3,800万円
公務員が一定規模を超えて不動産投資をする際の手順

先程、公務員の方が副業で不動産投資をおこなっても問題ないと判断される基準を解説しました。しかしなかには、「規模を大きくしたい」「家賃収入をさらに増やしたい」と考える方もいるでしょう。副業とみなされるには、所属している機関の首長などの許可を得なければなりません。本章では具体的な手順を解説します。
一定規模を超えて不動産投資をするための手順
地方公務員の方は、不動産投資に関する副業の規定がないか、確認しましょう。禁止されているようであれば不動産投資はできません。就業規則に違反すると、処分を受ける可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。
次に申請に必要な書類を集めます。具体的な書類については後述しますが、発行を依頼しなければならないものもあります。一部の書類はオンラインで請求できるため、うまく活用しましょう。
書類が揃ったら、所属している機関の首長などに申請します。許可が下りるまでに時間がかかる可能性もあるため、早めに行動することが望ましいです。
申請に必要な書類
国家公務員の方は、承認を申請する場合には、人事院規則で定められた以下の書類を提出する必要があります。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 自営兼業承認申請書 (不動産等賃貸関係) |
人事院ホームページ |
| 不動産登記簿謄本 | 法務局 |
| 賃貸契約書の写し | 不動産管理会社 |
| 管理業務を委託する契約書の写し | 不動産管理会社 |
| 人事記録の写し | 所属している機関 |
それぞれどういった書類なのか、詳しく見ていきましょう。
自営兼業承認申請書
自営兼業(副業)の申請をするための書類です。申請書には、投資対象の物件数や床面積、予定の年間家賃収入額などを記載します。
不動産登記簿謄本
不動産登記簿謄本とは、土地や建物の所有者の氏名や不動産の権利関係などが記載されている書類です。次の3つの請求方法があります。
- オンラインで請求する
- 法務局で請求する
- 郵送で請求する
請求方法によって、手数料が違うため注意しましょう。
| 請求方法 | 受け取り方法 | 手数料 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| オンライン | 窓口 | 480円 | 平日8時30分〜21時まで |
| 郵送 | 500円 | ||
| 法務局 | 600円 | 平日9時〜17時まで | |
平日に時間を確保することが難しい場合は、オンラインでの請求が便利です。オンラインサービスは、平日の21時まで利用可能なので、ぜひ活用しましょう。
賃貸借契約書
賃貸借契約書とは、所有している物件を他者に貸し出す際に、貸主と借主の間で締結する契約書です。不動産管理会社によって発行されます。
管理委託契約書
参考:国土交通省「 賃貸住宅標準管理委託契約書」
繰り返しますが、ここで取り上げたのは国家公務員の場合です。なお、神戸市では、不動産賃貸や太陽光電気の販売について具体的な基準や申請書が設けられています。所属している地方公共団体がどのような基準を設けているか、事前に確認しておきましょう。
申請するタイミング
一定規模を超えて不動産投資をおこないたい場合は、いつ申請すればいいのでしょうか。人事院規則では、申請するタイミングは定められていません。しかし、早めに申請しておいたほうが安心でしょう。公共財団法人東京市町村自治調査会「公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書〜職員のスキルアップ、人材戦略、地域貢献の好循環を目指して〜」によると、2019年には、首長の許可なくアパートを経営し、年間約600万円の家賃収入を得ていた公務員が減給の処分を受けています。このような事態を避けるためにも、許可が下りてから、売買契約などの本格的な活動を開始しましょう。
公務員が不動産投資をする際の注意点

公務員の方が不動産投資をする際には、気をつけなければならない点があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
就業規則に違反しないようにする
公務員の方が不動産投資をおこなう際には、就業規則に違反しないようにすることが大前提です。これまで解説してきたように、公務員の方は職務に専念する義務があります。不動産投資によって、本業が疎かにならないようにしなければなりません。また、一定規模を超えておこなう場合には、所属する機関の首長などに許可を取る必要があります。
先述したように規則を守らなかったために処分を受けた例もあります。さらに、地方公共団体によっては、独自の基準を設けられている場合もあるため、必ず確認しましょう。
無理のない返済ができる範囲でおこなう
公務員の方に限りませんが、不動産投資は無理のない返済ができる範囲でおこないましょう。特に公務員の方の場合、収入が安定していることから、借入可能額が多くなる傾向があります。たとえ低金利であっても、借入額が多くなれば、月々の返済負担も重くなるでしょう。大切なのは、不動産投資ローンを借り入れることではなく、安定した家賃収入を得ながら、ローンを完済することです。そのためにも、無理なく返済ができる範囲でおこないましょう。投資をおこなう前に、想定される家賃収入や完済時の年齢など、事前にシミュレーションをすることが大切です。
確定申告を忘れずにおこなう
不動産投資をおこない、年間20万円を超える所得を得た場合には、必ず確定申告をしましょう。通常、公務員の方は源泉徴収がおこなわれているため、確定申告をする必要はありません。しかし、給与以外の所得が20万円を超えた時には、確定申告が必要です。なお、この所得は家賃収入から固定資産税や減価償却費などの経費を差し引いた金額となります。確定申告の時期は、毎年2月16日〜3月15日で、申告だけでなく納税も同時期となっています。申告に必要な書類は多いため、余裕を持って準備するようにしましょう。
信頼できる不動産管理会社を選ぶ
公務員の方が不動産投資をおこなう際は、本業に影響が出ないよう、管理業務を不動産管理会社に委託しなければなりません。先述したように、管理業務は3つに分かれており、安定した家賃収入を得るためにはどれも欠かせません。また、所属している部署によっては、多忙になる時期もあるでしょう。他にも災害が発生した場合、突発的に忙しくなる可能性もあります。そういった時にも、信頼できる不動産管理会社に委託していれば、本業に専念できるでしょう。
まとめ
この記事では、公務員の方が不動産投資をおこなっても問題ないのかについて解説しました。国家公務員法や地方公務員法により、一定の制限が設けられていますが、副業が完全に禁止されているわけではありません。国家公務員の方の場合、人事院規則で定められている基準以下であれば、許可を得なくても不動産投資は可能です。しかし、一定規模を超えておこなう場合には、所属している機関の首長などに許可を得る必要があります。
他にも、公務員の方は国民のために働く立場であることから、本業に支障が出ないように管理業務を委託しなければなりません。管理業務は多岐に渡るため、信頼できる不動産管理会社を見つけ、不動産投資で安定した収入を得ましょう。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ



