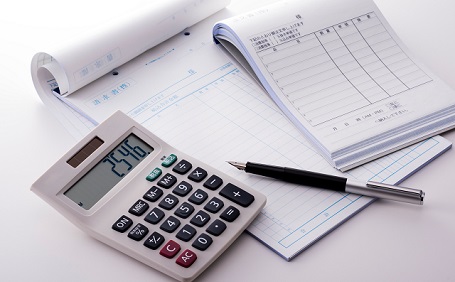不動産投資は節税にならない?言われる理由や節税の仕組みを解説!年収別シミュレーションも!

記事の目次
不動産投資が節税になる仕組み

不動産投資をすると「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」「法人税」の4つにおいて、節税効果が期待できます。どのような仕組みなのか、税金の種類ごとに見ていきましょう。
所得税・住民税
不動産投資をすると、所得税と住民税を節税できる可能性があります。それは「減価償却」と「損益通算」の2点があるからです。まず減価償却とは、事業に用いる資産の購入費用を、耐用年数に応じて経費として計上する処理のこと。不動産は長期間に渡って使用できる資産であるため、この減価償却を活用できます。経費として計上すると、所得が圧縮できるため、結果として所得税と住民税が抑えられるという仕組みです。
次に「損益通算」とは、赤字と利益を相殺すること。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じた赤字は、損益通算ができます。例えば、給与所得が750万円で、不動産所得が200万円の赤字だった場合、損益通算をすると所得は550万円となります。こちらも減価償却と同様、所得が圧縮されるため、所得税と住民税が抑えられます。
相続税
相続税も、不動産投資で節税が可能な税金です。相続税は預貯金や不動産など、金銭に見積もることができる財産が課税対象。不動産の場合、次の3つの理由から、税金を抑えられます。
- 相続税の計算のもととなる相続税評価額が低くなる
- 賃貸不動産は活用方法が限られるため、さらに相続税評価額が低くなる
- 小規模用宅地の特例を適用できる
それぞれ詳しくみていきましょう。
相続税の計算のもととなる相続税評価額が低くなる
例えば、現金7,000万円を相続する場合、相続税評価額は額面どおりの7,000万円となります。一方、不動産の場合は次のように相続税評価額が設定されます。
土地:固定資産税評価額の約80%
建物:固定資産税評価額の約70%
もし、土地が4,000万円、建物が3,000万円の不動産を相続する場合は次のように計算できます。
土地の相続税評価額
4,000万円 × 80% = 3,200万円
建物の相続税評価額
3,000万円 × 70% = 2,100万円
合計の相続税補評価額
3,200万円 + 2,100万円 = 5,300万円
現金を相続する場合と比較して、相続税評価額を1,700万円引き下げることができました。
賃貸不動産は活用方法が限られるため、さらに相続税評価額が低くなる
賃貸不動産の場合、他人に貸していることから活用方法が限られるため、さらに相続税評価額が下がります。具体的な計算式は次のとおりです。
-
貸家が建てられている土地の相続税評価額 = 更地の評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸家の相続税評価額 = 建物の固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
借地権割合とは、土地の値段のうち何割を借地が占めているかということ。地域によって異なりますが60〜70%が一般的です。借家権割合は一律30%と設定されています。賃貸割合とは、簡単にいうと入居率のこと。例えば、次の条件の場合の相続税評価額を計算してみましょう。
<条件>
更地の評価額:4,000万円
建物の固定資産税評価額:3,000万円
借地権割合:70%
賃貸割合:100%
貸家が建てられている土地の相続税評価額
4,000万円 ×(1 - 70% × 30% × 100%)= 3,160万円
貸家の相続税評価額
3,000万円 ×(1 - 30% × 100%)= 2,100万円
貸していない時と比較して、相続税評価額を40万円下げることができました。このように賃貸不動産は相続の際、相続税評価が下げられるため、節税が可能です。
小規模用宅地の特例を適用できる
小規模用宅地の特例とは、一定の要件を満たした土地について、通常の評価額から一定の割合を減額できる制度です。亡くなった方の土地に高額な相続税を課した場合、相続人が住んだり、事業を引き継いだりすることができなくなる可能性があります。そこで、一定の割合を減額することで、相続税の負担を減らし、相続人が相続した土地を活用できるようにするものです。賃貸に出されている土地の場合、200平方メートルまで50%減額できます。
贈与税
不動産投資は、贈与税でも節税が可能です。それは、所有している投資物件の価値が予想される時に「相続時精算課税制度」を活用して生前贈与した場合です。相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子どもや孫に対して財産を贈与した場合に選択できるもの。
贈与時に贈与税が2,500万円までは非課税となり、非課税枠を超える場合の贈与税は一律20%で計算します。そして、相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算するというものです。例えば、贈与財産が3,000万円の場合の贈与税を計算してみましょう。
3,000万円 - 2,500万円 = 500万円
500万円 × 20% = 100万円
この場合、贈与税が100万円となりました。ポイントは、相続時に課税価格として加算される金額が、贈与時の価格であるという点です。もし相続する際に価値が上がると考えられる場合は、生前贈与をすると、相続時の相続税を抑えられるでしょう。
法人税
不動産投資を法人としておこなう場合は、法人税の節税メリットが期待できます。個人の所得に対する税率は累進課税制度が採られており、所得が高いほど税率も上がっていきます。例えば、所得が4,000万円以上の場合、税率は45%。一方、法人の所得に対する税率は15%〜23.2%となっています。
不動産投資の所得が同じだった場合、法人のほうが税金を抑えられるでしょう。また法人の場合、赤字を10年間繰り越せるのもメリット。ただし、税務署に青色申告書を提出していること、継続して確定申告をおこなっていることが条件です。
不動産投資が節税にならないと言われる理由

不動産投資が節税になる仕組みを税金の種類ごとに解説しました。しかし一方で、「不動産投資は節税にならない」とも言われます。その理由はなぜなのかを見ていきましょう。
赤字でないと損益通算ができない
前章で、所得税と住民税で節税できる理由として「損益通算」を挙げました。先述したように、損益通算は赤字と利益を相殺することです。つまり、赤字が出ていなければ損益通算はできません。具体例を2つ見ていきましょう。
<例1>
給与所得:500万円
不動産所得:300万円の赤字
例1の場合、課税所得は以下のようになります。
500万円 - 300万円 = 200万円
<例2>
給与所得:500万円
不動産所得:200万円
例2の場合、課税所得は次のとおりです。
500万円 + 200万円 = 700万円
例1では不動産所得が赤字のため、課税所得が低くなり、税金も抑えられます。一方、例2では不動産所得が黒字のため、合算した所得700万円に対して税金がかかります。損益通算による節税は、不動産投資の収益が赤字である場合にできるものである点を理解しておきましょう。
節税効果は年々薄くなる
不動産投資の節税効果は年々薄くなる点も、「節税にならない」と言われる理由です。節税効果が薄くなる理由としては、次の3つが挙げられます。
- 不動産取得に関する経費は初年度のみかかる
- 減価償却期間が決まっている
- 不動産投資ローンの利息が減っていく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
不動産取得に関する経費は初年度のみかかる
不動産取得にかかる経費は、初年度のみとなります。具体的には次のようなものがあります。
- 頭金
- 仲介手数料
- 印紙代
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 融資事務手数料
- 融資保証料
初期費用は一般的に、物件価格の15%程度とされています。例えば、物件価格が4,000万円であれば600万円と大きな金額です。そのため、初年度は赤字になるケースが多く、節税効果も高くなります。しかし、翌年からはこれらの経費はかかりません。固定資産税など、経費に計上できる項目が少なくなるため、節税効果は低くなります。
減価償却できる期間が決まっている
減価償却できる期間が決まっている点も、節税効果が弱まる理由の1つです。減価償却できる期間である法定耐用年数と、減価償却費の計算に必要な償却率は建物の構造によって、以下のように決められています。
| 建物の構造 | 法定 耐用年数 |
償却率 |
|---|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 鉄筋コンクリート造(RC造) |
47年 | 0.022 |
| 金属造(4mmを超えるもの) | 34年 | 0.03 |
| 木造 | 22年 | 0.046 |
| 木骨モルタル造のもの | 20年 | 0.05 |
(2007年4月1日以降取得のもの)
参考:国税庁 減価償却資産の償却率表[PDF]
例えば、6,000万円の新築物件(金属造)を購入した場合の減価償却費を計算してみましょう。
計算式は次のとおりです。
- 減価償却費 = 物件価格 × 償却率
例の場合は下記のようになります。
6,000万円 × 0.030 = 180万円
この場合、34年間は180万円を減価償却費として計上できます。しかし、それ以後は計上できません。経費計上できるものが少なくなれば、節税効果は薄くなります。
不動産投資ローンの利息が減っていく
不動産投資ローンの利息は、経費として計上できます。不動産投資ローンの返済が進むと、利息も減っていくことになります。その分、経費計上できる金額も減っていくため、節税効果は弱まります。また、不動産投資ローンを元利均等返済している場合、デッドクロスに気をつけなければなりません。デッドクロスとは、不動産投資ローンの元金返済額が減価償却費を上回る状態のこと。元金返済額は経費の計上ができませんが、実際には支払わなければなりません。
反対に、減価償却費は実際には支出がありませんが、経費としては計上できます。デッドクロスになると、キャッシュフローが悪化しますが、税務上は黒字となり、所得税が多くなるでしょう。
不動産投資で節税効果が高まりやすい物件と効果が出にくい物件

先述したように、建物の構造によって減価償却できる期間は異なります。つまり、減価償却費を多く計上できれば、節税効果を高めることが可能です。本章では、節税効果が高まりやすい物件と、効果が出にくい物件をそれぞれ解説します。
節税効果が高まりやすい物件
節税効果が高まりやすい物件は、木造の築古物件です。木造の建物の法定耐用年数は22年と、他の構造と比べて短くなっており、減価償却費を大きく計上できます。築古とは、建築されてから一定の年数が経った建物のこと。一般的には30年以上経っている物件を指します。法定耐用年数を過ぎている場合、償却期間は次の式で求めます。
- 償却期間 = 法定耐用年数 × 20%
なお、法定耐用年数の一部を経過している場合は、次のとおりです。
償却期間 =(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
例えば、築35年の木造アパートを2,500万円で購入した場合の減価償却費を計算してみましょう。法定耐用年数である22年を過ぎているため、まずは償却期間を求めます。
22年 × 20% = 4.4年
端数を切り捨て、償却期間は4年となります。次に、減価償却費を計算します。
2,500万円 × 0.250 = 625万円
この場合、625万円を4年間、減価償却費として計上できます。
節税効果が出にくい物件
不動産投資で節税効果が出にくい物件は、新築の区分マンションです。マンションの構造は鉄筋コンクリート造が一般的です。そのため、法定耐用年数は47年となり、減価償却期間が長いことから、1年間で計上できる減価償却費は少なくなります。
例えば、鉄筋コンクリート造の新築区分マンションを6,000万円で購入したとしましょう。この場合、1年で計上できる減価償却費は次のとおりです。
6,000万円 × 0.022 = 132万円
同じ金額で、木造の新築アパートを購入した場合はどうなるのかを見てみましょう。
6,000万円 × 0.046 = 276万円
この場合、276万円を22年間計上できます。購入費用が同じでも建物の構造が違うため、計上できる減価償却費が100万円以上変わるのがわかりました。繰り返しになりますが、計上できる減価償却費が減れば、節税効果が薄くなります。
不動産投資が節税になる?年収別シミュレーション

年収がいくらあれば不動産投資は節税になるのでしょうか。本章では、年収別にシミュレーションしてみましょう。ここでは不動産投資を検討し始める方が多い年収600万円と700万円、また1,000万円でシミュレーションをおこないます。
なお、計算を簡略化するために単身世帯、所得控除は給与所得控除と基礎控除のみで計算しています。また、実際には2037年(令和19年)までは復興特別所得税をあわせて申告・納付することになります。
<条件>
家賃収入:10万円/月
年間経費:180万円
年収600万円の場合
| 項目 | 不動産投資を しなかった場合 |
不動産投資を した場合 |
|---|---|---|
| 所得税における課税所得 | 388万円 | 328万円 |
| 住民税における課税所得 | 393万円 | 333万円 |
| 所得税 | 34万8,000円 | 23万円 |
| 住民税 | 39万8,000円 | 33万8,000円 |
| 所得税と住民税の合計 | 74万6,000円 | 56万8,000円 |
不動産投資をした場合としなかった場合で比較をしてみました。不動産所得が赤字であることから、課税所得が減り、所得税・住民税の金額ともに減っていることがわかります。
年収700万円の場合
| 項目 | 不動産投資を しなかった場合 |
不動産投資を した場合 |
|---|---|---|
| 所得税における課税所得 | 462万円 | 402万円 |
| 住民税における課税所得 | 467万円 | 407万円 |
| 所得税 | 49万6,000円 | 37万6,000円 |
| 住民税 | 47万2,000円 | 41万2,000円 |
| 所得税と住民税の合計 | 96万8,000円 | 78万8,000円 |
先ほどと同じ条件でシミュレーションをすると、18万円の節税になりました。年収600万円の場合と比較すると、2,500円とわずかですが節税できる金額も増えていることがわかります。
年収1,000万円の場合
| 項目 | 不動産投資を しなかった場合 |
不動産投資を した場合 |
|---|---|---|
| 所得税における課税所得 | 757万円 | 697万 |
| 住民税における課税所得 | 762万円 | 702万円 |
| 所得税 | 110万5,000円 | 96万7,000円 |
| 住民税 | 76万7,000円 | 70万7,000円 |
| 所得税と住民税の合計 | 187万2,000円 | 167万4,000円 |
不動産投資をした場合、19万8,000円の節税になりました。年収が上がるにつれて節税できる金額も増えていることがわかるでしょう。もしかすると、予想よりも少ないと感じる方も多いかもしれません。あくまでシミュレーションであるため、不動産投資の収益や経費によって節税効果は異なります。経費計上できる金額が多ければさらに節税できるでしょう。
また、不動産投資で得たいものは何か、目的をよく確認しましょう。将来のための資産形成であることが多いのではないでしょうか。節税はあくまで不動産投資による副産物であると認識しておくことも大切です。
不動産投資が節税につながる人の特徴

不動産投資をすると節税につながる人はどのような人なのでしょうか。本章では、2つの特徴を解説します。
課税所得が900万円以上ある人
課税所得が900万円以上ある方は、不動産投資によって節税効果を得られる可能性が高いです。課税所得に対する税率と控除額を下表にまとめました。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円 から 329万9,000円まで | 10% | 9万 7,500円 |
| 330万円 から 694万9,000円まで | 20% | 42万 7,500円 |
| 695万円 から 899万9,000円まで | 23% | 63万 6,000円 |
| 900万円 から 1,799万9,000円まで | 33% | 153万 6,000円 |
| 1,800万円 から 3,999万9,000円まで | 40% | 279万 6,000円 |
| 4,000万円 以上 | 45% | 479万 6,000円 |
参考:国税庁 「No.2260 所得税の税率」
先述したように、日本では累進課税制度が採用されており、課税所得が900万円の方の税率は33%となります。課税所得が高い方ほど、不動産投資をして課税所得を減らすことで、より多くの節税効果が得られます。
相続税対策が必要な人
相続税対策が必要な方も、不動産投資によって節税効果を得られる可能性があります。相続税には基礎控除があり、下記の式で計算が可能です。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
参考:国税庁「相続税の計算」
法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人のことです。配偶者や子ども、祖父母、兄弟などが該当します。基礎控除額を引いても相続税が課税される場合には、対策をしておくと、遺された家族の負担を減らせるでしょう。具体的な対策としては、資産の組み換えが挙げられます。
先述した「不動産投資が節税になる仕組み」でも解説したように、不動産は固定資産税評価額に基づいて相続税が課税されます。この固定資産税評価額は、市場価格と比較すると低くなっていることから、現金で相続税するよりも相続税が抑えられます。
また、もし不動産事業を法人化し、家族を雇うと、給与も経費として計上が可能です。先に説明したとおり法人は個人よりも所得税率が低いため、より節税効果が高まるでしょう。
まとめ
本記事では、不動産投資が「節税にならない」と言われる理由や節税になる仕組みを解説しました。不動産投資では、減価償却や損益通算などによって、課税所得を減らすことで、所得税や住民税を抑えられます。そのため、課税所得が900万円以上ある方は、所得税の税率が高いことから、不動産投資をするとより高い節税効果を得られるでしょう。年収が低い方でも、不動産投資をすると節税になる可能性があります。しかし、節税はあくまで副産物であり、本来の投資目的を忘れないようにしましょう。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ