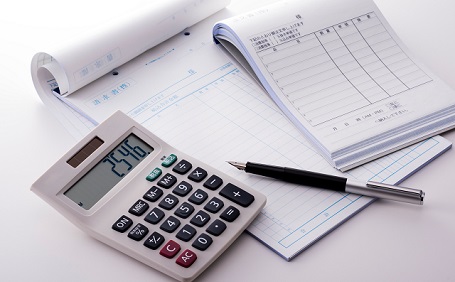不動産投資にかかる税金は?種類や軽減効果を徹底解説

しかし、不動産投資に関連する税金の制度は複雑で、具体的にどのタイミングでどのような税金が発生するのかを把握できていない方も少なくありません。そこで本記事では、不動産投資に関係する税金の種類を詳しく解説します。さらに、不動産を相続する際に課される税金に関しても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
不動産投資で購入時にかかる税金

不動産投資では、さまざまな種類の税金が課されます。まずは収益物件を購入する際に必要となる、以下3つの税を確認しましょう。
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
また、建物の購入金額には10%の消費税が課されるため、忘れないようにしましょう。一方で、土地に対しては消費税が課されないことも覚えておきましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を購入、贈与、譲渡などの方法で取得した場合に課される地方税の一種です。さらに、等価交換(例えば土地と建物の一部を等しい価値で交換するケース)や新築家屋の建築時にも課税されます。
ただし、相続によって不動産を取得した場合は、原則として課税の対象外となります。
不動産取得税の税額は「課税標準額(取得した不動産の価格)×税率」で計算が可能です。
納税は、不動産取得後半年から1年半の間に都道府県から送付される納税通知書に基づいておこなうのが一般的です。通常の税率は土地・建物ともに4%ですが、2027(令和9)年3月31日までに取得した場合は軽減措置が適用され、税率は3%となります。
軽減措置を含む制度内容は頻繁に変更されるため、不動産取得のタイミングで最新の情報を確認しておくことが重要です。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記をおこなう際に課される国税であり、「固定資産税評価額×税率」で税額が計算できます。この税率は、不動産の種類や登記の内容によって異なります。以下で詳しくみていきましょう。
土地購入時(所有権移転登記の場合):通常2%
※2026(令和8)年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5%
建物購入時
・新築物件(所有権保存登記の場合):0.4%
※2027(令和9)年3月31日までの間に登記を受ける場合は0.15%
・中古物件(所有権移転登記の場合):2%
※2027(令和9)年3月31日までの間に登記を受ける場合は0.3%
・不動産投資ローンを利用して購入する場合(抵当権設定登記の場合):0.4%
※2027(令和9)年3月31日までの間に登記を受ける場合は0.1%
なお、この軽減措置の適用期間も制度の変更にともない見直される可能性があるため、事前に詳細を確認することをおすすめします。
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書や建設工事請負契約書、そして不動産投資ローンの金銭消費貸借契約書などに課される国税です。契約書に記載された金額に基づいて税額が決定され、収入印紙を貼付することで納税が完了します。
また、2027(令和9)年3月31日までに作成される不動産売買契約書や建設工事請負契約書に関しては、軽減措置が適用されるため、実際の税負担が軽減される場合があります。詳しくは以下の表を参考にしてください。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
不動産投資で運用中にかかる税金

不動産投資をおこなっている期間中は、固定資産税や都市計画税、所得税、住民税などのさまざまな税金を納める義務があります。また、収益物件の規模によっては、消費税や個人事業税が課される場合があることにも注意が必要です。
以下では、運用中に発生する6種類の税金の特徴や計算方法を詳しく解説していきます。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税
適用可能な軽減措置に関しても触れているので、ぜひ節税対策の参考にしてください。
固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している方に課される地方税です。さらに、事業用の機械や器具なども償却資産も課税対象となります。
税額は「固定資産税評価額(課税標準額)×税率」で計算され、標準税率は1.4%です。
ただし、自治体によって税率が異なる場合もあるため、物件所在地の市町村で確認が必要。納税通知書は毎年4〜6月頃に送られてくるので、指定された期日までに納付をおこないましょう。
また、住宅用地(土地)には以下の特例措置が適用され、税額が大幅に軽減されるケースがあります。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):固定資産税評価額×1/6
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):固定資産税評価額×1/3
住宅の定義は「1棟=1戸」ですが、アパートなど集合住宅の場合は「1室=1戸」として計算されます。そのため、多くの物件では土地全体が小規模住宅用地に該当し、固定資産税が軽減される仕組みとなっています。
都市計画税
都市計画税は、固定資産税と同様に不動産所有者に課される地方税の一種です。しかし課税対象は、都市計画法で定められた市街化区域内にある土地・建物に限定されます。また、償却資産には課税されません。
税額の計算方法は「固定資産税評価額(課税標準額)×税率」で、税率は地域によって異なり、上限は0.3%とされています。正確な税率に関しては物件が所在する自治体に確認しましょう。
都市計画税にも固定資産税と同じく住宅用地の特例措置があり、減税の対象となることもあります。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):固定資産税評価額×1/3
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):固定資産税評価額×2/3
所得税
不動産投資による収入から必要経費を差し引いた金額は「不動産所得」と呼ばれ、給与所得など他の所得と合算した課税所得に対して所得税が課されます。不動産所得に含まれる収入の例としては以下のものが挙げられます。
- 家賃収入
- 更新料
- 返還不要の敷金・保証金
- 共益費(電気代・水道代・清掃費など)
一方で、必要経費として認められる支出には、以下のような項目があります。
- 修繕費
- 損害保険料
- 設備の減価償却費
- 固定資産税・都市計画税
- 不動産賃貸事業の運営費用
所得税率は課税所得金額に応じて以下のように定められています。
| 課税所得金額 | 税率(控除額) |
|---|---|
| 195万円以下 | 5%(控除無し) |
| 195万円超~330万円以下 | 10%(控除額9万7,500円) |
| 330万円超~695万円以下 | 20%(控除額42万7,500円) |
| 695万円超~900万円以下 | 23%(控除額63万6,000円) |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33%(控除額153万6,000円) |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40%(控除額279万6,000円) |
| 4,000万円超 | 45%(控除額479万6,000円) |
参考:国税庁「所得税の税率」
住民税
住民税は自治体に納める地方税で、所得割と均等割の2種類があります。
- 所得割:前年の所得金額に基づいて計算され、税率は一律10%
(市町村民税6%、都道府県民税4%)※ - 均等割:所得額に関係なく一定額が課税される
通常は市町村民税3,000円、都道府県民税1,000円の合計4,000円
※政令指定都市は、道府県民税が2%、市民税が8%
なお、復興特別税の臨時措置により、均等割りは2014年度から2023年度まで1,000円引き上げられていました。2024年度からは森林環境税が徴収されています。
消費税
消費税は不動産投資をおこなうすべての人に課されるわけではありません。前々年度の課税売上高が1,000万円を超えている場合、課税事業者として納税義務が発生します。
対象となるのは以下の収入です。
- 事業用賃貸物件の家賃収入
- 建物の売却代金
- 返還不要の敷金や保証金
また、課税事業者が1,000万円以上の建物を購入した場合、その年度から3年間は課税事業者としての登録が義務付けられます。
個人事業税
規模の大きな不動産投資をおこない、不動産貸付業として認められた場合、個人事業税が課されます。この税額は以下の計算式で算出されます。
- (不動産所得+青色申告特別控除額事業主控除)×5%
事業主控除額として290万円を差し引けるため、課税所得が290万円以下であれば個人事業税は発生しません。また、家族や親族が不動産運営に従事している場合、事業専従者給与額を控除することも可能です。
不動産投資で売却時にかかる税金

不動産投資で収益物件を売却する際には、税金が発生します。売却時に発生する税金は、以下の3種類に分けられます。
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税
上記の税金は売却により得られる収益に基づいて課されるものと、売却手続きにともなって発生するものがあります。手元に残る金額を最大化するためには、それぞれの税金の特徴を理解し、節税対策を取ることが重要です。
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)
譲渡所得税とは、不動産売却によって利益が生じた場合に課される税金で、所得税・住民税・復興特別所得税を含んだ総称のことです。課税対象となる譲渡所得は、次の計算式で求められます。
- 譲渡所得額=売却価格−取得費−譲渡費用
・取得費
物件購入時の費用で、建物の購入代金、建築費、仲介手数料などが当てはまります。建物の費用は、築年数に合わせた減価償却費分を差し引いた額で計算します。
・譲渡費用
売却時にかかった費用で、印紙税や仲介手数料、解体費用などが含まれます。
譲渡所得がプラスの場合、譲渡所得税を納付する必要があります。ただし、税率は不動産の所有期間にあわせて異なるため、注意が必要です。
・短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)※
・長期譲渡所得(所有期間が5年を超える場合)
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)※
※2037(令和19)年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付します
所有期間の判断基準は、売却した年の1月1日時点で所有していた期間です。短期と長期では税率が約半分になるため、売却タイミングを見極めることが節税のポイントとなります。
登録免許税
売却時には、不動産に設定されている抵当権の抹消手続きが必要です。この手続きにともない、登録免許税が発生します。
登録免許税額
不動産1件につき:1,000円
例:土地と建物それぞれの抵当権抹消をおこなう場合、合計で2,000円
登録免許税は譲渡所得税や印紙税に比べると負担額が小さいものの、忘れずに予算に組み込んでおきましょう。
印紙税
不動産売買契約書には収入印紙を貼付し、印紙税を納める必要があります。売却時の印紙税は購入時と同じ基準が適用され、売買価格によって課税額が異なります。
印紙税の負担額は譲渡所得税と比べて少額ですが、高額物件を複数所有している場合は合計で高額になることも。あらかじめコストを計算しておくことが重要です。
相続時の登録免許税と相続税

不動産を相続する場合にも税金が発生します。相続時の税金には、相続税と登記に関する登録免許税が含まれます。
相続税
被相続人から相続した遺産の金額に合わせて課税され、税率は10%〜55%に設定されています。ただし、相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は発生しません。
-
基礎控除額の計算式:
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
参考:国税庁「相続税の税率」
登録免許税
相続した不動産を登記する際の登録免許税は、次の計算式で求められます。
- 登録免許税=不動産価格×税率(0.4%)
不動産価格とは、「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額のことです。なお、2025年3月31日までは、土地の所有権移転の登記は免税となります。
どちらも不動産を相続した際に、重要な税なので忘れないようにしましょう。
不動産投資で得られる税金軽減効果

不動産投資は、単に税金を軽減する効果を得るだけでなく、利益を生み出し、資産形成を目的とした「投資手法」の一つです。そのため、不動産投資を始める際は、税金対策のみを理由にするのではなく、リスクやリターンを十分に考慮する必要があります。税金対策としてしっかりメリットを得るためには、基礎知識を学び、計画的に進めることが大切です。
不動産投資をおこなうことで得られる主な税金軽減の仕組みを詳しく解説します。
青色申告特別控除を受けられる
青色申告特別控除とは、青色申告をおこなうことで受けられる所得控除です。不動産所得を得る事業をおこなっている場合、一定の条件を満たすことで適用されます。
控除額には10万円、55万円、65万円の3種類があり、それぞれの要件が異なります。
<55万円の控除を受けるための条件>
・取引内容を複式簿記で記録する。
・確定申告時に貸借対照表や損益計算書を添付し、控除額を申告書に記載する。
・不動産所得が55万円を下回る場合は、その所得額が控除の上限となる。
<65万円の控除を受けるための条件>
上記の条件に加えて、以下のいずれかを満たす必要があります。
・電子帳簿で仕訳帳や総勘定元帳を保存している。
・e-Taxを使用して確定申告をおこなう。
<10万円の控除>
上記の条件を満たさない場合でも、青色申告をおこなっている場合には10万円の控除を受けられます。
必要経費を計上できる
不動産投資では、所得を得るためにかかった費用を必要経費として計上できます。必要経費が増えると不動産所得が減少し、それにともない課税額も軽減されます。
計上可能な経費例
- 物件の修繕費
- 仲介手数料
- 固定資産税
- 火災保険料など
ただし、すべての支出が経費として認められるわけではありません。例えば、親族間での地代や家賃の支払いなどは、経費として計上できません。
損益通算ができる
不動産所得が赤字となった場合、その損失を他の所得(給与所得や事業所得など)から差し引ける仕組みを損益通算といいます。不動産所得の損失を補填することで、課税対象となる所得金額を減らすことが可能です。
ただし、損益通算には以下のような制限があるため注意が必要です。
損益通算の対象外となるもの
- 別荘など生活に必要とされない資産の貸付けによる損失
- 土地取得のための負債利子に相当する金額
- 特定の組合契約に基づく事業から生じた損失
- 国外の中古建物で、簡便法による減価償却費を計上した場合の損失
また、土地と建物を購入した場合、土地部分の借入金やその利子額を明確に分けておく必要があります。
減価償却費を計上できる
減価償却費とは、不動産などの固定資産が年数とともに価値が下がることを考慮し、毎年分割して経費として計上するものです。不動産投資では、建物部分の費用を耐用年数に応じて減価償却費として計上できます。
まとめ
不動産投資をすることで、どれだけの利益が上がるかだけではなく、どのくらい出費が出るのかも把握しておかなければなりません。
そのため不動産投資を始める際は、それぞれの工程ごとにさまざまな税金がかかることを理解しておく必要があります。一つ一つの税額は低くても、合わさることで大きな出費になる可能性も。不動産投資に関する知識だけではなく、税金に関する知識も身に付けてからおこないましょう。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ