マンションオーナーになるには?必要なものや平均年収、手順までを徹底解説!

記事の目次
マンションオーナーになるには?

マンションオーナーになるためには、何から始めればいいのでしょうか。そもそも、マンションオーナーの仕事内容はどういったものなのでしょうか。本章では、仕事内容とマンションオーナーになるために必要なものを解説します。
マンションオーナーの仕事内容
マンションオーナーの仕事は、投資用マンションを所有し、家賃収入を得ることです。具体的な仕事内容としては、次のようなものがあります。
- 入居者の募集
- 賃貸契約の手続き
- 家賃の回収
- 入居者の対応
- マンションの修繕
- 共有部分の清掃や管理
マンションを購入した場合には、入居者を集めなければなりません。チラシを作成したり、不動産会社のホームページに掲載してもらったりなど、広告活動をおこないます。入居者が決まったら賃貸契約を締結します。
家賃の回収も、マンションオーナーの仕事です。もし滞納者がいる場合には、家賃収入が得られなくなってしまいます。また、入居者からのクレームや問い合わせの対応もマンションオーナーの仕事。迅速に対応できるかで、入居者の満足度が変わります。
さらに、マンションの修繕や共有部分の清掃・管理も大切な仕事です。誰しも汚いマンションに住みたいとは思わないでしょう。こまめにメンテナンスをおこない、きれいな状態を維持することで、入居者の満足度を高められます。入居率が維持できれば、安定した家賃収入を得られるだけでなく、売却する際にも高い価格で売却できるでしょう。
これらの仕事は、不動産管理会社に委託できます。しかし、不動産管理会社に任せきりにするのではなく、マンションオーナーとして積極的に経営判断をすることで、より安定したマンション経営をおこなえるでしょう。
マンションオーナーに必要なもの
マンションオーナーになるためには、何が必要なのでしょうか。ここでは3つ解説します。
マンション経営に関する知識
マンションオーナーになるために必要なものは、マンション経営に関する知識です。マンション経営で収益を上げられるかは、物件選びが鍵を握っているといっても過言ではありません。なぜなら、立地がよく、高い入居率を維持できるマンションであれば、家賃収入を安定して得られるからです。収益性の高いマンションを選ぶためには、立地や築年数、周辺環境など、どのような物件を選ぶといいのかといった知識が必要です。
また、法律や税金に関する基本的な知識も押さえておきましょう。売買や賃貸の手続きの場面では、専門的な話が多くなります。不動産会社も同席することが一般的ですが、「専門用語ばかりでまったくわからない」という状況は避けたいもの。わからないまま手続きを進めてしまうと、自分にとって不利な契約になっていることに気付かないかもしれません。
さらに、マンション経営では、税金や保険料、修繕費など、さまざまな費用がかかります。経費にできるもの、できないものがあるため、正しく理解をしていなければ、誤って会計処理をしてしまうおそれがあります。税理士などの専門家に依頼することもできますが、正確な処理をおこなうためにも、最低限の知識を身に付けておきましょう。
信用力
マンションオーナーになるためには、信用力も必要です。信用力とは、返済能力とも言い換えられます。マンションは高額であるため、金融機関から不動産投資ローンを借り入れることが一般的。借り入れる際には、金融機関から審査を受けることになります。審査の内容としては、次のとおり。
- 属性(勤務先、年収、勤続年数など)
- 過去の信用情報
- 購入するマンションの収益性
不動産投資ローンは高額な融資であることから、返済能力を厳しく審査されます。そのため、安定して返済できるか、勤務先や年収などのマンションオーナーの属性も確認されます。また、これまでのローンの返済状況や借入状況なども。万一、返済を滞納している場合は、返済能力がないとみなされ、審査に通ることは難しくなるでしょう。
さらに、マンションの収益性も確認されます。不動産投資ローンは家賃収入から返済していくため、収益性があるのかをチェック。万が一、マンションオーナーが返済できなくなった場合には、金融機関がマンションを売却し、売却したお金で不動産投資ローンの残債を回収します。
自己資金
マンションオーナーになるためには、ある程度の自己資金が必要です。なぜなら、不動産投資ローンの融資を受ける際に、頭金として、金融機関から借入金額の一定割合を用意するよう求められることがあるからです。頭金は物件価格の10〜20%が目安。
また、頭金を多く用意することで、金融機関から返済能力があるとみなされたり、借入金額が減りキャッシュフローが多くなったりといったメリットもあります。
さらに、マンション経営を始めたあとに、想定外の修繕費がかかったり、空室が多く家賃収入が減ってしまうことも考えられます。自己資金があれば、そういった事態でも赤字になることなく、安定した経営を継続できるでしょう。
マンションオーナーになるメリット

マンションオーナーになると、「家賃収入を得られる」と考える方は多いでしょう。しかし、それ以外にもメリットはあります。本章では、5つのメリットを解説します。
長期的に安定した収入を得られる
マンションオーナーになることで、長期的に安定した家賃収入を得ることができます。人々が生活をしていくうえで、住宅は基盤となるもの。そのため、住宅の需要は常に安定しています。また、自然災害でマンションが被災するといったことがない限り、一度入居が決まれば、入居者は継続して入居するものです。そのため、安定して家賃収入を得られる点はメリットでしょう。
さらに、立地がいいマンションであれば、資産価値が上昇する可能性もあります。購入時より高い価格で売却できれば、売却益も得られます。その売却益で、新たな投資物件を購入するなど、不動産投資の規模を広げることもできるでしょう。
少ない資金で実物資産を保有できる
少ない資金で実物資産を保有できることも、マンションオーナーになるメリットです。先述したように、マンションを購入する際は、不動産投資ローンを組むことが一般的。不動産投資ローンを借り入れることで、自己資金が少なくても、大きな資産を保有できます。また、マンションは、そのものに価値がある実物資産であることも魅力です。実物資産には、景気や社会情勢の景況を受けにくいというメリットも。
さらに、一棟マンション投資では、マンションが建築されている土地も所有権を持つことになります。マンション自体は築年数が経つと、資産価値が減ることもありますが、土地の価値は減りません。マンションを売却したあとも、土地の用途を変更したり、売却したりなど、活用できる点もメリットでしょう。
インフレ対策になる
インフレ対策になることも、マンションオーナーになるメリットの一つです。インフレとは物価が上昇し、お金の価値が下がること。前項で説明したように、マンションは実物資産であることから、インフレになっても資産価値は下がりにくい傾向にあります。
また、物価が上昇すると、家賃を上げることができるため、家賃収入の増加が期待できます。例えばインフレ時に、家賃を9万円から11万円に上げた場合、家賃収入が年間で24万円増えることに。このように、マンション経営は、インフレ対策になる点がメリットです。
節税対策になる
マンションオーナーになると、節税対策が可能な点もメリットです。具体的には、次の3つにおいて節税が期待できます。
- 所得税・住民税
- 相続税
- 贈与税
それぞれ詳しくみていきましょう。
所得税・住民税
マンションオーナーになると、所得税や住民税を節税できる可能性があります。それは「損益通算」と「減価償却」によるものです。「損益通算」とは、赤字と利益を相殺することで、不動産所得が赤字だった場合は、他の所得と損益通算ができます。例えば、給与所得が800万円で、不動産所得が-300万円だった場合。損益通算をしたあと、課税所得を500万円として、所得税や住民税が計算されます。課税所得が減るため、結果として納める税金が抑えられます。
「減価償却」とは固定資産の購入費用を、法定耐用年数に応じて経費計上することです。例えば、鉄筋コンクリート造のマンションの場合、47年間に渡って、購入費用を経費として計上できます。経費が多ければ、その分不動産所得が抑えられ、納めるべき税金も減るでしょう。
相続税
マンションオーナーになると、相続税も節税できます。なぜなら、不動産は相続税の計算のもとになる相続税評価額が低くなるからです。例えば、現金1億円を相続する場合は、相続税評価額は額面どおり1億円。しかし、不動産の場合、土地は固定資産税評価額の約80%、建物は約70%となります。例えば、固定資産税評価額が土地6,000万円、建物4,000万円だった場合、相続税評価額は次のようになります。
土地の相続税評価額
6,000万円×80%=4,800万円
建物の相続税評価額
4,000万円×70%=2,800万円
合計の相続税評価額
4,800万円+2,800万円=7,600万円
現金1億円を相続した場合と比較すると、相続税評価額を2,400万円引き下げることができました。また、賃貸に出している不動産は、活用方法が限られることから、さらに相続税評価額が低くなります。
贈与税
マンションオーナーになると、贈与税においても節税が可能です。具体的には、「相続時精算課税制度」を活用し、生前贈与をした場合に限られます。相続時精算課税制度とは、贈与時に2,500万円まで贈与税が非課税となり、非課税枠を超える場合は、一律20%で計算するというもの。60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子どもや孫に対して財産を贈与した時に選択できます。贈与時の価格を、相続時に課税価格として加算するため、相続時に価値が上がると考えられる場合に生前贈与をすると、相続税が抑えられるでしょう。
生命保険の代わりになる
マンションオーナーとなりマンションを保有することは、生命保険の代わりにもなります。なぜ、生命保険の代わりになるのでしょうか。それは、不動産投資ローンを借り入れる際、団体信用生命保険(以降、団信)に加入するからです。団信とは、万が一マンションオーナーが亡くなったり、高度障害になったりした場合、不動産投資ローンの残債を保険金で完済するという保険。マンションオーナーに何かあっても、残された家族は、不動産投資ローンの返済負担を負うことなく、マンションから家賃収入を得ることができます。これが生命保険の代わりになるといわれる理由です。
さらに、不動産投資ローンを定年退職するまでに完済できれば、家賃収入が年金の代わりにもなるでしょう。
マンションオーナーになるデメリット

長期的に安定した収入を得られる可能性があるマンションオーナーは魅力的に感じるでしょう。しかし、メリットばかりではありません。本章では、マンションオーナーになるデメリットを解説します。
さまざまなリスクがある
マンションオーナーになり、マンション経営をするにあたって、さまざまなリスクがともないます。例えば、次のようなものです。
- 空室リスク
- 金利変動リスク
- 自然災害リスク
空室リスクとは、入居者が決まらず、空室状態が続くことです。空室が続けば、当然その間の家賃収入は得られず、収益が下がります。また、金利変動リスクとは、変動金利の不動産投資ローンを利用している場合、金利の上昇によって返済額が増加すること。もし満室状態であれば、不動産投資ローンを問題なく返済できるでしょう。しかし、空室が多い場合には収益が悪化し、最悪の場合破綻するおそれもあります。
自然災害リスクとは、地震や台風などの自然災害によって、収益物件が損害を受けること。収益物件の資産価値が減少したり、入居者に補償しなければならないかもしれません。マンションオーナーになる場合には、これらのリスクを理解し、事前に対策を講じておくことが重要です。
コストがかかる
マンションオーナーになる時には、初期費用だけでなく、継続的にさまざまなコストがかかります。具体的には、次のようなコストがあります。
- 固定資産税
- 修繕費
- 管理手数料
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している方に課せられる税金です。収益物件を所有している間、毎年支払わなければなりません。修繕費は、収益物件の老朽化にともなう修繕にかかる費用のこと。国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、大規模修繕工事は、全体の約7割が12〜15年周期でおこなわれています。また、工事金額は4,000万円〜6,000万円の割合が一番高くなっています。さらに、マンションの管理を委託している場合、管理手数料も必要。管理手数料は収益物件の規模やサービス内容によっても異なります。ここに挙げた費用は、ほんの一部でしかありません。得られる家賃収入だけでなく、コストも見越したうえで、手元に残る金額はいくらなのかをシミュレーションしましょう。
流動性が低い
マンションオーナーになるデメリットとして、流動性が低い点も挙げられます。流動性が低いとは、現金化するまでに時間がかかるということです。例えば、株式や債券であれば、証券取引所が営業している時間であれば、自由に売買できます。
しかし、マンションの場合は簡単に売却できません。売却を依頼する不動産会社を決めたり、買い手を探したりと数カ月はかかるでしょう。また、収益物件の立地や築年数、間取りなどによっても買い手が付きやすいかが変わります。マンションオーナーになる際には、あらかじめ売却時のことも考えて、収益物件を購入しましょう。
マンションオーナーは儲からない?

マンションオーナーになることは魅力的なメリットがある一方、リスクがあったり、コストがかかったりとデメリットもあります。それでは、マンションオーナーは儲からないのでしょうか。本章では、マンションオーナーの平均年収やマンションを購入した際のシミュレーションをおこないます。
マンションオーナーの平均年収
マンションオーナーに限ったデータはありませんが、不動産所得を得ている方の平均年収のデータはあります。国税庁の「申告所得税標本調査」(令和4年分)によると、不動産所得を得ている方の平均所得金額は約542万円です。
また、下表は所得金額の構成割合をまとめたものです。
| 所得金額 | 構成割合 |
|---|---|
| 100万円超 | 0.8% |
| 100万円超200万円以下 | 5.2% |
| 200万円超300万円以下 | 7.8% |
| 300万円超500万円以下 | 17.3% |
| 500万円超1,000万円以下 | 29.7% |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 21.6% |
| 2,000万円超5,000万円以下 | 12.6% |
| 5,000万円超1億円以下 | 3.2% |
これを見ると、所得金額500万円超1,000万円以下が一番多く29.7%となっています。不動産所得を得ている約3人に1人が、500万円超の所得を得ていることになります。
マンションオーナーになった場合の収入シミュレーション
気になるのは、マンションオーナーになると、どれくらいの収入が得られるかということでしょう。ここでは、マンション一棟を買った場合と区分マンションの一室を買った場合でシミュレーションをおこないます。
マンションを一棟購入した場合の収入シミュレーション
まずは、マンションを一棟購入した場合のシミュレーションをみてみましょう。なお、条件は次のとおり。
| シミュレーション条件 | |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 物件の価格 | 8,000万円 |
| 家賃収入(年間) | 1,800万円 |
| 購入時の自己資金 | 2,000万円 |
| 融資金額 | 6,000万円 |
| 融資金利 | 3.0% |
| 融資期間 | 30年 |
| 経費率 | 20% |
手元に残る収入は、次の式で計算できます。
年間家賃収入 ー 支出(諸経費 + 不動産投資ローンの返済額)
この条件の場合の、年間の家賃収入と経費は以下のとおりです。
1,800万円×80%=1,440万円
1,800万円×20%=360万円
次に、手元に残る家賃収入を計算します。
1,440万円ー(360万円+303万円)=777万円
手元に残る家賃収入は777万円となりました。次に、この場合の実質利回りを計算してみます。実質利回りとは、取得費や経費などを含めた利回りで、実態に近いものとなります。なお、計算式を次のとおり
実質利回り(%)=
(年間の家賃収入 - 年間の必要経費)÷
(投資物件の取得費 + 取得時の諸経費)× 100
物件取得時の諸経費を物件価格の15%とした場合、取得費と諸経費は次のとおりです。
8,000万円+1,200万円=9,200万円
777万円÷9,200万円×100=8.44%
この条件の場合、実質利回りは8.44%となりました。
区分マンション一室を購入した場合の収入シミュレーション
次に、区分マンションを一室購入した場合のシミュレーションをみてみましょう。なお、条件は次のとおりです。
| シミュレーション条件 | |
|---|---|
| 部屋数 | 1部屋 |
| 物件の価格 | 2,000万円 |
| 家賃収入(年間) | 120万円 |
| 購入時の自己資金 | 800万円 |
| 融資金額 | 1,200万円 |
| 融資金利 | 3.0% |
| 融資期間 | 30年 |
| 経費率 | 20% |
この場合の年間家賃収入と経費は次のように計算できます。
120万円×80%=96万円
120万円×20%=24万円
次に、手元に残る家賃収入を計算してみましょう。
96万円ー(24万円+61万円)=11万円
この条件の場合、手元に残る家賃収入は11万円となりました。年間で11万円であるため、1カ月1万円以下になります。この場合の実質利回りも計算してみましょう。
2,000万円+300万円=2,300万円
11万円÷2,300万円×100=0.4%
この場合、実質利回りは0.4%となりました。今回は空室率を高く設定しているため、このシミュレーションを上回ることも考えられます。しかし、一棟マンションを購入した場合と比較すると、得られる家賃収入は当然少なくなるでしょう。
マンションオーナーになる際の初期費用
マンションオーナーになる際には、初期費用がかかります。特にマンションを一棟購入する場合は、高額であることから、不動産投資ローンを借り入れることが一般的です。不動産投資ローンを借り入れる際には、頭金があると信用力を高められ、借り入れやすくなるでしょう。また、頭金以外にも、必要な費用があります。具体的には、次のようなものです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料のこと ・物件価格が400万円超の場合: 物件価格の3%+6万円+消費税 |
| 不動産登記費用 | 物件の所有権を登記する際に必要な費用 ・10万円程度 |
| 不動産投資ローン 事務手数料 |
不動産投資ローンの融資を受ける際に 金融機関に支払う手数料 ・定額制:3万円程度 ・定率制:借入額の1~3% |
| 登録免許税 | 物件の所有権を登記する際に必要な費用 ・所有権保存登記の税率→4% ・所有権移転登記の税率→2% ・土地の購入(所有権移転登記)→2% |
| 印紙税 | 契約書類の作成時に必要な費用 ・500万円を超え1,000万円以下の場合:5,000円 ・1,000万円を超え5,000万円以下の場合:1万円 ・5,000万円を超え1億円以下の場合:3万円 ※2027年(令和9年)3月31日までの軽減後の金額 |
| 不動産取得税 | 土地や建物を購入(取得)した時にかかる税金 ・物件価格(固定資産税評価額)の4% |
| 固定資産税 | 地方自治体が課す不動産関連の税金 ・毎年支払いが必要になる税金で税率は約1.4% |
| 火災保険料 | 購入した物件には火災保険や地震保険を かけるのが一般的 月払いや年払いではなく一括払いにすると 保険料が割安になる ・契約期間5年で3万6,000円程度 |
一般的に、不動産投資を始める際、物件価格の2〜3割程度の自己資金が必要とされています。無理をして借り入れてしまうと、家賃収入では返済できず、自己資金で補填しなければならないかもしれません。家賃収入ばかりでなく、初期費用や経費も踏まえたうえで、収支シミュレーションをおこないましょう。
マンションオーナーになる際の手順
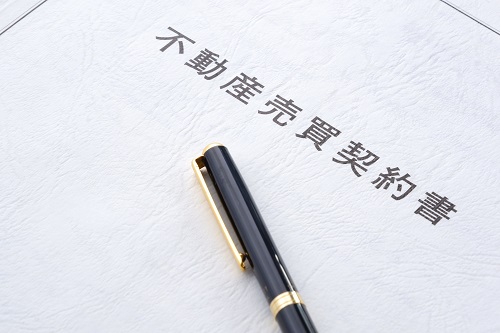
マンションオーナーになるには、何から始めればよいのでしょうか。本章では、マンションオーナーになる際の手順を解説します。
- STEP 1購入したいマンションの条件を決める
- STEP 2不動産会社に問い合わせる
- STEP 3金融機関で不動産投資ローンの審査を受ける
- STEP 4売買契約を締結する
- STEP 5管理会社を選定し、管理委託契約を締結する
- STEP 6金銭消費貸借契約を締結する
- STEP 7決済・引き渡しがおこなわれる
それぞれ詳しくみていきましょう。
ステップ1.購入したいマンションの条件を決める
まず、購入したいマンションの条件を決めましょう。予算はどれくらいなのか、理想とする土地やマンションの条件は何か、希望を洗い出します。不動産情報サイト アットホームでは、物件価格や駅からの距離などから、物件情報を絞り込むことができます。いろいろな物件を見ていると、購入するマンションに求めるものも見えてくるでしょう。
ステップ2.不動産会社に問い合わせる
気になるマンションがあったら、不動産会社に問い合わせましょう。物件概要だけでなく、維持費や固定資産税評価額がわかる資料も用意してもらうといいでしょう。これらの資料があれば、マンションの収益性が判断でき、金融機関から融資を受けられるかの判断材料となります。また、実際に現地に足を運ぶことも大切です。共有部分や周辺環境、日当たりなど、現地でなければわからないこともあるでしょう。入居者の立場になって、住みたいと思えるマンションなのか、考えてみましょう。
ステップ3.金融機関で不動産投資ローンの審査を受ける
購入したいマンションが決まったら、金融機関で不動産投資ローンの審査を受けましょう。なお、ここで受ける審査は仮審査となります。本審査は、売買契約の締結でなければ申し込めないため、注意しましょう。審査では、申込者の属性やマンションの収益性などが確認されます。初めて不動産投資をおこなう場合は、不動産会社と提携している金融機関を紹介してもらうと、サポートを受けられるため、安心でしょう。
ステップ4.売買契約を締結する
売買契約書に基づいて、契約が締結されます。一度締結をすると、あとから変更できません。契約書に記載されている内容をよく理解し、不明な点は必ず質問しましょう。売買契約書に記載されているものは、次のとおりです。
- 売買価格
- 引き渡し時期
- マンションの状態
専門用語も多くなるため、疑問点や不明点は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談しましょう。また、売買契約には「ローン特約」を付けておくと安心です。ローン特約とは、万一不動産投資ローンの審査に通らなかった場合、不動産売買の契約を解除できるというもの。もし付けなかった場合、不動産投資ローンの審査に通らなかったとしても、支払った手付金が返還されません。なお、手付金は売買価格の5〜10%が目安です。
ステップ5.管理会社を選定し、管理委託契約を締結する
マンションの管理を委託する、管理会社を決めましょう。不動産の管理は「賃貸管理」と「建物管理」の2つに分けられます。賃貸管理は、入居者の募集や賃貸の契約手続きなど。建物管理は、故障箇所の修繕手配や共用設備の点検などです。マンションやアパートなど一棟投資の場合は、1つの管理会社がまとめて対応することが一般的。管理会社によって、入居者の満足度や入居率が大きく変わるため、信頼できる会社を選びましょう。
ステップ6.金銭消費貸借契約を締結する
不動産投資ローンの金融機関の本審査に通ったら、金銭消費貸借契約を締結します。金銭消費貸借契約とは、金融機関から不動産投資ローンを借り入れる際に締結するものです。借入金額をはじめ、金利や返済期間、返済方法などが記載されます。売買契約書と同様、締結後はあとから変更できません。必ず内容を理解したうえで、契約しましょう。
ステップ7.決済・引き渡しがおこなわれる
売買契約、金銭消費貸借契約を締結したら、決済・引き渡しがおこなわれます。決済をする前には、不動産会社や売主とともにマンションの状態や不具合を確認しましょう。問題がなければ、決済をおこない、金融機関からおりた不動産投資ローンの借入金で、残りの売買代金を支払います。また、マンションの所有権が移転するため、不動産登記もおこないます。不動産登記は必要となる書類が多く、手続きが複雑であることから、司法書士に依頼することが一般的です。
マンションオーナーになる際の注意点

購入するマンションによっては、大きな収益を上げることが期待できます。しかし、マンションオーナーの誰もが望む結果を得られるわけではありません。本章では、安定した家賃収入を得るために、マンションオーナーになる際の注意点を解説します。
情報収集を怠らない
一つ目は、情報収集を怠らないことです。マンションは高額な買い物であり、経営をするにあたってリスクをともないます。安定した収入を得るためには、事前に情報収集をおこない知識を深めることが欠かせません。特に成功の決め手となるのが、マンション選びです。賃貸需要の高いマンションであれば、高い入居率を維持し、安定した家賃収入を期待できるでしょう。周辺環境や交通アクセス、家賃相場など、さまざまな視点から判断する必要があります。適切な投資判断ができるよう、複数の不動産会社や他のオーナーから情報を集めましょう。
購入時から出口戦略を立てておく
マンションの購入時から出口戦略を立てておきましょう。出口戦略とは、売却する時の戦略のこと。高額な不動産投資ローンを借り入れて、無事に完済したとしても、売却時に売却価格が低ければ、大きな損失を被る可能性があります。
出口戦略としては、次の3パターンがあります。
- 居住用物件として売却する
- 投資用物件のまま売却する
- 更地にして売却する
マンション経営の状況によっても、最適な出口戦略は異なるでしょう。しかし、あらかじめ出口戦略を立てておくと、それに向けた経営が可能です。そうすれば、できるだけ資産を増やした状態でマンション経営を終えられるでしょう。
事前に詳細な収支計画をシミュレーションする
マンションオーナーになる際には、事前に詳細な収支計画をシミュレーションしましょう。繰り返しになりますが、マンション経営では空室リスクや金利変動などのリスクがともないます。予想外の支出や家賃収入の減少を見越したシミュレーションをおこなうことで、収益の悪化を最小限に抑えられるでしょう。
また、収支のシミュレーションは、ランニングコストや諸経費を考慮した実質利回りでおこないましょう。表面利回りは簡易的に計算が可能ですが、実態とかけ離れたものになる可能性があります。
信頼できる不動産会社を選ぶ
マンション経営で安定した家賃収入を得るために、信頼できる不動産会社を選びましょう。マンション経営では、マンションの選び方や不動産市場の動向など、幅広い知識が必要です。自分自身で勉強することも大切ですが、信頼できる不動産会社と関係を築くことで、失敗するリスクを軽減できるでしょう。また、売買契約や不動産投資ローンの融資など、さまざまな場面でのサポートが期待できます。評判や実績などを確認し、自分に合った不動産会社を選びましょう。
まとめ
今回の記事では、マンションオーナーになるにあたって必要なものや平均年収を解説しました。安定したマンション経営をおこなうには、適切なマンション選びが欠かせません。しかし、知識や経験が浅い状態で、一人で決断することは難しいでしょう。適切なアドバイスを受けるためにも、不動産市場の動向や家賃相場などの情報を持ち、経験豊富な不動産会社を探しましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ








