不動産投資詐欺の手口とは?知っておきたい詐欺業者の特徴や被害に遭わないための方法を解説

本記事では、具体的にどういった不動産投資詐欺があるのか、代表的な手口やよく使われるセールストークをご紹介します。また、不動産投資詐欺に遭わないための方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
不動産投資詐欺の代表的な5つの手口
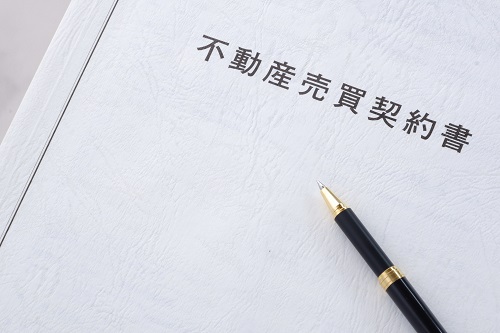
不動産投資詐欺と一口にいっても、さまざまな手口があります。本章では、代表的な5つの手口を解説します。
手付金詐欺
不動産投資の「手付金詐欺」とは、物件を紹介され、手付金を支払ったあとに音信不通になり物件が手に入らないという詐欺です。手付金とは、投資用物件の売買契約時に、買主から売主に対して支払うものです。手付金には大きく3つの種類があります。
-
解約手付
理由を問わず、購入を撤回するためのものです。買主側から解除する場合は、買主は手付金を放棄します。一方、売主側から解除する場合は、売主は手付金の2倍の金額を支払わなければなりません。 -
証約手付
買主の購入意思を示すものです。また、契約が遂行されなかった場合には違約金として利用されます。 -
違約手付
買主または売主が契約どおりに債務がおこなわれない時に損害賠償にあてられるものです。もし買主側に債務不履行があった場合には、買主が支払った手付金が没収されます。一方、売主側に債務不履行があった場合には、売主は買主が支払った手付金を2倍にして支払わなければなりません。
なお、実際の売買契約で支払う手付金は解約手付であることがほとんどです。不動産投資詐欺では「いい物件なので手付金を払ってキープしたほうがいい」などと誘導し、手付金を支払わせるというケースがあります。また、1つの物件に対して、複数の契約を取り付け、手付金を支払わせて持ち逃げするというケースもあるようです。
二重譲渡詐欺
「二重譲渡詐欺」とは、すでに他の購入者に売却済みの物件を販売するという詐欺です。投資用物件の所有権は、契約をした順番ではなく、登記をしたかで決まります。他の方が登記を済ませていれば、売却代金を支払っていても、物件は手に入りません。詐欺グループがおこなっているケースもあれば、売主が知らずに発生するケースもあります。
デート商法詐欺
「デート商法詐欺」は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。恋愛感情を利用して不動産投資を持ちかける詐欺です。独立行政法人国民生活センターにも、「婚活サイトなどで知り合った相手から、将来のための資産形成を口実に投資用マンションなどを購入してしまった」という相談が寄せられています。また、不動産投資ということもあり、1人あたりの購入平均額は約3,012万円と、かなり高額になっています。
参考:独立行政法人国民生活センター「婚活サイトなどで知りあった相手から勧誘される投資用マンション販売に注意!!」
入居状況詐欺
「入居状況詐欺」とは、実際には空室が多い物件を満室物件と偽って販売する詐欺です。具体的には次のようなケースがあります。
- サクラに入居してもらい満室を装う
- 資料の入居率を高く偽る
- 満室を偽り、利回りを高く見せる
購入したあとにサクラが退去し、空室が多くなることから収支が赤字になり、賃貸経営が立ち行かなくなる恐れがあります。実際に物件を見に行っても、入居者がいるように装われているため、見抜くことは難しいでしょう。それぞれの部屋の契約状況を確認し、不自然な点がないかを調べましょう。
海外不動産投資詐欺
「海外不動産投資詐欺」とは、海外不動産の取引にあたっておこなわれる詐欺のことです。例えば、次のようなケースがあります。
-
法的に問題がある物件を販売される
建築基準法に違反していたり、不動産登記がされていなかったりなど、法的に問題がある物件を販売する詐欺です。 -
物件が存在しない
架空の物件を紹介し、手付金を騙し取るという詐欺です。 -
物件の価値を過大評価する
実際の物件価格より高い価格で物件を販売する詐欺です。
海外の不動産投資は国境を越えた取引となるため、リスクが高くなる点に注意が必要です。信頼できる現地の不動産会社を見つけ、適切なサポートを受けるようにしましょう。
知らない間に不動産投資詐欺の当事者になっているケース

不動産投資詐欺では、知らない間に当事者となり、詐欺に荷担しているケースがあります。事前に知っておくことで、取引相手がきちんと法律に則り、実務をおこなっているか確認できるでしょう。
属性の改ざん
不動産投資詐欺のなかには、投資家の属性情報を改ざんし、虚偽の情報で売買契約を締結させるという手口があります。2018年に発生した「かぼちゃの馬車事件」をご存じの方も多いのではないでしょうか。これは、投資用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を販売していた株式会社スマートデイズが経営破綻に陥ったことをきっかけに、金融機関を巻き込んだ不正が発覚した事件です。例えば、かぼちゃの馬車事件では、被害者の預貯金残高の資料は50万円だったにも関わらず、不動産コンサルティング会社が4,000万円に改ざんして金融機関に提出していました。
知らない間に改ざんされていても、金融機関には虚偽の報告をしたことになるため、万一ばれてしまった場合には、不動産投資ローンの一括返済を求められる可能性があります。
二重売買契約
「二重売買契約」とは、不動産の売買契約書とは別に、金融機関に提出するための契約書を作成し、実際の売買代金よりも高い金額を記載して融資を受ける手口です。
例えば、金融機関が融資割合を担保価値の6割に設定していたとしましょう。販売価格7,000万円の物件があった場合、融資上限は6割の4,200万円となります。しかし、金融機関に1億2,000万円で締結した売買契約書を提示した場合、6割である7,200万円の融資が受けられます。書類が偽造されていることが金融機関にばれると、不動産投資ローンの一括返済を求められる可能性があります。
また、購入者は実際の売買代金よりも多い金額を借り入れるため、月々の返済負担が大きくなり、場合によっては家計が苦しくなるかもしれません。
1法人1物件スキーム
「1法人1物件スキーム」とは、物件を1つ購入するにあたり、法人を1つ新設し、金融機関から融資を受けるものです。所有している物件が1つの場合は問題ありませんが、それ以上になると、それぞれ別の金融機関から融資を受けることになります。個人信用情報には融資に関する情報は記載されないため、それぞれの金融機関に借り入れ状況を知られることはありません。しかし、金融機関に借り入れ状況を知らせず、融資を受けることは違法行為になる可能性があります。不動産会社からこの手法を勧められても、断るようにしましょう。
不動産投資詐欺でよく使われるセールストーク

詐欺師は言葉巧みに信用させ、財産を騙し取ります。本章では、不動産投資詐欺でよく使われるセールストークを解説します。
「絶対儲かる」
「絶対儲かる」は、不動産投資詐欺でよく使われるセールストークです。不動産投資に限りませんが、投資はリスクがともなうものであり、必ず儲かるという保証はありません。甘い言葉に惑わされず、冷静に判断することが重要です。
「節税できる」
「節税できる」も、よく使われるセールストークの一つです。節税は不動産投資のメリットとしてよく取り上げられますが、不動産投資で節税効果が高いのは「相続税」と「贈与税」です。具体的には、そのままの金額で評価される預貯金と違い、不動産の相続税評価が低く評価されることが理由。相続税評価額が低ければ、その分相続税も安くなります。不動産投資がどういう理由で節税になるのかを知っておけば、騙されることはないでしょう。
「頭金なしで始められる」
「頭金なしで始められる」というセールストークにも気を付けましょう。自己資金が少ない方にとっては魅力的に感じられるかもしれません。しかし、フルローンになれば、不動産投資ローンの借入金額も多くなり、月々の返済額も高くなります。もし、賃料収入が減ってしまった場合、家計にも影響が出る可能性があります。詳しいシミュレーションをしない状態で、フルローンを勧められた場合は、毅然と断りましょう。
「家賃保証がある」
不動産投資詐欺でよく使われるセールストークの一つが「家賃保証がある」です。サブリース契約をともなう不動産投資でよく使われます。
サブリース契約とは、サブリース会社が所有者から建物を借り、入居者に貸すというもの。家賃保証があるなどと契約書に記載があっても、借地借家法により、支払われる賃料が減額される可能性があります。また、契約書にサブリース会社から解約することができると規定がある場合、契約期間中でも解約される可能性があります。メリットのみばかり伝えるような勧誘の場合は気をつけましょう。
消費者庁からもサブリース契約において注意喚起がされています。「チラシ(賃貸住宅経営(サブリース方式)をお考えの方向け)(PDF形式)」をよく読んでおきましょう。
「年金対策になる」
「年金対策になる」というセールストークも、不動産投資詐欺でよく使われる手口です。不動産投資では、入居者がいる場合には、賃料収入を安定して得られます。また、長期的に運用をおこなえば、収益を老後資金にあてることもできるでしょう。しかし、収益がそのまま自分の資産になるわけではありません。不動産投資ローンの返済をはじめ、管理費や修繕費用などを払う必要があります。そういったデメリットを説明せず、年金対策になる点ばかりを主張している場合は、詐欺が疑われるでしょう。
要注意!不動産投資詐欺における業者の特徴

「損をしたくない」という投資家の心理を突いて言葉巧みに騙すのが詐欺師です。本章では、詐欺業者の特徴を解説します。
リスクを伝えない
先述したように、投資はリスクをともなうものです。しかし、詐欺業者はリスクを隠したり、軽視したりして、投資家を騙そうとします。例えば、「一切家賃収入が下がりません!」など。広告でメリットばかり強調して、リスクを小さく見せる表示をしている場合は、誇大広告に該当する可能性が。また、本来告知しなければならない瑕疵(かし)について、説明しないケースもあります。瑕疵には次の4種類があります。
-
法的瑕疵
建築基準法や消防法などの法律に抵触している物件 -
環境的瑕疵
暴力団体や宗教団体の施設がある、騒音がひどいなどの周辺環境が悪い物件 -
心理的瑕疵
過去に死亡事故や殺人事件、自殺などの不審死が発生しており、心理的な抵抗感を与える物件 -
物理的瑕疵
大雨や地震などの影響で建物にダメージがある物件
これらの瑕疵がある場合には、不動産会社は重要事項説明書に記載し、説明しなければなりません。瑕疵がある投資用物件を購入すると、大規模な修繕が必要になる可能性もあります。ただし、不動産会社が気付いていないケースもあるため、瑕疵の有無を確認するようにしましょう。
おとり広告を表示している
不動産投資詐欺業者の特徴として、おとり広告を表示することが挙げられます。おとり広告とは、購入したくなるようないい条件の物件情報を「おとり」にし、購入希望者に別の物件を売るというものです。おとり広告の内容としては次のようなものがあります。
- 実際には存在しない不動産を広告に表示する
- 売約済みなどで実際には取引できない不動産を広告に表示する
- 実際には取引する意思がない不動産を広告に表示する
これらは不当表示にあたり、本来やってはならないものです。物件名や住所が非表示の場合、他の不動産会社におとり広告をばれないようにしている可能性が高いため、必ず記載されているかを確認しましょう。
参照:消費者庁「不動産のおとり広告に関する表示」
アットホームの情報審査活動について>>
事務所がない
事務所を構えず、カフェやホテルなどで商談をおこなうような会社には注意しましょう。宅地建物取引業法では、不動産会社の事務所の設置を義務付けています。また、継続的に使用できる施設であることを設置要件に挙げており、月単位で契約するシェアオフィスなどは認められていません。不動産会社のホームページに住所が載っていない、事務所以外の場所で商談をしようとする場合は、信用できないでしょう。
契約の締結を急かす
契約の締結を急かすような言動をする場合にも、注意が必要です。「今買わないと損しますよ」「今契約すると特典があります」など時間的な制約を設け、判断する時間をなくします。不動産投資をおこなう際は、しっかりと情報収集をし、冷静に判断をするようにしましょう。
不動産投資詐欺に遭わないための5つの方法

不動産投資詐欺の手口やセールストークなどを解説してきました。それでは不動産投資詐欺に遭わないためにはどうすればいいのでしょうか。本章では5つの方法をご紹介します。
不動産投資の知識を身につける
不動産投資詐欺に遭わないための方法の1つ目は、不動産投資の知識を身につけることです。例えば、「不動産投資の節税効果が高いのは相続税や贈与税」ということを知っていれば、「節税効果がある」というセールストークをされても、「理由は何ですか?」と質問できます。もし取引相手が答えられなかったり、曖昧な回答をした場合には、怪しいと判断できるでしょう。
また、知識を身につけることで、取引相手からも信用を得やすくなるでしょう。不動産投資の知識を身につける方法としては、次の方法が挙げられます。
- 不動産投資に関する本を読む
- セミナーに参加する
- インターネットで検索する
不動産情報サイト アットホームでは、必要な知識をわかりやすく解説しています。ぜひご一読ください。
物件を確認する
物件をよく確認することも、不動産投資詐欺に遭わないための方法の1つです。先述したように、おとり広告では、実際には存在しない不動産を表示しているケースもあります。不動産会社から送られた資料どおりなのか、自分の目で確かめてみましょう。しかし、なかにはサクラが入居している可能性もあります。部屋の契約状況に不審な点がないかもよく確認しましょう。
不明点をそのままにしない
不動産投資は法律や税金、市場動向など、多方面の知識が必要になります。不動産投資は高額な取引のため、不明点をそのままにすると、詐欺でなくても後悔する可能性があります。わからない点はそのままにするのではなく、必ず質問するようにしましょう。もし回答が曖昧だったり、誠実な対応がされなかったりした場合には、取引をしないという判断もできます。
不動産会社の実績や口コミを調べる
不動産会社の実績や口コミを調べることも重要です。不動産会社が国土交通大臣または都道府県知事から許認可を受けているかは、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」により検索できます。取引予定の不動産会社の情報が掲載されているか、確認するようにしましょう。
検索してみると、最初に免許を取得した日や、免許を申請した際の資本金額が掲載されています。また、不動産業界は資金力が重要となるため、資本金額も確認しておきたいところです。他にも、不動産会社の口コミを検索する方法も一つです。もし検索をして、悪い口コミばかり出てくるようであれば、避けるのが無難でしょう。
専門家のアドバイスを受ける
専門家のアドバイスを受けることも、詐欺被害に遭わないために有効です。専門家の具体例として、地域のニーズであれば不動産会社、税金に関することであれば税理士、法律に関することであれば弁護士などが挙げられます。不動産投資では市場動向や地域のニーズなど、さまざまな知識や情報が必要となります。もちろん自分で知識や情報を得ることも大切です。しかし、信頼できる専門家のアドバイスを受けることで、自分が不足している点を効率よく補えるでしょう。
不動産投資の詐欺被害に遭った際の相談先

詐欺に遭わないように気を付けていても、知らない間に遭ってしまうこともあるでしょう。本章では、詐欺に遭った際の相談先をご紹介します。
消費生活センター
消費生活センターでは、商品やサービスなどに関する苦情や問い合わせなどを専門の相談員が受け付けています。全国に857カ所(2024年4月1日現在)あり、すべての市区町村に消費生活相談窓口が設置されています。消費者ホットライン「188」ではお住まいの近くにある消費生活センターや消費生活相談窓口を教えてくれます。どこに相談していいかわからない場合は、一人で抱え込まず、消費者ホットラインを利用しましょう。
参照:消費者庁「消費者ホットラインの概要」
保証協会
保証協会には「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」と「公益社団法人不動産保証協会」の2種類があります。どちらも、売買物件の購入者や賃貸物件の賃借人と、保証協会に加入している宅建建物取引業者のトラブルに関する苦情の解決をおこなっています。先ほどもご紹介した国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、不動産会社がどちらの保証協会に加入しているかを調べられます。
参照:公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
参照:公益社団法人不動産保証協会
免許行政庁
免許行政庁は、不動産会社がどこから免許の許可を受けているかによって相談窓口が異なります。国土交通大臣から許可を受けていれば「国土交通大臣免許業者」、都道県知事から許可を受けていれば「都道府県免許業者」となります。こちらも、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索が可能。例えば、検索した際に「各地方整備局等」と記載があれば、管轄区域の地方整備局が相談窓口となります。地方整備局であれば「地方整備局に関する窓口」で、都道府県免許業者であれば「都道府県に関する窓口」で相談窓口がわかります。
国土交通省からも不動産投資に関して執拗な勧誘を受けた場合は、具体的な状況や様子を記録し、免許行政庁まで知らせるよう注意喚起がされています。不動産会社とのやり取りで困ったことがあった場合には、その場で返事をするのではなく、いったん保留にし、免許行政庁に連絡するようにしましょう。
参考:国土交通省「国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)」
弁護士
不動産投資詐欺に遭った際、弁護士も心強い味方となるでしょう。弁護士は法的な手続きに関する知識や経験が豊富で、被害者にとって有利な証拠を集めたり、訴訟を起こしたりすることができます。ただし、弁護士に依頼する場合には費用がかかるため、被害額によってはマイナスになる可能性もあります。しかし、知識や経験のある弁護士が自分に代わって詐欺の相手と交渉してくれる点は、精神的や時間的な負担の軽減となるでしょう。
「どういった弁護士がいるのかわからない」「弁護士費用がどれくらいかかるかを知りたい」という場合は、法テラス(日本司法支援センター)に相談してみましょう。法テラスとは、国によって設立された、法的トラブルを解決するための総合案内所です。公式ホームページでお近くの相談窓口を検索できます。
まとめ
この記事では、不動産投資詐欺の代表的な手口やよく使われるセールストーク、詐欺業者の特徴を解説しました。詐欺業者は言葉巧みに騙し、財産を奪い取ります。しかし、不動産投資に関する知識を身につけ、リスクなどを理解していれば、騙されにくくなります。また、信頼できる不動産会社などの専門家を見つけることも詐欺に遭わないための方法の一つ。売買などの決断をする時はすぐにその場で決めるのではなく、情報収集をしてから冷静に判断しましょう。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





