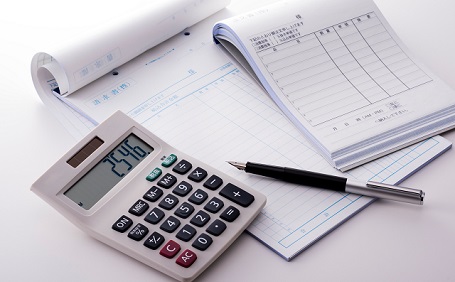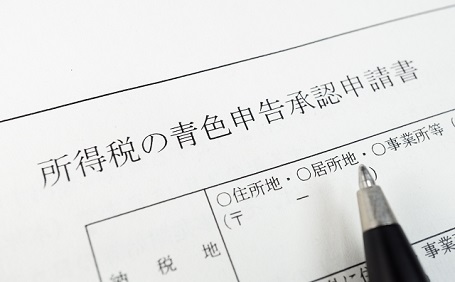アパート経営で税金はどれくらいかかる?具体的な計算方法や節税する方法を解説

本記事では、アパート経営でかかる税金にはどのような種類があるか、それぞれいくらかかるのかを解説します。税金の計算方法や、税金を最適化する方法を知っていれば、アパート経営で有利となります。今後のアパート経営にて、利益を最大化するために知識を身に付けましょう。
記事の目次
アパート経営でかかる税金は?

アパート経営でかかる税金は、不動産を取得する際にかかる税金のほか、運用で得た収益に対する税金や、事業規模に応じた税金など、さまざまです。本章では、以下の税金を解説していきます。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 不動産取得税
- 登録免許税
固定資産税
固定資産税は、アパートなどの不動産を所有している場合に毎年課税される税金。1月1日時点の不動産の評価額に基づいて計算され、納付書が送られてくるので、特に手続きは必要ありません。納付先はアパートがある所在地の市町村区です。
都市計画税
都市計画区域内にある不動産に対して課される税金で、固定資産税と一緒に納付します。都市計画税は、都市計画事業のための財源として使われる税金。都市計画税の規定は、アパートの所在する市町村区によって定められます。なお、市街化調整区域にある場合、都市計画税は必要ありません。
所得税
アパート経営による収益は、不動産所得として所得税の対象となります。収入から必要経費を差し引いた金額に対して課税されます。必要経費とは、固定資産税、修繕費、管理費、減価償却費など。自ら確定申告をして、納税額が決まります。
住民税
所得税と同様に、不動産所得に対しても住民税が課税されます。住民税は地方税で、所得に応じて都道府県民税と市町村民税が課税されます。アパート経営の所得は総合課税で税金が計算され、所得が高くなるほど税率も高くなります。
個人事業税
アパート経営の規模が大きくなり、事業と認められる時に課される税金です。例えば、経営するアパートの部屋数が10戸以上、または5棟以上のアパートを経営している場合が該当します。ただし、個人事業税では事業者控除が認められるため、年間不動産所得が290万円以下の場合は、個人事業税はかかりません。
消費税
アパート経営で賃貸収入が年間1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者となります。住宅の賃貸料は非課税ですが、居住以外の店舗や事務所、駐車場収入などの賃貸収入は、消費税の課税対象。さらに、経営が始まってから支払う賃貸の共有部分の電気代や水道代も消費税の課税対象です。ただし、駐車場に関して、家賃のなかに駐車場代が含まれる場合は非課税となります。
不動産取得税
不動産取得税は、アパートを建築した場合や相続した場合に必要になる税金です。不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課される地方税となります。土地や建物を取得した場合に、その取得価額をもとに計算されます。
登録免許税
登録免許税も、アパートを建築した場合や相続した場合に必要になる税金。登録免許税は、不動産の所有権を登記する際に必要になります。所有権の移転や抵当権の設定などを公的に証明するための手続きで、法務局でおこなわれます。
アパート経営で税金はどのくらいかかる?

アパート経営にかかる税金の概要はわかりましたが、具体的にはいくらかかるのでしょうか。そこで本章では、アパート経営の主な税金として、所得税と住民税がいくらになるか、事例を用いてシミュレーションします。
【前提条件】
| 物件 | アパート1棟(合計8戸) |
|---|---|
| 年間収入 | 768万円 |
| 経費合計 | 528万円 |
| 固定資産評価額 | 7,500万円 |
| 確定申告方式 | 白色申告 |
| 所得控除 | 200万円 |
| 給与所得 | 700万円 |
なお、計算がしやすいように、その他の借り入れはないものとします。
所得税
所得税は、課税所得に税率をかけ、控除額を引いて算出します。
課税所得の算出にはまず不動産収入を算出して総所得を計算します。不動産収入は、【年間収入-経費】です。
768万円 - 528万円 = 240万円
不動産所得は総合課税なので、給与所得と合算し総所得を算出します。
240万円 + 700万円 = 940万円
総所得から所得控除を引いた金額が課税所得です。
940万円 ― 200万円 = 740万円
所得税の税率は、下表をもとに計算します。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円から 330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から 695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から 900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から 1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から 4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
課税所得が740万円の場合、税率は23%で、控除額が63万6,000円のため
740万円 × 23% - 63万6,000円 = 106万6,000円
よって、前提条件のアパート経営による所得税は、106万6,000円です。なお、今回の計算では、復興特別所得税の加算は加味しないものとします。
住民税
住民税は、所得に応じて決まる所得割と、均等割りの合計になります。所得割は、所得税をもとに計算され、所得税に一律で10%の税率です。均等割りは、東京都の場合は5,000円ですが、地域によって異なります。ここでは仮に東京都にあるとして、【前提条件】をもとに計算をしてみましょう。
106万6,000円 × 10% = 10万6,600円
10万6,600円 + 5,000円 = 11万1,600円
よって、前提条件のアパート経営による住民税は、11万1,600円です。
アパート経営の税金を最適化するには?

アパート経営では前章で紹介した所得税や住民税がかかりますが、事業規模によってはさらに多くの税金が課される可能性があります。税金を納めるのは大切なことですが、手元から資金がなくなってしまうため、できれば少なくしたいと思う方もいるでしょう。本章では、ルールに基づいて節税し、支払う税金を最適化する方法を紹介します。
経費をすべて計上する
認められる経費を漏れなく計上すると、アパート経営の税金を最適化できます。所得税や住民税は、アパート経営による利益に対して課されるからです。そのため、利益が少なく経費が多くなるほうが、納めるべき税金が減少します。経費と認められる費用は計上し、有効活用する点がポイントとなります。アパート経営で経費に認められるのは以下の費用です。
- 光熱費:アパートの共用部分の電気・水道代や清掃費、入居者に提供するインターネット設備の利用料なども含む
- 租税公課:不動産取得税や登録免許税、固定資産税などの税金
- 消耗品費(10万円以下):アパート経営の事務処理で必要な文房具やプリンターの購入
- 接待交際費:不動産会社に訪問した時に持参する手土産代など
- 交通費:経営するアパートの視察や現地確認、不動産会社や管理会社に訪問するための交通費
その他、減価償却費、修繕費、火災保険料や管理会社に支払う管理料も経費です。もれなく計上し、税金を最適化しましょう。
損益通算をする
損益通算(そんえきつうさん)は、複数の所得の間で利益と損失を相殺して、総所得金額を減少させられる制度です。アパート経営では、特定の所得の赤字を他の所得の黒字と相殺できます。これにより、全体の課税所得を減らし、納税額の軽減が可能です。
青色申告をする
青色申告をすると、アパート経営で得た利益に対する税金の節税になります。青色申告とは、個人事業主が所得税・法人税の申告をする際に利用できる制度で、詳細な帳簿を備え付けると税務上の特典が受けられる仕組みです。
まず、青色申告をすると特別控除が認められ、課税所得から最大65万円を控除できます。また、家族従業員給与や少額減価償却資産の即時償却など、経費として計上できる項目が増える点も有利です。さらに、赤字の繰越控除も認められ、将来の所得税負担が軽減されます。正確な帳簿管理が求められるため、敬遠する方もいらっしゃるかもしれませんが、その分税制上の優遇措置が多数存在するため、積極的な活用がおすすめです。
法人化をする
利益が多くなる場合は、法人化する方法も節税になります。法人化すると節税になる理由は、個人経営とは異なる税制の適用を受けられるためです。例えば、個人の最高税率が45%に対し、中小企業の法人税率は約23%。そのため、高所得者にとっては、法人化したほうが税率が下がります。また、法人の場合、役員報酬や福利厚生費、退職金など、法人特有の経費計上が可能です。これにより、経費を増やし、法人の課税所得を減らせます。また、個人では計上できないような費用も法人経営では経費として認められるため、結果として税負担の軽減が可能です。さらに、法人化すると、赤字を最長10年間にわたり繰り越せます。個人経営の場合、損失の繰越控除は最長3年間のため、この点でも有利です。
しかし、法人化で単純に節税ができると考えるのは早計です。法人の設立や運営にはコストがかかるため、法人化したために負担が増える可能性もあります。さらに法人の役員は社会保険に加入する義務があるため、個人事業主と比べて社会保険料の負担が大きくなる点に留意が必要です。また、法人化によって税務署の監査が厳しくなる点も考慮しなければなりません。総じて、アパート経営の法人化は、税負担を軽減する有力な手段ですが、その他のリスクを総合的にみて判断する必要があります。
アパート経営の税金に関するよくある質問
アパート経営でかかる税金についてよくある質問をまとめました。
アパート経営でかかる税金は?
固定資産税(不動産の評価額に基づいて課される)と都市計画税(都市計画区域内の不動産に対する税金)がかかりますが、これらは所有する不動産に対し毎年課される税金。続いて所得税と住民税がかかりますが、それぞれ収入から経費を差し引いた金額に課税されます。さらに、アパート経営の規模が大きい場合は個人事業税、賃貸収入が年間1,000万円を超える場合は消費税の対象となるため留意が必要です。なお、不動産取得時には一度だけ不動産取得税が、所有権の登記時には登録免許税が必要になります。アパート経営では、これらの税金を理解し適切に管理する対応が求められるでしょう。
アパート経営にかかる税金の金額は?
アパート経営にかかる税金の計算例を示します。
アパート8戸で年間収入768万円、経費528万円、固定資産評価額7,500万円、所得控除200万円、給与所得700万円のケースを例に計算をしていきます。
不動産所得 = 240万円(768万円 - 528万円)
総所得 = 940万円( 240万円 + 700万円)
所得控除200万円を引いた課税所得は740万円となります。
課税所得740万円に対する所得税は23%の税率と63万6,000円の控除額を用いて計算し、106万6,000円です。
住民税は、東京都を例にすると、所得税額に一律10%をかけ、均等割り5,000円を加算し、11万1,600円(10万6,000円 + 5,000円)です。
このように、前提条件に基づくアパート経営では、所得税106万6,000円、住民税11万1,600円がかかります。
アパート経営の税金を最適化するには?
アパート経営の税金を最適化するためには、経費計上を漏れなくおこなうことが重要です。例えば、光熱費や消耗品費、接待交際費、交通費、減価償却費、修繕費などが経費として認められます。損益通算の活用も忘れてはなりません。さらに、青色申告をおこなうと特別控除や家族従業員給与の経費計上、赤字の繰越控除などの税制上の特典が得られて有利です。
最後に、利益が多くなる場合は法人化を検討しましょう。法人化すると、個人の最高税率より低い法人税率が適用され、役員報酬や福利厚生費などの経費計上が可能。ただし、設立や運営コストなどの負担増加も考慮する必要があります。これらの方法を適切に活用して、アパート経営の税金を最適化し資金を有効に活用しましょう。
まとめ
本記事では、アパート経営でかかる税金にはどのような種類があるのか、それぞれいくらかかるのかを解説しました。アパート経営では、税金も含めたコストはつきものですが、どのように対処していくかによって、結果は大きく異なります。税金の計算方法や、税金を最適化する方法も紹介しているので、よく理解してアパート経営に活かしてみてください。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ