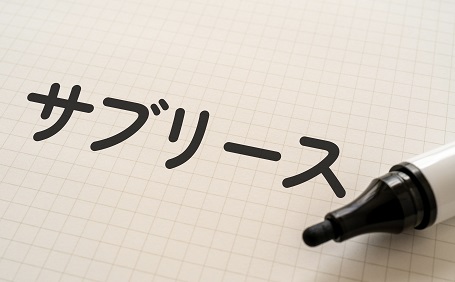アパートの一棟買いで失敗しないためのポイントとは?成功の秘訣も解説

また、建物全体の管理や修繕なども、オーナー自身が時期や内容を自由に決められるため、柔軟な経営が可能です。税金対策でも効果を期待でき、さらに住宅用地であれば「小規模宅地の特例」により固定資産税が軽減されるほか、相続税や贈与税の節税にもつながります。
しかし、他の不動産投資と同様にリスクがともなうため、失敗する可能性はゼロではありません。
本記事では、一棟アパート経営を検討している方に向けて、アパートの一棟買いで発生しやすい失敗や成功に導くコツなどを詳しく紹介します。
記事の目次
アパートの一棟買い・経営で起こりがちな失敗

一棟アパート経営には多くのメリットがありますが、実際に失敗してしまった方も多くいます。まずは、一棟アパート経営で起こりがちな失敗例を見ていきましょう。
借入金が多額でアパート経営が破綻した
アパート経営を始めるには、自分が所有する土地にアパートを建設するか、土地と建物を同時に購入することになります。どちらの場合でも、多くのオーナーは金融機関から融資を受け、購入資金を調達します。
しかし、借入金額が過剰になると、返済に追われ、経営が厳しくなるケースも少なくありません。借入金額が多すぎる場合、返済額が重くのしかかるだけでなく、空室や設備トラブルが発生した際の対応力も低下します。
また、アパート経営では、固定資産税や保険料、管理費などが継続的な出費として発生します。上記は賃料収入の1割程度といわれており、それぞれ単体では大きな負担になりません。しかし、そこに多額のローンの返済が加わると、大きな負担となります。
さらに、アパートローンは建物の耐用年数内に設定されることが一般的。耐用年数とは、建物の価値を会計上費用として分配できる期間を指します。建物構造によって異なり、木造は22年、鉄筋コンクリート造では47年と大きな違いがあります。この期間を過ぎると減価償却費が計上できなくなり、税負担が増すため、経営がさらに厳しくなる可能性もあります。
回避策
まずは、返済スケジュールを明確に立てることが大切です。借入金額は返済負担が過大にならない範囲に抑えましょう。
土地と建物を同時に購入する場合は、借入金額が大きくなりやすいため、キャッシュフローの見通しを慎重に検討し、返済可能な額を見極めましょう。建物の老朽化による家賃低下や空室リスクも考慮し、収支シミュレーションをおこなうことが重要です。
また、返済期間を耐用年数以上に延ばした場合は特に注意が必要です。月々の返済負担は軽減しますが、減価償却費が計上できなくなるため、税負担が大きくなり経営圧迫につながる恐れがあります。
自己資金ゼロでアパート経営を始めた
アパート経営では、すべての資金を自己資金だけで始めるケースは稀で、多くのオーナーは金融機関から融資を受けます。一部のアパートローンではフルローン商品を提供しており、頭金なしで全額の借り入れも可能です。そのため、自己資金がない状態でもアパート経営を始められる点がメリット。
しかし、自己資金なしで経営をスタートすると、借入金額が大きくなり、その返済負担が重くのしかかります。購入した建物は時間とともに劣化し、共用部の修繕費やリフォーム代などが必要になるため、資金繰りに余裕がないと対応が難しくなることも。空室が増えた場合は、経営が一気に苦しくなるリスクがあります。
回避策
一般的には物件価格や建築資金の1~3割程度の自己資金を用意することが望ましいとされています。自己資金があるとアパートローンの返済額を抑えられ、空室や突発的な支出にも対応しやすくなります。
自己資金に不安がある場合、アパート一棟ではなく区分マンションを選ぶことも一つの方法です。区分マンションであれば、都市部でもアパート一棟よりも購入価格を抑えられるため、投資リスクが低く、資金調達の負担も軽減されるでしょう。
安易な追加投資をした
所有するアパートの築年数が進み、空室が目立つようになると、賃料収入がアパートローンの返済額を下回るケースが発生します。このような状況を打開しようと、投資物件の追加購入に踏み切るオーナーもいます。不動産投資は物件数が増えれば収益源も増え、リスク分散が図れるため、一見魅力的な選択肢に思えるでしょう。
しかし、既存物件が赤字経営の場合、追加購入で黒字転換を図ることは簡単ではありません。一般的に1棟や2棟の追加購入だけでは十分な収益改善を見込めないことが多いです。
さらに、自己資金が不足している場合には、新たな多額の借り入れが必要になり、返済額がさらに膨らむリスクがあります。そして、最終的には資金繰りが悪化し、経営が行き詰まる可能性もあります。
回避策
追加投資に頼らず、資産規模を拡大させるために「買い替え」を検討することも一つの方法です。既存の物件を一度売却して自己資金を確保し、その資金をもとに新たな投資物件を購入することで、借入割合を抑えた経営が可能になります。
ただし、赤字経営の場合は売却価格が希望通りにならないこともあるでしょう。また、売却には数カ月以上の時間がかかるため、緊急で資金が必要な状況には不向きです。慎重な計画のもとで売却と買い替えを検討しましょう。
賃貸需要や立地を見誤った
アパート経営では物件の立地や需要を見誤ると、深刻な空室問題に直面する可能性があります。例えば、駅から離れた場所や周辺環境が整っていないエリアでは、そもそも賃貸需要が少なく、空室が続いてしまうことがあります。
アパートは高層マンションに比べて建築規制が緩く、不便な場所にも建てられるため、安価な土地に物件を建てがちです。しかし、安さだけを理由に購入しても、駅から遠い、周辺施設が少ないなどの条件が重なると、満室経営は難しくなるでしょう。
また、その地域の特性や入居希望者層の特徴も重要です。例えば、子育て環境が充実しているエリアではファミリー向け物件の需要が高い一方で、単身者向けのワンルームや1Kでは空室が目立つことがあります。
ターゲット層を考慮せず物件を選定してしまうと、経営がうまくいかない原因となるでしょう。
回避策
賃貸需要のあるエリアを選定する際には「人口移動数」などのデータを活用することが大切です。人口流入が少ないエリアでは、物件が埋まる見込みは低いと考えられます。一方で、人口流入が活発で物件数が不足している地域では、賃貸需要が高まる傾向にあります。
また、現地調査や不動産会社へのヒアリングも効果的。地元の不動産会社は、その地域の需要動向に詳しいため、具体的なアドバイスが期待できます。
実際に現地に足を運べない場合は、不動産ポータルサイトを活用して、賃料相場や空室情報を調べてみるとよいでしょう。周到なリサーチとデータ分析をおこなうことで、空室リスクをできるだけ回避できる物件が見つかるでしょう。
高利回り物件を購入した
利回りは不動産投資の重要な判断材料の一つです。利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の2種類があり、表面利回りは物件価格に対する年間賃料収入の割合を示します。一方、実質利回りとは物件購入時にかかる費用と、年間賃料収入から諸経費を差し引いた金額の割合のこと。実質利回りのほうが、より現実的な指標とされています。
しかし、利回りが高いからといって優良物件とは限りません。例えば、地方の中古物件では利回りが高く見える場合がありますが、空室リスクが高いため、実際の収益は思うように上がらないこともあります。また、多少立地が不便でも新築物件ならば、最初は満室になる可能性が高いです。しかし、築年数が経つとその魅力が薄れ、空室が発生しやすくなるため、注意が必要です。
回避策
高利回り物件を選ぶ際には注意が必要です。特に地方エリアの中古物件では、賃貸需要が低い場合があるため、空室リスクを見込んだ慎重な判断が必要です。利回りは満室状態を前提として算出されるため、利回りの高さだけに惑わされず、物件の収益性を総合的に判断しましょう。
物件を選ぶ際は、周辺エリアの需要や物件の将来性、メンテナンス費用などをトータルで検討することが重要です。地道なリサーチをして、継続的な収益を見込める物件を選ぶことが、安定したアパート経営につながります。
サブリース契約の仕組みを理解していない
サブリース契約は、不動産管理会社がアパートを丸ごと借り上げ、その物件を入居者に転貸する管理形態です。オーナー自身が物件管理をする場合、入居者の募集や設備管理など多岐にわたる業務を自ら担う必要があります。
しかし、サブリース契約では上記の業務を管理会社に一任できるため、管理経験が少ないオーナーにとっては大きなメリットです。また、物件が満室でなくても一定の賃料収入が保証される点も魅力でしょう。
ただし、保証される賃料は必ずしも一定ではありません。空室が長期化した場合や建物の劣化が進んだ場合、保証賃料の見直しや引き下げがおこなわれるケースもあります。また、サブリースでは管理会社が家賃を一部控除したうえでオーナーに支払うため、受け取る収入は実際の賃料よりも8割程度に留まることが一般的。そのため、自主管理よりも利回りが低くなる点に注意が必要です。
回避策
サブリース契約のトラブルを避けるためには、契約前にメリットとデメリットを正確に把握しておくことが重要です。保証賃料の設定根拠や管理費用の詳細なども事前に確認しましょう。特に、保証賃料が適正かは、オーナー自身が見極める必要があります。物件の状態や立地条件など、さまざまな要素が賃料に影響を与えます。将来的な賃料の見直しや保証額の減額も考慮し、長期的な収支計画を立てることが大切です。
節税目的でアパート経営を始めた
アパート経営を節税対策として始める方は少なくありません。減価償却費の計上による税負担軽減や、所得税・住民税の節税効果を狙うケースが一般的です。特に建物の取得時には減価償却費が大きく計上できるため、節税メリットが期待できます。
しかし、節税目的だけで安易にアパート経営を始めると、かえって失敗する可能性も。なぜなら、減価償却期間が終了すると経費計上ができなくなり、所得が増えて税負担が重くなるからです。この際、節税効果が薄れたにも関わらず、高額なアパートローンの返済が続くケースでは、資金繰りに困る事態が生じることもあります。
また、築年数が経過するにつれて建物の老朽化が進み、修繕費用が増加します。加えて、空室リスクも高まるため、賃料収入が減少する可能性もあるでしょう。節税だけを目的に計画を立てると、こうした経年劣化に対応する資金確保が十分におこなえず、最終的に経営難に陥るリスクがあります。
回避策
節税目的だけでなく、長期的な収益確保を視野に入れたアパート経営計画を立てることが大切です。減価償却費の計上期間が終了することを見越し、節税効果が薄れたあとも経営が成り立つ収支計画を検討しましょう。
また、物件選びの段階で将来的な修繕費や維持管理費用も考慮し、老朽化リスクへの対応策を考えることが重要です。修繕積立金を定期的に確保しておくことで、突発的な出費にも柔軟に対応できるでしょう。
地方物件の管理でコストがかさんだ
地方物件は都心に比べて取得費用が低く、利回りも高い傾向にあります。そのため、初期費用を抑えたいオーナーにとっては魅力的に見えるでしょう。
しかし、遠隔地の物件管理には多くの課題がともないます。特に、物件の維持管理やトラブル対応に関しては、手間とコストがかかることは避けられません。物件の老朽化が進むと修繕費も増加し、予想外の出費が経営を圧迫するケースもあります。
さらに、地方物件は地元の管理会社に管理業務を依頼するケースが多い傾向にあります。しかし、すべての管理会社が優秀なわけではありません。対応が遅い、トラブル解決能力が低いなどの問題に直面することもあります。このような管理体制の不備で入居者の満足度が低下し、退去率が上昇するリスクもあります。
回避策
地方物件の管理では、信頼できる地元の管理会社を選定することが重要です。管理会社を選ぶ際は、管理実績や対応力、口コミなどを十分に調査しましょう。管理会社が提供するサービス内容を比較検討して、慎重に見極めることが大切です。また、定期点検や迅速な修繕対応、入居者対応の質などを重視して判断することで、物件価値の維持も期待できるでしょう。
もし可能であれば現地視察をおこない、物件の状態や周辺環境を確認することもおすすめです。遠隔地の管理に不安がある場合は、オンラインでの報告体制を整えている管理会社を選ぶと、情報共有がスムーズになります。
加えて、複数物件を一括管理できるプラットフォームを活用し、管理効率を向上させることも一つの手です。
修繕費用の見積もりが甘かった
アパート経営では、物件の修繕費用を正確に見積もることが重要です。しかし、初心者のオーナーにありがちな失敗として、修繕費用の過小見積もりが挙げられます。
物件の築年数が浅いうちは大きな修繕は必要ないでしょう。しかし、築年数が経過するにつれて外壁の塗装、配管の交換、屋根の補修など、大規模な工事が必要となる場合があります。上記の費用が予想外に発生すると、資金繰りが苦しくなる可能性も。
特に中古物件では、購入時点での状態が悪ければ、購入直後から修繕費用が必要となるケースもあります。安価な物件を選んでも、初期の修繕費用が膨らみ、結果的に総コストが高くなるリスクも無視できません。
回避策
物件の購入時には、専門家による物件調査(インスペクション)を依頼しましょう。専門家に調査してもらうことで、現在の物件状態や将来的な修繕の必要性を把握できます。また、修繕費用の見積もりを複数の会社から取得し、予算計画に反映させることが重要です。
さらに、修繕費用を事前に積み立てておくことも経営リスクを軽減するための一つの手。定期的なメンテナンスを怠らず、問題が大きくなる前に対処することで、長期的な修繕費用を抑えられるでしょう。アパート経営では、修繕費用の管理も重要な経営戦略の一部ととらえるべきです。
家賃滞納で収益が悪化した
アパート経営では、家賃滞納は深刻な問題となる可能性があります。入居者が家賃を支払わない場合、毎月の収益が減少し、固定費の支払いが難しくなることもあります。特に、アパートローンを組んで物件を購入している場合、賃料収入に依存してローン返済をおこなうケースが多いため、滞納が続くと資金繰りが悪化する恐れもあるでしょう。
また、家賃滞納が発生すると、督促や法的手続きが必要となり、手間とコストがかかります。退去手続きがスムーズに進まない場合は、さらに空室期間が長引き、経済的なダメージが拡大してしまうこともあるでしょう。
回避策
家賃滞納リスクを軽減するためには、入居者審査を厳格におこなうことが重要です。収入状況や勤務先、信用情報などを確認し、支払い能力が安定している入居者を選定しましょう。また、保証会社を利用することで、滞納リスクを抑えやすくなります。保証会社を利用すれば、滞納時の家賃回収や督促業務を代行してくれるため、オーナーの負担が軽減されます。さらに、契約時に「口座引き落とし」を設定し、自動的に家賃が振り込まれるようにして支払い遅延を防ぐことも効果的です。
家賃滞納が発生した場合には、早期対応が重要です。初期の段階で適切に督促をおこない、問題の深刻化を防ぎましょう。法的手続きが必要な場合は、弁護士に相談して迅速に対応することを検討しましょう。
不動産市場の変動で経営が悪化した
不動産市場は常に変動しています。地域の経済状況や人口動態、政策変更、金利動向など、さまざまな要因が市場価格や賃料相場に影響を与えます。例えば、景気後退時には賃貸需要が減少し、家賃の下落や空室リスクが高まる可能性も。また、地域の再開発やインフラ整備の影響で物件価格が変動することもあります。
経営当初は高利回りが見込まれた物件でも、市場変動で収益性が低下するケースは珍しくありません。市場変動に対応できない場合、経営が行き詰まるリスクもあるため、注意が必要です。
回避策
市場動向を常に把握するためにも、信頼できる情報源を活用しましょう。不動産ニュースや経済指標のチェックを日常的におこない、変動要因を早期に察知することが重要です。また、複数のエリアや物件タイプに分散投資をおこなえば、特定市場の変動リスクを軽減できます。
さらに、賃料相場の下落に対応するために、物件の付加価値を高める工夫をおこなうことも有効です。内装リフォームや設備のアップグレードをすることで、競争力を維持・向上できるでしょう。必要に応じて家賃設定を柔軟に見直し、市場変動に対応できる経営戦略を構築することが重要なポイントです。
アパートの一棟買いで失敗しないためのポイント

アパートの一棟買いは大きなリターンを期待できる一方、事前準備や運用方法を誤ると大きなリスクをともないます。ここでは、失敗を防ぐための具体的なポイントを詳しく解説します。
賃貸需要をしっかり調査する
購入前にエリアの賃貸需要を調査することは、成功するための基本です。不動産投資は一度購入すると長期的な運用が一般的なため、入居者が安定して確保できるエリアを見極める必要があります。
具体的には、人口や世帯数の推移、地域の経済状況、周辺施設、交通アクセスなどを調べることが重要です。不動産仲介会社は地域の賃貸市場に詳しいため、直接ヒアリングして情報を集める方法も有効でしょう。
また、購入後に部屋のリノベーションをおこない、物件の価値を高めることもおすすめです。建築会社と相談してデザインや設備を整えることで、競争力のある物件に生まれ変わるでしょう。
資金計画は余裕を持って立てる
アパート経営では、余裕のある資金計画を立てることが経営を成功させる鍵です。特に空室リスクに備えるためには、賃料収入が減少してもローンの返済に支障がないよう、事前に積立資金を確保しておきましょう。
建物は月日の経過とともに老朽化するため、屋根や外壁の塗装など大規模な修繕費用が十数年ごとに必要になります。修繕費用や管理コストも含めた長期的な資金計画を立てることで、突発的な支出に対応できる余力を持てるでしょう。リスクに備えた資金管理は、安定した経営を支える重要なポイントです。
税金対策ではなく収益化を優先する
アパート経営には所得税対策の側面がありますが、収益を第一の目的に据えることが重要です。税金対策ばかりを優先し、赤字を意図的に作り出すような経費計上を繰り返すと、本来の収益が見込めなくなります。
アパート経営では、支出を抑えつつ収益を最大化する工夫が必要です。例えば、設備投資をおこなう際にはコストパフォーマンスを意識し、入居者の満足度を高める改修に重点を置いてみましょう。事業の本質である「利益を生む」観点を見失わず、健全な経営を目指すことが大切です。
賃貸管理会社に管理を委託する
アパート経営では、物件管理を賃貸管理会社に任せると効率的です。自分で管理をする場合、入居者募集や契約手続き、賃料の入金管理、原状回復工事の手配、設備トラブル対応など、煩雑な業務が発生します。
賃貸管理会社に委託すれば、上記の手間を軽減でき、トラブル時にも迅速な対応が期待できるでしょう。経験豊富な担当者が対応することで、入居者対応の質が向上し、退去率の低減にもつながります。
管理業務の内容や手数料を比較し、信頼できる管理会社を選定することが大切です。適切な管理がおこなわれることで、アパート経営はより安定したものになるでしょう。
信頼できる不動産会社をパートナーにする
不動産投資では、信頼できるパートナーを見つけることが成功の鍵です。管理業務を専門の管理会社に任せると、アパート経営の負担を軽減できます。経験豊富な担当者から空室対策や入退去時の契約手続きに関するサポートも受けられるため、効率的な経営が可能になるでしょう。
さらに、事業計画の立案や融資の相談など、経営面でのアドバイスも期待できます。信頼関係を築けるパートナーと協力することで、アパート経営がよりスムーズに進むでしょう。
まとめ
アパート一棟経営では、物件全体の計画や修繕方針などをオーナーが自ら決定できるため、自由度が高い点がメリットです。一方で、戸数が多いため管理に手間がかかり、専門知識がないと経営に支障をきたすこともあります。
そのため、不動産会社のサポートを積極的に活用し、管理業務や運営計画を効率化することが重要です。経験豊富な専門家のアドバイスを受けることで、予測されるリスクを事前に回避できるでしょう。
また、アパート経営に必要な知識をしっかり身につけ、リスク対策を取っておけば、長期的、かつ安定的な運営が可能です。事前準備を徹底し、プロの力をうまく借りながらアパート経営の成功を目指しましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ