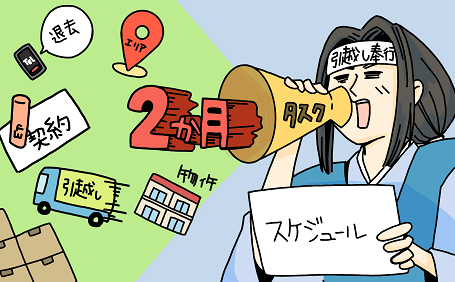シングルマザーでも賃貸は借りられる?入居審査時の注意点や利用できる手当・助成金

賃貸物件を借りられるか不安に感じている方は、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
「シングルマザーは入居審査を通りにくい」は本当?
一般的に、シングルマザーが賃貸物件を借りることは難しいといわれています。しかし、しっかり対策を取れば、賃貸物件を借りることは可能です。詳しくは後述しますが、入居審査はさまざまな項目がチェックされます。大家さんや不動産会社などが項目を確認して特に問題なければ、審査通過は可能です。契約する際の流れや審査項目を事前に把握しておくと、入居審査で有利に働くでしょう。
シングルマザーが賃貸物件を契約する際の流れ
一般的に、部屋探しから引越しするまでの流れは以下となります。
- STEP 1住みたいエリアや希望する条件を決める
- STEP 2不動産情報サイトで物件を探す
- STEP 3不動産会社に連絡をする
- STEP 4物件を内見する
- STEP 5入居の申込・入居審査
- STEP 6物件引き渡し・入居
賃貸物件を探す場合、条件にこだわらなければすぐに物件を決めることができます。しかし、子どもが公立の小学校や中学校に通っていれば、今までと変わらない学区のエリアに引越すのか、もしくは違う学区に引越すのかを決めなければなりません。
また、自治体の住宅手当を申請するのであれば、条件なども事前に調べる必要があります。引越しを決めてから物件を探し、実際に引越すまでには、一般的に1~2カ月くらいの期間かかると考えておくといいでしょう。
シングルマザーが入居審査で確認されることは?

ここからは、シングルマザーが賃貸物件に申し込みをした場合、入居審査で確認される項目を紹介します。事前に内容を把握して、対策しておきましょう。
家賃の支払い能力
通常の入居審査においても重要ですが、家賃の支払い能力があるかは大切なポイントです。家賃を滞りなく支払い続けられるのか、源泉徴収票や数カ月分の給料明細をもとに判断されます。一般的に、家賃は手取りの3分の1以下に抑えるとよいといわれていますが、収入が少ない場合は手取りの4分の1以下に抑えて選ぶようにすると安心です。
職業や勤務年数
働いている場合は、職業や勤務年数についても確認されます。前述した「家賃の支払い能力」の有無に直結しますが、安定して家賃を支払い続けられるかを、勤務先情報などから判断されるのです。正社員や派遣社員であれば、収入が安定していると見てもらえるでしょう。パートやアルバイトの場合でも、長期間勤務していたり月の勤務日数が多かったりすると、収入は安定していると判断されやすくなります。
連帯保証人の有無
連帯保証人は契約者と同等の責任を負うことになるため、重要な役割を担っています。支払い能力のある2親等、あるいは3親等以内の親族を連帯保証人として立てられれば、入居審査は問題なく通過できるでしょう。連帯保証人になれる人がいない場合、大家さんや不動産会社が指定する賃貸保証会社(家賃保証会社)の利用が必須となります。
身なりや人柄
一般的な審査でも見られる部分ですが、不動産会社への対応、身なりなども審査に影響する可能性があります。例えば、内見時に無断で遅刻をしたり、横柄な態度を取っていると「家賃を滞納されそう」「入居後にトラブルを起こされそう」となどと判断され、審査に落ちるかもしれません。不動産会社の担当者が感じた印象が、大家さんや管理会社にそのまま伝わります。はじめから身なりを整え、丁寧に対応するようにしましょう。
子どもの年齢
シングルマザーの場合、子どもの年齢も審査対象です。子どもが小さいうちは夜泣きなどの可能性があり、近隣住民からクレームが入りやすくなります。大家さんや管理会社にとって、トラブルに発展する可能性はできるだけ避けたいものです。「夜泣きが少ない」「比較的おとなしく室内で走りまわったり大声を出したりすることはない」など、子どもの特徴を伝えて安心感を与えるようにしましょう。
収入がない・連帯保証人がいない場合の対処法
賃貸物件を借りるには、入居審査に通ることが必須です。しかし、事情があって一時的に収入がなかったり、連帯保証人を立てられなかったりすることもあるでしょう。その場合の対処法について、以下で解説していきます。
| 収入あり | 収入なし | |
|---|---|---|
| 連帯保証人 あり |
・親族などで安定した収入がある人に依頼 |
・元夫からの養育費を収入として申告する
・銀行の残高証明を提出して支払い能力があることを伝える
・親族や元夫名義で賃貸借契約する
|
| 連帯保証人 なし |
・賃貸保証会社を利用する |
・元夫からの養育費を収入として申告する
・銀行の残高証明を提出して支払い能力があることを伝える
・親族や元夫など安定した収入のある人を契約者にする
・生活保護を申請する
|
収入がなく、連帯保証人がいる場合
上の表にもあるように、収入がない場合でも連帯保証人がいれば、審査に通過する可能性があります。元夫からの養育費を収入として申告したり、預貯金があることを証明するために銀行の残高証明を提出したりするようにしましょう。連帯保証人は、支払い能力がある親族に依頼するのが基本です。
収入がなく、連帯保証人がいない場合
収入がないうえに連帯保証人も立てられない場合は、預貯金があることを証明するほか、親族に代理契約してもらったり生活保護を申請したりする方法があります。ただし、必ずしも生活保護を受けられるとは限りません。また、代理契約だと補助金や手当が受けられない可能性もあるため、事前にお住まいの自治体に確認するようにしましょう。
収入があり、連帯保証人がいる場合
収入があって連帯保証人がいる場合は、比較的審査に通りやすくなっています。連帯保証人は2~3親等以内の収入のある親族が有利です。ただし、連帯保証人がいても賃貸保証会社の加入が必須な物件も増えています。賃貸保証会社に加入するには別途費用が必要になるため、賃貸保証会社の加入が不要な物件を選ぶようにしましょう。
収入があり、連帯保証人がいない場合
一方、入居者本人の収入はあるものの連帯保証人になれる親族がいない場合は、賃貸保証会社の利用が必須です。賃貸保証会社を利用すれば、万が一入居者が滞納してしまった場合でも、賃貸保証会社が代わりに家賃を支払ってくれるため、大家さんのリスクを減らすことができます。賃貸保証会社の利用は、加入時と更新時にお金がかかる点には注意しましょう。
賃貸物件を借りる時にいくら必要?
部屋を借りる際にはどれくらいのお金がかかるのでしょうか。
初期費用の相場は家賃の4~6カ月分
部屋を借りる際には、敷金・礼金・家賃の他、鍵交換費用代や仲介手数料などの費用がかかります。 一般的に、部屋を借りる際に必要となる初期費用は家賃の4~6カ月分が相場となります。
家賃5万円の部屋を借りる際にはおおよそ以下の費用がかかることになります。
| 内訳 | 家賃5万円の場合 |
|---|---|
| 敷金 | 5万円 |
| 礼金 | 5万円 |
| 仲介手数料 | 5万5,000円 |
| 前家賃 | 5万円 |
| 火災保険料 | 1万5,000円 |
| 鍵交換費用 | 1万5,000円 |
| 賃貸保証会社利用料 | 5万円 |
| 合計 | 28万5,000円 |
※敷金、保証金、礼金は家賃1カ月分、仲介手数料は、家賃1カ月分+消費税、鍵交換代と火災保険料はそれぞれ1万5,000円と仮定。賃貸保証会社利用料は、家賃の1カ月分で計算。
上記のような賃貸物件を借りるときに必要な初期費用のほかに、引越してからの生活費用となる食費なども必要になります。また、引越し費用や家具・家電購入費用なども、引越し時に必要です。そのため、30万~40万円ほどのある程度まとまったお金を準備しておくようにしなければなりません。
シングルマザーに給付される手当や補助金は?
国や自治体では、さまざまな生活補助の手当を支給しています。母子・父子家庭など、ひとり親世帯のための支援もあるため、そのような手当や助成金は積極的に利用しましょう。
児童手当
児童手当は、次代の児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。対象となるのは日本国内に住所がある中学生までの児童で、以下のように年齢ごとに支給額が決まっています。支払い月は毎年2月・6月・10月で、前月までの4カ月分を支払ってもらえるので、期限内に役所へ行って申請するようにしましょう。
| 児童手当支給額(月額) | |
|---|---|
| 3歳未満の子ども | 1人あたり15,000円 |
| 3歳以上 小学校修了前までの子ども |
1人あたり10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 1人あたり10,000円 |
児童手当制度のご案内(出典:こども家庭庁)
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親の生活の安定や自立の促進のために、児童福祉の増進を図る目的で支給されます。対象となるのは、18歳までの児童を監護しているひとり親の方です。支給額は以下のとおりで、所得によっても異なります。要件を満たしていれば、児童手当と同時に受給することも可能です。
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 児童1人の月額 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
| 児童2人目の加算額 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
| 児童3人目以降の加算額 (1人あたり) |
6,100円 | 6,090円~3,050円 |
| 支払期月 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | |
児童扶養手当制度の概要(出典:こども家庭庁)
住宅手当
一部の自治体では、住宅手当が支給されることもあります。
実際に、家賃補助はどれくらいもらえるのか東京都世田谷区を例に見てみましょう。
| 制度概要 | 18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯(母子家庭・父子家庭)の方が、区内の民間賃貸住宅(本制度の対象住宅に限る)に転居される場合に、区が賃貸人(家主等)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額が減額されます。 |
|---|---|
| 資格要件 |
(1)世田谷区内に1年以上在住していること(賃貸借契約を締結する時点)
(2)以下の理由に該当し、18歳の誕生日から最初の3月31日を迎えるまでの子どもを養育する世帯であること
・配偶者と婚姻を解消した方
・配偶者が死亡した方
・配偶者の生死が明らかでない方
・ドメスティック・バイオレンスで裁判所からの保護命令が出された方
・婚姻せず子どもを出産、または養育をしている方(事実婚の場合を除く)
(3)入居世帯員全員の所得を合算した金額が月額21万4,000円以下(多子世帯(※1)の場合は月額25万9,000円以下)であること
(※1)18歳未満の子どもが3人以上いる世帯 (4)生活保護法に規定する住宅扶助費や生活困窮者自立支援法に規定する住居確保給付金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する住宅支援給付を受給していないこと
(5)暴力団関係者でないこと
(6)住宅を所有していないこと
|
| 減額となる 金額 |
本来家賃-公営住宅並み家賃(※2) =減額となる金額(上限4万円) (※2)住宅の面積、所得金額等によって変わる |
| 減額を受けられる期間 | 最長10年間 ※補助期間・補助総額は、入居する住宅や所得金額によって変わる |
住宅手当の条件は、都道府県や市区町村によって異なり、住宅手当・家賃補助・住宅費助成制度など名称もさまざまです。詳細については役所に問い合わせしてみましょう。
児童育成手当
児童育成手当は、ひとり親等の児童福祉の増進を図ることを目的に設けられた、東京都が実施している制度です。18歳までの児童を養育している方が対象で、支給額は1人あたり月13,500円が6月・10月・2月に4カ月分ずつ支給されます。ただし、所得制限や申請要件もあるため、事前に確認して申請するようにしましょう。
こども医療費助成制度
こども医療費助成制度は、18歳までの児童を対象に、医療機関で治療を受けたときの保険診療の自己負担分を助成する制度です。2023年(令和5年)4月から、就職や結婚をしている高校生等も対象になりました。各自治体がおこなっているので、要件を満たしているか確認したうえで助成制度を受けるようにしましょう。ただし、健康保険が適用されない診療について対象外となる点には注意が必要です。
ひとり親家庭の医療費控除制度
ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の18歳以内の子どもがいる場合を支給対象に、ひとり親や子どもが健康保険の自己負担分が一部助成される制度です。この制度も所得制限限度額が決まっていますが、自治体によって金額が異なります。生活保護を受けている場合や、子どもが児童福祉施設等に入所している場合などは制度対象外となるため、要件をあらかじめ確認しておきましょう。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神や身体に何らかの障害を持つ子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。20歳未満の精神または身体に障害を持つ子どもを育てる両親などを対象に、等級別に決められた金額が支払われます。受給資格者の前年の所得によって支給されるかが異なるため、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
障害福祉手当
障害福祉手当は、重度障害を持つ20歳未満の方を対象に、負担軽減の一助として支給されます。2023年(令和5年)4月より支給月額は15,220円が適用となり、受給資格者やその配偶者などの前年の所得によっては支給対象外となる可能性があります。手続きの前に、対象要件に当てはまるか確認してみましょう。
シングルマザーにおすすめの間取りは?

子育て環境を整えるには、賃貸物件の周辺環境だけでなく室内も重要なポイントです。快適に子育てをするためには、物件選びの際に間取りもしっかりチェックしておきましょう。シングルマザーにおすすめの間取りについて、以下で解説します。
子どもが未就学児の場合は1DK・1LDK
子どもが未就学児のうちは、母親にとってあまり目が離せない時期です。室内とはいえ、危険なことが起こらないように子どもと同じ空間にいて、いつでも様子をうかがえるようにしておきたいと考える方が多いでしょう。そのため、間取りは1DKや1LDKあると十分な広さといえます。逆に、ワンルームや1K程度でもいいと考える方もいるかもしれません。しかし、1Kなどの間取りは単身者向けの賃貸物件の可能性が高く、子どもの泣き声や走りまわる音で騒音トラブルに発展する可能性があります。
広さが必要ないと感じても、子どもが未就学児のうちは1DKや1LDKの広さが適しているといえるでしょう。
子どもが小学生以上の場合は2DK・2LDK
子どもが小学生以上の年齢になると、宿題をしたり趣味の時間をつくったりと、子どもに自室が必要になることが考えられます。親子でコミュニケーションがとれるリビングダイニングと子ども部屋、寝室があると十分なスペースを確保できるので、2DKや2LDKの間取りがおすすめです。
ただし、子どもの成長に合わせて家の間取りを変えるには、引越しやそのためのまとまった資金が必要になります。家賃が収入を圧迫しない範囲であれば、子どもの成長を見越してはじめから2DK以上を選ぶのも一つの方法です。
子どもが2人以上の場合は2LDK以上
子どもが2人以上いる場合では子どもが小さいうちは、子ども部屋を一つにまとめて暮らしていても問題ない場合が多いでしょう。しかし、子どもが成長していくうちに、子ども同士でもそれぞれのプライベート空間が必要だと感じるようになります。また、家族3人以上となると人だけでなく荷物も増えていき、部屋数が最低2つ以上なければ十分なスペースを確保しにくくなるでしょう。子どもや家族全員が生活しやすくするため、また近隣住民への配慮も兼ねて、子どもが複数人いる場合は2LDK以上の間取りをおすすめします。
この記事のまとめ
ここまでご紹介してきた、シングルマザーが賃貸物件を契約する際の気になる情報をまとめました。
シングルマザーでも賃貸物件を借りられる?
一般的にシングルマザーが賃貸物件を借りることは難しいといわれていますが、しっかり対策すれば不可能ではありません。入居審査では収入状況や勤務状況、連帯保証人の有無などさまざまな項目がチェックされますが、大家さんや不動産会社などが問題ないと判断すれば、賃貸物件を借りることができます。
入居審査の際、どんなところをチェックされる?
特にチェックされるのが、賃料の支払い能力があるかです。また、賃貸保証会社(家賃保証会社)の利用も一つの方法ではありますが、連帯保証人の有無も重要視されたり、子どもの年齢や勤務条件などもチェック対象となります。また、身なりや人柄なども大家さんや不動産会社への印象を左右するため、初期からの対応も非常に大切です。
ひとり親世帯だと住宅手当がもらえる?
居住する地域によっては、ひとり親世帯に対して住宅手当を支給しているケースがあります。具体的な内容や受給条件などは自治体によって異なるので、あらかじめ確認してみてください。
シングルマザーが賃貸物件を借りる際、まとまった資金が必要になったり物件の条件が絞られてしまったりと、通常の単身居住とは異なる点に配慮しなければなりません。実際に入居審査に落ちて、どのように対処すれば良いかわからず不安な方も多いでしょう。しかし、今回ご紹介したような物件選びの際のコツを押さえておくと、比較的スムーズに賃貸物件を借りることが可能です。入居後の生活が不安な方は、当てはまる補助金制度がないか探して活用しましょう。手続きの方法がわからない場合は、お住まいの自治体に相談することをおすすめします。