住宅ローンの滞納は何回までなら大丈夫?滞納しないための対策も解説

記事の目次
住宅ローンの滞納回数と金融機関の対応
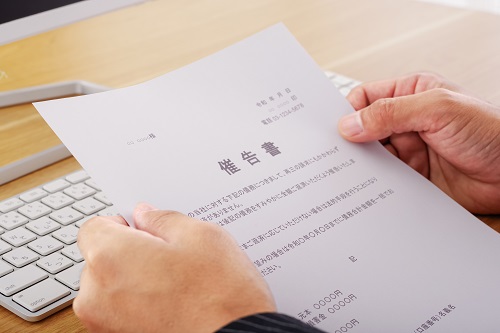
住宅ローンを滞納すると、具体的にどのようなことが起きるのでしょうか。本章では、滞納回数に応じた金融機関の対応を解説します。もし滞納してしまった場合の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
1〜2回滞納した時
通常、住宅ローンを1〜2回滞納した場合、金融機関から強硬な対応を受けることはありません。金融機関は1〜2回程度の滞納であれば、一時的なものととらえる傾向にあります。ただし、すぐに対応することを心がけましょう。なぜ、早急な対応が必要なのか、理由を次項で詳しく解説します。
遅延損害金が発生する
住宅ローンの返済が1回でも遅れると、支払い期日の翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金の年利は、一般的に14%〜14.6%と高めに設定されています。具体的な計算式は次のとおり。
遅延損害金 = 元金返済分 × 遅延損害金の利率 × 滞納日数 ÷ 365日
例えば、次の条件の遅延損害金を計算してみましょう。
<条件>
元金返済分:10万円
遅延損害金の利率:14%
滞納日数:10日
10万円 × 14% × 10日 ÷ 365日 = 383円
※元金の100円未満、計算して出た金額の1円未満は切捨てとなります。
1日でも遅れると遅延損害金が発生するため、気をつけましょう。もし遅れてしまった場合は金融機関に連絡し、遅延損害金を合わせて返済する必要があります。
優遇金利が解除される可能性がある
住宅ローンを滞納すると、優遇金利を解除される可能性があります。優遇金利とは、商品やサービスでいう割引のこと。住宅ローンの金利は、金融機関のホームページで公表されている基準の店頭金利から、優遇金利が差し引かれた金利が適用されることがあります。
例えば、店頭金利が3.86%、優遇金利が1.5%だった場合、実際に適用される金利は2.36%です。金利が低くなると、その分利息の支払いも減るため、総返済額が抑えられるというメリットがあります。しかし、この優遇金利は金融機関が優良な顧客に対して、今後もいい関係を構築したいという思いから適用されるもの。住宅ローンの滞納は、金融機関からの信頼を失うことになるため、優遇金利を解除される可能性があります。
3回以上滞納した時
住宅ローンを3回以上滞納すると、金融機関からの対応も厳しいものになります。これは、単なる支払い忘れではなく、返済能力に問題があるとみなされるためです。住宅ローンを3回以上、もしくは61日以上滞納すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。信用情報機関とは、ローンの契約や返済状況、クレジットカードの返済状況などの記録をまとめている機関のこと。事故情報として登録されると、5年間は記録に残ります。
金融機関は申込者の返済能力を確認したい時、信用情報機関に信用情報の照会をおこないます。その際に事故情報が登録されていると、返済能力に問題があると判断されることに。そのため、クレジットカードを作ったり、ローンの審査に通ることは難しくなるでしょう。
住宅ローンの滞納から競売までの流れ

住宅ローンを滞納したまま放置していると、金融機関は債権を回収するために住宅を差し押さえて競売にかけます。具体的にどのような流れで進むのか、把握しておきましょう。簡単な流れは次のとおりです。
- STEP 1【滞納1〜2カ月】 支払い請求が届く
- STEP 2【滞納3カ月】 催告書が届く
- STEP 3【滞納3~6カ月】 期限の利益喪失通知が届く
- STEP 4【滞納6〜8カ月】 競売開始決定通知書が届く
- STEP 5【滞納12~16カ月】 期間入札通知書が届く
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【滞納1~2カ月】支払い請求が届く
住宅ローンを1〜2カ月滞納すると、金融機関から支払い請求が届きます。金融機関は、滞納が一時的なものであると考えているため、支払い請求をおこなうことで、返済を促します。滞納期間が長くなるほど、遅延損害金の金額も増えるため、早めに支払うようにしましょう。金融機関に連絡すると、遅延損害金を合わせた返済額を教えてもらえます。
【滞納3カ月】催告書が届く
住宅ローンを滞納して3カ月ほど経つと、金融機関から催告書が届きます。催告書は、金融機関からの最後の警告で、これまでのDMや電話連絡などとは異なり、内容証明郵便で届きます。内容証明郵便とは、郵便局が差出人や宛先、内容などを証明するもの。金融機関は、滞納を続けている契約者の返済意思が薄いと判断し、法的措置を進める準備を始めます。
また先述したように、この時点で信用情報にも事故情報として登録されます。これにより、将来的な取引に大きな影響を及ぼす可能性が高まります。催告書を受け取ったら、金融機関に連絡して状況を説明しましょう。また、弁護士に相談し、適切な対応を講じることも大切です。
【滞納3~6カ月】期限の利益喪失通知が届く
住宅ローンを滞納して3〜6カ月経つと、「期限の利益喪失通知」が届きます。期限の利益とは、住宅ローンの元金を分割して返済できる権利のこと。この権利を失うと、住宅ローンの残債を一括返済しなければなりません。
もともと分割で返済していたものを、一括で返済することは難しいでしょう。そこでおこなわれる手続きが「代位弁済」です。これは、保証会社が債務者に代わって一括で返済します。保証会社が代わりに返済しただけであり、債務者の返済義務がなくなったわけではありません。債務者は金融機関ではなく、保証会社に対して返済することになります。
【滞納6〜8カ月】競売開始決定通知書が届く
住宅ローンの滞納が6〜8カ月に達すると、裁判所から「競売開始決定通知書」が届きます。これは、金融機関や保証会社の申し立てにより、裁判所が競売の手続きを開始したことを示す文書です。通知書が届いても、すぐに競売にかけられるわけではありません。裁判所の執行官や不動産鑑定士による現況調査が実施されます。これは権利関係や土地・建物の状況を調査するもので、写真撮影や聞き取りなどがおこなわれます。この段階まで来てしまうと、自分の力だけで解決することは困難です。弁護士などの専門家に相談しましょう。競売を回避するためには、任意売却も選択肢の一つとなります。
【滞納12~16カ月】期間入札通知書が届く
住宅ローンを滞納して12〜16カ月経つと、期間入札通知書が届きます。これは、競売の入札が始まることを知らせるものです。具体的には、次のような内容が記載されています。
- 入札期間:入札する期間
- 開札日:入札結果が決定する日
- 売却基準価額:裁判所が設定する入札基準となる価格
もし任意売却をする場合には、開札日の前日までに手続きを済ませなければなりません。入札期間が決まると、不動産競売物件情報サイトに情報が公開されます。物件情報や写真が掲載されるため、競売にかけられていることが知人や近所の方に知られる可能性が高まります。そのため競売を避けたい場合は、早めに対処するようにしましょう。
住宅ローンを滞納しないための対策

収入の減少や物価の上昇など、さまざまな理由から住宅ローンの返済が厳しいと感じている方もいるでしょう。そこで本章では、住宅ローンを滞納しないための対策を解説します。滞納するほど金融機関からの対応も厳しくなり、選択肢も狭まるため、早めの対応を心がけましょう。
金融機関に相談する
まずは住宅ローンを借り入れている金融機関に相談しましょう。金融機関にとっても、滞納はできるだけ避けたいもの。返済計画を立て直し、返済を続けてもらうことを望んでいます。例えば、「フラット35」では生活状況の変化に応じ、返済方法を変更したケースが紹介されています。
このように、一定期間の減額や返済期間の延長など、対応してもらえることがあります。早めに相談することで、経済面だけでなく、精神的にもゆとりが生まれるでしょう。各金融機関には相談窓口が設けられているため、積極的に活用しましょう。
家計を見直す
家計を見直すことも、住宅ローンを滞納しないための方法の一つです。なぜ、住宅ローンの返済が厳しく感じられるのか、今一度収支を見直してみましょう。特に家計簿をつけていない場合、気付かない間に支出が増えていることも。収支のバランスや固定費の見直しなどをおこないましょう。ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談すると、改善点を的確にアドバイスしてもらえます。
住宅ローンを借り換える
住宅ローンの借り換えも、滞納しないための方法です。借り換えとは、新しい住宅ローンで現在借りている金融機関のローンを返済してから、新しい住宅ローンを組み直すこと。金利が低い住宅ローンに借り換えることで、毎月の返済額を減らせるため、返済負担を軽減できます。
ただし、住宅ローンを再度契約することになるため、融資手数料や印紙税などの諸費用がかかります。また、審査ももう一度受けなければなりません。もし転職して日が浅かったり、収入が減っていたりする場合には、審査に通ることが難しくなるでしょう。これらのデメリットを踏まえ、メリットが得られるかどうかを検討しましょう。
任意売却する
これまでご紹介した方法を実践しても改善が見込めない、競売を避けられそうにない場合は、任意売却という方法があります。任意売却とは、金融機関の許可を得て住宅を売却するものです。売却価格は住宅ローンの返済に充てることができます。ただし、それでも住宅ローンの残債がある場合は、手持ちの資金で返済したり、分割で返済を続けなければなりません。しかし、任意売却は市場価格で売買できるため、競売よりも高く売却できる可能性があります。少しでも高く売却するために、複数の不動産会社に査定を依頼するようにしましょう。
住宅ローンの滞納に関するよくある質問
住宅ローンの滞納に関するよくある質問をまとめました。
住宅ローンを何カ月滞納したら差し押さえられる?
金融機関によって、住宅ローンの滞納に対する対応のスピードは異なるため、一概に答えられません。しかし、裁判所は「競売開始決定通知書」を出す前に、住宅の差し押さえを宣言します。つまり、自宅に「競売開始決定通知書」が届いた時には、すでに差し押さえられていることになります。
住宅ローンの滞納は何回までなら大丈夫?
住宅ローンの滞納は1〜2回までであれば、一時的なものとみなされる傾向にあります。しかし、返済が1日でも遅れると、ペナルティとして遅延損害金が発生します。また、優遇金利が解除される可能性もあるため、なるべく早く金融機関に連絡し、返済しましょう。
残高不足で住宅ローンが再度引き落としになった時はどうなる?
残高不足で住宅ローンの引き落としができなかった場合は、すぐに口座に入金しましょう。返済期日に間に合わなかった場合は、遅延損害金の分も合わせて引き落としがされます。引き落としには時間がかかる場合もあるため、金融機関に事前に連絡をしておくとスムーズでしょう。
まとめ
本記事では、住宅ローンの滞納について解説しました。1〜2回までの滞納なら、一時的なものとみなされる可能性がありますが、遅延損害金が発生するなどのペナルティがあります。また、3回以上の滞納となると、返済能力に問題があると判断され、金融機関からの対応も厳しいものになります。各金融機関では、相談窓口が設けられているため、滞納する前に相談しましょう。返済期間の延長や一定期間の減額など、負担軽減のための方法を提案してくれるでしょう。
物件を探す

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







