住宅ローンの連帯保証人のまま離婚するとどうなる?リスクや外れる方法、手順をわかりやすく解説

記事の目次
住宅ローンの連帯保証人とは

まず、連帯保証人とはどういう人を指すのかを押さえておきましょう。
連帯保証人とは
住宅ローンにおける連帯保証人とは、主債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合、代わりに返済する責任を負う人のことです。通常、保証会社を利用することが一般的であるため、連帯保証人は不要です。しかし、ペアローンを組む場合や収入合算で組む場合などには、連帯保証人が必要です。
住宅ローンにおける連帯保証人の義務
連帯保証人とよく似た言葉に、「保証人」があります。しかし、責任の重さが異なります。連帯保証人は、保証人に認められている次の3つの権利がありません。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
それぞれ詳しく見ていきましょう。
催告の抗弁権がない
催告の抗弁権とは、金融機関に対して「主の債務者に請求してください」と主張する権利のことです。連帯保証人には催告の抗弁権がないため、金融機関から主債務者に代わって返済を求められた場合、返済しなければなりません。
例えば、1つの物件に対して2つのローンを契約するペアローンを夫婦で組んだ場合。この時には夫婦それぞれが債務者となり、お互いに連帯保証人となります。もし、夫が返済できなくなり、金融機関から返済を求められた時には、連帯保証人である妻が全額を返済しなければなりません。
検索の抗弁権がない
検索の抗弁権とは、金融機関が返済を要求した場合、保証人が「主債務者の資産から回収してください」と主張できる権利のことです。連帯保証人には検索の抗弁権がないため、主債務者の資産を優先的に差し押さえるよう要求できません。例えば、主債務者である夫が返済できなくなった場合、金融機関は連帯保証人である妻に返済を要求できます。この時「夫に資産があるからそちらに請求してください」とは主張できません。結果として、妻が返済する義務を負うことになります。
分別の利益がない
分別の利益とは、保証人が複数いる場合、各保証人はその人数に応じて負担を分け合う権利のことです。例えばローンの残債が1,000万円で、保証人が2人いる場合。それぞれの保証人は、500万円までの責任を負えば問題ありません。しかし、連帯保証人には分別の利益がないため、人数に関係なく、全額を返済する義務を負います。
住宅ローンの連帯保証人のまま離婚するとどうなる?
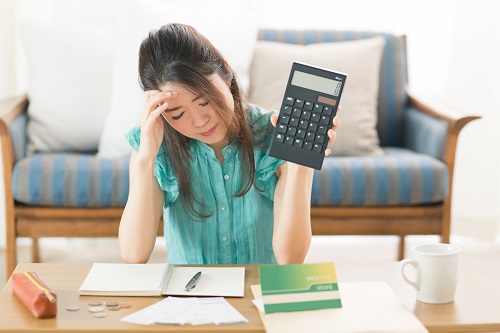
住宅ローンの連帯保証人のまま離婚をすると、どのようなリスクがあるのでしょうか。本章では、2つのリスクを解説します。
万が一の場合に返済を求められる可能性がある
住宅ローンの連帯保証人のまま離婚した場合、主債務者が返済を滞らせてしまった時に、返済を求められる可能性があります。先述のとおり連帯保証人には、保証人に認められている3つの権利がありません。そのため、金融機関から返済を求められた時に、連帯保証人として全額を返済する義務があります。
離婚をしたからといって、自動的に連帯保証人から外れるわけではありません。たとえ「契約者が住宅ローンの返済を続ける」と話し合いで決めたとしても、連帯保証人から外れる手続きをしなければ、万が一の場合に全額返済を求められます。
新しいローンを組む際に影響が出る可能性がある
住宅ローンの連帯保証人のまま離婚をすると、新しいローンを組む際に影響が出る可能性があります。ローンを組む際には、返済能力を判断するために、金融機関は信用情報機関に対して、信用情報の照会をおこないます。信用情報とは、ローンの契約や返済状況などをまとめた情報のこと。この信用情報には、連帯保証人になっているかも含まれています。
すでに住宅ローンの連帯保証人になっている場合、万が一の時に返済する義務を負うことから、金融機関からリスクが高いと判断される可能性も。そのため、住宅ローンの連帯保証人になっていることが原因で、新しいローンを組めないおそれがあります。離婚後に新しい生活を送る際、住宅ローンに限らず何かしらローンを組むこともあるでしょう。そのため離婚時に、連帯保証人から外れる手続きをしておくことをおすすめします。
住宅ローンの連帯保証人から外れる方法

住宅ローンの連帯保証人のまま離婚をすると、万が一の場合に返済を求められるリスクがあります。そのため離婚をする際には、連帯保証人から外れたほうがいいでしょう。本章では、住宅ローンの連帯保証人から外れる方法を4つ解説します。
連帯保証人を変える
住宅ローンの連帯保証人から外れる方法の一つは、連帯保証人を変更することです。しかし、新しい連帯保証人が経済的に安定しており、返済能力があると金融機関から認められなければなりません。離婚にともなって連帯保証人を変える場合、住宅ローンの主債務者の親族から選ぶことが一般的です。のちのトラブルを防ぐためにも、誰を連帯保証人にするか、早めに相談しましょう。
住宅ローンを借り換える
住宅ローンを借り換えることも、連帯保証人から外れる方法の一つです。住宅ローンの借り換えとは、別の金融機関で新しくローンを組み、もとの住宅ローンの残債を完済すること。これにより、もとの住宅ローンは完済されて契約が終了するため、連帯保証人から外れることが可能です。
ただし、住宅ローンを借り換える際には、再度審査を受けなければなりません。ペアローンや収入合算でローンを組んでいた場合、一人の収入では返済能力が不足していると判断され、審査に通らない可能性がある点を把握しておきましょう。
他の財産を担保に入れる
新しく連帯保証人になる人が見つからない場合、他の財産を担保に入れることで、連帯保証人から外れられます。ただし、担保に入れる財産が、金融機関にとってローンの返済を十分にカバーできるものでなければなりません。
例えば、別荘や土地、有価証券などが挙げられます。担保価値が不十分であれば、認められない可能性もある点に注意しましょう。
家を売却する
家を売却することも、住宅ローンの連帯保証人から外れる方法の一つです。売却によって得た売却益で住宅ローンを完済できれば、返済義務がなくなるため、連帯保証人としての責任を負わずに済みます。ただし、住宅ローンが残っている家を売却する際には、金融機関から承諾を得なければなりません。また、売却益で住宅ローンを完済できなかった場合は、残りのローンを返済する必要があります。この場合、どのように返済を続けるか、のちのトラブルを防ぐためにも、しっかり話し合いましょう。
離婚時に住宅ローンの連帯保証人から外れる際の手順

住宅ローンの連帯保証人のままでいると、離婚後にもリスクがともないます。本章では、連帯保証人から外れる手順を解説します。簡単な流れは次のとおりです。
- STEP 1 住宅ローンの契約内容を確認する
- STEP 2 配偶者とよく話し合う
- STEP 3 金融機関で手続きをおこなう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
step1:住宅ローンの契約内容を確認する
まずは、住宅ローンの契約内容を確認しましょう。具体的には、以下のとおりです。
- 住宅ローンの名義人
- 家の名義人
- 住宅ローンの残債
- 家の査定価格
離婚をする際には、住宅ローンが残る家をどうするか、ローンの返済をどうするかなど、話し合わなければならないことが多々あります。この時、住宅ローンの残債と家の査定価格がどういう関係なのかによって、今後の動きも変わります。
先述したように、住宅ローンの残債よりも売却価格が高ければ、ローンの完済が可能。ローンを完済し、残った金額で財産分与ができます。反対に、売却価格よりも住宅ローンの残債が多ければ、売却自体が難しくなります。家や住宅ローンを今後どうするのかを決めるためにも、これらの内容を確認しておきましょう。
step2:配偶者とよく話し合う
住宅ローンの契約内容を確認したら、配偶者とよく話し合いましょう。具体的には次の点について、決めておく必要があります。
- 家や住宅ローンの名義人をどうするか
- 住宅ローンの返済をどうするか
- 連帯保証人を誰にするか
これまでの不満から、感情的になってしまうこともあるかもしれません。2人だけでの話し合いが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
step3:金融機関で手続きをおこなう
話がまとまったら、金融機関で手続きをおこないましょう。なお、連帯保証人の変更手続きは、主債務者がおこなわなければなりません。また、住宅ローンを借り換える場合には、新しい金融機関に申し込み、審査を受ける必要があります。ただし、これまでに住宅ローンを滞納していた場合、連帯保証人の変更、ローンの借り換えのどちらも難しくなります。これまで返済をしっかり続けたからこそ、選択できる方法であることを理解しておきましょう。
離婚時の住宅ローンの連帯保証人に関するよくある質問
離婚時の住宅ローンの連帯保証人に関するよくある質問をまとめました。
離婚したら住宅ローンの連帯保証人から抜けられる?
離婚をしたら住宅ローンの連帯保証人から自動的に外れるわけではありません。連帯保証人から外れるためには、金融機関の承諾を得る必要があります。具体的な方法としては、「新しい連帯保証人を立てる」、「他の財産を担保にする」の2つです。また、住宅ローンを借り換えたり、家を売却して住宅ローンを完済することで、連帯保証人から外れることも可能です。
離婚後も住宅ローンの連帯保証人の場合、配偶者は責任を負う?
離婚後も住宅ローンの連帯保証人のままでいる場合、返済義務を負います。連帯保証人には、保証人には認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。そのため、主債務者がローンの返済ができなくなった場合は、離婚後であっても連帯保証人として全額返済する義務を負います。
住宅ローンの連帯保証人が亡くなった場合はどうなる?
もし住宅ローンの連帯保証人が亡くなった場合、相続人に連帯保証人が引き継がれます。しかし、相続人が相続放棄をした場合には、引き継がれません。ただし、金融機関から新しい連帯保証人を立てるよう求められる可能性があります。
まとめ
本記事では、住宅ローンの連帯保証人のまま離婚をするとどうなるのかを解説しました。連帯保証人は保証人よりも責任が重く、主債務者に万が一のことがあった場合、全額返済する義務を負います。離婚後も連帯保証人のままでいると、新しくローンを組む際に影響が出る可能性もあるため、連帯保証人から外れたほうがいいでしょう。
連帯保証人から外れる方法はいくつかありますが、新しく連帯保証人を立てる場合は、返済能力があると判断されなければ認められません。また、住宅ローンの残債や家の査定価格によって、選択肢も異なります。まずは現在の住宅ローンの残債がいくらなのか、売却するとしたらいくらなのかを調べてみましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







