住宅ローンの利息の計算方法とは?金利タイプを理解してから算出しよう

そこで本記事では、住宅ローンの利息の計算方法をご紹介します。住宅ローンを取り扱っている金融機関のサイトには、無料のシミュレーションツールが用意されていることもあるので、それらも利用しながら無理なく返済できる範囲の借り入れ額を把握しておきましょう。
記事の目次
住宅ローンの金利タイプ

住宅ローンを利用する際、まずは金利タイプと利息の仕組みをしっかりと把握することが大切です。住宅ローンを組むと、金利や返済期間をもとにして利息が計算され、毎月決められた金額を返済していくことになります。
他のローンに比べて住宅ローンは借入金額が大きく、返済期間も長期にわたります。全期間固定金利型を選ばない限り、契約時から完済まで同じ金利が適用されることはほとんどありません。
住宅ローンの代表的な金利タイプ
一般的に、住宅ローンの金利タイプには実勢に応じて金利が変動する「変動金利」、そして一定期間または完済までずっと金利が変わらない「固定金利」が挙げられます。
固定金利には「全期間固定金利」と「固定金利期間選択型」があり、それぞれのタイプで利息の計算方法が異なるため、自分の金利タイプを理解しておきましょう。
住宅ローンの利息を計算する前に知っておくべきこと

住宅ローンの返済額は、「元金」だけではありません。「利息」も含まれています。返済方法によって、元金と利息の割合が変わるため、利息の計算をする前に自分の返済方法を知っておくことが重要です。住宅ローンには主に「元利均等返済」と「元金均等返済」の2つの返済方法があります。詳しくは以下で解説するので、確認しておきましょう。
ローンの返済額に含まれるもの
例えば、住宅ローンで4,000万円を借りた場合、単純にその金額だけを返済するわけではなく、元金に発生する利息も返済しなければなりません。利息は元金に加えて支払うものとイメージしておくとよいでしょう。利息の金額は、借り入れた元金と適用される金利に基づいて計算されます。
元利均等返済と元金均等返済の違い
住宅ローンの返済方法には、元利均等返済と元金均等返済の2種類があります。それぞれの特徴を理解することで、自分に合った返済方法を選べるでしょう。
元利均等返済は、返済初期は利息の割合が高く、元金の返済が緩やかな点が特徴です。そのため、常に返済額は一定ですが、元金が減るペースは遅くなります。
元金均等返済では、毎回返済する元金の額が一定で、初期の返済額は高くなります。しかし、返済が進むにつれて利息が減るため、総返済額は少なくなっていきます。元金均等返済のほうが総支払利息は少なく済むものの、初期の負担が大きくなる点には注意が必要です。

- 元金均等返済と元利均等返済の違いは?メリット・デメリットや向いている人を解説
- 住宅ローンを組んで持ち家を購入しようと考えている方は、住宅ローンについていろいろと調べるなかで、専門用語が多く
続きを読む

住宅ローンの金利から利息を計算する方法
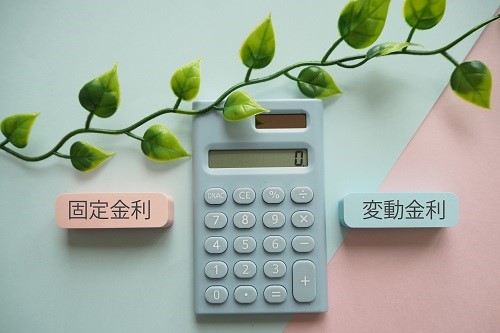
ここからは、住宅ローンの金利から利息を算出する方法を解説します。通常、私たちが目にする「金利」は年利であり、実際の利息を計算するには年利を月利に換算しなければなりません。
計算式は以下のとおりです。
年利(%)÷ 12 = 月利(%)
月利を使って、月々の利息を計算します。
住宅ローン残高 × 月利(%)= 月々の利息額
上記を参考にしながら、計算していきましょう。
元利均等返済の計算方法
元利均等返済では、まず月々の返済額を計算し、そのあとに利息を計算します。計算式は以下のとおりです。
※「^」は累乗
利息の返済額 = 直近のローン残高 × 月利
元金返済額 = 月々の返済額 - 利息
【計算例】
借入金額:4,000万円
返済期間:35年
金利:0.5%
毎月返済額 = 4,000万円 × 0.5% / 12 ×(1+ 0.5% / 12)^420 / {(1+ 0.5% / 12)^420 ー1} = 103,834円(ボーナス決済なし)
利息 = 4,000万円 ×(0.5% ÷ 12)=1万6,666円
月々の返済額 = 10万3,834円 -1万6,666円 =8万7,168円
返済が進むと、利息の額はローン残高に合わせて減少していきます。特定の時期(例えば、1年後、10年後など)の利息を知りたい場合は、その時点の残高で計算をおこないます。
元金均等返済の計算方法
元金均等返済では、計算が少しシンプルになります。元金部分が一定のため、利息も返済が進むにつれて減っていきます。
元金返済額 = 借入金額 ÷ 返済回数(35年は12カ月 × 35年 = 420回)
利息 = 住宅ローン残高 × 月利(%)
月々の返済額 = 元金返済額 + 利息
【計算例】
借入金額:4,000万円
返済期間:35年
金利:0.5%
利息 = 4,000万円 ×(0.5% ÷ 12)=1万6,666円
月々の返済額 =9万5,238円 +1万6,666円 = 11万1,904円
※小数点以下は切り捨て
同じ条件でも元金均等返済のほうが初期の月々の返済額が高いことがわかります。返済期間が進むごとに利息が減るため、総返済額は元利均等返済よりも低く抑えられる点が特徴です。
利息や返済額を計算する際のポイント
住宅ローンの返済額や利息を計算する際に知っておきたいのは、計算結果が必ずしも実際の返済額に一致しないことです。特に変動金利や期間選択型の固定金利を選んだ場合、金利の変動によって当初の計算よりも利息が増加する可能性があります。
低金利を前提にして、返済可能なギリギリの金額で借り入れをおこなった場合、金利が上昇した際に返済が困難になる恐れも。全期間固定金利を選ばない限り、金利上昇のリスクがあることを念頭に置き、複数のシミュレーションをおこなっておくことが大切です。
また、利息の計算は難しく、自分で計算するのは手間がかかります。そのため、住宅ローンを比較する際には、シミュレーションツールを活用するのがおすすめです。
例えば、住宅金融支援機構が提供している「返済プラン比較シミュレーション」では、最大3つのプランを同時に比較し、返済額や利息を簡単に確認できます。また、不動産情報サイトアットホームの「不動産 資金計算シミュレーション」でも、返済額のシミュレーションが可能。
このようなツールを活用することで、手軽に複数の返済プランを比較できるため、自分に合ったローン選びが可能になるでしょう。
金利タイプごとの計算方法

金利プランによって、住宅ローンの利息支払い総額は大きく異なります。ここでは、4,000万円の住宅ローンを組んだ場合の各金利プランの特徴と利息支払い総額のシミュレーションを参考にしながら見ていきましょう。
全期間固定金利の場合
全期間固定金利は、返済開始から完済まで同じ金利が適用されるプランです。金利が変わらないため、長期的な返済計画を立てやすい点がメリット。
ただし、一般的にほかの金利プランに比べて金利が高く設定されているため、総返済額も大きくなりやすいデメリットがあります。金利上昇のリスクを避けられる一方で、金利が下がった際は逆に返済負担が大きくなることも。
<シミュレーション条件>
借入金額:4,000万円
返済期間:35年
金利:全期間固定金利1.7%
返済方式:元利均等方式
| 毎月の返済額 | 12万6,430円 |
|---|---|
| 総返済額 | 5,310万430円 |
| 利息支払い総額 | 1,310万430円 |
固定金利期間選択型の場合
固定金利期間選択型は、契約当初に設定した期間(例:5年や10年)に関しては固定金利が適用され、そのあとは変動金利に切り替わるプランです。
固定期間終了後に再度固定金利を選択することも可能で、特にローン開始直後に大きな支出が予定されている方におすすめです。短期的な金利変動リスクを避けつつ、長期的な金利の変動に柔軟に対応できる点が特徴です。
<シミュレーション条件>
借入金額:4,000万円
返済期間:35年
金利:返済開始から10年間は1.5%、その後は1.8%に上昇
返済方式:元利均等方式
| 当初10年間の毎月の返済額 | 12万2,473円 |
|---|---|
| 10年後の見直し後の毎月の返済額 | 12万6,837円 |
| 総返済額 | 5,274万7,830円 |
| 利息支払い総額 | 1,274万830円 |
上記の結果から、全期間固定金利と比較して利息支払い総額は約35万円少なくなることがわかります。
変動金利の場合
変動金利は、半年に一度金利の見直しがおこなわれるプランです。しかし、返済額は見直し後すぐに反映されるわけではありません。
5年間は返済額が一定となる「5年ルール」と、返済額の変動幅を125%以内に抑える「125%ルール」が特徴ですが、一部のネット銀行ではこのルールを適用していない場合もあるため、事前に確認が必要です。
<シミュレーション条件>
借入金額:4,000万円
返済期間:35年
当初10年間の金利:1%
11~20年目の金利:1.5%
21年目以降の金利:2%
返済方式:元利均等方式
| 当初10年間の毎月の返済額 | 11万2,914円 |
|---|---|
| 11~20年目の返済額 | 11万9,824円 |
| 21年目以降の返済額 | 12万4,218円 |
| 総返済額 | 5,028万7,831円 |
| 利息支払い総額 | 1,028万7,831円 |
上記のシミュレーション結果では、変動金利が他と比べて利息支払い総額を抑えられることがわかりました。ただし、変動金利は市場金利の影響を受けるため、金利が急上昇した場合には支払額が増加するリスクがあります。
金利の変動による影響

日本は長期間にわたり低金利政策を維持していました。
しかし残念ながら、現在はマイナス金利政策が解除されてしまいました。国内大手の銀行では、住宅ローンの金利基準である「短期プライムプレート」が上昇し始めているのです。
2024年12月には日銀が利上げすると見込まれており、現在安易に変動金利を選ぶのは危険かもしれません。現在住宅ローンを検討している方は、状況を見極め、自分の資産と相談しながら慎重に決めることが大切です。
金利が変動することで、上記のシミュレーションにどのような違いが生まれるのか、以下で見ていきましょう。
<シミュレーション条件>
借入金額:4,000万円
返済期間:35年
当初金利:2%
返済方式:元利均等方式
金利が変動しなかった場合
| 毎月の返済額 | 13万2,505円 |
|---|---|
| 総返済額 | 5,565万1,862円 |
| 利息支払い総額 | 1,565万1,862円 |
金利が1%上昇した場合(10年後に3%に上昇)
| 最初の10年間の返済額 | 13万2,505円 |
|---|---|
| 金利上昇後の返済額 | 14万8,247円 |
| 総返済額 | 6,037万4,671円 |
| 利息支払い総額 | 2,037万4,671円 |
金利が1%下がった場合(10年後に1%に下落)
| 最初の10年間の返済額 | 13万2,505円 |
|---|---|
| 金利低下後の返済額 | 11万7,817円 |
| 総返済額 | 5,124万5,689円 |
| 利息支払い総額 | 1,124万5,689円 |
上記のように、金利が1%上昇すると利息負担は約472万円増加し、逆に1%下がると約441万円減少します。金利変動によって総返済額が大きく変わるため、状況に合わせて借り換えや繰り上げ返済を検討したほうがよいでしょう。
低金利が続いているうちに将来に備えて資金を確保し、繰り上げ返済をおこなうことで利息支払いを減らす手もあります。
住宅ローンを選ぶ際に気をつけるべきポイント

住宅ローンの返済計画を立てる際は、支払う利息を把握しておくべきです。しかし、それ以外にも注意すべき点も多くあります。それぞれの注意点を以下で見ていきましょう。
ライフプランに合わせて慎重に金利タイプを選ぶ
金利タイプの選択は、将来のライフプランや金利の動向を見据えておこなうことが大切です。例えば、金利の変動に柔軟に対応したい方は、変動金利を選ぶとよいでしょう。変動金利では、金利が下がれば、利息や総返済額が予想より少なくなる可能性があります。
一方、一定期間の利息を安定させたい方には期間選択型の固定金利が適しています。上記のタイプは、返済開始時の金利が比較的低く設定されていることが多く、固定期間中は金利変動の影響を受けにくいため安心です。
返済額の変動を避けて長期的な見通しを立てたい場合は全期間固定金利が適しています。教育費や老後の資金計画も立てやすくなるため、なるべくライフプランを崩したくない方におすすめです。
返済方法の違いによる影響があることを理解する
返済額を計算すると、返済方法によって月々の支払い額や総返済額に大きな違いが出ることがわかります。例えば、元利均等返済は借り入れ当初の月々の支払い額を抑えたい場合に適しています。しかし一方で、総返済額を少なくしたいのであれば、元金均等返済のほうが利息の支払いを減らせます。
どちらの返済方法にも利点と注意点があるため、一概にどちらがよいとはいえません。自身の家計状況やライフプランを考慮し、どちらの方法がより適しているかを慎重に検討しましょう。返済計画に迷った場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することもおすすめです。
諸費用がかかることも考慮しておく
住宅ローンを組む際には、利息だけでなく、契約時に発生する諸費用も準備しておく必要があります。主な諸費用として以下があります。
- 印紙税:ローン契約書に貼付する印紙代。ただし、電子契約の場合は不要。
- 事務手数料:融資手続きにかかる費用。金融機関によっては保証料が別途発生することも。
さらに、不動産購入時には以下のような手数料や税金も発生します。
- 売買契約や建築契約の印紙税
- 司法書士手数料:不動産登記の際の報酬
- 登録免許税:不動産登記時に支払う税金
- 不動産取得税:物件取得時に支払う地方税
- 火災保険料:ローン契約に必須の保険
- 不動産仲介手数料:仲介会社を利用する際の手数料
- 修繕積立基金:将来の大規模修繕のための費用
- 水道加入金:建売住宅の場合に発生することが多い
また、住宅購入後には引越し費用や新たな家具・家電の購入費用も発生します。これらの支出も考慮し、資金計画をしっかり立てておくことが重要です。必要な費用を見越し、余裕をもった資金計画を立てることが、安心してマイホームを手に入れるためのポイントです。
まとめ
本記事では、住宅ローンの利息の計算方法を具体的に解説しました。
住宅ローンの返済方法と利息の計算を理解し、無理のない返済プランを立てることが重要です。変動金利や固定金利などそれぞれの特徴を知り、自分の返済能力やライフプランに合った選択をすることで、長期間の返済でも家計への圧迫を避けられるでしょう。
物件を探す

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







