個人事業主の住宅ローンは経費になる? 住宅ローン控除を受ける方法も紹介

本記事では、個人事業主の住宅ローンは経費になのか解説し、住宅ローン控除についても詳しく紹介します。
記事の目次
個人事業主の住宅ローンは経費になる?

居住用のスペースが一定以上ある住宅であれば、個人事業主が事業用に使用するスペースがあっても住宅ローンを組んで購入できます。一部でも事務所利用するために住宅ローンを組んだ場合、経費にできる部分があるか解説します。
返済の元本は経費にできない
住宅ローンの元本は経費にできません。住宅ローンに限らず、借りたお金は事業に関わる費用であっても、経費に算入しないことになっているからです。そのため、住宅ローンを返済する費用は経費に算入できません。借入金などは損益に該当しないと税務上判断されることから、現行の制度では住宅ローンの元本部分の返済を経費に算入しない仕組みとなっています。
利息部分のみ経費にできる
住宅ローンの元本部分は経費にできませんが、発生する利息部分に関しては経費に算入できます。ただし、住宅兼事務所のようにすべてのスペースを事業用として使用していない場合は、利息部分の全額を経費に算入できません。
経費を計算するなら、一般的に建物のスペースのなかで事業に使用する割合を計算し、割合に基づいて利息を計算します。これを「家事按分」と呼び、生活費と事業費を切りわける考え方です。住宅ローンの利息部分は経費に算入できますが、家事按分により明確な基準をおいて事業に必要な経費に該当する部分を計算して算入する必要があります。
個人事業主が経費にできる費用の考え方

個人事業主が住宅兼事務所において、住宅ローンの利息部分以外の費用を経費に算入できるか判断するには、経費にできる費用について理解することが重要です。以下に3つ紹介します。
- 事業に必要な費用のみを経費にできる
- 事務所は事業用と居住用で明確にわける必要がある
- 事務所の減価償却費・固定資産税を経費にできる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
事業に必要な費用のみを経費にできる
前提として個人事業主が経費にできるのは、事業に必要な費用のみです。反対にいえば、事業に必要と認められない費用を経費に算入できません。経費になるかわからない費用は、客観的に事業に必要であると認められることが重要です。
事務所は事業用と居住用で明確にわける必要がある
個人事業主の生活と事業において重要な拠点である住宅兼事務所は、事業用のスペースと居住用のスペースで明確に分ける必要があります。明確に分けなければ、事業に必要な費用と事業に必要でない生活費などの出費が混在してしまうからです。事業に必要と認められない費用を経費に算入できないことから、明確に分けたうえで経費として申告します。
家事按分は、生活費と事業費を切りわける考え方ですが、住宅ローンの利息だけでなく以下のような費用に対しても求められます。
- 電気料金
- ガス・水道料金
- 通信費
電気料金は、自宅のコンセントで事業用に使用している差し込み口の数の割合から経費を求める方法などで算出可能であり、ガス・水道費や通信費は事業で使用した時間を基準に経費を算出できます。住宅ローンの利息部分を経費として申告するなら、家事按分の考え方を必ず理解しておきましょう。
事務所の減価償却費・固定資産税を経費にできる
住宅兼事務所では住宅ローンの利息部分を経費にするだけでなく、事業用に使用する面積に応じた減価償却費・固定資産税を経費にすることも可能です。減価償却は、固定資産の購入額を分割し、複数年にわけて経費に計上します。固定資産税は、住宅などの所有する固定資産に対して課せられる税金ですが、所得にかかる税金でないことから経費に算入できます。
住宅兼事務所において、事業に使用する面積が大きいほど経費に算入できる費用は高まりやすいといえるでしょう。しかし、面積が大きすぎると住宅ローンで借り入れができない場合や、後述する住宅ローン控除を受けるうえで不都合が生じる点に注意が必要です。
個人事業主が住宅ローン控除を受けるには?

住宅ローン控除は、住宅ローンの年度末残高を基準に一定の控除率で税金を控除する制度です。個人事業主が住宅兼事務所を住宅ローンで購入して、住宅ローン控除を受ける場合も、共通した住宅ローン控除の適用条件を満たすことで可能です。適用条件を以下にまとめました。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 居住のタイミング | 工事完了から6カ月以内 |
| 住宅の床面積 | 50平方メートル以上 |
| 居住用の床面積 | 50%以上 |
| 返済期間 | 10年以上 |
上記の適用条件において、住宅兼事務所で控除を受けるために注目したいポイントは居住用の床面積の割合です。それぞれのケースにおける住宅ローン控除の適用状況を見ていきましょう。
居住用の床面積を50%以上にする
住宅ローン控除は居住用の床面積を50%以上にすることで受けられます。例えば、居住用の床面積を70%、事業用の床面積を30%にすれば住宅ローン控除を受けられますが、全額の控除は受けられません。
住宅ローン控除も居住用の床面積の割合に応じた控除となるため、居住用の床面積が100%の場合と比較すると控除額が減少します。
居住用の床面積を90%以上にすれば全額控除可能
住宅兼事務所の住宅ローン控除は、事業用の床面積の割合に応じて減額しますが、居住用の床面積が90%以上で事業用の床面積が10%以下であれば居住用の床面積を100%として控除が可能です。
また、10%以下の事業用のスペースで発生した費用に関しても経費に算入可能です。居住用の床面積を90%以上にすれば、住宅ローン控除で全額控除しながら、住宅ローンの利息などの経費を申告できます。
住宅ローン控除と経費のどちらを優先するべき?

住宅ローン控除の控除額と住宅兼事務所で発生する経費は、床面積の割合において逆相関の関係にあります。事業用のスペースを増やせば経費に算入できる費用は増えますが、居住用の床面積が減るため控除額が減少します。一方で、居住用の床面積が増えると住宅ローン控除の控除額は増加しますが、算入できる経費は減少します。
居住用の床面積を90%以上にして、居住用の床面積を100%として控除額を計算し、10%以下の事業用のスペースで発生した費用を経費に算入することが節税メリットの最大化において理想です。しかし、各々の事業の都合によっては不可能になる場合もあるため、ケースで分けて考えていきます。
事業をメインに居住用のスペースも確保する
事業をメインにおこなう場合は、居住用の床面積の確保は住宅ローン控除が受けられる50%以上にしたいところです。住宅ローン控除を受けながら、住宅ローンの利息・減価償却費・固定資産税などの経費に算入できる費用をすべて申告するようにしましょう。
居住をメインに事務所の機能も備える
居住をメインに事務所の機能も備える住宅兼事務所であれば、事業用の床面積を10%以下に抑えて、住宅ローン控除で全額の控除が受けられるようにするとメリットは大きくなります。居住をメインに考えている場合は、床面積の割合を意識して住宅ローン控除で全額控除を受けられる状態にしましょう。
個人事業主が住宅ローン控除を受ける場合のシミュレーション
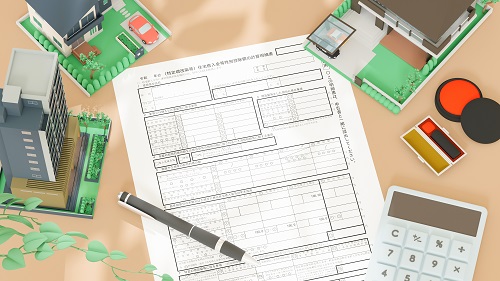
個人事業主が住宅ローン控除を受ける場合のシミュレーションを、居住用の床面積でケース分けしておこなっていきます。
居住用の床面積を90%以上にして全額控除する
まずは、全額が控除できるケースで住宅ローン控除の計算をしていきましょう。
- 住宅ローンの年度末残高:4,000万円
- 住宅の種別:長期優良住宅
- 控除率:0.7%
- 居住用の床面積の割合:90%
- 事業用の床面積の割合:10%
- 4,000万円(住宅ローンの年度末残高)×0.7%(控除率)=28万円(控除額)
こちらのケースでは、住宅ローン控除で全額控除が受けられるため、ローンの年度末残高に控除率をかけて全体の控除額が求められます。
居住用の床面積を50%にして控除を受ける
次に、居住用の床面積が50%で住宅ローン控除が一部のみ受けられる場合の計算をおこないます。
- 住宅ローンの年度末残高:3,000万円
- 住宅の種別:長期優良住宅
- 控除率:0.7%
- 居住用の床面積の割合:50%
- 事業用の床面積の割合:50%
- 3,000万円(住宅ローンの年度末残高)×0.7%(控除率)=21万円(全体の控除額)
- 21万円(全体の控除額)×50%(居住用の床面積の割合)=10.5万円(居住用の床面積に基づく控除額)
最初に全体の控除額を求めたあとで、居住用の床面積の割合をかけることで、正確な控除額が求められます。
また、住宅ローン控除は納税者の収入を含めた納税状況によって、実際に控除される金額は変化する点に注意が必要です。個別具体的なケースにおいて、節税効果を最大化するなら、事業の確定申告を含めて税理士などのお金の専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
個人事業主が契約する住宅ローンは、事業用に使用する面積の利息部分のみ経費に算入できます。ただし、住宅ローンを組む場合は居住用のスペースが一定以上求められることもあり、住宅ローン控除の控除額を最大化するほうがメリットは大きくなりやすいです。ご自身の事業にあわせて、メリットの大きい床面積の割合を考え、申告できる経費と利用できる節税制度はすべて利用することで節約につながります。
物件を探す

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





