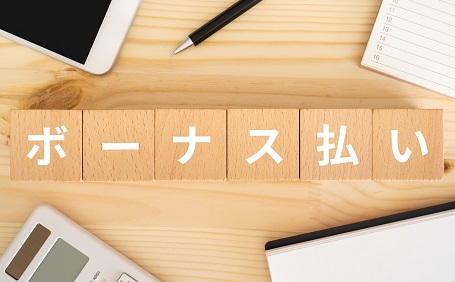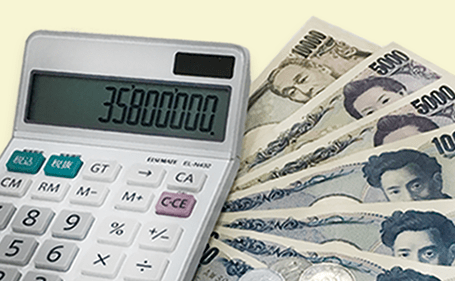公務員は住宅ローンの金利が優遇される?審査に落ちる理由や住宅ローンを比較する際のポイントを解説
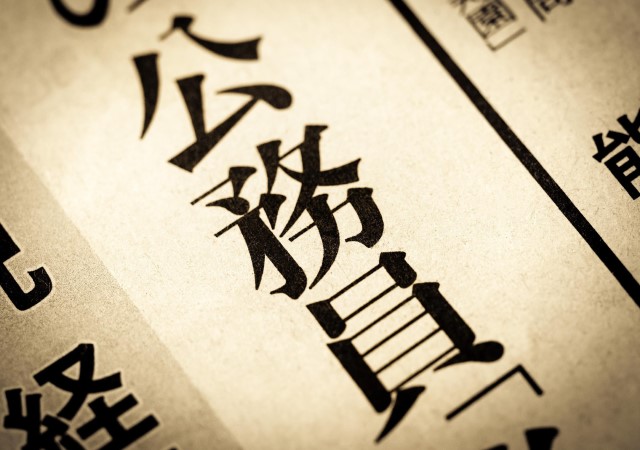
記事の目次
公務員が住宅ローンの金利で優遇される理由

なぜ、公務員が住宅ローンの金利で優遇されるのでしょうか。それには3つの理由があります。それぞれ詳しく解説します。
収入が安定している
公務員が住宅ローンの金利で優遇を受けやすくなっている理由は、収入が安定しているためです。地方公務員の給与は、各地方自治体の給与条例によって定められています。国家公務員の場合も、法律に基づいて定められており、民間企業における賃金との適正な均衡を確保しながら調整されています。なお、総務省の「令和5年地方公務員給与実態調査結果等の概要―平均給与月額」によると、全地方公共団体の公務員(一般行政職)の平均給料月額は31万5,159円となっています。
雇用が安定している
雇用が安定していることも、公務員が住宅ローンの金利で優遇される理由の一つです。公務員は、国家公務員法や地方公務員法によって身分が保証されています。また、経済状況に左右されないため、経営不振によるリストラをされる心配もありません。情報漏えいや横領などの不祥事を起こさなければ、定年まで働き続けられます。これらのことから、公務員は安定した返済能力があると判断され、金利が優遇されます。
退職金制度がある
公務員には退職金制度があることも、住宅ローンの金利で優遇を受けられる理由です。退職金の金額は法律で規定されており、勤続年数や役職によって異なります。総務省の「令和5年地方公務員給与の実態」によると、一般職員の勤続25年以上の定年、または応募認定退職者一人当たりの平均退職者手当は、60歳定年等退職者で2,117万1,000円。定年退職後にも住宅ローンの残債がある場合、退職金は返済する際の十分な資金源となるでしょう。退職金制度が整っていることは、金融機関から見ると信用度が高く、安心して融資できることから、金利が優遇されやすくなります。
公務員でも住宅ローンの審査に通らない時の理由

公務員の方は、雇用や収入が安定していることから、住宅ローンの金利が優遇される傾向にあります。しかし、場合によっては審査そのものに通らないことも。なぜ審査に通らないのか、その理由を解説します。
信用情報に傷が付いている
信用情報に傷が付いていると、公務員の方でも住宅ローンの審査に通ることは厳しくなります。信用情報とは、ローンの申込状況や返済状況などの記録のこと。もし、クレジットカードの返済が遅れたり滞納していたりした場合、「事故情報」として登録されます。住宅ローンの審査では、金融機関は信用情報を確認し、返済能力に問題がないかを判断します。事故情報が登録されていた場合、返済能力に問題があるとみなされることから、住宅ローンの審査に通らない可能性が高くなります。住宅ローンに申し込む前は、すでに借り入れているローンを確実に返済しましょう。ご自身の信用情報がどうなっているかを知りたい場合は、事前に信用情報機関に確認することができます。
借入金額が大きい
雇用や収入が安定している公務員の方であっても、借入金額が多すぎると、住宅ローンの審査に通らない可能性があります。先述したように、金融機関は申込者の返済能力を評価します。借入金額が多いと返済負担率が高くなることから、返済が滞るリスクがあると判断されます。返済負担率とは、収入に対して住宅ローンの返済額が占める割合のこと。住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携する「フラット35」では、返済負担率が次のように設定されています。
| 年収 | 400万円未満 | 400万円以上 |
|---|---|---|
| 基準 | 30%以下 | 35%以下 |
例えば、年収450万円の場合、年間の返済額は157万5,000円以下でなければなりません。また、この返済額は住宅ローンだけではなく、マイカーローンや教育ローンなども含めたものです。なお、一般的に無理のない返済負担率は20%以下とされています。
健康状態に問題がある
健康状態に問題がある場合、公務員であっても住宅ローンの審査に通らない可能性があります。住宅ローンを契約する際には、金融機関から団体信用生命保険(以降、団信)への加入を求められることが一般的です。団信とは、住宅ローンの契約者が死亡したり、高度障害になったりした場合、住宅ローンの残債を保険金でまかなうもの。契約者に万が一のことがあった場合、残された家族の経済的な負担が大きくなることから、団信への加入が求められます。
しかし、団信に加入する際には、健康状態を申告しなければなりません。もし健康状態が悪い場合、団信に加入できず住宅ローンの審査に通らないことがあります。しかし、なかには団信に加入するための基準が緩和されているものや、団信への加入を義務付けていないローンもあります。健康状態に不安がある場合は、これらの住宅ローンを利用することも一つの方法です。
公務員が住宅ローンを借りるならどこがいい?比較するポイント

さまざまな金融機関が住宅ローンを提供しています。そのなかから一つのローンを選ぶとなると、何を基準にすべきか迷われる人も多いでしょう。本章では、住宅ローンを比較する際のポイントを5つ解説します。
審査基準
金融機関によって、住宅ローンの審査基準は異なります。審査基準は公表されているものではありませんが、申込条件を見ると、どのような人物が求められているのかを読み取ることができます。例えば、SBI新生銀行の場合、次のように年収や雇用形態に関する申込条件が盛り込まれています。
引用:SBI新生銀行「<パワースマート住宅ローン>商品説明書」
公務員の方であっても、転職して間もなく年収が基準に満たない場合や臨時職員などの場合は、申し込んでも審査に通らない可能性が高いでしょう。公務員の方が住宅ローンに申し込む際は、申込条件を満たしているかを確認しましょう。
諸費用
住宅ローンを借り入れる際、金融機関や借入金額によって諸費用が異なります。諸費用には、融資を実行するための事務手数料や保証料、火災保険料などがあります。例えば、事務手数料には定額型と定率型の2種類があります。2種類の違いは次のとおりです。
- 定額型:手数料が一律で定められている
- 定率型:借入金額に応じて手数料の金額が変動する
定率型は、借入金額に対して2.2%とされていることが一般的です。もし借入金額が2,000万円の場合は48万4,000円、5,000万円の場合は110万円が手数料としてかかることに。もし金利が優遇されても、これらの諸費用が高ければ、総合的に見たコストは多くなってしまいます。そのため、金利の優遇だけでなく、諸費用がいくらかかるのかも確認しておきましょう。
金利タイプ
金利タイプも、住宅ローンを比較する際の重要なポイントの一つです。金利タイプは大きく、固定金利と変動金利の2つに分けられます。それぞれの違いは次のとおりです。
固定金利
固定金利は、借り入れ当初から完済まで金利が固定されるタイプです。金利変動の影響を受けにくいため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。固定金利には、「固定期間選択型」と呼ばれるものもあります。これは、契約者が選んだ期間の金利が固定されるタイプ。3年、5年、10年などから、固定期間を選択できます。固定期間の終了後は、再度固定金利か変動金利かを選択します。
変動金利
変動金利は、市場の金利変動に応じて金利が変動するタイプです。市場金利が上昇すると、住宅ローンの金利も上昇し、返済負担が増える可能性があります。金融機関によっては、返済額の増加による経済的な負担を軽減するため、「5年ルール」や「125%ルール」を設けているところもあります。5%ルールが適用されると、金利が変動しても5年間は返済額が変わりません。125%ルールが適用された場合は、以前の返済額の125%までしか引き上げることができません。
金利タイプによって、住宅ローンの返済額や返済計画は大きく変化します。それぞれの違いを押さえ、自分に合ったものを選びましょう。
金利水準
公務員の方が住宅ローンを借り入れる際、金利水準も確認しておきましょう。金利水準は金利タイプだけでなく、金融機関によっても異なります。例えば、ネット銀行は実店舗がなく、人件費が削減されていることから、金利が低く設定されています。実際に、固定期間選択型10年の金利を比較すると、三菱UFJ銀行が年3.89%に対して、楽天銀行は年2.36%となっています。このように同じ金利タイプでも、金融機関によって金利水準は異なるため、検討している住宅ローンがあれば金利水準を確認しておきましょう。
付帯サービス
付帯サービスも、住宅ローンを借り入れる際にチェックしておきましょう。各金融機関は、顧客満足度向上のため、さまざまなサービスを提供しています。
例えば、三井住友銀行では対象店舗でクレジットカードを利用するとポイントが還元されるプログラムを実施。住宅ローンを契約すると、このポイント還元率が1%アップします。また、三菱UFJ銀行では、住宅ローンを借り入れている方が、出産前後6カ月以内に申し出ると、1年間適用金利から金利が0.2%引き下げられます。このように、各金融機関によって付帯サービスは異なります。あくまで住宅ローンの契約がメインですが、付帯サービスに注目すると、より自分に合ったものを見つけやすくなるでしょう。
公務員でも住宅ローンの返済がきつい?借入金額別シミュレーション

公務員の方で金利の優遇を受けていても、返済が厳しいと感じることがあります。そこで本章では、借入金額別にシミュレーションをおこないます。先ほど取り上げた地方公務員の平均給料月額(31万5,159円)をもとに、返済負担率も算出。ご自身の給与に当てはめてシミュレーションするとイメージしやすくなるでしょう。なお、条件は以下のとおりです。
<条件>
返済期間:35年
借入金利:1.85%(全期間固定)
返済方法:元利均等返済
借入金額3,000万円の場合
まずは、借入金額3,000万円の場合をシミュレーションしてみましょう。
| 借入金額3,000万円の場合 | |
|---|---|
| 月々の返済額 | 9万7,085円 |
| 年間返済額 | 116万5,020円 |
| 10年後残高 | 2,330万4,648円 |
| 総返済額 | 4,077万5,428円 |
月々の返済額は、9万7,085円と10万円を下回っています。しかし、返済負担率を見ると30.8%となっており、すでに無理のない返済負担率である20%を超えてしまっています。共働きで家計に余裕がある場合は問題ないかもしれません。しかし、もし妻が妊娠・出産で働けない期間が発生した場合、返済が苦しくなるおそれも。将来のライフプランを見越して、返済計画を立てる必要があるでしょう。
借入金額4,000万円の場合
次に、借入金額4,000万円の場合をシミュレーションしてみましょう。
| 借入金額4,000万円の場合 | |
|---|---|
| 月々の返済額 | 12万9,446円 |
| 年間返済額 | 155万3,352円 |
| 10年後残高 | 3,107万2,974円 |
| 総返済額 | 5,436万7,452円 |
返済負担率は41.0%となり、給料の半分近くを住宅ローンの返済に充てなければなりません。一馬力では当然家計は苦しくなるでしょう。もし、妻も夫と同じ給料があると仮定した場合の返済負担率は、20.5%となり、家計にも余裕が生まれます。
借入金額5,000万円の場合
最後に、借入金額5,000万円の場合をシミュレーションしてみましょう。
| 借入金額5,000万円の場合 | |
|---|---|
| 月々の返済額 | 16万1,808円 |
| 年間返済額 | 194万1,696円 |
| 10年後残高 | 3,841万1,172円 |
| 総返済額 | 6,795万9,307円 |
返済負担率は51.3%となっており、給料の半分以上を住宅ローンの返済に充てなければならない結果となりました。借入金額4,000万円の時と同様、妻が夫と同じ給料があると仮定した場合の返済負担率は、25.6%となります。他に借り入れがある場合や子どもの教育費がかかる場合、家計が苦しいと感じるおそれがあります。
借入金額別にシミュレーションをおこないましたが、家族構成や他の借り入れ状況などから、人によって無理のない借入金額は異なります。将来のライフプランを見越したうえで、無理のない返済計画を立てることが大切です。
公務員の住宅ローンに関するよくある質問
公務員の住宅ローンに関するよくある質問をまとめました。
公務員は住宅ローンを年収の何倍まで組める?
住宅ローンの借入金額に対する年収の明確な基準はありません。借入金額は、申込者の年齢や勤続年数、他の借入状況などによって異なります。しかし、住宅金融支援機構の「2023年度 フラット35利用者調査」によると、物件タイプ別に見た年収倍率は次のようになっています。
| 物件タイプ | 年収倍率 |
|---|---|
| 土地付注文住宅 | 7.6倍 |
| 注文住宅 | 7.0倍 |
| 建売住宅 | 6.6倍 |
| マンション | 7.2倍 |
| 中古マンション | 5.6倍 |
| 中古戸建て | 5.3倍 |
これを見ると、5〜8倍で組まれる方が多いようです。ただし、あくまで目安となるため、これを鵜呑みにするのではなくご自身に合った借入金額を設定することが大切です。
公務員は住宅ローンの審査に通りやすい?
公務員の方は、一般的に住宅ローンの審査に通りやすい傾向にあります。それは、雇用や収入が法律によって規定されており、経済状況にも左右されないため、安定した返済能力があるとみなされるからです。ただし、信用情報に傷が付いている場合、住宅ローンの審査に通る可能性は厳しくなります。クレジットカードの返済や借り入れがある場合は着実に返済しましょう。
公務員の住宅ローンの適正額はいくら?
一人ひとり収入や借り入れ状況などが異なるため、一概には言うことができません。子どもの進路をどこまでサポートするのか、老後はどう過ごしたいのかなど、将来のライフプランによって、住宅に充てられる金額は異なります。ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら、ご自身に合った住宅ローンの借入金額を決めましょう。
まとめ
本記事では、公務員の方が住宅ローン金利の優遇を受けられる理由を解説しました。公務員の方は法律や条例によって雇用や収入が規定されており、安定した返済能力があると判断されるため、住宅ローンの金利が優遇される傾向にあります。しかし、信用情報に傷が付いていたり、借入金額が大きい場合は審査に通らないことも。公務員で雇用や収入が安定しているからといって、確実に優遇されるわけではありません。
ご自身の収入や家計状況、今後のライフプランを踏まえ、適切な住宅ローンを選択することが大切です。住宅ローンを比較する際には、金利タイプや諸費用など、さまざまな観点から検討する必要があります。ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら、ご自身に合った住宅ローンを選択しましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ