耐火建築物とは?木造でも建てられる?確認方法や準耐火建築物・防火構造との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

そこで、本記事では耐火建築物の基礎知識やメリット・デメリット、よくある質問などを解説します。耐火建築物の注文住宅を建てたい方や、他の建物との違いを把握しておきたい方はぜひ参考にしてください。
記事の目次
耐火建築物とは

耐火建築物とは、建物の壁や柱、床などの主要構造部に耐火性能のある材質などが使用されており、延焼の恐れのある窓やドアなどの開口部に火災を遮る設備がある建物のことです。主要構造部が耐火構造であることに加え、建物の利用者や居住者が避難するまでの間建物の性能を維持することができ、近隣への延焼を防げるのが条件です。一定の特殊建築物や防火地域内の一定の建築物は、耐火建築物にする必要があります。
耐火建築物となるのは、一般的に鉄筋コンクリートや石、レンガなどの燃えにくい素材でつくられた建物。日本の住宅に多い木造の場合でも、現在主流になりつつある2×4(ツーバイフォー)工法などであれば耐火建築物として承認されますが、高い技術が求められます。耐火建築物の条件について、以下の表にまとめました。
| 建築物の部分 | 時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 | 最上階から数えた階数が5以上で9以内の階 | 最上階から数えた階数が10以上で14以内の階 | 最上階から数えた階数が15以上で19以内の階 | 最上階から数えた階数が20以上の階 | ||
| 壁 | 間仕切壁 (耐力壁に限る) |
1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
| 外壁 (耐力壁に限る) |
1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | |
| 柱 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 | 3時間 | |
| 床 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | |
| はり | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 | 3時間 | |
| 屋根 | 30分間 | |||||
準耐火建築物との違い
耐火建築物と似たものに「準耐火建築物」があります。準耐火建築物は、耐火建築物と比べて少し緩やかな条件の耐火性能を満たした建物となっています。火災の拡大を防ぎ、避難の安全を確保する区画や開口部に防火設備などが設置されている点は耐火建築物と同様で、準耐火構造は「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」です。
耐火建築物は最大3時間火災による倒壊を防げるのに対し、準耐火建築物は最大1時間防ぐことが可能です。 また、耐火建築物よりも建物の階数が低く、延床面積が小さい場合に該当する基準となっています。
防火構造との違い
耐火建築物や準耐火建築物と間違えやすいのが「防火構造」です。防火構造は火事による延焼を防ぐ造りのことで、防火地域や準防火地域内にある住宅などの小規模な建物を建てる際に求められます。なお、耐火建築物などのように倒壊を防ぐ機能はありません。周囲で発生した火災の延焼に巻き込まれないように、外壁と軒裏に防火性のある材料を使用しています。30分間の加熱でも性能に支障のある変形や破壊がないことに加え、その裏面が出火に至る危険温度にならないことが条件です。
耐火建築物は、建物の主要構造部に耐火性能のある資材を使用し、防火設備を有する「建物」を指します。一方、防火構造は周辺の建物からの延焼を抑制する「構造」を指していることを覚えておきましょう。
一般的な住宅の場合、建築条件に該当しないため耐火建築物にするケースは多くありませんが、万が一に備えて防火構造を採用するケースが多い傾向にあります。安全な家づくりをするために、マイホームを建てる際は防火構造にするのがおすすめです。
木造でも建てることができる
先述のとおり、一定の基準を満たせば木造でも耐火建築物にすることは可能です。耐火建築物とするためには、建築基準法で定められた技術的基準を満たさなければなりません。技術的基準は以下の3つがあります。
-
適合ルートA
国土交通大臣が定める告示の例示仕様または大臣認定を受けた構造方式を用いる方法 -
適合ルートB
耐火性能検証法を用いて主要構造部の非損傷性、遮熱性、遮炎性を確かめる方法 -
適合ルートC
国土交通省の指定機関で高度かつ専門的な知識で性能を確認する方法
木造住宅では適合ルートAが用いられることが多く、適合ルートBやCは天井の高いドームや体育館の建設に採用されます。耐火建築物を木造で建てれば、比較的建築費を抑えやすく、総重量も軽くなり基礎への負担を少なくできるでしょう。
耐火建築物の確認方法
耐火建築物かを確認したい場合は、建築確認申請書や設計仕様書・設計図面、住宅性能を示すパンフレットなどを確認してみましょう。建築確認申請書は、建物を建てるときに建築基準法や条例などに適合している建物であるかの確認を受けることを目的に、検査機関に提出する書類のことをいいます。建築確認申請書が確認できない場合は、施工会社が発行した証明書類で確認するとよいでしょう。
耐火建築物のメリット

ここからは、建物が耐火建築物であることのメリットを紹介していきます。耐火建築物であれば、火災が起こりにくく、より安全に生活しやすくなります。また、家計に響きやすい固定費を抑えることで、経済的にも安心です。以下でそれぞれ解説します。
火が広がりにくい
耐火建築物であれば、万が一火災が発生した際にも火が広がりにくくなります。耐火構造の建物は燃えづらい材料を用いて建築しており、火災が発生しても避難する時間を確保できるためです。また、柱や梁などの主要構造部分は一定時間変状が生じないように定められていることから、鎮火したあとも大幅な修復は不要になります。耐火建築物に住む家族や自分はもちろん、近隣への被害も極力抑えられるでしょう。
防火地域に建築できる
耐火建築物は防火地域に建築が可能です。防火地域は都市計画法において、市街地における火災の危険を防除するために定める地域として指定されるエリアで、建物の密集地や駅前の繁華街などが指定されます。防火地域内に建てる建築物は、建物の階数や延床面積に応じて厳しい建築制限があります。防火地域では耐火建築物または準防火建築物であることが一般的で、耐火建築物の住宅であれば、駅近など周辺施設が充実している防火地域に住めるのは魅力の一つでしょう。
一方、準防火地域とはどんな地域なのか、防火地域との違いなどについては以下の記事を参考にしてください。
火災保険が安くなる
火災保険料が安くなる点も耐火建築物のメリットです。火災保険料は保険会社やお住まいの地域などに加えて建物の構造によっても変動し、建物の構造が火災や災害に強いほど火災保険料が割安になります。詳しくは後述しますが、耐火建築物は建築費用が割高になりがちです。しかし、その分5年や10年ごとに支払いが必要な火災保険料を安く抑えられます。火災発生によるリスクを軽減しつつ、建築費用との差額も小さくできるでしょう。
耐火建築物のデメリット
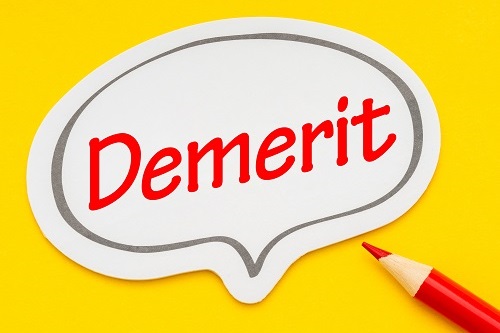
耐火建築物にはいくつかデメリットも存在します。耐火建築物の住宅にするかを決めるには、メリットだけでなくデメリットも把握しておくことが重要です。
建築費用が高い
耐火建築物は特殊な素材を使用するため建築費用が高くなりがちです。国土交通大臣認定の部材を使用する必要があるほか、一定時間建物が倒壊しないように厚めの部材の使用が求められます。一カ所あたりの部材費が高額になり、結果的に建物全体の費用が上がることは避けられません。ただし、できるだけシンプルな間取りにすることで特殊な素材を使用する箇所を少なくでき、建築費用を抑えやすくなります。また、建築費用が高い分、火災保険料は割安になるので、継続してかかる固定費を抑えられるでしょう。
デザインに制限がかかる
次に、建物のデザインに制限がかかることが挙げられます。耐火建築物の場合、防火扉や防火窓などの設備が必要になるためデザインの自由度が下がります。デザインが画一的になる場合がありますが、有事の際に命の危険を脅かしかねないデザインを避けることが可能です。
リフォームがしにくい
リフォームがしにくいことも、耐火建築物のデメリットです。耐火建築物では壁・床・柱・梁・屋根・階段などの主要な構造部に一定の耐火性能があることが求められます。厳しい基準のなかでのリフォームとなるため、なかなか思い通りのリフォームは難しいかもしれません。また、リフォームすると取り壊し費用や産廃費用が高額になりがちです。ライフステージや家族構成の変化に合わせてリフォームをしたい場合は、可動の間仕切りや家具を用いるなどして大規模な工事をせず間取り変更をおこなうとよいでしょう。費用をかけずに自由に間取りを変更することが可能です。
耐火建築物にしなければならない建物
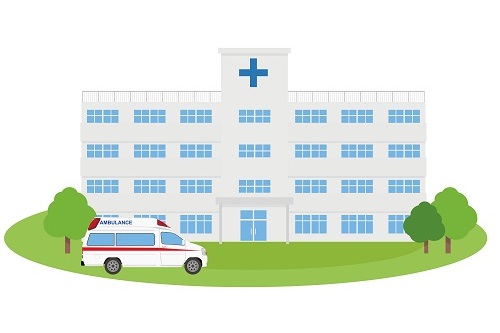
耐火建築物にしなければならない建物は、建築基準法第27条・61条・62条の条文で定められており、建物の「用途」「立地」「規模」によって耐火建築物としなければならないことが明記されています。耐火建築物としなければならないのは、主に以下のような建物です。
- 劇場
- 映画館
- 病院
- ホテル
- 百貨店
- 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
- 学校
- テレビスタジオ など
建物の用途上の特性に応じ、かつ一般の建物と区分したうえで上記のような用途にする部分の階数や床面積に応じて主要構造部に非損傷性や遮熱性などの一定の性能が求められます。
耐火建築物についてよくある質問

ここからは、耐火建築物に関するよくある質問について紹介します。
耐火建築物とは?
耐火建築物とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要構造部が耐火構造となっている建物のことです。耐火構造は1~3時間の加熱に対する非損傷性、遮熱性、遮炎性が確保されている耐火性能を有する構造であり、火災が収まるまでの間、建築物の倒壊および延焼を防止するために必要な構造として建築時の条件となっています。耐火建築物にする必要があるのは、劇場や映画館、病院、ホテル、学校などさまざまです。
準耐火建築物や防火構造の違いは?
準耐火建築物は、主要構造部を準耐火構造とする建物のことをいいます。耐火建築物が火災発生から最大3時間倒壊に耐えられるのに対し、準耐火建築物は最大1時間など、耐火建築物の条件に比べて緩やかになっています。また、防火構造は火事による延焼を防ぐ構造のことを指し、耐火建築物よりも比較的小規模な建物を建築する際に求められます。建物の倒壊を防ぐ機能はないものの、30分間の加熱でも支障のある変形や破壊がないことに加え、その裏面が出火に至る危険温度にならないことが条件です。一般的な住宅を建てる際は、防火構造にすることをおすすめします。
耐火建築物のメリット・デメリットは?
耐火建築物のメリットは、主に「火が広がりにくい」「防火地域に建築できる」「火災保険が安くなる」ことが挙げられます。一方、デメリットは「建築費用が高い」「デザインに制限がかかる」「リフォームがしにくい」などがありますが、工夫次第でメリットととらえることも可能です。メリットとデメリットの両方をしっかり理解することで、耐火建築物の住宅にするか悩んだときに選択しやすくなるでしょう。
まとめ
耐火建築物を建てるにはさまざまな建築条件があるほか、耐火建築物ならではのメリットやデメリットもあります。基本的に大規模な商業施設や公共施設などの安全性を確保しなければならない建築物に求められるものであり、一般的な住宅で耐火建築物とする条件になることはほとんどありません。しかし、家族や自分にとってより安全かつ健康的な暮らしを求めるのであれば、耐火建築物にするのは有効な方法といえるでしょう。どのような家づくりをしたいか悩んだときは、ハウスメーカーなどの建築会社と相談しながら決めていくことをおすすめします。
物件を探す







