平屋と二階建ての固定資産税はどちらが安い?計算結果を比較してシミュレーション
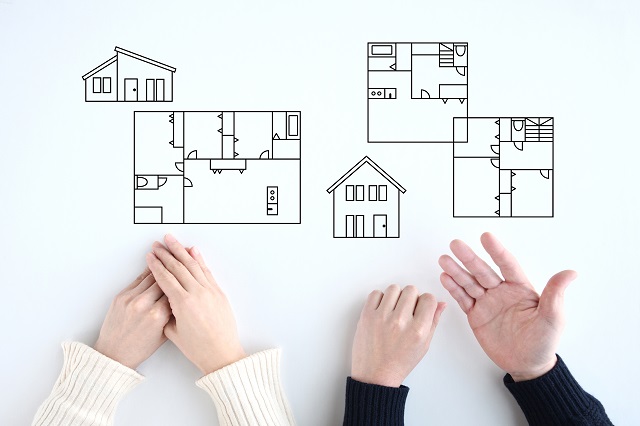
本記事では、平屋と二階建てで固定資産税はどちらが安いのか、家の固定資産税を節約する方法を解説します。より詳細に説明するため、固定資産税の計算の流れを確認したうえで、具体的な例を用いてシミュレーションを紹介。記事を読むことで、建物の種類を含めた実用的な固定資産税の知識がわかるようになるでしょう。
記事の目次
平屋と二階建ての固定資産税はどちらが安い?

固定資産税は、地方自治体が条例に基づき課す地方税の一種であり、所有する固定資産の価値に見合った税負担を求めるものです。課税対象となる固定資産には、土地、建物、他には事業用機械や備品などの償却資産があります。
納税通知書は毎年4月~5月頃に市区町村から発送され、通常年4回にわたって分割して納付します。固定資産税の概要を踏まえたうえで、平屋と二階建てでは固定資産税はどちらが安いのかを順序立てて解説します。
固定資産税は土地・建物でそれぞれ納める必要がある
家を所有している方が支払う固定資産税は、土地・建物でそれぞれ納める必要があります。土地にかかる固定資産税は、土地そのものの評価額に基づき課税される仕組みです。平屋・二階建てであっても、土地の使い方によって税額が変わることはありません。
一方で、建物の固定資産税は、構造・床面積・壁・屋根などで使用される資材の量などが考慮されます。適正に税を課すために、3年ごとに評価替えをおこなう仕組みです。家全体にかかる固定資産税は土地・建物の固定資産税を合算した価格になります。
固定資産税が安いのはどっち?
同じ延床面積を持つ平屋・二階建てを比較する場合、一般的に二階建てのほうが固定資産税は安い傾向にあります。なぜなら土地部分を比較すると、平屋は同じ延床面積を持つ二階建てと比較して、その分広い土地が必要になります。よって、平屋の土地の評価額は上がりやすくなるため、固定資産税が多くかかるというわけです。
また、建物部分も同じ延床面積であれば、平屋のほうが基礎や屋根の面積が必要になります。したがって、建てる際に必要な建材の量も多くなるため、固定資産税も増加しやすいでしょう。以上のことから、土地・建物を総合して平屋のほうが固定資産税はかかりやすいため、二階建てのほうが固定資産税は安いと結論付けられます。
家の固定資産税を計算する流れ

家の固定資産税の計算は、以下の3つの手順によっておこなわれます。
- STEP 1土地・建物の固定資産税評価額を調べる
- STEP 2該当する固定資産税の軽減措置を適用する
- STEP 3土地・建物で計算した税額を合算する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP1.土地・建物の固定資産税評価額を調べる
固定資産税を計算するには、土地・建物のそれぞれの固定資産税評価額を調べる必要があります。ただし、固定資産税評価額を最終的に決定するのは市区町村であるため、新築物件において、正確な固定資産税評価額を知ることは難しいでしょう。
固定資産税評価額は目安を求めることになりますが、計算方法は以下のとおりになります。
- 建物の評価額:再調達原価の50%または60%
- 土地の評価額:公示価格の70%
再調達原価は再び同じ建物を建てるにあたってかかる費用のことです。土地の公示価格は、国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」で調べられます。
STEP2.該当する固定資産税の軽減措置を適用する
固定資産税には、複数の軽減措置が設けられています。土地・建物、それぞれに軽減措置があるため分けて解説します。
土地の住宅用地特例
土地の住宅用地特例は、土地の面積に応じて以下の軽減率で課税標準額が減額されます。
| 区分・面積 | 軽減率 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200平方メートルまで) | 6分の1 |
| 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 3分の1 |
例えば、500平方メートルの土地を持っている場合は、200平方メートルまでは軽減率6分の1で計算。200平方メートルを超える300平方メートルの部分の軽減率は、3分の1で計算する仕組みです。
新築住宅に係る税額の減額措置
面積が50平方メートル~280平方メートルの新築住宅について、建物部分の120平方メートルに限り固定資産税が軽減されます。
| 区分 | 年数 | 軽減率 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅以外 | 3年 | 2分の1 |
| 認定長期優良住宅 | 5年 | 2分の1 |
年数が限定されますが、建物部分にかかる固定資産税の評価額が減額される措置です。目安が大きく変化するため、固定資産税評価額を計算する場合は、利用できる軽減措置を適用するようにしましょう。
STEP3.土地・建物で計算した税額を合算する
固定資産税の税額は、各評価額に標準税率の1.4%を乗じて計算します。標準税率は各自治体によって異なることがあるため、目安を計算する際は、家が所在する自治体の標準税率を調べておきましょう。土地・建物で計算した税額を合算することで、固定資産税の総額を求められます。
平屋と二階建ての固定資産税の計算シミュレーション

上述した計算の流れを踏まえて、実際に例を挙げて平屋と二階建ての固定資産税を比較してみましょう。具体的な条件は以下のとおりに設定しました。
- 延床面積:共通して30坪(約100平方メートル)
- 土地の建ぺい率:50%
- 土地の容積率:100%
- 土地の価格:20万円/平方メートル
- 再調達原価:平屋が3000万円、2階建てが2,650万円
- 土地の評価額:購入価格の70%
- 建物の評価額:再調達原価の60%
- 固定資産税の標準税率:1.4%
また、固定資産税の計算結果において、100円未満の端数がある場合は切り捨てる仕組みです。平屋・建物の土地部分・建物部分の計算方法をそれぞれ見ていきましょう。
平屋
まずは平屋のほうから計算してみましょう。
土地部分
土地の建ぺい率が50%の条件で30坪(約100平方メートル)の平屋を建てるには、必要な土地の広さは200平方メートルになります。土地の固定資産税の評価額は、以下のように計算可能です。
- 土地の購入価格 = 20万円 × 200平方メートル = 4,000万円
- 土地の固定資産税評価額 = 4,000万円 × 70% = 2,800万円
土地の住宅用地特例を適用して、標準税率をかけて税額を求めると以下のとおりです。
- 平屋(土地部分)の固定資産税 = 2,800万円 × 1/6 × 1.4% =6万5,300円
建物部分
建物部分の再調達原価が3,000万円、再調達原価の60%を建物の評価額と仮定するため、以下のとおりに計算します。
- 建物の固定資産税評価額 = 3,000万円 × 60% = 1,800万円
建物部分の軽減措置は2分の1であるため、標準税率をかけて税額を計算します。
- 平屋(建物部分)の固定資産税 = 1,800万円 × 1/2 × 1.4% = 12万6,000円
二階建て
次に、二階建てのほうをシミュレーションしてみましょう。
土地部分
容積率100%であれば、1階部分と2階部分でそれぞれ50平方メートルの延床面積を持つ建物が建てられます。建ぺい率が50%であるため、100平方メートルの土地が必要です。土地における固定資産税の評価額の計算を以下にまとめました。
- 土地の購入価格 = 20万円 × 100平方メートル = 2,000万円
- 土地の固定資産税評価額 = 2,000万円 × 70% = 1,400万円
平屋と同様に、土地の住宅用地特例の軽減税率をかけて、固定資産税額を計算します。
- 二階建て(土地部分)の固定資産税 = 1,400万円 × 1/6× 1.4% =3万2,600円
建物部分
二階建ては平屋と比較して、再調達原価が安いことから今回は2,650万円と仮定しました。平屋と同様に再調達原価を60%として計算します。
- 建物の固定資産税評価額 = 2,650万円 × 60% = 1,590万円
建物部分の軽減措置は、認定長期優良住宅とそれ以外の住宅で適用できる年数は異なるものの、軽減税率は共通して2分の1です。
- 二階建て(建物部分)の固定資産税 = 1,590万円 × 1/2× 1.4% = 11万1,300円
平屋と二階建ての固定資産税の比較
上記で計算した平屋・二階建ての固定資産税を合算すると以下のとおりです。
- 平屋の固定資産税:6万5,300円 + 12万6,000円 = 19万1,300円
- 二階建ての固定資産税:3万2,600円 + 11万1,300円 = 14万3,900円
よって、同じ延床面積の平屋と二階建ての固定資産税の差は、シミュレーションの結果4万7,400円になりました。比較すると大きな差はないように思えますが、継続して支払い続けることを考えるとそうとはいい切れません。
また、今回は新築を前提に計算しました。しかし、築年数が経過した建物の評価額は、年月とともに下がることから、経年減価補正率をかけて調整します。
家の固定資産税を節約するポイント

最後に、少しでも固定資産税を安くするために、家の固定資産税を節約するポイントを以下にまとめました。それぞれ詳しく見ていきましょう。
必要以上に土地・建物の面積を広げない
土地の敷地面積を必要以上に広く取得すると、土地の固定資産税評価額が上がり、土地部分の固定資産税が増えます。固定資産税を節約するなら、建物を建てるにあたって必要最低限の広さを持った土地を取得するようにしましょう。
また、家の延床面積が増えて建物が大きくなるほど、建物の固定資産税評価額は上昇しやすくなります。必要以上に土地・建物の面積を広げないようにすることで、固定資産税額の減少を期待できるでしょう。
建材に木材を検討する
建物の評価額は、構造や建材によっても変動します。建材のなかでも、木材は経年減点補正率が大きいため、築年数が増加するほど固定資産税の評価額は低くなります。固定資産税の節約を重視して建材を選ぶなら、長期的に税金を支払うことを考えると木材がおすすめです。木造住宅は、他の構造と比較して建築費用も安い傾向にあるため、固定資産税を含めて総合的にコストを削減しやすいです。
シンプルな構造・設備を選ぶ
固定資産税は、一般的に建物がシンプルな構造・設備であるほど、低い傾向にあります。複雑な間取りを避けて、部屋数を減らし、大きな空間を確保するシンプルな内装のほうが評価額は抑えられるでしょう。
また、ホームエレベーター・床暖房などの設備、さまざまな機能が搭載された豪華なキッチンなどは固定資産税を増加させる原因となります。こだわりがない部分をシンプルにして、不要なオプションを付けないことで、税負担の軽減と建築費用の節約につながるでしょう。
家屋調査には必ず協力する
固定資産税評価額は、自治体職員による家屋調査に基づいて決定されます。家屋調査はプライベートを守るために拒否することが可能であり、その場合は図面や似た建物の資料を用いて算出されます。
しかし、家屋調査を拒否すると、算出される固定資産税が調査に協力した場合と比較して高くなる可能性も。家屋調査には必ず協力して、正確な固定資産税を算出してもらうようにしましょう。
認定長期優良住宅を取得する
新築の認定長期優良住宅を取得した場合は、戸建ての場合は5年間、マンションの場合は7年間にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。
認定長期優良住宅は、耐震性・耐久性・省エネ性などの基準を満たした家のことで、一般住宅より建築費用が高騰しますが、固定資産税の節税においてはメリットが大きいです。高い住宅性能は快適に暮らすうえで重要になります。耐久性・耐震性はコストが下がると考えても節約してはならない部分であるため、固定資産税の節約を含めて認定長期優良住宅の条件はこだわるポイントになるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?同じ延床面積の平屋・二階建てでは、二階建てのほうが固定資産税は安いということがわかりました。平屋は取得する土地が広く、建物部分の基礎・屋根面積も増えるため、建材が増加することが原因になります。しかし、固定資産税を節約する方法はどちらも共通しています。
固定資産税が安いことを理由に二階建てを選ぶ場合も、平屋をどうしても建てたい場合も、できる限り固定資産税を節約したい方は、設計段階から考慮しましょう。
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ




