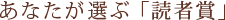架空の町
原稿には、「靴千個分、直進」するまで風景描写がつづいている。そしてその描写は僕が見ているものからは外れていない。外れようがないし、ぴったり合いようがないとでもいうべきだろうか。たとえば――「壁に身を寄せてもたつく空気が自転車に脅されて上昇するのに目を瞑ってみれば、その下ではガスが澱になっている」「ほこりが踊り止めることはない」「この道は、知らない犬が歩いた道だ」「微生物のようには呼吸ができない、なかなか重力と折り合いをつけきれない人間たちが歩き、絶えず片方の靴が宙に浮く」
彼はいったいなにをこわがっているのだろう。原稿用紙を破り、文字を書いた瞬間に文字を消そうとでもするような筆圧だった。楽しんで書いているというより、なにかに脅迫されているようにさえ思える。実際に目に見えるものではなく、自分の内側に見えるものに語りかけ、返事がないのにさらに語りかけているようで、僕は苦しくなる。それとも、彼には本当に、書いたことが見えていたのだろうか。
語り手は立ち止まらないが、僕は立ち止まった。束から抜き取って手に握った頁も、読まれなければ立ち止まっているのだということにした。「夏だというのに、空は白髪のように曇りはじめた」が、それでも充分に暑い。僕は汗を拭って、ペットボトルの水を飲んだ。バックパックのなかにもどすとき、したたった水滴が原稿用紙をにじませた。信じられないことに、原稿用紙の枚数は三百枚にのぼる。図書館が開いてから、閉まるまでの時間で、彼はそれを書いたのだ。
彼は語り手が架空の町を探す理由をこう書いている。
「その町のことをはじめて知ったときのことはもう思い出せない。現実だったのかも、夢のなかだったのかもわからない。それでもそこを明確にするならば、記憶のなかというのがふさわしい。ある日、私は記憶のなかでそこを知った。つまり、その日以前の過去に遭遇したのだ。私はどこかに立っていた。崖のようだが、決して崖ではない、なにかが途切れた縁に立っていた。体中が痛く、頭痛や腹痛が私になってしまったようだった。しかし、うずくまることはできなかった。時間というものがそこにあるとすれば、途方もない時間、途切れた先を見ていた。すると不意に、私のなかから声がした。進め。その声はそういった。進め、進め、進め、進め――と、体そのものに押されるように、私は進んだ。するとそこに、あの町があった。架空の町は私を歓迎してくれるだろうか、瞬間に思った。そのときにはもう、そこは過去になっていて、思い返すような存在になっていた。私は進んだ、進みつづけた」
架空の町