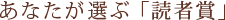おせんべいの由来
しかし、禍福はあざなえる縄のごとしといいますが、思いがけない運命がお仙を待ち受けていたのです。
美人で、利口者(りこうもの)、街道一の茶屋娘として、すっかり名高くなったお仙を見に来る、または、ごきげんを取りに来る近所の若い者はひきもきらず。その中でもとりわけ熱心なふたりの男が、二人ながら彼女に求婚しました。心やさしいお仙は、どちらの男を選ぶか思いなやんだあげく、どちらの男を選ぶとも決心がつかず、ついに荒川に身を投げて死んでしまったのです。
お仙の心根(こころね)を哀れとなげいた宿場の人々は、お仙の茶屋のあったところに祠(ほこら)を建てて、彼女の菩提をながくとむらいました。それがのちにお仙稲荷として信仰を集めたということです。
みなさんは、神社といいますものは、神話に出てくる神さまを祀(まつ)ったものだとお思いかもしれませんが、天神さまをはじめ、不遇の死をとげたあとの鎮魂のために設けられたものも多い。とりわけ、悲恋のために死んだ女の人というと、村人はかならずあわれむことになっています。道成寺の清(きよ)姫(ひめ)、妹背山(いもせやま)のお三輪(みわ)、西洋ではシェイクスピア「ハムレット」のオフェリア姫を思い出してください。
そういった同情心ばかりでなく、もともと草加かいわいは、荒川からもたらされる良質な水を利用して、稲作がさかんに行なわれていた地です。おせん餅(べい)が発明されてからは、あまった米をむだにしないよう、村人は残り飯を団子にし、塩をまぜてのし、竹筒で丸く抜いて乾燥させて焼き、保存食としていました。やがて、さっき申し上げた将軍さまの一件もあり、換金性の高い菓子・おせんべいは、しょうゆの製造、茶の栽培の普及などともあいまって、大消費地・江戸へ出荷されるようになりました。草加はたんなる農村・宿場町ではなく、埼玉県、当時の武蔵(むさしの)国(くに)南部を代表する大問屋町・商業都市となったのです。
ずっと時代がくだって、明治になってからも、たとえば初めて鉄道が敷かれたとき、草加駅の東口に「おせんさん」記念の碑が建てられ、現在も旅人の目をひきつけております。
おせんべいの由来
ページ: 1 2