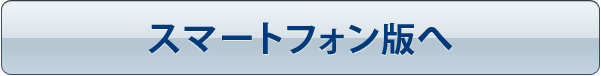資金計画を立てよう
住まいを買うのに必要な総コストを確認しよう
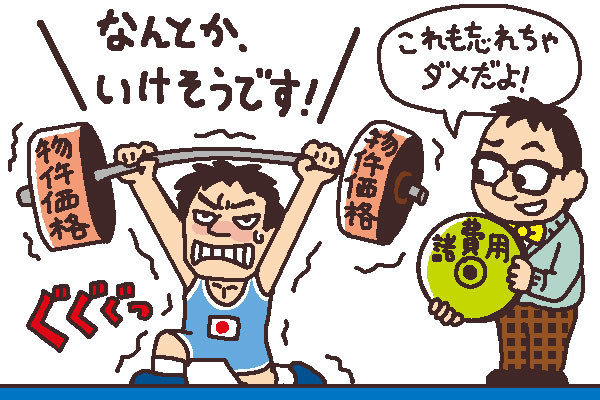
まずは、諸費用を含めて住まいを買うために必要な費用の総額を固めることが必要です。
一般に諸費用の額は、新築なら物件価格の3~7%、中古では6~10%と言われています。一般的に中古の方が高くなるのは、売主から直接買うケースが少なく、仲介手数料が必要となることが多いためです。例えば物件価格3,500万円の新築なら諸費用は最大245万円程度、中古なら最大350万円程度がかかることになります。
決して小さな負担ではないので、この諸費用を物件価格に加算した総コストに基づいて、資金計画を練る必要があります。
頭金と住宅ローンの考え方

それでは、頭金としてどのくらいの資金があればよいのでしょう? 最近では、頭金0円で住まいを購入する人も増えていますが、かつては物件価格の2割程度を用意するのがよい、とされていました。
頭金を差し引いた残りは、住宅ローンで支払うことになるので、頭金が多いほど借り入れは少なくて済みます。その結果、利息が減るので、総支払額を抑えることができます。また、ローンによっては頭金がある方が審査に通りやすかったり、優遇金利が適用されたりといったメリットもあるようです。
ローンのことを考えるときには、月々支払えるギリギリの金額を返済に充てるのは避けましょう。快適に暮らすためには、生活費はもちろん、貯蓄や子供の教育費など、さまざまなコストが必要です。これらコストに大きな影響が出ない範囲の返済額と返済期間を考えて、家計のバランスを崩さない資金計画を立てるようにしましょう。
親からの資金援助を検討してみる

そんなとき、もしも親からの資金援助が期待できるなら、その力は大きなものになりますから、検討をおすすめします。
親から援助を受ける具体的な方法には「贈与」「借り入れ」「共有」の三つがあります。
「贈与」は、資金をもらうことです。もらったお金をそのまま頭金に充てることができます。但し、贈与額によって贈与税がかかります。また、税制の特例による非課税枠などもあるので、国税庁の情報などを確認してください。
「借り入れ」は、文字通り親からお金を借りることです。身内からの借り入れですから、金利や返済期間、返済金額には融通が利くでしょう。担保の必要がないというのも大きなメリットですね。ただし、親子ということに甘えてばかりいると「贈与」とみなされてしまうので、「借用書」を作成する必要があります。金利、返済方法、返済期間などをきちんと取り決めて、明記しておくことが大切です。
「共有」は、資金援助を受けた分を親の持分として、共有名義で不動産登記をする方法です。共有のメリットは、贈与税の対象にならずに資金援助が受けられることです。借用書も不要です。ただし、親も住宅を所有することになるので、親に対しても不動産取得税や持ち分に応じた固定資産税などが課せられます。また、親が亡くなった場合は持ち分を相続する形になり、その分の相続税が課せられます。兄弟姉妹がいる場合は相続についてあらかじめ取り決め、確認をしておく必要があります。