厄年に引越しをしても大丈夫?引越しをする場合の対策と厄年の過ごし方

本記事では、厄年の基本知識から、厄年に引越しをする際の注意点、さらに安全に過ごすための対策まで詳しく解説します。厄年に不安を感じる方も、適切な対策を取ることで安心して新生活を迎えられます。正しい知識を身に付け、厄年を前向きに乗り切るためのヒントを一緒に見ていきましょう。
記事の目次
そもそも厄年とは?

厄年(やくどし)とは、日本で災厄が降りかかりやすいとされる年齢を指します。この概念は陰陽道に由来し、平安時代から根付いた風習です。
科学的な根拠はないものの、人生の転換期にあたることが多く、心身のバランスを崩しやすい時期とも言われています。
一般的に、男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳・61歳が厄年とされ、特に42歳の男性と33歳の女性は「大厄」と呼ばれ、注意が必要とされます。
しかし、現代では厄年を単なる不運な時期ととらえるのではなく、自己を見つめ直し、成長の機会とする前向きな考え方も広まっています。慎重に生活しながら、厄除けや厄払いをおこなうことで、安心して過ごせるでしょう。
前厄・本厄・後厄とは
厄年には「前厄」「本厄」「後厄」の3つの期間があり、それぞれ微妙に厄の重さが異なります。
-
前厄
本厄の前年にあたり、厄の前兆が現れはじめる時期です。環境の変化や体調の乱れが生じやすいとされています。 -
本厄
厄年の中心で、もっとも注意が必要な年です。人生の重要なイベントが起きやすく、慎重な行動が求められます。 -
後厄
本厄の翌年で、厄が徐々に薄れていく時期です。「厄晴れ」とも呼ばれ、本厄の影響を引きずらないためのケアが推奨されます。
なお、厄年の年齢は数え年で計算され、男女で異なります数え年では生まれた日からその年を1歳と数え、次の1月1日で2歳となります。このため、通常の年齢の数え方である満年齢とは異なります。
満年齢では、生まれた日を0歳とし、生まれた年の誕生日が来ると1歳とカウントされます。そのため、同じ人でも数え年と満年齢では異なった年齢が表示されることになるので注意が必要です。
男性と女性で異なる厄年の早見表
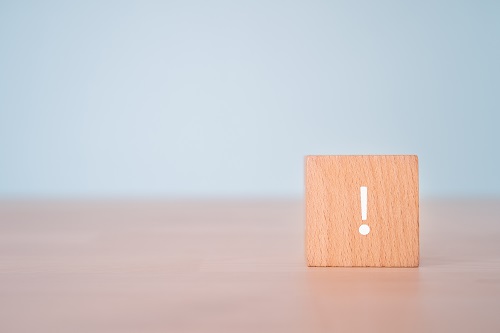
厄年は男性と女性で異なり、迎える年齢や回数に違いがあります。特に、本厄の回数は女性のほうが多く、30代に2回(33歳・37歳)訪れます。
また、もっとも注意すべき大厄は、男性が42歳、女性が33歳です。これは「42 = 死に」「33 = 散々」との語呂合わせも影響しています。
さらに、女性の厄年は結婚・出産などの人生の大きな変化と重なることが多く、心身に影響をおよぼしやすい時期とされています。
厄年を正しく理解し、慎重に過ごすことが大切です。下記の2025年厄年年齢早見表で、自身の厄年を確認しましょう。
男性の厄年
| 前厄 | 2002年生 | 1985年生 | 1966年生 |
|---|---|---|---|
| 24歳 | 41歳 | 60歳 | |
| 本厄 | 2001年生 | 1984年生 | 1965年生 |
| 25歳 | 42歳 | 61歳 | |
| 後厄 | 2000年生 | 1983年生 | 1964年生 |
| 26歳 | 43歳 | 62歳 |
※年齢は数え年での年齢です
女性の厄年
| 前厄 | 2008年生 | 1994年生 | 1990年生 | 1966年生 |
|---|---|---|---|---|
| 18歳 | 32歳 | 36歳 | 60歳 | |
| 本厄 | 2007年生 | 1993年生 | 1989年生 | 1965年生 |
| 19歳 | 33歳 | 37歳 | 61歳 | |
| 後厄 | 2006年生 | 1992年生 | 1987年生 | 1964年生 |
| 20歳 | 34歳 | 38歳 | 62歳 |
※年齢は数え年での年齢です
厄年に引越しをして大丈夫?

「厄年に引越しをするとよくない」と耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、仕事の都合や家庭の事情で、厄年に引越しをしなければならないケースもあります。
厄年は人生の転換期とされ、新たな環境へ移るタイミングと重なることもあります。新居の購入、結婚、就職・転職などの大きな変化を起こす行動は、慎重に進めるべきとされています。しかし、必要以上に不安を感じる必要はありません。
大切なのは、厄除けや厄払いを活用しつつ、前向きな気持ちで新生活に臨むことです。自分を見つめ直す機会と厄年をとらえ、心の準備をすれば、新しい生活をよりよい形でスタートさせられるでしょう。
厄年に引越しをする場合の対策

それでは、どうしても厄年に引越しをしなければならない時の具体的な対策をご紹介します。
厄除け
厄除けとは、神社やお寺で祈祷を受けて、災いを遠ざけることを指します。
特に厄年を迎えた人がおこなうことが多く、新年から立春までの時期に受けるのが理想ですが、一年を通していつでもおこなえます。また、大安など縁起のよい日を選んでお祓いを受ける人も多く、その効果は約1年間続くとされています。
厄除けの方法にはさまざまなものがあります。神社やお寺でのお祓いだけでなく、断捨離で不要なものを処分する、酢水を使った掃除、海岸で朝日を浴びるなど、自分でできる厄除けの方法もあります。
さらに、親しい人たちを招いて食事をふるまうことも、厄を分散させる方法の一つとされています。厄除けは、単に災難を避けるためのものではなく、自分自身を振り返る節目にもなるでしょう。
厄払い
厄払いとは、身に付いた厄を祈願によって取り除き、運気を好転させる儀式です。
特に厄年におこなわれますが、それ以外にも不運が続く時におこなうことが多いです。主な方法として、神社やお寺での祈願(初穂料5,000~10,000円程度)、お餅やお菓子などを配る贈与があります。
厄落とし
厄落としとは、意図的に厄を生み出しそれを取り除くことで、これ以上の災厄を防ぐための風習です。
特に厄年におこなうことが多いですが、それ以外のタイミングでも実施できます。方法はさまざまで、一番よく知られているのは神社やお寺での祈願です。
それだけではなく、例えば大きな買い物をしてお金を手放したり、髪や爪を切ったりすることも、厄落としの方法の一つです。
また、食べ物を通じた厄落としも昔からおこなわれてきました。小豆は魔除けの象徴とされ、赤飯やぜんざいとして食べる風習があります。桃は長寿や厄除けの力があると信じられています。塩おにぎりは、塩の浄化作用と米の豊穣の力を兼ね備えた縁起のよい食べ物です。さらに、昆布は「よろこぶ」に通じて縁起がよく、鰯は邪気を払う魚として知られています。梅干し、しょうが、にんにくなども厄落としの効果があるとされ、普段の食事に取り入れることで運を開くともいわれています。
厄落としは、お正月から節分の間におこなうことが多いですが、特に時期に決まりはなく、ご自身のタイミングでおこなっても問題ありません。また、地域によって風習も異なります。例えば、長野県では火祭りでみかんを投げる風習があり、福岡県の太宰府天満宮では梅の木を奉納することで厄を払うとされています。
昔から伝わる厄落としの方法を取り入れながら、自分なりの方法で運気を整えてみるのもいいかもしれません。
方違え
方違えとは、引越しや移動の際に凶方位の影響を避けるため、一度別の場所に仮住まいし、そこから最終目的地へ向かう風習です。平安時代の陰陽道に基づき、災厄を回避する目的で広くおこなわれていました。
仮住まいを経由することで、最終的な引越し先が吉方位となるよう調整できるため、運気を守りたい人に適した方法とされています。少し手間ですが、確実に凶方位の影響を軽減できると考えられています。
2025年の詳しい吉方位・凶方位を確認したい方はこちらをご参照ください。
厄年を安全に過ごす方法

厄年は、年齢を重ねれば誰しも必ず迎えます。それほど恐れるものでもありませんが、安心して過ごすためにも、具体的な対策をいくつかご紹介します。
掃除・断捨離をする
掃除や断捨離は、物理的な汚れだけでなく、厄を落とす効果があるとされています。
特にトイレ掃除は風水で厄落としの場とされ、清潔にすることで悪い気を流し、幸運を呼び込むと考えられています。玄関掃除も重要です。外からの厄を払い、よい気を呼び込みます。
また、床の水拭き掃除は足下に溜まった悪い気を取り除く効果があるとされています。断捨離も厄落としの一環として有効です。
不要な物を処分すると、滞っていた気の流れがよくなります。さらに、人間関係の整理や過去への執着を手放すことで、新たな縁を呼び込むきっかけにもなるでしょう。
掃除と断捨離を習慣化することで、心身ともに軽やかになり、運気向上が期待できます。
整理整頓をする
整理整頓とは、モノをきれいに整え、使いやすく配置することで、日々の生活を快適にする習慣です。きちんと収納しておけば、必要なものをすぐに取り出せるようになり、ムダな時間を減らせます。
また、整理整頓をすると空間がスッキリするだけでなく、気分も晴れるのがメリットです。風水の考え方では、整った空間は気の流れをよくします。
さらに、心にもよい影響を与えます。片づいた部屋にいるだけで気持ちが落ち着き、ストレスが軽減します。自分が気分よく過ごせることこそ一番の開運法です。
新しいことや大きな決断は避ける
厄年は心身が不安定になりやすく、新しい環境への適応が難しくなる時期とされています。
思わぬトラブルやリスクが高まり、判断力が低下しやすいため、大きな買い物や重要な決断には注意が必要です。
また、新しい職場や環境の変化によるストレスが、厄年の不安定さと重なり負担が増す可能性もあります。
ただし、厄年を人生の転機ととらえる考え方もあり、慎重に状況を見極めながら前向きに行動することが大切です。
健康のための食事や運動を心がける
厄年は心身ともに不安定になりがちな時期とされるため、健康的な食事と運動を心がけましょう。
バランスの取れた食事と適度な運動は免疫力を高め、ケガや病気のリスクを軽減します。また、ストレスを和らげ心身を整える効果もあります。さらに健康管理を意識することで前向きな姿勢を維持し、厄年をポジティブに乗り切れるでしょう。
風水を取り入れる
厄年のエネルギーを緩和するのに、風水が有効です。まず、アメジストとルチルクォーツのパワーストーンを身につけることで、厄除けと開運の効果が期待できます。
また、空間の浄化も重要です。ホワイトセージやお香を焚き、窓を開けて邪気を払いましょう。さらに、観葉植物を南東に配置すると、自然のエネルギーが空間のバランスを整え、よい気の流れを生み出します。
色彩の工夫も効果的です。ラベンダーカラーの寝具は癒しをもたらし、ブルーやグリーンは心を落ち着かせます。さらに、水琴鈴の音を取り入れることで、魔除けの力を高められます。
最後に、水回りを清潔に保ち、日当たりのよい環境を整えましょう。排水溝の詰まりは運気の詰まりです。日が当たらない薄暗い場所は、人工照明でもよいので、明るくすることが大事です。
縁起物を身に付ける
厄年に縁起物を身に付けることで厄を払い、運気を高めるとされています。昔から親しまれている縁起物には、それぞれ意味があり、厄除けのお守りとして活用されています。例えば、「破魔矢(はまや)」です。破魔矢には、邪気を払う力があるとされ、正月に家に飾る習慣があります。
「羽子板」は、羽根を付くことで厄を跳ね返すとされ、女性や子どもの無病息災を願うアイテムです。そして、だるまは「七転び八起き」の象徴。願いを込めて片目を入れ、成就したらもう片方の目を入れることで、努力が実を結ぶとされています。
また、身に付ける縁起物として代表的なのが「お守り」です。厄除けや家内安全、合格祈願など、目的に応じて選べるので、自分に合ったものを持つとよいでしょう。
節分に飾るヒイラギも、鬼や邪気を遠ざけるとされ、古くから厄除けの習慣として受け継がれています。
アクセサリーでは、厄除けブレスレットが人気です。マラカイトは邪気を寄せ付けないとされ、オニキスは悪縁を断ち切る石として知られています。さらに、天眼石は災難を防ぐ力があるとされ、厄年のお守りとしてよく選ばれます。
ほかにも厄を遠ざけるとされているのが、七色のものや長いもの(ネクタイやスカーフなど)です。これらは長寿を象徴しています。特に真珠は、七色に輝くことから厄払いのアイテムとして重宝されてきました。
大切なのは、縁起物をただ身に付けるだけでなく、「感謝の気持ち」を持って扱うことです。そうすることで、厄年を前向きに乗り越える力となるでしょう。
厄年を気にし過ぎずに過ごす
厄年は人生の節目とされますが、必要以上に恐れる必要はありません。自己認識の向上につながり、これまでの経験を振り返るよい機会となります。
また、深刻にとらえすぎるとストレスが増すため、ポジティブに受け止める姿勢が大切です。文化的にも、厄年は成長や変化を象徴するものとされ、悪いことが起こる年ではなく、新たなライフスタイルへの移行の時期とも考えられています。
地域や個人の価値観によってとらえ方は異なり、柔軟に受け入れるのがよいでしょう。
厄年を「変化の年」として活かし、新しい挑戦や自己成長の機会ととらえましょう。冷静な判断と前向きな行動が、よりよい未来を切り開く鍵となります。
厄年の引越しに関するまとめ
ここまで、厄年とは何か、厄年に引越しをしても大丈夫か、引越しする場合の具体的な対策をご紹介しました。最後に大切なことを振り返っておきましょう。
厄年とは
厄年とは、日本で災厄が起こりやすいとされる年齢のことです。陰陽道に由来し、男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳・61歳が該当します。特に42歳の男性と33歳の女性は「大厄」とされ注意が必要です。人生の転換期にあたることが多く、心身のバランスを崩しやすい時期ともされています。
厄年に引越しをしても大丈夫?
厄年の引越しは慎重に進めるべきとされますが、必要以上に不安を感じる必要はありません。厄除けをおこない前向きな気持ちで臨めば、新生活をよりよい形でスタートできます。
厄年に引越しをする場合の対策
厄年に引越しをする際は、厄除けや厄払いを活用しましょう。神社やお寺での祈祷、断捨離、方違えなどが効果的です。また、風水を取り入れた環境づくりや、縁起物(破魔矢・お守り・厄除けブレスレットなど)を身に付けるのもおすすめです。厄年は人生の転換期とされますが、慎重な行動とポジティブな心構えを持ち、柔軟に受け入れましょう。
厄年は決して不運なだけの年ではなく、自分を見つめ直し、成長する機会でもあります。
新しい環境に挑戦する際は、不安を抱えすぎるよりも、「今までためこんできた不要なものを手放し、よい流れを作るための切り替えの期間」ととらえ、充実した日々を過ごすことが大切です。
どのような時も冷静な判断と前向きな行動が人生をよくします。厄年と柔軟に向き合い、引越しや新しい環境を楽しみましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる







