引越し時の保険証の住所変更とは?マイナ保険証の手続き方法と期限・注意点について解説

そこで今回は、転居時の保険証の住所変更について、詳しい手続きの流れや気を付けたいポイントなどをご紹介。なお2024年12月2日より、従来の保険証は廃止となり、マイナンバーカードと紐付けした「マイナ保険証」に移行しました。本記事においても、新たなマイナ保険証の手続き方法に基づいて解説していきます。
記事の目次
2024年12月2日より従来の保険証は廃止に

冒頭でお伝えしたように2024年12月2日から、基本的にはマイナンバーカードを健康保険証として利用する、マイナ保険証を使うシステムへと移行されました。このマイナ保険証を基本とする仕組みにともない、今までの健康保険証は廃止され、今後は新規発行も再発行もできません。
なお勤務先で加入している健康保険証と国民健康保険証の双方ともに、現時点で所持しているカードは、2025年12月1日までのうちで設定された有効期限まではそのまま利用が可能。ただし引越しをして住所変更が発生した際には、いずれも新たな保険証は発行されません。
ちなみにマイナ保険証の登録をしていない場合でも、これまでと同様に、保険診療が受けられる仕組みはあります。とはいえマイナ保険証の利用により、新たに便利になるメリットも多いので、この機会に移行しておくのがおすすめです。
マイナンバーカードと保険証を一体化するメリット
大前提として、マイナンバーカードと保険証を連携させることで、それぞれを別々に所持・持参する必要はなくなるのが利点です。その他にも、マイナ保険証を使うことで、次のようなさまざまなメリットがあります。
- 新しい保険証の発行を待つ必要がない
- これまでの処方薬剤や特定健診の記録が確認できる
- 災害時などの常備薬の処方にも活用できる
- 確定申告における医療控除の申請手続きが簡単になる
- 高額療養費の限度額超過分の免除がその場で適用される(窓口での一時負担なし)
例えば引越しや転職などで保険証の切り替えがある時でも、マイナ保険証であれば新規のカード発行をする必要がなく、新たな交付を待たずに利用できるのが大きなメリット。また、これまでの診療情報などがシステム上で自動的に反映・共有されるため、医療機関での受診時には自分で説明する手間もありません。こうした電子記録により、災害などの緊急時の処方箋にできたり、医療費関連の各種申請も簡単にしやすくなったりするのも便利なポイントです。
マイナンバーカードと保険証を一体化させる方法
マイナ保険証の利用に向けては、次のような準備や手順が必要です。
【事前準備】
- マイナンバーカード
- あらかじめ設定した4桁の暗証番号(マイナポータルサイトのログイン情報)
- 「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」または
「パソコンとICカードリーダー」 - 「マイナポータルアプリ」のダウンロード(スマートフォンの場合)
【手順】
- STEP 1マイナポータルの「利用を申し込む」から申し込みページを開く
- STEP 2利用規約の確認および同意(同意ボタンをクリック)
- STEP 3登録ページが出てきたら「申し込む」のボタンをクリック(パソコンの場合はICカードリーダーでマイナンバーカードを読み込み、「申し込む」を押下)
- STEP 4マイナンバーカード発行時に決めた暗証番号4桁を入力
- STEP 5「正常に受け付けました」の画面が出てきたら完了
出典:マイナポータル
まずマイナ保険証の利用には、マイナンバーカードが必要なので、まだ持っていない場合には新規発行の手続きが必要です。なおマイナ保険証の利用登録は、パソコンまたはスマートフォン(対応機種のみ)から可能ですが、医療機関や薬局、コンビニなどにある「セブン銀行ATM」からもできます。
またマイナポータルやセブン銀行ATMからマイナ保険証を申請する際には、マイナポータルへのログイン用に決めた暗証番号(利用者証明用電子証明書)の入力が必須のため、あらかじめ確認しておきましょう。ちなみに忘れてしまった場合には、役所にて再設定の手続きが必要となります。なお、医療機関や薬局においては暗証番号以外に顔認証で登録することが可能です。
引越ししたら保険証の住所変更が必要
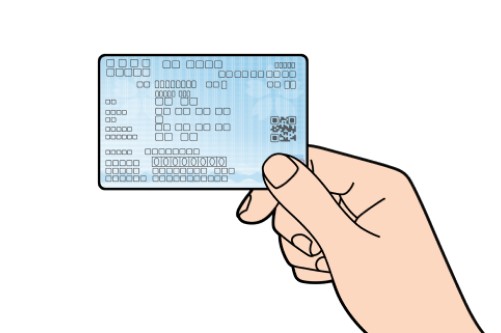
マイナ保険証への移行後は、住所変更にともなう新たなカード発行はありませんが、登録内容の更新手続きそのものは必須です。なお会社に勤めている場合には社会保険の健康保険、雇用されていない場合には国民健康保険に加入するのが一般的で、それぞれで手続きの内容は異なります。まずは、国民健康保険と社会保険でどう届出方法が変わるのか、大まかな違いから見てみましょう。
| 国民健康保険(75歳未満) | 社会保険 | |
|---|---|---|
| 加入対象 |
・非雇用者(自営業、フリーランス、農家など)や退職者
・勤務先の社会保険未加入者(パート、アルバイトなど)
・国民健康保険の被扶養者・1年以上日本に滞在する外国人登録者
|
社会保険が適用される勤務先で働く雇用者 |
| 運営主体 | 自治体(都道府県・市区町村) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)、各種健康保険組合 |
| 保険料 | すべて自己負担 | 勤務先による 半額負担あり |
| 手続き方法 | 被保険者が手続きをおこなう | 会社(雇用主)を通じて手続きをおこなう |
勤務先による社会保険に入っていなければ、一部例外を除き、基本的には国民健康保険への加入は義務とされています。そのため、例えば「転職して社会保険から外れている」などのケースでは、必ず国民健康保険に入らなければなりません(任意継続時には不要)。なお75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者や、生活保護受給者は、国民健康保険が免除されています。
では以下から、国民健康保険と社会保険の健康保険のそれぞれで、どのような手続きがあるのか詳しく解説していきます。
国民健康保険の手続き

国民健康保険の住所変更は、お住まいの市区町村役場の窓口で手続きをします。ここからは、引越し時の国民健康保険の手続き方法を詳しく見ていきましょう。
手続きの期限は14日以内
国民健康保険は、住民票の異動とともに引越し日から14日以内に手続きをして、転居先の地域にて新たに加入し直す必要があります。ちなみにマイナ保険証の場合、マイナンバーカード自体が国民健康保険証です。そのためマイナ保険証では、マイナンバーカードの住所変更ができれば、国民健康保険の加入情報も更新されます。
なお14日を過ぎた場合、申請期限を超過した期間にかかった医療費があると、その分は全額自己負担になる可能性も。もしくは大幅に申請期限を過ぎている場合、実際に加入すべき時期までさかのぼって、保険料の納付が求められるケースもあります。国民健康保険の住所変更ができていないと、本来受けられる行政サービスが適用されなくなってしまうリスクがあるので必ず14日以内に手続きをおこないましょう。
異なる市区町村に引越しする場合
引越しによるマイナ保険証の住所変更は、異なる市区町村間と、同一市区町村内の引越しで手続き方法は変わってきます。まずは、異なる市区町村に転居する際の申請の流れから解説します。
資格喪失手続き
まずは国民健康保険の住所変更にともない、もともと住んでいた居住地にて、「資格喪失」の手続きをする必要があります。なお引越しによる国民健康保険の資格喪失は、旧居住地での転出届の転出を通じて、自動的におこなわれるのが一般的です。
なお転出届(資格喪失)は、基本的には、旧居住地の市区町村役場の窓口にて提出します。ただしマイナンバーカードを持っている場合、マイナポータルより、オンラインで転出届を申請
する方法も可能です。
各地域の役所の窓口に出向いて、転出届(資格喪失)の手続きをする際には、次のものの持参が必要です。
<必要書類など>
- マイナンバーカード(マイナ保険証)
- 本人確認書類
- 今までの健康保険証(所持している場合)
またマイナンバーカードを使った、オンラインの転出届(資格喪失)では、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号(マイナポータルへのログイン)が必要です。オンライン申請をおこなう時は、あらかじめ確認しておきましょう。ちなみに自治体ごとに、手続きの流れや必要な持参物が異なる場合もあるため、お住まいの市区町村のホームページなどもあわせてチェックしてみてください。
加入手続き
旧居住地にて転出届(資格喪失)の手続きをおこない、新居に引越しをしたら、新しく住む市区町村役場で転入届を提出する必要があります。そして転出届の申請をしたら、国民健康保険の再加入・マイナ保険証の継続利用の手続きをして、基本的には完了です。
国民健康保険の転入届(加入手続き)は、新しい居住地の役所に来庁して手続きをします。また国民健康保険の手続きには、以下を持っていきましょう。
<必要書類など>
- マイナンバーカード(マイナ保険証)
- 本人確認書類
- 転出証明書
- キャッシュカード、または通帳、銀行印(口座振替用)
転出届(資格喪失)の際に、オンラインではなく役所窓口にて手続きをした場合には、旧居住地にて「転出証明書」が発行されます。この転出証明書は、保険加入の申請にともなう転入届の提出時に必要となるため、大切に保管して手続きの際に持参するようにしましょう。オンラインでの転出届時には、転出証明書は交付されないので不要です。
なお自治体によっては、国民健康保険料の納付は、口座振替を原則としているケースも見られます。そうした場合には、口座登録用のキャッシュカードや銀行印などの持参が求められることも。転入届(加入手続き)を出す際も転出届(資格喪失)と同様に、各自治体で手続き方法や持参物が異なる場合もあります。同じく、お住まいの市区町村のホームページなどもあわせて確認しておきましょう。
ちなみに窓口での転出届(資格喪失)や加入手続きは、委任状を利用した代理人による申請も可能です。
同じ市区町村に引越しする場合
同じ市区町村内で引越しをする場合は、国民健康保険の管轄地域が変わらないため、資格喪失や再加入の手続きは不要です。ただし居住地自体は以前と異なるため、「転居届」による住所変更の手続きが必要となります。国民健康保険自体の手続きはないものの、転居届の提出は必須となるので、忘れずに申請をするようにしましょう。ちなみに同一市区町村での引越し時には、お住まいの地域の役所窓口にて、転居届を出したら完了です。なお手続きの際には、次のものを持参するのが一般的です。
<必要書類など>
- マイナンバーカード(マイナ保険証)
- 本人確認書類
なお必要書類などは、自治体ごとに相違する場合もあるので、あらかじめお住まいの地域のホームページなどを確認しておきましょう。
マイナンバーカード・マイナ保険証を持っていない場合
マイナンバーカードやマイナ保険証を現在持っていない場合、従来の国民健康保険証は今後使えないため、引越しにともなって新規発行の申請や利用登録をしましょう。ただしマイナ保険証は任意利用ができるものでもあり、未発行・未登録者には、保険証代わりとなる「資格確認書」が交付されます。
医療機関にかかる際には、この資格確認書を提示すれば、今までと同様の自己負担分のみで診療・処方などを受けることが可能です。とはいえ資格確認書では、カルテの電子記録や医療費関連の申請の簡易化など、マイナ保険証にともなう新たなサービスの対象にはなりません。このようにマイナ保険証がなくても、従来どおりの医療にかかることはできますが、さまざまなメリットは受けられないため注意しましょう。なお資格確認書は、マイナンバーカードやマイナ保険証がない場合に、特に申請などの手続きはしなくても自動的に無料交付されます。
また資格確認書の住所変更の手続き方法は、基本的にはマイナ保険証とほとんど同じです。マイナンバーカード(マイナ保険証)の代わりに、資格確認書を持参して資格喪失や再加入、もしくは転居届の申請をします。
社会保険の場合の手続き

自身で加入する国民健康保険とは異なり、勤務先による社会保険の手続きは、通常は職場内の担当部門などで対応してくれます。例えば人事部や総務部などで代行してもらえるので、引越しによる住所変更があった時には、必ず担当部門に伝達するようにしましょう。
【手順】
- STEP 1会社の担当部署に引越しの報告・住所変更の依頼をする
- STEP 2カード本体の記載事項は自分で更新する(市区町村役場の窓口)
引越しにともなう住所変更の具体的な申請方法は、勤務先のルール次第で異なります。承認フローが決まっているケースもあるため、引越しの際に必要な手続きは、就業規則や上司などに一度確認してみましょう。
なおマイナ保険証を利用していて、マイナンバーカード本体の記載事項が変わる際には、お住まいの自治体にて自分で書き換えをする必要があります。転居の各種手続きと一緒に、新しい居住地の役所窓口にて、忘れずに対応するようにしましょう。

- 【例文あり】会社への引越し報告はいつまでにする?しないとどうなる?
- 引越しをしたら、住民票や免許証など、住所変更をしなければならないものがいくつもあります。こうした手続きのなかで、忘れずに
続きを読む

資格確認書を使う場合の住所欄の修正方法
もしマイナ保険証ではなく、資格確認書を使うのであれば、住所欄は手書きなどで修正します。新規発行はされないので、住所変更があっても、記載事項が更新された健康保険証を受け取ることはできません。なお資格確認書の利用時も、社会保険の手続き自体は勤務先が代行してくれるので、記載事項の修正のみ自分で対応します。
保険証の住所変更手続きをしないとどうなる?

万が一、引越し時に保険証の住所変更が漏れてしまった場合に、どのような事態が生じるのか見ていきましょう。
医療費が全額負担になる
保険証の住所変更をしないまま使うことは原則できません。そのため保険証の住所変更をしないまま医療機関にかかってしまうと、その際に発生した医療費は全額負担となるので注意が必要です。
たとえ保険料をきちんと納付していたとしても、正しく手続きがされていないと、医療費の全額負担が生じてしまい大きな出費になってしまう可能性も。仮に住所変更の手続き前に医療機関にかかった場合、手続き後の過払い金の払い戻しを受けられます。ただし、2年の払い戻し期限が設けられていたり、別途、書類を集めて申請が必要だったりなど手間が増えるので、保険証の住所変更はすみやかに手続きができるように対処しましょう。
保険料の納付書などの重要書類が届かない
国民健康保険は、自治体から送られてくる納付書を使って納税するため、住所変更がされないまま納付書が未達になると、保険料の支払いが滞ってしまうリスクも。また国民健康保険には加入義務があり(社会保険加入時を除く)、保険料の未納が発生すると、督促状や電話・通達書・訪問員などによる催告がおこなわれます。それでも未納のままになっていると、財産差し押さえなどのペナルティが科されてしまうため注意が必要です。知らず知らずのうちに未納にならないためにも、必ず保険証の住所変更手続きは早めに進めておきましょう。
未納期間による年金額減少の可能性がある
健康保険の住所登録は、年金の納税にも紐付いています。正しく手続きがされていないと、場合によっては年金の未納も発生してしまい、将来的な受給額が減ってしまう可能性も。住所変更にともなう保険料の未納が発生すると、さまざまなリスクにつながるため、きちんと正しく支払いができるように手続きをするようにしましょう。
国民健康保険料の過払い・未払いが発生した時の対処法

例えば「国民健康保険から社会保険に切り替えた」などの場合、住所変更にともなう資格喪失や再加入の手続きのタイミング次第では、保険料の二重払いや未納が発生する可能性も。ちなみに社会保険内の住所変更では、勤務先にて適宜対応してもらえるため、基本的には過払いや未払いはないと考えてよいでしょう。なお国民健康保険料の過払いや未払いになってしまった時には、次のように対処します。
重複期間があり過払いが発生した場合
もし健康保険加入の重複期間があり、保険料を支払いすぎてしまったら、過払い金の還付請求によって返金してもらうことが可能です。なお還付請求ができる期間には制限があり、原則は国民健康保険の脱退から2年間とされています。保険料の払いすぎに気が付いた時には、必ず早めにお住まいの市区町村役場の専門窓口に相談して、手続きを進めるようにしましょう。
再加入が遅れ未払いが発生した場合
住所変更にともなう再加入が遅れてしまい、未納が発生した場合には、支払い義務が発生した資格取得時まで逆算した保険料(最長2年)をまとめて納めなければなりません。保険料の未払い金は、基本的に一括で支払う必要があるので要注意。一度に高額な支払いを求められるリスクをはじめ、延滞金の追加や本来受けられる行政サービスの適用外になるケースもあります。未納にならないためにも、引越ししたら漏れなくすみやかに手続きするようにしましょう。
住所変更手続き前に病院に行きたい場合どうする?

仮に住所変更の手続きをする前に、医療機関まで受診しなければならない場合には、自分で全額立て替えて払い戻しを申請することになるでしょう。やむを得ず全額負担となった時には、加入先の協会や組合に申請するか、もしくは国民健康保険ならお住まいの自治体の役所窓口にて手続きをします。
医療費の払い戻しを申請したい場合は以下の書類を用意し、医療費を支払った日から2年以内に手続きをおこないましょう。手続きの方法・必要なものに関しては、申請先によって異なりるので注意が必要です。
<必要書類など>
- 健康保険療養費支給申請書
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 被保険者記号番号がわかるもの(マイナ保険証または資格確認書など)
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
なお「マイナンバーカードの発行中でまだ手元にない」などの際には、保険証の代用となる資格確認書の交付申請をする方法もあります。交付申請により、早急に資格確認書の受け取りができ、実際に医療機関にかかる時の保険証として使うことが可能です。
引越し後に保険証と一緒に済ませたい手続き

引越しにともなう保険証の住所変更と同時に、なるべく早めに対処しておきたい各種手続きの一例をまとめていきます。
- マイナンバーカードの記載変更
- 印鑑登録
- 運転免許証
- 車検証や車庫証明
- 児童手当
- 母子手帳
- ライフライン関連(水道、ガス、電気、インターネット、携帯など)
- 郵便物の転送
- その他各種サービス(銀行口座、クレジットカードなど)
マイナンバーの記載事項は、異なる市区町村間なら継続利用、同じ市区町村内なら券面更新手続きによって更新ができます。なおマイナンバーの他、印鑑登録・児童手当・母子手帳などの住所変更は、いずれも役所窓口での手続きとなるのでまとめて対応しましょう。
ちなみに運転免許に関しては、2025年3月よりマイナンバーカードとの一体化が進められる方針です。マイナンバーカードに連携されれば、運転免許証の住所変更は省略されるでしょう。また各種手続き方法は、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
引越し時の保険証の手続きについてよくある質問

最後に、引越しにともなう健康保険証の取り扱いや住所変更などで、よくある質問についてまとめていきます。
現行の保険証からマイナ保険証に切り替えないといけない?
基本的にはマイナ保険証の利用が推奨されており、なるべく移行するのがおすすめです。ただし現時点ではマイナ保険証への移行は任意となっており、従来の保険証は廃止されるものの、医療機関にかかる際には代わりとなる資格確認書を使うことができます。
保険証は住所変更しなくても使える?
健康保険は、お住まいの自治体による行政サービスとして適用されるため、住所変更がされていない保険証は利用できません。保険証の住所変更がされていない時には、医療費は全額負担となるので注意しましょう。
引越し先で国民健康保険に加入しなくてもいい?
もし勤務先の社会保険に加入していれば、国民健康保険に入る必要はありません。ただし転居前から国民健康保険を利用していたり、引越し時に社会保険から抜けたりする場合には、新たな居住地での加入手続きをしなければなりません。基本的に社会保険に入っていなければ、国民健康保険の加入義務対象として、引越し先でも新たに入り直すことが求められます。
学生が一人暮らしする場合の保険証も住所変更が必要?
高校や大学などの進学によって、一時的に一人暮らしをするため、住民票を移さずに引越しする場合は、住所変更をせずに元々の保険証(資格確認書)を使うことができます。
一人暮らしする際に住民票を移す場合でも転居前の居住地にて、就学にともなう被保険者の特例(マル学)申請をすることで、転入先で新たに国民健康保険に加入しなくても、転出前に住んでいた市区町村に保険料を納めることができます。
まとめ
2024年12月2日から今までの保険証がなくなり、マイナンバーカードと一体になったマイナ保険証に切り替わりました。それにともない手続きが従来の方法と異なるケースもありますが、引越し前の段階でマイナ保険証の利用登録が済んでいれば、転居先でも新たなカード発行を待つことなく、すぐにでも使いはじめることが可能に。もちろん住所変更の手続きは必要ですが、再発行のタイムラグがなく、保険証を利用できるのが便利なポイントです。
まだマイナ保険証への移行をしていない場合には、本記事も参考に、新たな利用登録を検討してみるのもおすすめ。マイナ保険証をお使いで引越しの予定がある際には、ぜひ本記事もチェックしつつ、必要な住所変更手続きを進めていきましょう。
物件を探す




