家賃収入は副業になる?副業とみなされる基準や会社にバレる理由を解説

記事の目次
家賃収入は副業にあたらないと考えられる理由
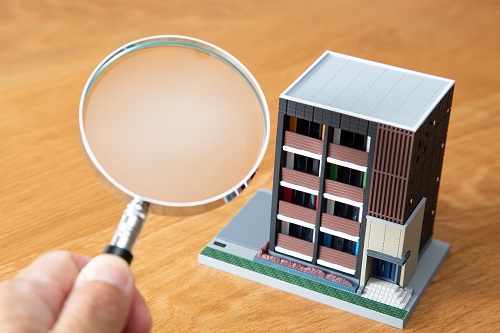
家賃収入を得ることは、副業になると考えている方もいるでしょう。しかし、実際には副業にあたらないと考えられることが多いです。その理由はなぜなのか、本章では3つ解説します。
資産運用の一つとみなされる
家賃収入を得ることは、資産運用の一つとみなされるため、副業にあたらないと考えられています。実際に、すでに株式投資や投資信託などの運用をおこなっている方もいるでしょう。
ただし、証券会社や金融機関に勤めている方は、インサイダー取引にあたる可能性があることから、個別株やFXへの投資は禁止されていることも。勤め先によっては制限されることもありますが、一般的に家賃収入を得ることは資産運用の一つと考えられるため、副業にはあたらないと考えられます。
意図せず家賃収入を得るケースがある
意図していないにも関わらず、家賃収入を得るケースがあります。例えば、親が亡くなって投資物件を相続したり、転勤をきっかけに自宅を貸し出したりするケースです。これらはやむをえない事情であるため、会社も禁止できません。そのため、副業の禁止規定から賃貸経営は除外されていると考えられます。
副業禁止規定の有効性は認められない
これまでの裁判例を踏まえると、副業禁止規定の有効性は認められないと考えられています。日本国憲法の第22条では「職業選択の自由」が保障されており、副業を禁止する法律はありません。労働以外の時間をどのように過ごすかは、労働者の自由とされており、副業も問題ないとされています。しかし、副業することで本業に支障をきたす場合や、企業秘密が漏洩する場合には、副業禁止規定は有効と考えられています。
本業への影響や情報漏洩のリスクを考慮して会社で副業が禁止されている場合でも、家賃収入はそれらに該当しないため、副業とみなされないでしょう。
家賃収入が副業とみなされる基準

家賃収入を得ることは、基本的に副業にあたらないと考えられますが、一定の基準を超えると副業とみなされる可能性があります。本章では、家賃収入が副業とみなされる基準を解説します。
一定規模以上の不動産投資をしている
一定規模以上の不動産投資をおこなっている場合、副業とみなされる可能性があります。「一定規模以上」とは、次のとおりです。
“(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。”
引用:国税庁 No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
独立家屋とは一戸建ての物件を指します。上記、どちらかの基準を満たしている場合、事業としておこなっていると判断されるため、副業にあたる可能性があるでしょう。
一定規模以上の駐車場経営をしている
家賃収入は、アパートやマンションの部屋を貸し出す以外にも得られるものです。一定規模以上の駐車場経営をしている場合も、副業と判断される可能性があります。
明確な基準が提示されているわけではありませんが、車5台分を1室として換算し、50台以上停められる駐車場の場合、事業として判断されるようです。また、コインパーキングなど一括で貸し出している場合も、事業とみなされ、副業にあたると考えられます。
娯楽施設を経営している
規模や内容に関わらず、娯楽施設を経営している場合も、副業とみなされる可能性があります。娯楽施設の具体例としては、カラオケボックスや映画館など。これらの娯楽施設の経営は一般的な賃貸経営と異なり、取引先が多くなることから、事業的な要素が強いと判断されます。娯楽施設の経営は業務が多いことから、副業でおこなうことは稀でしょう。しかし、相続で引き継ぐ場合は注意しましょう。
家賃収入が事業的規模となる場合、副業とみなされるケースがあります。そのため、就業規則で副業が認められていない会社では、この基準を超えないように注意しましょう。
家賃収入が会社にバレる理由は?

事業的な規模で賃貸経営をおこなっていなくても、家賃収入を得ていることが会社に知られてしまうことがあります。もし、副業禁止規定で禁止されていた場合は、会社から何かしらの罰則を受けるかもしれません。なぜ会社にバレてしまうのか、本章ではその理由を解説します。
住民税額が変わる
副業で家賃収入を得ると、課税所得が増えることから、住民税額が変わることがあります。住民税は、前年の所得に基づいて計算されます。また会社員の場合、住民税は給与から差し引かれます。
そのため、住民税額が大きく増えていれば、会社から給与以外に所得を得ていると疑われる可能性があるでしょう。
会社に知られたくない場合は、給与から差し引くのではなく、自分で支払うよう手続きをしましょう。
税務署から会社に連絡が入る
副業で得た家賃収入が一定の要件を満たした場合、確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告を怠ったり、不正な申告をおこなったりした場合、税務調査で税務署から会社に連絡が入る可能性があります。確定申告を適切におこなわなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることも。また、会社に税務調査が入ることで、会社での立場も危ぶまれるでしょう。
会社に告げ口をされる
副業で家賃収入を得ていることがバレる理由として、同僚や上司などからの会社への告げ口が挙げられます。例えば、副業で成功している様子を目にした同僚が、妬みや嫉妬から告げ口をすることも考えられるでしょう。副業が禁止されていない会社であっても、必要以上に家賃収入について口外しないほうがいいでしょう。また、SNSでの発信も、誰が見ているかわからないため、気を付けましょう。
副業で家賃収入を得るメリット

会社員が家賃収入を得るメリットは、収入源が増えるだけではありません。本章では、副業で家賃収入を得るメリットを解説します。
融資を受けやすい
副業で家賃収入を得るメリットは、融資を受けやすいことです。会社員が副業で賃貸経営をおこなう場合、本業の収入が安定しているため、金融機関から融資を受けやすくなります。賃貸経営をおこなう際には、不動産投資ローンを組んで投資物件を購入することが一般的。
不動産投資ローンの審査では、借り手の属性も確認されます。属性とは、勤め先や年収、借入状況などのこと。不動産投資ローンは高額な融資であるため、借り手に返済能力があるかが判断されます。本業で安定した収入を得ていれば、不動産投資ローンの融資も受けやすくなるでしょう。
節税効果が期待できる
副業で得た家賃収入が赤字だった場合、節税効果が期待できます。これは、家賃収入の赤字を本業の給与所得で相殺する「損益通算」によるものです。例えば、家賃収入が100万円の赤字で、給与所得が700万円だった場合、損益通算をすることで課税所得が600万円となります。課税所得が減るため、所得税や住民税などの税金負担を軽減できます。
投資物件が資産になる
会社員が家賃収入を得るメリットの一つが、購入した投資物件が資産になることです。不動産は、そのものに価値がある現物資産であるため、経済状況が変動しても資産価値が下がりにくい傾向にあります。また、インフレ時には、物価の上昇にともなって資産価値も上昇します。さらに、投資物件を子どもや孫などに相続することも可能。家賃収入を得られるだけでなく、購入した投資物件が資産になることがメリットです。
管理の手間がかからない
賃貸経営には、投資物件のメンテナンスや入居者の募集・契約など、さまざまな管理業務が必要です。しかし、これらの業務を管理会社に委託すれば、本業に支障をきたすことなく、賃貸経営が可能となります。ただし、管理会社によって管理手数料やサービス内容が異なるため、事前の情報収集が欠かせません。安心して任せられる管理会社を見つけるためにも、複数を比較検討し、納得のいく管理会社を選択しましょう。
副業で家賃収入を得るデメリット

副業で家賃収入を得ることは、メリットだけではありません。本章ではどのようなデメリットがあるのか、3つ解説します。「こんなはずではなかった……」と後悔しないためにも、メリット・デメリットを理解したうえで、検討しましょう。
初期費用や維持費用がかかる
副業で家賃収入を得るデメリットとして、初期費用や維持費用がかかることが挙げられます。先述したように、投資物件を購入する際には、不動産投資ローンを組むことが一般的。しかし、購入費用だけでなく、ローンの事務手数料や火災保険料、仲介手数料など、さまざまな諸費用がかかります。初期費用の目安としては、物件価格の15%程度。例えば、物件価格が8,000万円であれば、1,200万円が初期費用として必要となります。
また、賃貸経営が始まったあとも維持費用がかかります。具体的には、固定資産税や修繕費用など。これらは家賃収入から支払うことが前提ですが、空室が多く出た場合には、手持ちの資金から出さなければならないかもしれません。まとまった初期費用や継続的に維持費用がかかることは、デメリットといえるでしょう。
さまざまなリスクがある
副業で家賃収入を得ることは、さまざまなリスクがあることもデメリットです。例えば、空室リスクや金利上昇リスク、自然災害リスクなどのリスクがあります。空室リスクとは、投資物件が空室になって家賃収入が減ってしまうこと。長期間にわたって空室になると、不動産投資ローンの返済に影響が出ることも考えられます。
また、金利上昇リスクとは、変動金利を利用している場合、金利の上昇によって、不動産投資ローンの返済額が増加してしまうこと。急激に金利が上がれば、返済負担が増え、経営が破綻してしまうおそれもあります。
最後に自然災害リスクとは、台風や地震などの自然災害によって、投資物件が損壊し、家賃収入を得られなくなってしまうリスクのことです。入居者が住めなくなれば、入居者に対して補償をしなければならないかもしれません。このように、賃貸経営はさまざまなリスクがあるため、リスク許容度に応じておこないましょう。
物件選びが難しい
安定した家賃収入を得るためには、投資物件選びが重要です。しかし、初心者の場合、数多くある物件のなかから、収益性が高く、リスクの少ない投資物件を選ぶことは簡単ではありません。投資物件を選ぶ際には、立地や築年数、周辺環境など、さまざまな要素を考慮する必要があります。不動産情報サイトを見るだけでなく、現地に足を運ぶことも必要になるでしょう。
自分に合った投資物件を見つけるためには、時間と手間がかかるもの。本業をしながら投資物件を探すとなると、時間を捻出することが難しいかもしれません。不動産会社など、信頼できるパートナーを見つけるといいでしょう。
副業で家賃収入を得た場合の確定申告
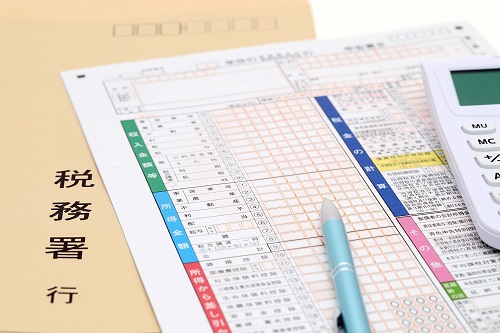
副業で家賃収入を得た場合には、確定申告が必要になる可能性があります。確定申告を怠るとペナルティが課されることも。適切な申告をおこなうためにも、どのような場合に確定申告が必要なのかを把握しておきましょう。
家賃収入で得た所得が20万円以上の場合
家賃収入は、不動産所得に該当します。不動産所得が20万円以上の場合、確定申告をする必要があります。ただし、家賃収入がそのまま不動産所得とみなされるわけではありません。具体的な計算式は次のとおりです。
- 不動産所得=家賃収入ー経費
例えば、家賃収入が80万円で、経費が30万円かかった場合。不動産所得は50万円となり、確定申告をしなければなりません。また、家賃収入は、部屋を貸し出して得た賃料だけではなく、礼金や更新料なども該当します。正確な申告をおこなうためにも、家賃収入や経費にあたる費用を、きちんと理解しておきましょう。
損益通算をおこないたい場合
家賃収入が赤字で、給与所得と損益通算をおこないたい場合も、確定申告をしましょう。例えば、賃貸経営を始めた年は高額な初期費用がかかるため、赤字になることが一般的です。先述したように、給与所得と赤字を相殺することで、課税所得が減り、結果として納める税金も少なくなります。確定申告をしなければ、損益通算はできないため、積極的に活用しましょう。ただし、間違えて申告をすると、修正をしなければなりません。税理士などの専門家に相談しながらおこなうといいでしょう。
まとめ
本記事では、家賃収入は副業にあたるのか、副業とみなされる基準を解説しました。一般的に、家賃収入を得ることは、資産運用の一つとみなされるため、副業にあたらないと考えられています。しかし、一定以上の規模でおこなうと、副業とみなされる可能性があります。
家賃収入で所得が増えると住民税額が増えるため、会社に知られてしまう可能性もあります。家賃収入を得ることが問題ないか、事前に会社に確認を取っておくと安心でしょう。また、家賃収入で得た所得が20万円以上となると確定申告が必要になります。無申告だとするとペナルティが課されることも。税理士などに相談し、適正な申告をおこないましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ










