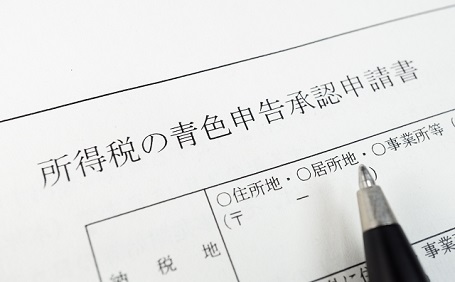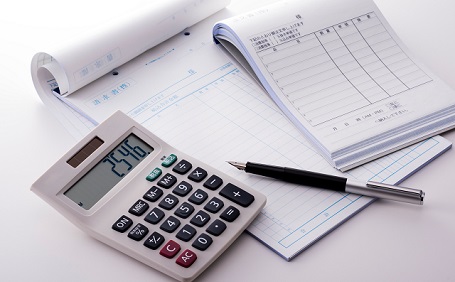不動産投資で確定申告をすると還付金はいくら?シミュレーションや節税効果を高めるポイントを解説

記事の目次
不動産投資における税金の種類

不動産投資をすると、さまざまな税金がかかります。なお、確定申告で申告をする税金は所得税ですが、それ以外にどのような税金があるのか把握しておきましょう。なかには経費として計上できるものもあるため、しっかり押さえておきましょう。
不動産の購入時にかかる税金
投資用物件の購入時には、次の3つの税金がかかります。
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
それぞれ詳しくみていきましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは、投資用物件を建築したり、購入した際にかかる税金のことです。投資用物件が所在する都道府県に納めます。
※2027(令和9)年3月31日までの軽減措置で、本則は4%
登録免許税
登録免許税とは、投資用物件の権利関係を公的に証明する登記手続きをおこなう際に支払います。なお、登記をおこなう内容によって、税率が異なるため注意しましょう。
所有権保存登記:固定資産税評価額 × 0.4%
所有権移転登記:固定資産税評価額 × 2.0%
抵当権設定登記:投資用ローンの借入額 × 0.4%
印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書などの契約書に貼るものです。印紙税の税率は、契約金額によって異なります。具体的には次のとおり。
| 契約金額 | 印紙税額(本則) | 税額(軽減後) ※2027年(令和9年) 3月31日まで |
|---|---|---|
| 100万円超 500万円以下 |
2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 |
1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 |
2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 |
6万円 | 3万円 |
| 1億円超 5億円以下 |
12万円 | 6万円 |
ここで取り上げたものは、すべて経費として計上できます。支払った時の領収書など、きちんと保管しておきましょう。
不動産の運用時にかかる税金
投資用物件を運用する際にも、さまざまな税金がかかります。具体的には、次の3つです。
- 固定資産税・都市計画税
- 所得税・住民税
- 個人事業税
それぞれ詳しくみていきましょう。
固定資産税・都市計画税
固定資産税とは、土地や投資用物件などの固定資産を所有している方に課せられる税金です。毎年、固定資産が所在する地方自治体に納めなければなりません。また、都市計画税とは、投資用物件が市街化区域内にある場合に課される税金です。具体的な計算式は次のとおり。
固定資産税:固定資産税評価額 × 1.4%
都市計画税:固定資産税評価額 × 0.3%
どちらも経費として計上できるため、領収書の保管を忘れないようにしましょう。なお、新築の場合、固定資産税は3年間、マンションの場合は5年間にわたって、2分の1に減額されます。これは2026年3月31日までの措置である点に注意しましょう。
所得税・住民税
不動産投資によって得られた所得に対して、所得税や住民税が課されます。これらは、所得に対してかかる税金であることから、経費として計上できない点に注意しましょう。所得税の計算式は次のとおりです。
所得税:課税所得額 × 税率 - 控除額
また、住民税は所得に応じて負担する「所得割」と、所得に関わらず一定の金額を負担する「均等割」を合わせたものを納めます。
個人事業税
個人事業税とは、個人事業主が事業所のある都道府県に対して納める税金です。事業内容によって税率が異なり、不動産貸付業の場合は5%となります。なお、控除額が290万円のため、課税所得が290万円以下の場合には、納める必要がありません。具体的な計算式は次のとおりです。
個人事業税:(不動産所得 - 事業主控除290万円)× 5%
複数の投資用物件を所有し、不動産投資の所得が多い場合は、個人事業税がかかる可能性があります。なお、確定申告をした場合は、別途申告する必要はありません。申告書の「事業税に関する事項」の欄に、必要事項を記入しましょう。
不動産の売却時にかかる税金
投資用物件を売却した際にも、売却益に対して税金がかかります。これは譲渡所得税と呼ばれるもので、投資用物件の所有期間によって税率が異なります。具体的には次のとおりです。
| 長期譲渡所得 | 短期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 税率 | 20.315% | 39.63% |
| 内訳 | 所得税:15.315% 住民税:5% |
所得税:30.63% 住民税:9% |
※2037年までの税率には、復興特別所得税の2.1%が上乗せされます
投資用物件の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。ただし、この所有期間は、売却した年の1月1日時点を基準に判断する点に注意しましょう。例えば、2019年12月1日に投資用物件を購入した場合。5年後の2024年12月1日に売却をした時、暦のうえでは5年経過しています。しかし、2024年1月1日時点では、5年を経過していないため、短期譲渡所得として扱われます。短期譲渡所得の場合、税率が高くなるため、税金を抑えたい場合は、所有期間や売却するタイミングに注意しましょう。
不動産投資において確定申告が必要なケース

不動産投資の還付金を受け取るためには、確定申告をしなければなりません。具体的にどのような場合に、確定申告が必要なのか、3つのケースを解説します。
不動産所得が20万円を超える場合
給与所得があり、不動産所得が20万円を超える場合は、確定申告をしましょう。なお、不動産所得とは、不動産収入から必要経費を引いたものです。例えば次の場合、不動産所得が20万円を超えるため、確定申告をしなければなりません。
不動産収入:60万円
必要経費(固定資産税など):20万円
不動産所得
60万円 - 20万円 = 40万円
なお、不動産所得が赤字だった場合でも、確定申告をしたほうがいいケースがあります。詳細はのちほど解説します。
青色申告をおこなう場合
青色申告をする場合も、確定申告をしなければなりません。青色申告で一定の要件を満たすと、青色申告特別控除額として最大65万円を不動産所得から差し引くことができます。例えば、不動産所得が100万円だった場合、65万円の控除を受けると所得は35万円となり、その分税金が抑えられます。ただし、青色申告で最大の65万円の控除を受けるためには、一定規模以上で不動産投資をしなければなりません。一定規模以上とは次のとおり。
アパートやマンションの場合:10室以上
戸建て住宅の場合:5棟以上
そのため、青色申告はある程度の規模で不動産投資をおこなっている場合の選択肢となるでしょう。なお、青色申告をする場合には、税務署に事前に届出をしなければなりません。
損益通算をおこなう場合
損益通算をおこなう場合も、確定申告をしましょう。損益通算とは、給与所得や事業所得などの所得と、赤字の不動産所得を相殺することです。損益通算をすると、課税所得が減少し、所得税や住民税を抑えられる可能性があります。例えば、給与所得が800万円、不動産所得がマイナス300万円としましょう。給与所得のみの場合、所得税率は23%となります。しかし、損益通算をおこなった場合、課税所得が500万円となるため、税率は20%となります。このように損益通算をおこない、課税所得が圧縮されたことにより、税金の負担を軽減できます。
不動産投資の確定申告をした際に受け取れる還付金はいくら?

それでは、不動産投資の確定申告をした際に、受け取れる還付金はいくらになるのでしょうか。本章では実際にシミュレーションをしてみましょう。
所得税における還付額のシミュレーション
まずは所得税で還付金をいくら受け取れるのか、シミュレーションをおこないます。なお、条件は次のとおりです。
<条件>
年収:800万円
社会保険料など:200万円(年収の25%と仮定)
給与所得:600万円
不動産所得:-200万円
給与所得に対する所得税額
600万円 × 20% - 42万7,500円 = 77万2,500円
不動産所得を確定申告した場合
課税される所得 600万円 - 200万円 = 400万円
給与所得と不動産所得を合わせた所得に対する所得税額
400万円 × 20% - 42万7,500円 = 37万2,500円
還付される金額
77万2,500円 - 37万2,500円 = 40万円
今回の場合、給与所得のみでは所得税額が77万2,500円でした。しかし、赤字の不動産所得と損益通算をすることで、課税所得が400万円となり、所得税額は37万2,500円まで抑えられました。そのため、不動産投資によって受け取れる還付金の金額は、差額の40万円となります。
住民税の還付額シミュレーション
次に、住民税の還付額はいくらになるのか、シミュレーションをしてみましょう。なお、条件は先ほどと同様です。住民税の計算式は次のとおり。
住民税 = 課税所得 × 10% + 5,000円
給与所得のみの場合
600万円 × 10% + 5,000円 = 60万5,000円
給与所得と不動産所得を合わせた時の住民税額
400万円 × 10% + 5,000円 = 40万5,000円
今回の場合、住民税が20万円安くなることがわかりました。なお、住民税は還付金として受け取れるわけではなく、翌年の住民税が抑えられます。所得税のように、還付金が金融機関の口座に振り込まれない点に注意しましょう。
不動産投資は節税にならない?還付金を増やすためのコツ

節税目的で不動産投資を始めたにも関わらず、還付金が多くないと感じている方もいるかもしれません。本章では、不動産投資で節税するためのコツを解説します。
青色申告を選択する
青色申告とは、税制上の優遇措置が受けられる申告方法です。青色申告をすると、次のメリットがあります。
- 青色申告特別控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 事業専従者控除を受けられる
先述したように、青色申告をする際に一定の要件を満たすと、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。控除を受けることで、課税所得を圧縮でき、納めるべき税金が抑えられます。また、赤字を3年間繰り越せる点もメリット。青色申告をした年が赤字で、翌年が黒字でも、黒字から赤字分を差し引くことができます。そのため、こちらも課税所得を大きく減らせる可能性があります。最後に、事業専従者控除を受けられる点もメリットです。事業専従者とは、青色申告をおこなっている事業主のもとで働く家族のこと。この家族に支払う給与を全額経費として計上できるため、節税効果を高められます。
ただし、青色申告をするためには、開業届や青色申告承認申請書を、事前に税務署へ提出しなければなりません。また、青色申告特別控除の最大金額である65万円の適用を受けたい場合には、他の要件を満たす必要があります。
経費を適切に計上する
経費を適切に計上することで、節税効果を高められます。経費として計上できる費用は、次のとおりです。
- 減価償却費
- 租税公課(固定資産税・都市計画税など)
- 委託管理費用
- 修繕費
- 投資用ローンの利息
ここに挙げたものは不動産所得を得るために、必要不可欠な経費です。これ以外にも、交通費や新聞図書費、通信費など、不動産所得を得るためにかかった費用は、経費として計上できます。経費として計上する際には、不動産投資に関連するものであると証明できなければなりません。そのため、領収書や明細書などはきちんと保管しておきましょう。また、計上していいのか判断に迷う時は、税理士などの専門家に相談しましょう。
耐用年数に注意して投資用物件を選ぶ
不動産投資において節税効果を高めるためには、耐用年数に注意して投資用物件を選びましょう。耐用年数が短い投資用物件を選ぶことで、より多くの減価償却費を計上でき、課税所得を減らして節税効果を高められます。建物や設備などの固定資産は、時間の経過とともに価値が減少。このことを考慮し、固定資産を購入する際にかかった費用を耐用年数に応じて経費計上することを、減価償却といいます。
建物の構造に応じて耐用年数が定められており、木造は22年、鉄筋コンクリート造は47年です。もし、投資用物件の購入価格や築年数が同じだった場合、木造のほうが減価償却費を多く計上できます。節税効果を高めたいのであれば、耐用年数も考慮して投資用物件を選びましょう。
不動産投資における確定申告の手順と還付金の受け取り方法

不動産投資で還付金を受け取るためには、確定申告をしなければなりません。簡単な流れは次のとおりです。
- STEP 1申告の方式を決める
- STEP 2必要書類を用意する
- STEP 3書類を作成する
- STEP 4税務署に提出する
それぞれ詳しくみていきましょう。
STEP1.申告の方式を決める
まずは確定申告の方式を決めましょう。青色申告だけではなく、白色申告もあります。白色申告は青色申告特別控除といった税制上のメリットはありません。しかし、青色申告と比較して必要な書類が少なく、手続きも比較的簡単です。どちらの方式が自分に合っているか、慎重に判断しましょう。
STEP2.必要書類を用意する
申告方式を決めたら、必要書類を用意しましょう。具体的に必要な書類は、次のとおりです。
不動産投資の確定申告で必要な書類一覧
| 不動産関連の書類 | 不動産売買契約書 | 投資用物件の売買契約を締結した書類 |
|---|---|---|
| 賃貸契約書 | 借主に部屋を貸す際に賃貸借契約を締結した書類 | |
| 家賃の送金明細書 | 管理会社に委託している場合に回収した家賃などを清算した明細 | |
| 売渡精算書 | 投資用物件を購入する時に発生した費用の明細 | |
| 経費関連の書類 | 税金の納付通知書 | 不動産取得税、固定資産税などの納付書 |
| 借入の返済表 | 前年1年間の不動産投資ローンの返済表(ただし、不動産所得が赤字の場合、土地取得分の金利は経費計上できない) | |
| 管理費、修繕積立金の証明書類 | 建物のメンテナンスや将来の修繕のために積み立てたりしたお金の領収書 | |
| 譲渡対価証明書 | 減価償却を算出するために必要な書類 | |
| 控除関連の書類 | 損害保険料の証券や領収書 | 一括で支払う火災保険や地震保険の保険料は、単年度で経費化 |
| 源泉徴収票 | 会社員の方が不動産投資をしている場合、以下の計算のため源泉徴収票が必要 ・所得税の還付を受けられる場合
・不動産投資の赤字を損益通算する場合
|
書類が不足している場合、申告が遅れてしまうおそれもあります。また、正確な申告をおこなうためにも、これらの書類は必要です。種類が多いため、余裕を持って準備しておきましょう。
STEP3.書類を作成する
必要書類が用意できたら、書類を作成しましょう。用意した書類をもとに、確定申告書や決算書(白色の場合は収支内訳書)に記入します。正確な所得を計算するためにも、間違いがないように記入しましょう。不明点がある場合は、税理士や税務署の職員などに質問しましょう。
STEP4.税務署に提出する
書類を税務署に提出しましょう。以下の3つの提出方法があります。
- 税務署に持参する
- 税務署に郵送する
- e-Taxを利用する
e-Taxは電子申告で、事前に利用者識別番号や電子証明書の取得が必要です。しかし、インターネット環境があれば自宅でも利用できるため、手軽に確定申告ができます。またe-Taxは、青色申告で65万円の青色申告特別控除を受けるための要件の一つにもなっています。不明点や疑問点がある場合には、税務署に持参して、相談しながら申告をしましょう。
不動産投資の還付金を受け取れる時期
確定申告をおこなう時期は、原則として2月16日〜3月15日までとなっています。還付金を受け取れる時期は、1カ月〜1カ月半程度。なお、e-Taxを利用した場合は、3週間程度で処理されるとのことです。しかし、申告した内容が誤っていたり、書類が不足していたりする場合には、受け取りが遅れる可能性があります。還付金を早く受け取りたい場合は、正確に申告をおこなうようにしましょう。
不動産投資の還付金を受け取る方法
確定申告による還付金の受け取り方法は、次の2つがあります。
- 金融機関口座への振り込み
- ゆうちょ銀行または郵便局に出向いて受け取る
振り込みで受け取る場合には、確定申告書に口座情報を記入する欄があるため、正確に記入しましょう。なお、一部のネット銀行については振り込みができないため、事前に利用可能かを確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、不動産投資で確定申告をすると還付金はいくらなのか、シミュレーションをおこないました。節税効果を高めるためには、経費をもれなく計上することが大切です。投資用物件の購入時に納めた、不動産取得税や登録免許税なども、経費として計上できます。何を経費にできるのかを把握し、適切に計上しましょう。不動産投資による所得が赤字でも、確定申告をすることで、還付金を受け取れる可能性があります。不明点や疑問点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士 大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ