不動産小口化商品は危険?メリット・デメリットや投資する際の注意点を解説

記事の目次
不動産小口化商品とは

不動産小口化商品とは何なのか、まずは基礎知識を身に付けましょう。本章では仕組みと種類を解説します。
不動産小口化商品の仕組み
不動産小口化商品とは、複数の投資家から集めた資金で、事業者が特定の不動産を購入し、その収益を投資家に分配するもの。収益には賃料収入や売却益があり、投資額に応じて分配されます。事業者は、原則として国土交通大臣や都道府県知事の許可を受ける必要があります。しかし、2017年に「小規模不動産特定共同事業」が創設され、事業者の参入要件が緩和。一定の要件を満たせば、事業ができるようになりました。
不動産小口化商品の種類
不動産小口化商品には、3種類あります。違いをまとめたものが次の表です。
| 不動産小口化商品の種類 | 賃貸型 | 任意組合型 | 匿名組合型 |
|---|---|---|---|
| 投資金額 | 100万円〜 | 100万円〜 | 1万円〜 |
| 運用期間 | 長期 | 長期 | 短期 |
| 所有権 | あり | あり | なし |
| 所得区分 | 不動産所得 | 不動産所得 | 雑所得 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
賃貸型
賃貸型とは、複数の投資家が1つの不動産を購入し、事業者に貸し出すというもの。投資家は、事業者に不動産の管理を任せられ、家賃収入を得られます。投資家が不動産を購入するため所有権があり、名義が登記されます。登記とは、不動産の権利関係を公的に証明するものです。事業者が倒産した場合、運営が難しくなることから、取り扱われる数は多くありません。
任意組合型
任意組合型は、投資家と事業者が「任意組合契約」を締結し、共同で不動産を所有・運用するもの。出資方法として、「現物出資」と「金銭出資」の2種類あります。現物出資とは、投資家が事業者から共同持分を購入し、その持分を任意組合に出資する方式。この場合、賃貸型と同様、投資家は所有者として登記されます。
一方、金銭出資とは、投資家が任意組合に出資をし、その資金で不動産を購入して、共有財産として運用をする方式です。この場合は、所有者として登記されません。なお、どちらの方式も相続税対策になります。なぜなら、税制上、投資家が不動産を直接保有している場合と同様に扱われるからです。不動産の相続税評価額は、現金よりも低く評価されるため、相続税対策となります。
匿名組合型
匿名組合型とは、投資家と事業者が「匿名組合契約」を締結し、収益が投資家に分配されます。これまで見てきた2つのタイプと違い、事業者が不動産の所有権を有しています。そのため、投資家が受け取った分配金は、雑所得となります。また、投資家と事業者は金銭のやりとりのみであることが一般的です。
不動産小口化商品と他の不動産投資との違い
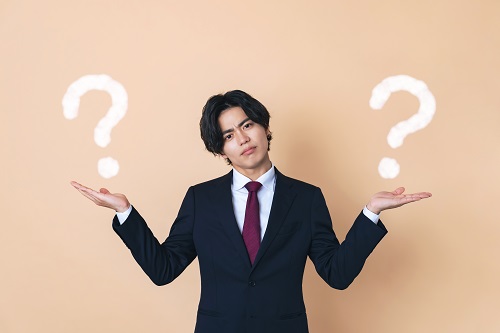
不動産投資にはさまざまな種類があります。不動産小口化商品と、他の種類との違いは何なのでしょうか。ここでは、REIT(リート)や現物不動産投資との違いを解説します。
REIT(リート)との違い
REIT(リート)とは、不動産投資信託と呼ばれる、投資信託の一種です。投資家から集めた資金で、不動産投資法人が不動産を購入し、投資家に家賃収入や売却益を分配します。下表は違いをまとめたものです。
| 比較項目 | 不動産小口化商品 | REIT(リート) |
|---|---|---|
| 投資対象 | 不動産 | 不動産投資法人 |
| 所得の区分 | 賃貸型・任意組合型 :不動産所得 匿名組合型 :雑所得 |
配当所得 |
| 流動性 | 低い | 高い |
| 節税効果 | 高い | 低い |
投資対象
不動産小口化商品では、不動産に対して投資をおこないます。一方、REIT(リート)の場合は、不動産投資法人が対象です。そのため、不動産小口化商品では投資したい物件を選べますが、REIT(リート)では選べません。
所得の区分
また、所得にも違いがあります。先述したように、不動産小口化商品の賃貸型と任意組合型は不動産所得、匿名組合型は雑所得となります。一方、REIT(リート)は配当所得。配当所得とは、株式投資や投資信託で得られる分配金による所得のことです。なお、通常、配当所得を総合課税の所得として確定申告する場合、配当控除が適用されますが、REIT(リート)は適用されない点に気を付けましょう。
流動性
不動産小口化商品とREIT(リート)は、流動性でも違いがあります。不動産小口化商品では、不動産を所有する権利を購入しています。また、運営をおこなっているのは事業者であるため、自分の持分のみを売買することはできません。そのため、不動産小口化商品の流動性は低いといえるでしょう。一方、REIT(リート)で購入しているものは、不動産投資信託の証券。株式と同様、証券取引所の営業時間内であれば、いつでも売買可能であることから、流動性は高くなります。
節税効果
不動産小口化商品の節税効果は高いですが、REIT(リート)は高くありません。なぜなら、不動産小口化商品の任意組合型では、不動産の所有権を有しています。そのため、相続税において、現金で保有するよりも、時価の2〜3割低い評価額で評価されます。一方、REIT(リート)は、不動産投資信託への投資であるため、上場株式と同じように評価。なお、上場株式は次の4つのうち、もっとも低い価格で評価されます。
-
・相続開始時の終値・相続開始時の月における毎日の平均終値・相続開始時の月の前月における毎日の平均終値・相続開始時の月の2カ月前における毎日の平均終値
不動産小口化商品の節税効果については、次章で詳しく解説します。
現物不動産投資との違い
次に、不動産小口化商品と現物不動産投資との違いを見ていきましょう。不動産小口化商品の場合、事業者が選定した物件のなかから、自分が投資する物件を決めます。物件の管理は専門会社がおこないますが、自分で管理会社を選べません。一方、現物不動産投資の場合は、一から自分で投資物件を決めることが可能。また、管理会社も選べるため、自由度は高いといえるでしょう。
しかし、相続時の遺産分割では、不動産小口化商品のほうが有利です。なぜなら、不動産小口化商品は、口数ごとに分割して相続できます。対して現物不動産投資の場合は、分割しにくいため、話し合いが進まずトラブルに発展するケースもあります。
不動産小口化商品のメリット

不動産小口化商品には3種類あり、所得の区分や所有権の有無などが異なります。それでは不動産小口化商品のメリットは何でしょうか。本章では5つのメリットを解説します。
少額から投資ができる
不動産小口化商品の魅力は、少額から投資できる点です。匿名組合型であれば、1万円から不動産投資が可能。まとまった資金がなくても、不動産投資を始められます。現物不動産投資であれば、金融機関から不動産投資ローンを借り入れることが一般的です。借り入れを完済するまで、責任を持たなければなりません。しかし、不動産小口化商品は少額からできるため、「不動産投資がどういったものか試してみたい」という方も、気軽に始められるでしょう。
プロが選んだ物件に投資ができる
プロが選んだ物件に投資できる点も、不動産小口化商品のメリットです。不動産投資で収益を上げるためには、物件の選定は重要です。プロが選んだ物件であれば、初めて不動産投資をおこなう方であっても安心して投資できるでしょう。また、個人だけでは投資できない、商業施設やオフィスビルなどの物件にも投資できる点も、不動産小口化商品の魅力です。
リスク分散ができる
不動産小口化商品は、複数の物件に分散投資することで、リスクを分散できます。例えば、複数のエリアに分ける、マンションやオフィスビルなど物件の種類に分けるなど。さまざまな物件に分けて投資すると、景気変動の影響を受けにくくなります。1つの物件で収益が思うように上がらなくても、他の物件でカバーすることが可能。個別の物件に投資する現物不動産投資と比較して、リスクを抑えながら不動産投資ができるでしょう。
管理の手間がかからない
不動産小口化商品は、物件の管理を事業者や専門の管理会社に任せることができるため、管理の手間がかからないというメリットがあります。もし自分で管理をするとなると、入居者対応や修繕工事など、幅広い業務をおこなわなければなりません。まったくの未経験では、それらを自分でおこなうことは難しいでしょう。経験豊富な事業者や管理会社であれば、管理も安心して任せられます。
相続税対策になる
REIT(リート)との違いでも解説したように、不動産小口化商品は相続税対策になります。現金を相続する時は、現金の金額がそのまま相続税の対象。例えば、3,000万円の現金を相続する時は、3,000万円が相続税の評価額となります。しかし、不動産小口化商品の場合、時価の2〜3割低く評価額が設定されます。
もし、3,000万円の不動産小口化商品を相続する場合、相続税の評価額は2,100万円〜2,400万円程度。現金で相続する場合より、相続税評価額を600万円〜900万円低く抑えられます。しかし、このメリットは不動産の所有権を持つ、賃貸型・任意組合型の時にのみ得られます。匿名組合型では不動産の所有権がないため、相続税対策にはならない点を理解しておきましょう。
不動産小口化商品のデメリット

不動産小口化商品は、少額からできる、プロが選んだ物件に投資できるなどのメリットがあることをお伝えしてきました。しかし、もちろんメリットだけではありません。本章では5つのデメリットを解説します。
元本割れのリスクがある
不動産小口化商品に限らず、投資は元本割れの可能性があります。元本割れとは、投資した金額より少ない金額しか戻らないことです。つまり、損をしているということです。不動産小口化商品でも、現物不動産投資と同様、空室リスクや資産価値減少のリスクなどがあります。
例えば、入居者が決まらず、空室が続けば家賃収入は減り、不動産の資産価値は築年数が経つにつれ下がっていきます。資産価値が下がれば、売却した際に元本割れをする可能性もあるでしょう。そのため、不動産小口化商品に投資する際は、物件の収益性や将来性を考慮しなければなりません。「プロが選んだ物件だから」と任せきりにするのではなく、自分でもよく調べるようにしましょう。
利回りが低い
不動産小口化商品は、現物不動産投資と比較すると、利回りが低い傾向にあります。その理由は、手数料がかかるためです。管理の手間がかからないというメリットは、その分手数料を負担しなければならないというデメリットに。現物不動産投資の場合、利回りは6〜10%程度です。しかし、不動産小口化商品は2〜7%程度とされています。ただし、商品によって利回りの定義が違うため、事前によく確認しましょう。
申し込み倍率が高い
不動産小口化商品は、申し込み倍率が高く、希望どおりに購入できない可能性があります。匿名組合型の不動産小口化商品は手軽に取り組めることから、特に人気を集めています。先着順の場合、募集が開始されてすぐに申し込みが殺到することも。なかなか応募ができない場合は、信頼できる複数の事業者に登録し、こまめに情報をチェックするようにしましょう。
融資を利用できない
不動産小口化商品のデメリットとして、融資を利用できない点が挙げられます。現物不動産投資の場合、購入する不動産を担保として不動産投資ローンを借り入れることが一般的です。高額な融資を受けることで、少ない自己資金でも大きな収益を得られるレバレッジ効果が期待できます。しかし、不動産小口化商品を対象にしたローンはありません。そのため、投資する場合は全額自己負担となります。もし元本割れした場合には、損益を被ることに。不動産小口化商品に投資する場合は、余裕資金でおこなうようにしましょう。
中途解約できないことが多い
不動産小口化商品は、中途解約できないことが多い点もデメリットです。不動産小口化商品は、運用期間が決まっていることが一般的。そのため、やむを得ない事情がない限り、中途解約できないことがほとんどです。例えば、不動産クラウドファンディングサービスの一つである「CREAL」では次のようになっています。
中途解約について
クーリング・オフ期間終了後の中途解約は、契約者の死亡による相続の発生、契約者の破産手続きの開始決定等の法定終了事由を除いて、原則不可となっております。
また、中途解約できる場合でも、持分を第三者へ売却することで可能としている事業者もあります。例えば、株式会社ACNの「Aシェア」では、事業者より参考売却価格を提示して、購入者を募集。共有持分譲渡契約を締結することで可能としています。また、自ら売却先を見つけ、理事長の承認を得れば、売却して解約できます。ただし、中途脱退となるため脱退事務手数料、理事長が売却先を紹介した場合は手数料が必要です。
不動産小口化商品に投資する際の注意点

不動産小口化商品にはメリットもありますが、デメリットもあります。投資を成功させるためにも、気を付けなければならない点を押さえておきましょう。
投資の目的を確認する
なぜ不動産小口化商品に投資するのか、目的を考えましょう。目的によって、投資すべき商品は異なります。例えば、短期的に収益を得たい場合は、運用期間の短い匿名組合型が向いているでしょう。もし相続税対策として投資をしたい場合は、不動産の所有権がある賃貸型や任意組合型が適しています。自分に合った商品に投資できるよう、今一度投資する目的を考えてみましょう。
運用期間を確認する
不動産小口化商品に投資する際は、運用期間をよく確認しましょう。商品によって、運用期間は異なります。また、デメリットでも取り上げたように、やむを得ない事情がない限り、中途解約できないことが一般的です。運用期間が長期の場合、金融危機などで不動産の資産価値が急激に下がることも考えられます。自身のリスク許容度に合わせて商品が選択できるよう、事前に運用期間を確認しましょう。
長期的な視点で投資する
不動産小口化商品に投資する際は、長期的な視点を持ちましょう。匿名組合型は運用期間が短いものもありますが、3カ月など最低でも数カ月かかります。繰り返しになりますが、投資は元本割れするリスクがあるため、余裕資金でおこなうことが大切です。運用期間の間、手元になくても問題ない金額の範囲内でおこなうようにしましょう。例えば、子どもの大学進学と、不動産小口化商品の運用期間が重なる場合は、あらかじめ出資額を少なくするなどの対策が必要です。資金計画が不安な場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するといいでしょう。
信頼できる事業者のサービスを利用する
2017年に法律が改正され、新規参入しやすくなったことから、不動産小口化商品を取り扱う事業者が増えています。残念ながら、すべてが信頼できる事業者ではありません。なかには無登録・架空業者による勧誘がおこなわれており、実際に被害に遭われた方もいらっしゃいます。不動産小口化商品に投資する際は、事業者の許可・登録状況を必ず確認するようにしましょう。国土交通省の「不動産特定共同事業法に基づく事業者及び適格特例投資家一覧」で許可や登録状況を確認できます。特に、インターネット上ですべてが完結する匿名組合型は注意が必要です。不明点があれば、不動産会社やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。
まとめ
本記事では不動産小口化商品の基礎知識からメリット・デメリット、注意点を解説しました。不動産小口化商品には3種類あり、所有権の有無や運用期間などが異なります。自分自身に合った商品を選ぶためにも、投資する目的をよく確認しましょう。また、中途解約が難しいため、投資する際は長期的な視点を持つことが大切です。さらに、架空業者が勧誘をおこなっている場合もあるため、信頼できる事業者なのか、許可や登録状況を必ず確認するようにしましょう。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ








