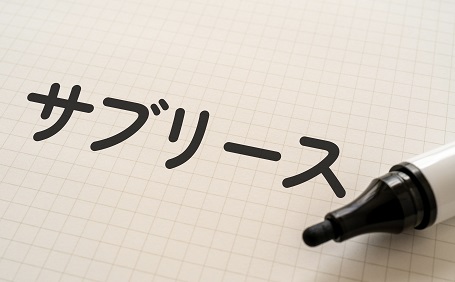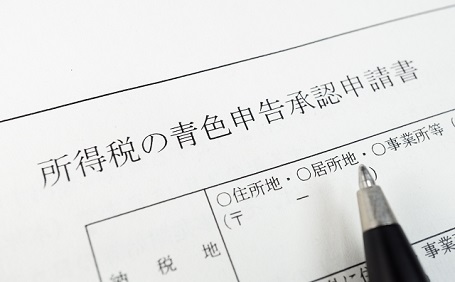マンション経営が「儲からない」と言われる理由は?失敗例や失敗しないためのポイントを解説!

そこで本記事では、マンション経営が「儲からない」と言われる理由や失敗例、失敗しないためのポイントを解説します。マンション経営で収益を上げられるよう、ポイントを押さえておきましょう。
記事の目次
マンション経営が「儲からない」と言われる理由

マンション経営が「儲からない」と言われる理由は、さまざまあります。しかし、事前にポイントを押さえておけば、防げるものもあります。本章では、どのような理由から収益が上がらないのか、詳しくみていきましょう。
需要がない物件を選んでいるから
マンション経営が「儲からない」と言われる理由の一つに、需要がないマンションを選んでいることが挙げられます。マンションに限った話ではありませんが、賃貸経営では物件選びが重要です。例えば、駅からの距離や生活利便施設の充実度などは、入居率に大きな影響を与えます。利便性が高い場所にあるマンションであれば、高い入居率を維持できるうえ、家賃相場も高くなることから、安定した家賃収入を見込めるでしょう。一方で需要のないマンションを選んでしまうと、入居者が集まらず空室となり、家賃収入が減少してしまうおそれがあります。
高額な投資用ローンを組んでいるから
高額な投資用ローンを組んでいることも、マンション経営が「儲からない」と言われる理由の一つです。マンションを購入する際には多額の資金が必要となるため、投資用ローンを組むことが一般的。投資用ローンは、マンション経営で得た家賃収入から返済します。しかし、空室が出たり、家賃滞納があったりするとキャッシュフローが悪化し、投資用ローンの返済が厳しくなることも。また金利が上昇し、投資用ローンの返済額が増えることも考えられます。これらを見込んでいなかった場合、経営が苦しくなることから、「儲からない」と感じる原因となります。
適切な物件管理ができていないから
適切な管理ができていないことも、マンション経営が「儲からない」と言われる理由です。マンションの購入はあくまでスタートであり、購入後は入居者の満足度を高められるよう適切な管理をおこなわなければなりません。例えば、入居者からのクレームやトラブルが発生した場合、迅速に対応しなければ入居者の満足度が低下し、退去につながるでしょう。また、定期的なメンテナンスをおこなわなければ、建物や設備の老朽化が早まり、入居者からのクレームにつながることも。このように、適切な管理ができていない場合、入居者満足度の低下により退去が増え、結果的に収益が減少してしまう可能性があります。
短期的な視点で考えているから
マンション経営が「儲からない」と言われる理由として、短期的な視点で考えていることが挙げられます。マンション経営は短期的ではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。先述したように、マンションを購入する際には多額の費用がかかるもの。そのため、短期間で費用を回収することは難しくなります。特に、マンション経営を始めた年は、多額の初期費用がかかるため、赤字になることが一般的です。これらを踏まえず、家賃収入を得ればすぐに黒字化すると考えていると、「儲からない」と感じる要因となるでしょう。
売却が難しいから
マンションは売却が難しいため、「儲からない」と言われる要因となります。建物の資産価値は完成直後がもっとも高く、時間が経つにつれて低くなっていくのが一般的です。売却時に不動産市場が低調だったり、周辺に新しい物件が建ち競争力が低下すると、想定していた売却価格より下がることも。家賃収入を得られていても、売却益によってはマンション経営が赤字で終わることも考えられます。
また、マンションの売却には、物件の広告掲載や内見対応、契約交渉など、多くの手間と時間がかかります。買主に渡るまでに時間を要するため、売却のタイミングを見誤るとさらに売却価格が低くなるおそれもあります。このように、タイミングによって想定していた価格で売却できず、収益を得られないケースがあることも、マンション経営が「儲からない」と言われる理由の一つとなります。
知識が不足しているから
マンション経営に関する知識が不足していることも、「儲からない」と言われる理由の一つです。マンションを経営するにあたり、物件の購入や管理、入居者の募集や契約など、幅広い業務をおこなわなければなりません。また、税金や資金計画、法律に対する知識も必要です。
しかし、これらの業務や専門知識を、初心者の方が一人で担うには限度があるでしょう。管理業務を管理会社に委託したり、税金に関する知識を税理士に補ってもらうなど、専門家の力を借りる必要があります。もし、知識不足のまま一人でマンション経営をすると、自身でさまざまな業務をしなければならず、手間が増えることも。また、経費にできるものを計上せず、本来納めるべき税金より多く納めなければならないかもしれません。知識不足のままマンション経営をおこなうと、手間がかかるわりに収益が上がらないことから、「儲からない」と感じる原因となります。
マンション経営の失敗例

前章では、マンション経営が「儲からない」と言われる理由をみてきました。本章ではイメージしやすくするために、具体的な失敗例を解説します。どうすれば失敗を防げるのか、考えながら読んでみてください。
投資用ローンを返済できなくなった
マンション経営の失敗例として、投資用ローンを返済できなくなったケースもあります。投資用ローンを返済できなくなる理由として、次のようなことが考えられます。
- 空室が増加した
- 金利が上昇した
- 不動産市場が低迷した
空室が増加すると、その分家賃収入が減るため、投資用ローンの返済が困難になります。家賃収入が減っても、投資用ローンは返済しなければなりません。また、管理業務を委託している場合には、委託先へ支払う管理手数料も必要です。そのため、空室リスクを見越してマンション経営を始めましょう。
さらに先述したように、金利が上昇すると、投資用ローンの返済額が増え、返済が難しくなることも。他にも、不動産市場の低迷を受けて、家賃を下げた場合、家賃収入が減るために投資用ローンの返済負担が増えることもあるでしょう。投資用ローンの返済が滞ると、最悪の場合、マンションを手放さなければならなくなるかもしれません。
節税目的のはずなのに税金が増えた
節税目的でマンション経営を始める方もいますが、知識が不足していたり、計画を立てていなかったりすると、かえって税金が増えることがあります。賃貸経営が節税になる理由は、「損益通算」と「減価償却」の2つが関係しています。
損益通算とは、賃貸経営の赤字を給与所得などの他の所得と相殺するもの。課税所得が減れば、納めるべき税金の金額も減ります。例えば、マンション経営が200万円の赤字、給与所得が800万円だった場合。損益通算をすると課税所得が600万円となります。給与所得のみの時と比較して、課税所得が200万円減ったため、その分税金も抑えられます。
減価償却とは、高額な資産を購入した場合、資産の法定耐用年数に応じて購入費用を経費として計上すること。実際に支払いが発生していない年でも経費として計上できるため、所得が抑えられて節税につながります。法定耐用年数は建物の構造によって異なり、鉄筋コンクリートで建てられることが多いマンションの場合には、減価償却できる期間は長くなります。減価償却できる期間が長くなる分、経費として計上できる金額は少なくなるため、節税効果は弱まります。
つまり、マンション経営で大きな節税効果を得られるタイミングは、赤字となることが多い初年度であり、その後は限定的。また、マンションよりも法定耐用年数が短い木造アパートのほうが、節税効果は高まります。これらの基本を押さえていない場合、思ったような収益を得られず、マンション経営に失敗してしまうかもしれません。
理解不足のままサブリース契約を結んだ
契約内容を十分に理解せずにサブリース契約を結んでしまうと、思わぬ損失を被り、失敗する可能性があります。サブリース契約とは、オーナーが所有する物件をサブリース会社が一括で借り上げ、入居者に転貸借(又貸し)するもの。管理業務を委託でき、家賃収入が保証されることから注目を集めています。しかし、借地借家法によってサブリース会社が保護されており、家賃保証額の減額や中途解約が認められています。
一方、オーナー側からの中途解約は、正当事由が必要であったり、違約金を支払わなければならなかったりと、難しくなっています。サブリース契約は管理の手間がかからず、一定の家賃収入が得られるため、魅力的に感じるでしょう。しかし、理解が不足していると損失を被り、マンション経営が立ち行かなくなってしまうことも。サブリースを検討する際には、メリット・デメリットをよく考えましょう。
利回りが低すぎた
マンション経営の失敗例として、利回りが低すぎたケースもあります。想定していた利回りより低くなってしまうと、投資金額を回収するまでに時間がかかってしまいます。また、突発的な修繕費が発生した場合、キャッシュフローが悪化し、最悪の場合には破綻してしまうおそれも。そもそも、広告に掲載されている利回りは、満室であることを想定した想定利回りであることが一般的です。広告の利回りを鵜呑みにするのではなく、初期費用や維持費を考慮した実質利回りを計算するようにしましょう。
想定外の出費でキャッシュフローが悪化した
想定外の出費でキャッシュフローが悪化し、マンション経営の計画が想定から外れてしまうケースもあります。マンション経営では、建物の老朽化にともない、外壁の塗装や設備の交換などの大規模修繕工事が必要です。国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、12〜15年周期で大規模修繕工事を実施。また、工事金額は1回目で4,000〜6,000万円の割合がもっとも高くなっています。
例えば、築年数の古いマンションを購入した場合、すぐに大規模修繕が必要になり、多額の費用がかかってしまうことも。また、区分マンションを購入し、最初は少なかった修繕積立金が、築年数が経つにつれて値上げされ、キャッシュフローが悪化するケースもあります。マンション経営では想定外の出費に備え、十分な資金を用意しておきましょう。
売却価格が低かった
前章の「儲からない」と言われる理由でも挙げたように、マンションの売却価格が低く、失敗するケースもあります。先述したように、マンションの資産価値は完成時が一番高く、徐々に下がっていきます。売却価格が低ければ投資用ローンを完済できず、負債だけ残ってしまうことも。また、マンションは流動性が低いため、買い手が付きにくい傾向にあります。売却しやすいマンションの特徴は、次のとおりです。
- 賃貸需要が高い
- エリアの将来性がある
- 付加価値・希少性がある
- 管理が行き届いている
人気の立地や間取り、付加価値のある物件などで賃貸需要が高ければ、安定した家賃収入を見込めることから、売却しやすくなるでしょう。将来賃貸需要が見込めるエリアも買い手が付きやすくなります。また、定期的にメンテナンスをおこなったり、入居者からのクレームも迅速に対応したりと、管理が行き届いていれば、入居者の満足度も高く、買い手も安心して購入できるでしょう。売却時のことを考えてマンションを購入、経営をおこなうようにしましょう。
入居者トラブルがあった
入居者トラブルも、マンション経営が失敗する原因の一つです。例えば、家賃滞納はオーナーの家賃収入の減少に直結します。家賃滞納は経済的だけでなく、精神的にもダメージを受けるもの。最悪の場合には、訴訟を起こさなければならないかもしれません。
他にも、入居者による騒音問題も考えられます。入居者同士の関係が悪化するだけでなく、近隣住民からの苦情につながり、マンション自体のイメージが悪くなる可能性も。退去が増えたり、入居者を募集しても集まらなかったりするおそれもあります。入居者トラブルを防ぐためには、入居審査をおこなったり、定期巡回を増やしたりするといいでしょう。また、トラブルが発生した際には、迅速に対応することも大切です。
入居者が集まらない
入居者が集まらないことも、マンション経営で失敗するケースの一つです。入居者が集まらないのには、さまざまな原因が考えられます。具体的には次のとおりです。
- 立地の悪さ
- 競合物件の増加
- 物件の老朽化
- 管理会社の集客力の弱さ
マンションの設備が最新でも、立地が悪ければ需要は低くなり、入居者が集まりません。また、周辺に新築物件ができたり、物件が老朽化し、見た目や設備が古くなると、入居者を確保することが難しくなります。さらに、管理会社の集客力も、大きな要因となります。
もし空室が出ても、管理会社の集客力が高ければ、空室期間を短くできるでしょう。しかし、管理会社の集客力が弱く、なかなか次の入居者が決まらない状態が続くと、その分家賃収入が減少してしまいます。特に区分マンションで一部屋しか所有していない場合、空室期間が長期化すると、経営が失敗する可能性は高まります。空室になった時の対策をどのようにしているのか、管理会社に確認しておくとよいでしょう。

- 区分マンション投資は儲からないって本当?知っておきたいデメリットと対処法を解説
- 「区分マンション投資を始めたいけど、儲からないって本当?」と悩んでいる方もいるでしょう。区分マンションは投資
続きを読む

マンション経営で失敗しないためのポイント

マンション経営は、多額の投資用ローンを組まなければならず、さまざまなリスクをともないます。経営に失敗する方がいる一方、成功している方がいることも事実です。それではマンション経営で失敗しないためには、どうすればよいのでしょうか。本章では、失敗しないためのポイントを8つ解説します。
需要のある立地を選ぶ
需要のある立地を選ぶことが、マンション経営で失敗しないためのポイントの一つです。立地のよし悪しが、マンション経営の成否に大きく影響します。需要のある立地であれば、入居者も集まりやすく、安定した家賃収入が見込めるでしょう。
例えば、駅やコンビニエンスストアなどが近い場所は、生活を送るうえで利便性が高いため、どのターゲット層からも選ばれやすくなります。ファミリー層をターゲットにするのであれば、公園や学校などが近い場所が人気を集めやすいでしょう。また、需要のある立地は、経営している時だけでなく、売却時にも高く売却できる要因になります。
自己資金を多めに用意する
自己資金を多めに用意すると、マンションの経営が安定します。先述したように、マンションを購入する際には多額の資金が必要となり、投資用ローンを借り入れることが一般的。自己資金を多めに用意すると、投資用ローンの借入金額を減らせるため、毎月の返済負担も軽くなります。返済額が減ると、キャッシュフローが安定し、想定外の支出にも対応しやすくなるでしょう。
また、自己資金が多いほど、金融機関から「返済能力がある」とみなされるため、より有利な条件で融資を受けられる可能性があります。さらに、返済額を抑えられれば、金利が上昇して返済額が増えても、キャッシュフローの悪化を防ぎやすくなります。このように、自己資金を多めに用意すると、キャッシュフローが安定するでしょう。
実質利回りを把握する
マンションを購入する際は、表面利回りではなく、実質利回りを把握することが大切です。表面利回りとは、物件価格に対する年間家賃収入の割合を計算したもの。一方、実質利回りとは、物件価格や諸費用などを含めて計算するもので、収益性をより把握しやすくなります。例えば、築年数の古い物件は物件価格が低いため、表面利回りが高くなります。しかし、修繕費がかかったり、空室リスクが高くなるため、実質利回りが低くなることもあるでしょう。
なお、理想的な実質利回りは、新築物件の場合が5%、中古物件の場合が6%前後とされています。安定したマンションの経営をするために、何を経費として計上できるのかを把握し、実質利回りを計算するようにしましょう。
長期的な視点で考える
マンション経営に取り組む際は、長期的な視点で考えましょう。特に、マンション経営で土地を購入する場合、初期費用は高額になり、費用を回収するまでに時間がかかります。経営を始めた年から数年は、赤字であることが一般的です。また、空室が出たり、修繕費がかかったりすると、確実に収益を積み上げられるとは限りません。家賃収入ばかりに目を向けるのではなく、初期費用や維持費なども踏まえて、長期的な視点で計画を立てましょう。
適切な管理方式を選ぶ
マンションを経営するにあたって、入居者の募集や契約、清掃、修繕対応など、さまざまな業務が必要です。一人でおこなうことは難しく、委託することが一般的でしょう。管理方式には、大きく次の4つあります。
- 全部委託管理
- 一部委託管理
- サブリース契約
- 自主管理
全部委託管理とはその名のとおり、マンションの管理業務すべてを管理会社に委託するものです。国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、72.9%のマンションで、全部委託管理が採用されています。一部委託管理とは、管理業務の一部を委託するもの。どちらも管理を委託する手数料として、家賃収入から管理委託料を支払います。相場は家賃収入の5%程度です。
サブリース契約も、契約時に定められた家賃から手数料分が差し引かれます。また、定期的に家賃の保証額が見直され、減額されることもあります。自主管理は自分でおこなうため、手数料はかかりませんが知識や経験がない状態では難しいでしょう。それぞれメリット・デメリットがあるため、理解したうえで、適切な管理方式を選ぶことが大切です。
1階の空室対策を工夫する
マンションの1階は、空室が発生しやすい傾向にあります。それは、通行人の目が気になるプライバシーの面や、空き巣に入られやすいといった防犯面に不安要素があるからです。そこで1階の空室対策を工夫することで、空室率を下げられます。具体的な空室対策は次のとおりです。
- ホームセキュリティシステムを導入する
- 防犯カメラを設置する
- 植栽を活用する
- 専用の庭を設置する
ホームセキュリティシステムを導入すると、入居者に安心感を与えられます。また、エントランスや廊下などの共有部分に防犯カメラを設置すると、不審者の侵入を抑止できるでしょう。さらに、道路側に緑化帯を設けると、通行人からの視線を自然に遮ることが可能。他にも、専用の庭を設置することで、付加価値を高められます。このように、1階の空室対策をおこなうと、空室率を下げられ、安定したマンション経営が可能になるでしょう。
戸数を10戸以上にする
マンション経営で失敗しないためには、戸数を10戸以上にすることをおすすめします。なぜなら、10戸以上にすると事業的規模とみなされ、青色申告の特別控除が受けられるためです。青色申告では、一定の要件を満たすと、最大で65万円の控除が受けられます。
また、青色申告では、家族や親族を従業員として雇った場合に支払った給与を、「青色事業専従者給与」として経費の計上が可能。戸数が少ないほうが管理の手間がかからないと思われる方が多いでしょう。しかし、10戸以上にすると節税効果が高まり、収益も増える可能性があります。ただし、青色申告をする際には、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出を忘れないようにしましょう。
付加価値を付ける
安定した経営をおこなうために、マンションに付加価値を付けましょう。付加価値を付けると、入居者から選ばれやすくなり、入居者の満足度を高め、長期的な入居につながります。また、付加価値を付けると、周辺の物件よりも高い家賃設定が可能になります。付加価値の付け方の例は、次のとおりです。
- 無料のインターネット環境を整備する
- 収納スペースを多くする
- ペットの飼育を可能にする
- 宅配ボックスを設置する
不動産情報サイト アットホームでは「不動産のプロに聞いた!「2024年上半期 問合せが増えた条件・設備~賃貸編~」ランキング」を公表しています。問い合わせで一番多かった設備が、「インターネット接続料無料」でした。リモートワークの普及にともない、インターネット環境の有無を気にされる入居者が多いことがわかります。また、2番目に問い合わせが多かった設備は「宅配ボックス」でした。入居者の不在時でも荷物を受け取れ、盗まれる心配もないことから、宅配ボックスの設置を希望する方が増えているようです。入居者のターゲット層に合わせて、適切な設備を導入すると付加価値が付き、入居率を維持しやすくなるでしょう。
信頼できる不動産会社の選び方

マンション経営で成功するためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。信頼できる不動産会社であれば、需要のある立地や物件の情報を提供してくれるでしょう。また、経営が始まったあとも、適切な管理をおこない、入居者の満足度向上につなげてくれるでしょう。そこで本章では、信頼できる不動産会社の選び方を解説します。
実績が豊富な不動産会社を選ぶ
実績が豊富な不動産会社を選びましょう。実績がある会社であれば、これまでに多くの物件を取り扱ってきた経験や、不動産市場の動向から、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。また、多くのオーナーと取引をした経験から、顧客のニーズを的確に把握し、自分に合った提案をしてくれる可能性も高くなります。さらに、金融機関やハウスメーカー、工務店など、幅広いネットワークを持っているため、さまざまな選択肢から自分に合ったプランを選択できます。
管理をするにあたっても、実績が豊富であれば、迅速に対応してくれるでしょう。また、クレームや家賃滞納などに対するノウハウも蓄積されており、適切な対応が期待できます。
評判のいい不動産会社を選ぶ
実績だけでなく、実際に取引をした経験のある方の口コミも調べておきましょう。インターネット検索をして、悪い口コミが多いようであれば避けておくと無難です。また、知り合いのオーナーに聞くのも一つの手です。不動産会社が主催するセミナーや相談会に参加すると、専門性や対応を直接確認できるでしょう。また、気になる不動産会社に問い合わせ、対応の丁寧さや専門知識の深さを確認することも有効な方法です。
複数社を比較検討する
不動産会社を選ぶ際は、複数社から比較検討するようにしましょう。複数の不動産会社から情報収集をすることで、それぞれの会社の強みや特徴を把握できます。一社に絞ってしまうと、視野が狭くなり、一社の情報だけを鵜呑みにしてしまうかもしれません。複数の不動産会社から情報を得ることで、家賃の相場感やその地域ならではの特徴なども把握できるでしょう。また、自分のニーズや予算に合った最適なプランを選ぶことが可能です。さらに、自分に合った担当者に出会える可能性も高くなります。信頼できる不動産会社を選ぶために、複数社を比較検討しましょう。
まとめ
本記事では、マンション経営が「儲からない」と言われる理由や具体的な失敗例を解説しました。マンション経営は多額の資金が必要になることから、投資費用を回収するまでに時間がかかります。また、購入する物件を誤ると、思うような収益を得られない可能性もあります。マンション経営で安定した収益を得るためには、賃貸需要の高い物件を選ぶことが欠かせません。そのような物件を購入するためには、信頼できるパートナーを見つけ、適切なアドバイスを受けることが重要です。複数から比較検討し、信頼できる不動産会社を探しましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ