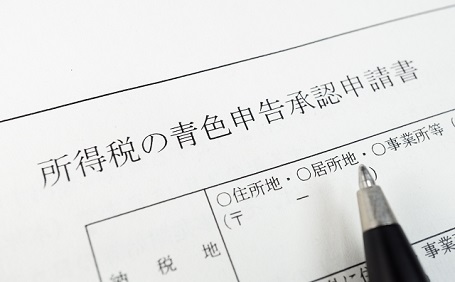マンション経営に潜むリスクとは?回避するための方法を解説

本記事では、マンション経営のリスクを詳しく解説します。対策方法や注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
マンション経営のリスク

まずは、マンション経営でどのようなリスクがあるのか見ていきましょう。
空室リスク
マンション経営では、入居者を募集してもすぐに入居者が集まるとは限らず、空室が発生するリスクがあります。空室が続けば家賃収入が減少し、場合によってはまったく得られなくなってしまうかもしれません。家賃収入が減少しても管理コストは発生し続けるため、赤字となる可能性があります。
また、入居者がいる場合でも、いつ退去されるかわかりません。そのため、空室が出てもすぐに入居者が見つかるように、対策を常に検討しておきましょう。
家賃滞納リスク
入居者を確保できても、必ずしも安定した家賃収入が得られるとは限りません。入居者から家賃の滞納があれば、想定した家賃収入を得られなくなります。そのため、入居審査は大変重要で、滞納に備えて資金の余裕を持つことも大切です。
最悪の場合、滞納したまま入居者と連絡が取れなくなるリスクもあり、滞納分の請求先がない事態に陥ることも考えられるでしょう。家賃滞納リスクを考慮し、余裕を持った収支計画を立てることが大切です。
金利上昇のリスク
マンションを購入するために変動金利の不動産投資ローンを利用した場合、金利上昇のリスクがあります。経済情勢の変動にともない、金利が上がれば、返済額が増大します。そのため、金利上昇のリスクを考慮したうえで、返済計画を立てることが大切。
実際に金利上昇にともない、不動産投資ローンの返済額が増えてしまい、投資物件の運営資金が不足して管理できなくなったケースもあります。金利上昇のリスクに備えるためには、融資条件を見直し、不動産投資ローンの負担を軽減できる方法はないか検討する必要があります。
入居者トラブルリスク
反社会的な入居者が購入したり、ルールを守らない入居者がいたりすると、入居者トラブルが起きるリスクが高まります。入居者トラブルが発生すると、「もうこのマンションに住みたくない」となり、退去を招いてしまうかもしれません。
悪いうわさが立てば、新規入居者の確保も難しくなり、空室リスクも高まるでしょう。
入居者同士の騒音や生活ルール違反などでもトラブルになり、貸主が対応を強いられることもあります。入居者トラブルを防ぐためにも、入居希望者の徹底した審査と、管理会社の適切な対応が重要です。
自然災害リスク
自然災害が起きると、マンションに損傷や倒壊などの被害を与えます。資産の価値が減少したり、消失したりするだけではなく、入居者への補償義務が発生する場合もあるでしょう。災害による損失はある程度は予防できても、完全に防ぐことは難しいです。
実際に、2011年3月に発生した東日本大震災時には一部のマンションで入居者の一斉退去が起こり、経営に深刻な打撃を与えた例もあります。災害発生時に業務を継続できるような事前の備えと計画が欠かせません。
売却できないリスク
経営しているマンションを売却したい場合でも、状況次第では簡単に売却できないリスクがあります。収益状況が悪ければ買手がつきにくく、思うような売却価格が望めないことも多々あります。
また、入居者がいる間は一戸ごとの売却はできません。周辺環境や立地の将来性など、事前に綿密な市場調査をしておくことで、売却できないリスクの軽減につながるでしょう。
管理会社の倒産リスク
マンションの管理を管理会社に委託している場合、管理会社の倒産リスクも考慮しておかなければなりません。
管理会社が倒産した場合は、自ら管理をおこなうか、新たな管理会社を探さねばならず、手間とコストがかかります。
管理会社の倒産リスクに備えるためにも、管理会社の経営状況をこまめにチェックしておきましょう。また、管理会社に委託する際は、複数社から信頼できる会社を選定することが重要です。安定した実績があり、長年の歴史がある管理会社であれば、安心して業務を委託できるでしょう。
増税リスク
マンションにかかる固定資産税や都市計画税などが引き上げられれば、経費が増大します。また、消費税が上がれば建築や修繕費用の負担も増えていくでしょう。
さらに、経営がうまくいっても、増えた所得の分に税金が課されます。増税するパーセンテージや経営の状態によっては、大きな負担となってしまうかもしれません。
マンション経営のリスクを回避するポイント

上記ではマンション経営のリスクを解説しましたが、対策する方法はあります。ここからは、マンション経営のリスクを回避するポイントを詳しく解説します。
需要と供給に合わせた立地を選ぶ
マンション経営で重要なのが立地選びです。需要と供給のバランスが取れた場所を選ばなければ、空室リスクが高まってしまいます。
例えば、オフィス街やキャンパス周辺なら、単身者向けのワンルームマンションに需要があると考えられるでしょう。一方、住宅地の場合はファミリー層向けの広めのLDKが望ましいです。
理想的な立地条件としては、以下のポイントが挙げられます。
- 最寄り駅から徒歩10分圏内
- 競合する物件数が少ない
- 生活利便施設が周辺に揃っている
- 学校があり、教育環境に恵まれている
- 治安が良好
上記の条件が整えば、安定した入居者の需要と収益性の高いマンション経営が可能になるでしょう。
周辺環境に過度に依存しない
特定の大企業やキャンパスの近くならば、そこに勤める従業員や通う学生を主な需要層と想定できます。しかし、企業が移転したり、大学が統廃合されたりすれば、突如需要が失われてしまうリスクがあります。
マンション経営では複数の需要層を見据えたうえで、ある程度需要の分散化を図ることがポイントです。周辺環境に過度に依存せず、幅広い層からの需要が期待できる立地を選びましょう。
余裕を持った資金計画を立てる
マンションの取得には多額の初期投資が必要です。それだけではなく、経営にともなう修繕費用など、さまざまなランニングコストも発生します。
不動産投資ローンを活用する場合でも、限度額いっぱいまで組むと、返済の負担が重くなりすぎ、経営や生活に余裕がなくなってしまうかもしれません。
将来の金利上昇リスクに備えるため、返済負担を無理なく抑え、自己資金の確保もできるように慎重に資金計画を立てる必要があります。一定の自己資金を確保できれば、不動産投資ローンへの依存度が下がり、金利変動の影響を受けにくくなるでしょう。
事業の安定性を高めるためにも、無理のない適切な資金計画を立てることが重要です。
損害保険に加入する
災害はいつ起きるかわかりません。地震や風水害、火災などでマンションが損傷・倒壊した場合、莫大な損失が発生します。災害リスクに備えるためにも、損害保険に加入しておきましょう。
基本的な火災保険に加え、地震保険への特約付加や補償範囲の拡大など、できる限り万全の備えをしておくことをおすすめします。
保険に入っていれば災害による莫大な修繕・再建費用の負担を大幅に軽減でき、事業の継続を図れます。災害リスク対策としての損害保険への加入は、マンションを経営する際の必須のステップといえるでしょう。
内覧を丁寧におこなう
インターネット上の情報や仲介会社の説明では、物件の実態が正確に把握できないことがあります。データ上は優良に見えても、実際は古びた内装や日当たりの悪さ、近隣トラブルの起きやすさ、入居者のモラルの低さなど、さまざまな問題が潜んでいる可能性があるのです。
そのためマンションの選定では、建物の実態を自らの目で確かめることが重要です。専有部分の状況はもちろん、共用部分の管理状態や騒音対策、防犯・防災対策の実情、周辺環境、入居者の雰囲気など、できる限り多角的な調査をおこないましょう。
内覧を怠れば、のちに大きな損失を被るリスクがあります。少しでもリスクを軽減するためにも、細かなところまでしっかり調べましょう。
利回りだけに囚われすぎない
マンションの投資価値を判断するうえで、期待利回りは一つの重要な指標となります。しかし、利回りだけに焦点を当てすぎると、見落としが生じ、失敗するリスクが高まります。
期待利回りはあくまでも将来の予測にすぎず、実際にはマンションの状態や立地環境の変化、市場ニーズの変動などによって、大きくその水準を割り込む可能性があるのです。投資物件を選ぶ際は、利回りも参考にしつつ、投資物件の価値や立地の将来性、需要動向など、さまざまな観点から総合的に判断することが大切です。
利回りだけに惑わされず、冷静かつ多角的な視点で検討を重ねましょう。
こまめに修繕をする
マンションは築年数を重ねるごとに、さまざまな部位で劣化や破損が生じてきます。大規模な損傷に至る前に、計画的なメンテナンスと、こまめな修繕をおこなうことが大切です。
放置しておけば劣化が進行し、やがて大がかりな補修やリフォームが必要となり、高額な費用がかかってしまうでしょう。マンション経営で適切なタイミング・適切な修繕をおこなうことは、中長期的なコストを軽減するうえでとても重要です。
また、入居者の快適性や安全性の確保にもつながります。収支を圧迫することなく、資産価値の維持・向上を図るためにも、適切なメンテナンスをおこないましょう。
マンション経営のメリット

ここまでマンション経営のリスクに焦点を当ててきましたが、もちろんメリットもあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
安定した収入が期待できる
マンション経営では、家賃収入が基本的な収益源です。家賃収入は比較的安定しており、災害などで建物が大きな損傷を受けたり、周辺環境が一変したりしない限り、短期間で家賃が大幅に下落するリスクは低いです。
また、入居や退去のタイミングが年度単位となることが多いため、年間を通して安定した収入が期待できるでしょう。
さらに、マンション経営では競合物件の状況を調査することで、適正な家賃水準を設定できます。競合物件の家賃相場を参考にすれば、需給バランスに見合った適正水準を割り出せるでしょう。
空室リスクを分散できる
マンションは、複数の住戸で構成されています。そのため、仮に一部の住戸が空室になっても、その影響は分散されます。
例えば15戸のマンションで家賃設定が同一の場合、3戸が1カ月空室になっても、マンション全体の年間収入への影響はそこまで大きくありません。
一方、一戸建ての賃貸経営では、その一戸建てが空室になれば家賃収入はなくなってしまいます。上記のように、マンション経営なら空室リスクを分散できるため、収支の変動が抑えられる点が大きな強みです。
管理の手間を減らせる
マンション経営には、入居者募集や契約手続き、家賃徴収、滞納・クレーム対応、共用部分の清掃・修繕など、さまざまな業務がともないます。自分でこれらの業務をおこなうのは大変な手間がかかります。
しかし、マンション経営の場合、基本的に家賃収入の数%程度の手数料を支払えば、専門の管理会社に業務を委託できます。
管理会社に業務委託できれば、平日の日中が忙しく、時間的に余裕のない会社員でも、ストレスなくマンション経営を続けられるでしょう。もちろん管理会社選びは重要ですが、連絡・報告・相談をきちんとしてくれる会社であれば、安心して任せられる可能性が高いです。
大きな資産になる
マンション経営をする際、建物だけでなく土地も所有物となります。仮にマンションが老朽化し価値が下がっても、土地自体の価値は残り続けます。将来的にマンションの価値がほとんどなくなった時点で、土地を売却したり、別の用途に転用したりすることも可能です。
さらに、立地条件によっては、建築時よりも需要が高まり、結果として高値で売却できるケースもあり得ます。このようにキャピタルゲインを上げられる機会があるのも大きなメリットです。
節税効果が期待できる
マンション経営には、相続税や固定資産税、所得税を抑えるさまざまな仕組みがあるため、節税効果が期待できます。
相続税では、土地にマンションを建築して相続したほうが、現金資産をそのまま相続するよりも税負担が軽くなります。貸家建付地評価減や借家権割合による評価減が適用されるため、相続税の課税価格が下がるからです。
さらに借入残高も負債にカウントされるため、実質的な資産価値が下がり節税につながるでしょう。
さらに、不動産を所有している場合は、毎年固定資産税がかかります。しかし、放置せず建物を建築すれば、固定資産税は軽減されます。
マンション経営ならさらに固定資産税が下がるため、節税効果が大きく期待できるでしょう。
土地に貸家が建築されている際の土地の評価額の計算方法は、下記のとおりです。
更地の評価額 ×(1- 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )= 評価額
所得税に関しては、建物の取得費用の一部を減価償却費として経費計上が可能です。マンションの場合、法定の耐用年数が長いため、減価償却費の計上期間が長くなり、長期にわたって所得税の負担を抑えられるのがメリットです。
まとめ
本記事では、マンション経営のリスクを詳しく解説しました。マンション経営には多くのリスクがあるため、事前に把握しておかなければ、大きな損失を招いてしまうでしょう。マンション経営はしっかりとリスクを把握して、対策を練りながらおこなうことが大切です。
本記事は、マンション経営のリスクに対する対策も解説したので、ぜひ参考にしてください。リスクに備えた万全の対策で、安定経営を実現させましょう。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ