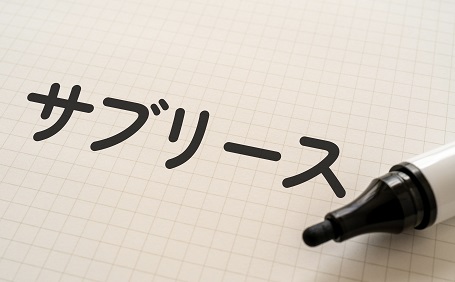不動産投資で騙される人の特徴は?失敗を防ぐ対処法と相談先や重要な心構えを徹底解説

実際、不動産投資は成功すれば安定した収益を得られる可能性があります。一方で、知識がないまま契約を結ぶと、高額なローンを組まされたり、利回りの低い物件を購入させられたりするリスクもあります。
そこで本記事では、不動産投資で騙される人の特徴や、よくある失敗事例から騙されない方法を解説します。また、悪質な不動産投資会社を見分ける方法や、投資を成功させるためのポイントも紹介。事前に正しい知識を身につけてリスクを回避し、安心して不動産投資を進めましょう。
記事の目次
不動産投資で騙される人の特徴

不動産投資で成功する人がいる一方で、騙されて失敗してしまう人がいることも事実です。では、どのような人が不動産投資で騙され、失敗するのでしょうか。本章では、不動産投資で騙されてしまう人の特徴を紹介します。不動産投資で騙されないために、以下の特徴を把握しておきましょう。
知識が足りない
不動産投資で騙される人に多い特徴が、知識が足りないことです。ここでいう「知識が足りない」とは、不動産投資の基本的な仕組み、物件の適正価格、利回りの計算方法、税金や契約内容などを十分に理解していない状態を指します。知識が不足していると、不動産会社が言う内容をそのまま信じてしまい、リスクを見抜けないまま契約してしまいかねません。
「必ず儲かる」「ローンを組めば実質無料で物件が手に入る」と甘い言葉に惑わされ、実際には割高な物件を購入してしまう場合もあります。また、修繕費用や管理費などのコストを考慮せずに投資を進めると、想定外の出費で赤字になりやすくなります。
知識不足のまま騙されてしまうと、借金を抱えたり、資産価値の低い物件を長期間持ち続け、投資どころか生活自体が苦しくなるかもしれません。こうした失敗を避けるためには、不動産投資の基礎知識を身につけた状態で投資をはじめ、専門家の意見を冷静に判断できる力を養っておきましょう。
都合のよい結果を想像しリスクに備えていない
不動産投資で騙される人は、都合のよい結果ばかりを想像し、リスクに備えていない点が顕著です。これは、投資すれば必ず利益が出る、空室が発生しない、想定外の費用がかからないと楽観的に考えている状態を指します。こうした人は、営業担当者の「手間をかけずに家賃収入を得られます」「ローンを組んでも家賃収入で返済できるため安心です」という甘い言葉を鵜呑みにし、現実的なリスクを見落とすでしょう。
詐欺会社はこうした心理を利用し、過大な利益シミュレーションを提示したり、不利な条件を隠した契約を結ばせるかもしれません。
リスクを考慮しないまま投資を始めると、想定外の空室や修繕費用、金利上昇によるローン返済額の増加などに直面した際に対応できず、大きな損失を出す可能性があります。
最悪の場合、赤字経営でローンの返済ができなくなり、投資用不動産を手放さざるをえなくなったり、多額の借金を抱える可能性があります。不動産投資はリスクを理解し、冷静な判断ができるようにしておかなければなりません。
他人任せで自分で情報を精査しない
不動産投資で騙される人は、「他人任せで自分で情報を精査しない」特徴もみられます。不動産会社や営業担当者の言うとおりにして、物件の詳細や契約内容を自分で確認せずに決める傾向があります。
特に初心者は、「プロが勧めるのだから安心」「みんなが成功しているなら大丈夫」と考え、リスクの確認を怠る傾向があります。このような姿勢の人は、営業担当者の「この物件は絶対に儲かります」「管理もすべてお任せください」などの甘い言葉に騙され、不利な条件を見逃してしまうこともあるでしょう。
例えば、購入後に高額な修繕費用が必要になったり、実際には家賃相場より高い想定収入でシミュレーションされていたりする点に気付けないことも。契約内容を確認しなければ、不利な特約や違約金の存在にあとから気付き、リカバリーできなくなります。その結果、家賃収入が予想より低く、ローンの返済が厳しくなる、維持費がかさむ、物件の価値が下がるなどの問題に直面するでしょう。最悪の場合、売却しても負債が残り、経済的に追い詰められる可能性があります。プロの意見も参考する必要がありますが、不動産投資は他人任せではなく、自分自身で情報を精査し、リスクを理解するようにしましょう。
熟考せず急いで判断してしまう
「熟考せず急いで判断してしまう」点も、不動産投資で騙される人の特徴です。これは、物件の購入や投資判断をする際に、情報収集やリスク分析を十分におこなわず、営業トークや周囲の雰囲気に流されて即決してしまう状態を指します。「今決めないと売れてしまう」「限定の優良物件」などの言葉に焦りを感じ、熟考せずに判断すると、リスクの見落としが発生しやすくなります。
不動産投資は、物件の立地、将来的な資産価値、管理費、税金、空室リスクなど、多くの要素を慎重に検討しなければなりません。しかし、短期間で判断を迫られると、これらを十分に確認できず、儲かるイメージだけで投資してしまうと失敗するでしょう。最終的に、投資用不動産を売却しても損失が大きく、ローンが残るケースも少なくありません。冷静に比較検討し、十分に情報を集める姿勢が、不動産投資で成功するためには欠かせません。
不動産投資で騙されているケースと対処法

不動産投資で騙されている場合、共通するパターンがあります。ではどのようなケースがあるのでしょうか。本章で具体例を確認し、もしもの時に冷静に対処できるよう準備をしておきましょう。
手付金を支払ったあと急に連絡が取れなくなってしまう
不動産投資で騙される典型的なケースの一つに、手付金を支払った途端、相手と連絡が取れなくなる事例があります。これは悪徳会社や詐欺グループが、不動産購入を検討しているオーナーを狙い、手付金を先に支払うよう巧みに誘導し、そのまま姿を消す手法です。
特に、不動産市場の動きが活発な時期には、「早く購入しないとよい物件が他の人に奪われてしまう」と焦らせ、オーナーから冷静な判断を奪い、詐欺被害に遭わせるケースがあるため、注意しましょう。
なお、手付金は契約の証で支払うことが通常ですが、詐欺会社は「この手付金を支払わないと契約が成立しない」「特別に割引しているので、今日中に支払えば契約できます」などの言葉でオーナーを誘導します。また、「手付金を支払わないと他のオーナーに売る」とプレッシャーをかけ、冷静に考える時間を与えません。
このような被害を防ぐには、以下のポイントに注意しましょう。
- 会社の信頼性を確認する:宅地建物取引業者の免許があるか、口コミや評判を調べる
- 契約内容を精査する:契約前に手付金の返還条件を含め、契約書をよく確認する
- 支払い方法を慎重に選ぶ:信頼できる不動産会社の指定口座に直接振り込む
- 焦らず検討する:その場で決断せず、いったん落ち着いてから検討する
手付金詐欺は、一瞬の判断ミスで大きな損失につながります。冷静に情報を集め、慎重な判断を心がけましょう。
満室と思っていたのに偽装されていた
不動産投資では、満室経営の物件は大変魅力的です。しかし、なかには意図的に満室を装い、実際には空室が多いにも関わらず、高収益物件に見せかける満室偽装の手口があります。この手口に騙されると、想定していた家賃収入を得られません。
あるオーナーが「駅近で利回り13%の優良アパート」と紹介された物件を購入したとします。提案時、不動産会社は、現在満室で家賃も安定している点を強調し、家賃収入がすぐに入るとアピールしていました。しかし、実際には半分以上の部屋が空室で、満室に見えていたのはダミーの入居者を入れていたというケースも。
満室偽装の目的は、物件の価値を実際よりも高く見せ、オーナーに割高な価格で購入させることです。不動産の価値は収益性で評価されるため、満室なら高い家賃収入を見込めると錯覚し、相場より高くても買い得と判断させられます。悪質な会社は、短期間だけ親族や関係者を住まわせ、契約成立後に退去させる「サクラ入居」をおこなう場合もあります。
このような被害を防ぐためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 賃貸借契約書を確認し、入居者の契約期間が短期間でないか、複数の部屋が同時期に契約されていないかをチェックする
- 家賃の入金履歴が過去数カ月にわたって安定しているかを確認する
- 物件を実際に訪れ、郵便受けや夜間の明かりの状況を確認し、実際に人が住んでいるかを確認する
- 信頼できる不動産鑑定士や管理会社などの第三者にチェックを依頼する
サブリースに関する詐欺にあった
サブリースとは、不動産会社(サブリース会社)が物件を一括で借り上げ、オーナーに対して一定の家賃を保証する仕組みです。表面的には、空室リスクがなく、安定収益が得られるなど魅力的に見えますが、契約内容によりオーナーが大きな損失を被るケースがあります。
例えば、あるオーナーがアパートを購入し、サブリース契約を結んだとしましょう。不動産会社は、30年間家賃を保証し安定した不労所得になると説明し、契約を促しました。しかし、数年後、市場の変化で家賃を下げる必要があると通知され、保証される家賃が大幅に減額。さらに、契約の解除を求めても違約金が発生すると言われ、オーナーは泣く泣く条件を受け入れるしかなくなるケースです。
サブリース契約で注意すべき点は、家賃保証が一生続くわけではないことです。多くの契約では、数年ごとに家賃が見直され、経営が苦しくなれば一方的に家賃を下げられるケースもあります。オーナーからすると、家賃保証と聞くと安心するため、契約内容を深く確認せずに契約してしまう人がいるかもしれません。あとになって、解約するなら高額な違約金がかかる不利な条件が発覚し、自由に契約解除できなくなり、損をするケースもあります。
このような被害を防ぐために、以下のポイントに注意しましょう。
- 家賃の見直し条件や、契約解除の際の違約金を明確にしておく
- 30年間家賃保証を信用しない
- サブリース契約を結ぶ前に、他の不動産会社などの専門家の意見を聞く
- 契約書を弁護士などの専門家に確認してもらう
サブリース契約は、正しく理解すれば有効な投資手法の一つですが、安易に契約すると大きな損失を被る可能性があるため、慎重に判断しましょう。
投資用不動産に対し住宅ローンを組まされた
投資用不動産の購入に対して、一般の住宅ローンを組まされてしまう不正も起きています。本来、住宅ローンは自分が住む物件にのみ適用されます。しかし、投資用不動産にも関わらず、悪質な不動産会社から、「住宅ローンのほうが金利が低くて得」、「審査に通りやすいから」と勧められ、誤って契約させられるかもしれません。
投資経験や知識が不足していると、言われるまま契約してしまうでしょう。しかし、あとになって銀行から、居住実態がないためにローンの一括返済を求められたり、不正利用のために信用情報に傷がつくなどの不利益が生じます。住宅ローンはあくまで、自分が住む住宅に使用することが前提です。
このような被害を防ぐには、以下のポイントに注意しましょう。
- 住宅ローンは居住用のみと理解する
- 金利が高くても、投資用不動産は投資用ローンを利用する
- 「金利が低くて得」、「簡単に審査に通る」などの言葉に騙されない
不動産投資は正しい知識を持っておこなえば資産形成に役立ちますが、甘い言葉に乗せられると取り返しのつかない損失になります。慎重に判断し、安全な投資を心がけましょう。
デート商法詐欺に引っかかった
「デート商法」とは、恋愛感情を利用して高額な商品やサービスを購入させる手口のことです。不動産投資でもこの手口が使われ、特に投資経験のない人や恋愛に慣れていない人が狙われています。加害者は魅力的な異性を装い、ターゲットと親密な関係を築いたあとに、「将来のために投資をしよう」などと勧誘するものです。
デート商法の例として、男性がマッチングアプリで知り合った女性から不動産投資に誘われます。男性は好意に付け込まれ、女性に言われるがままよく調べず契約を結ぶと、価値の低い物件のローン返済に苦しむことに。物件購入後、女性とは連絡が取れなくなり、結果的に多額の負債だけが残ってしまうというケースです。この場合、クーリングオフ期間が過ぎたあと、連絡がとれなくなるとクーリングオフも利用できません。
デート商法で、被害者が相手に好意を持っていると、冷静な判断ができなくなります。特に恋愛経験が少ない人や、異性からの評価を気にする人は、相手の言葉を疑わなかったり、断りにくいでしょう。また、不動産投資に関する知識が乏しいと、「絶対に儲かる」などの甘い言葉を真に受けてしまい、契約を急いでしまいます。
このような被害を防ぐには、以下のポイントに注意しましょう。
- 恋愛と投資を混同しない
- 人から勧められた物件は常に第三者に相談する
- 急かされてもすぐに契約しない
- SNSやインターネットで相手の情報を調べ、不動産会社と関係がないかを確認する
デート商法は、心理的な罠にはまりやすいため、騙されたと気付くのが遅くなる傾向にあります。しかし、恋愛とお金の話が絡んできたら、詐欺ではないかと疑いましょう。一度冷静に立ち止まり、第三者に相談するなど、本当に信頼できる人なのかを見極めてください。
メリットばかりを強調しリスクの説明が甘い
不動産投資の詐欺では、リスクを隠し、メリットだけを強調する手口があります。特に初心者向けのセミナーや営業トークでは、「ローリスクで確実に儲かる」、「自己資金ゼロでも始められる」、「家賃収入だけで将来安泰」などの言葉が並ぶでしょう。しかし、投資には必ずリスクがあります。これを理解しないまま契約すると、あとで大きな損失を被ります。
多くの人は投資に対する専門知識がないため、営業担当者の言葉をそのまま信じてしまうかもしれません。プロが言うなら間違いない、リスクの話が出ないから安全と誤解し、慎重に調査せず契約を結んでしまいます。
このような被害を防ぐには、以下のポイントに注意しましょう。
- リスクはあるものと理解する
- メリットばかりを強調するもの疑う
- 専門家に相談する
- 成功事例だけでなく、失敗事例も自分で調べてみる
- 営業トークを鵜呑みにしない
営業の言葉を鵜呑みにせず、自分で考えたり、信用できる専門家に確認することが肝心です。メリットばかりを強調する話には特に慎重になり、自分の資産は自分で守る意識を持ちましょう。
節税効果を強調してくる
不動産投資の勧誘でよく使われる手口の一つが、節税効果を強調する営業トークです。特に会社員や高所得者をターゲットに、投資用不動産を購入すれば税金が安くなると説明し、投資のメリットを大きく見せかけるでしょう。しかし、実際には期待したほどの節税効果を得られなかったり、そもそも赤字経営を続けなければ節税ができない仕組みだったりと、結果的に損をするケースがあとを絶ちません。
営業からみると、節税は魅力的なセールストークになります。「不動産の収支が赤字でも、その分税金が減るからお得」と説明すれば、オーナーは損をしている点に気付きにくくなります。また、税金対策を考える高所得者ほど、この手口に引っかかりやすいでしょう。
このような被害を防ぐには、以下のポイントに注意しましょう。
- 節税 = 利益ではないと理解する
- 税理士や不動産投資など専門家に意見を聞き、本当に節税になるのかを確認する
- 自分でシミュレーションしてみる
不動産投資の本来の目的は節税だけではないはずです。節税効果を過度に強調する勧誘には警戒しましょう。
契約内容の説明が曖昧である
契約内容の説明が曖昧な場合も注意しましょう。投資用不動産を購入する際、不動産会社や営業担当者が契約内容を十分に説明せず、オーナーが重要なリスクや条件を理解しないまま契約を結んでしまうケースがあります。
例えば、契約書の条文が専門用語だらけで、一般のオーナーには理解しにくい内容になっている時。また、重要事項が極小の文字で書かれており、細かい条件や注意点を見落としやすい時などは注意しましょう。
不動産会社が契約内容を曖昧にする主な理由は、契約のリスクや不利な条件を明確に伝えると、オーナーが契約をためらう可能性があるからです。また、営業担当者がノルマを達成するために、大丈夫だからと抽象的な表現で説明し、オーナーの警戒心を和らげる表現をする可能性もあります。
このような被害を防ぐために、以下のポイントに注意しましょう。
- 契約書のすべての条文を確認し、わからない部分は専門家(弁護士や不動産コンサルタント)に相談する
- 小さな文字も確認する
- 重要事項説明を録音する
- 第三者に相談する
不動産投資で騙された時の相談先

不動産に投資する際、十分に気を付けていても、騙されてたと気付いたらどのように対応すればよいのでしょうか。本章では、騙されたと気付いた時に取るべき対策を紹介します。
消費生活センターに相談する
不動産投資で騙されたと感じた場合、まずは「消費生活センター」に相談しましょう。消費生活センターは、国民生活センターや地方自治体が運営する消費者トラブルの相談窓口です。商品やサービスに関する契約トラブルを相談でき、専門の相談員が対応してくれるでしょう。不動産投資に関するトラブルでも、適切な助言を受けられます。消費生活センターに相談すると、不当な契約かどうかを判断してもらえ、契約解除や返金の可能性を助言してくれるでしょう。また、弁護士や適切な相談機関を紹介してもらえたり、内容が悪質な場合、事業者に対して行政機関を通じて指導をおこなう場合もあります。
消費生活センターへ相談するには、最寄りの消費生活センターを探します。全国各地にあるため、住んでいる地域のセンターを調べましょう。「188(いやや!)」の消費者ホットラインに電話すると、最寄りのセンターにつながります。相談前には、契約書やこれまでのやり取りの記録、具体的な被害内容が説明できるような準備をしておき、不動産投資でトラブルに巻き込まれた場合は、早めに相談しましょう。なお消費生活センターの相談自体は無料ですが、電話するには通話料がかかります。
宅地建物取引業保証協会に相談する
不動産投資で騙されたと感じた場合、「公益社団法人宅地建物取引業保証協会(宅建保証協会)」に相談する方法も有効でしょう。宅建保証協会とは、不動産会社の健全な運営を目的とした公益社団法人で、宅地建物取引業法に基づいて設立されています。不動産会社が倒産したり、契約不履行があった場合に、消費者を救済するための弁済業務をおこなう機関です。
宅建保証協会に相談すると、問題の会社が宅地建物取引業者に登録しているか、保証協会に加盟しているかを調査します。もし、不動産会社が倒産し、契約が履行されない場合には、保証協会から一定額の弁済を受けられるとともに、必要に応じて契約解除や法的対応の助言も受けられるでしょう。
宅建保証協会を利用するには、まず問題の不動産会社が宅建保証協会に加盟しているかを調べます。契約書やこれまでのやり取りの記録、具体的な被害内容が説明できるよう、準備をしておく点は、消費生活センターの時と同様です。なお、宅建保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)」と「不動産保証協会(全日保証)」の2種類があるため、該当する協会に問い合わせましょう。宅建保証協会は、金銭的な救済を受けられる数少ない機関のため、不動産会社とトラブルになった場合は早めに相談してください。なお、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、どちらに加盟しているかを検索ができます。
免許行政庁に連絡する
不動産投資で騙されたと感じた場合の相談窓口として、「免許行政庁」があります。免許行政庁とは、宅地建物取引業者に対して免許を交付する行政の機関です。免許を与えた会社が不正行為をおこなった場合、免許の停止や取り消しをおこなう権限を持っており、消費者が不動産会社に関する不正行為を訴える際に重要な役割を果たすでしょう。
免許行政庁に相談すると、不動産会社が契約違反や不正な営業をおこなった場合、免許行政庁が調査を開始します。その後、会社に対する注意や是正指導、場合によっては免許の取り消しや停止処分をおこないます。違法行為が確認されると、行政庁は、消費者に対する救済策を提案する場合もあるでしょう。
相談するにはまず最寄りの免許行政庁を確認し、相談の準備を整えます。多くの都道府県では、消費者相談窓口が設置されており、そこで初期対応を受けられるでしょう。免許行政庁への連絡は、不動産会社の不正を正すための重要な手段となりえます。早めに相談し、必要な手続きを進めましょう。
弁護士に相談する
弁護士への相談も有効な対処法です。不動産会社が虚偽の説明をした場合、契約内容を故意に隠した場合、不当な契約を解除したい場合などには、法的な手続きを通じて適切に解除するアドバイスを求めましょう。また、不正な取引や詐欺で金銭的な損失を受けた場合、その損害の賠償を求めます。弁護士に相談すると、法的なアドバイスや交渉支援、訴訟対応が期待できるでしょう。
相談するにはまず、不動産投資に詳しい弁護士や消費者問題を専門にしている弁護士を選びます。初回相談が無料の事務所も多いため、気軽に相談できるでしょう。相談時には、これまでの経緯を整理し、必要な書類や証拠になる情報を集めておきます。具体的に何が問題で、どのような解決を望むのかを事前に考え、弁護士に伝えましょう。相談後、法的措置の実行などが進めば費用が発生しますが、弁護士に相談すると、法的な専門知識をもとに適切なアドバイスや対応を受けられ、問題解決が進みやすくなります。
不動産投資で騙されないための心構え

騙されたと思ったら相談できる場所はありますが、時間や費用もかかり、心身的に疲れてしまう可能性が高いです。そのうえ、失った資産が戻ってこなかったり、戻ってきても訴訟の費用などでマイナスが解消しない場合もあるでしょう。大切なのは詐欺に騙されない予防です。そこで本章では、不動産投資で騙されないための対策を紹介します。
不動産投資の知識を十分身につける
不動産投資で騙されないためには、不動産投資の知識を十分に身につけることが不可欠です。知識が不十分だと、悪質な不動産投資会社に騙されるリスクが高まります。知識をつけるためにできる方法は以下があります。
- 書籍や専門書で学ぶ:不動産投資に関する基本的な知識を深めるため、専門書や実務書を読む
- セミナーや講座に参加する:信頼できる不動産会社や専門家が主催するセミナーや講座で実践的な知識を習得する
- 実務経験を積む:少額から実際に投資をおこない、経験を通じて市場の動きやリスクを学ぶ
市場動向や物件の価値を理解し、契約書の内容を理解できる状態でなければ、投資を実行すべきではありません。税金や維持費用に関する知識も十分身につけ、常に投資の成功・失敗を見極め、事前に対策したり、軌道修正をおこなえる力がついていない場合は、投資をしない判断が大切です。
投資用不動産が適正価格かを見極める
不動産投資で騙されず成功するためには、投資用不動産が適正かどうかを見極める力が不可欠です。特に、物件選びは投資の成否を大きく左右する最重要ポイントであり、ここでの判断を誤ると、あとからリカバリーすることは困難です。そのため、購入前に慎重な調査をおこなうようにしましょう。
まず、物件の収益性を正しく判断するためには、実質利回りを確認します。表面利回りだけではなく、管理費や固定資産税などの固定コストを差し引いた実質収入をもとに計算する点が重要です。
次に、家賃設定の適正性も確認しましょう。周辺の同じような広さや築年数の賃貸物件がどの程度の家賃で貸し出されているかを調べ、購入を検討している物件の家賃が適正かどうかを判断する必要があります。
表面利回りやメリットだけでなく、得られる家賃収入は物件価格に対して適切か、リスクについて正しく説明があるかなど購入前に不動産会社に確認しましょう。
また、長期的な運用を考えるうえでは、修繕費用の適正性も見極めなければなりません。修繕費用を低く見積もると、想定外の出費が発生し、キャッシュフローが悪化する原因となります。加えて、将来的な売却価格の想定も欠かせません。不動産投資は購入後の経営だけでなく、最終的に売却して利益を確定させるケースが多いため、出口戦略をしっかり考えるようにしましょう。
不動産投資は、購入した時点で勝敗がほぼ決まるといっても過言ではありません。不適切な物件を選んでしまえば、キャッシュフローが悪化し、売るに売れない状態に陥る可能性が高まります。だからこそ、購入前に十分な時間と手間をかけて調査し、慎重に判断しましょう。
入念に返済計画を立てる
不動産投資をおこなう際、入念な返済計画を立てなければなりません。悪質な不動産会社からの甘い言葉を鵜呑みにして、安易に融資を受け投資用不動産を購入すると、想定外の支出や金利変動に対応できず、最悪の場合は経済的に行き詰まるリスクがあります。しっかりとした返済計画を立て、リスクを回避し、安定した経営をおこないましょう。
返済計画を立てる際は、家賃収入だけでなく、維持費や突発的な支出を考慮します。ローンの返済額が家賃収入の範囲内に収まり、管理費や修繕費用、固定資産税などの支出を差し引いても、キャッシュフローが黒字になる状態が理想です。金利や返済期間、自己資金の割合を慎重に検討し、無理のないローンを選びましょう。金利上昇や空室リスクも考慮し、余裕を持ったシミュレーションをおこなう点も不可欠です。
収益は確実でないと理解する
収益は必ず出るものではなく、また得た利益がすべて自分のものになるわけではない点を理解することも重要です。不動産投資の収益は決して保証されているわけではありません。例えば、購入時は満室だった物件でも、近隣に新築マンションが建設されると競争が激化し、入居率が低下する可能性があります。
また、不動産投資にはさまざまな経費がかかります。管理費、固定資産税、修繕費用、ローンなどを差し引くと、手元に残る利益は想像以上に少なくなります。このようなコストを考慮しないまま投資を始めると、思った以上に利益が出ず、後悔しかねません。そもそも不動産投資の利益は絶対ではないと理解し、自己責任のうえ慎重におこないましょう。
信頼できる不動産会社か確認する
信頼できる不動産会社を見つけるのも不動産投資をおこなううえで重要です。見極めるためのポイントは以下のとおりです。
- 口コミや評判を調べる
- 設立年数や業績を調べる
- 取り扱っている物件の種類や数を調べる
- 取引をしている金融機関や不動産会社を確認する
- 自分に合うプランを提案してくれる
- リスクやデメリットを説明してくれる
- フォローの体制が整っている
口コミや評判は実際に取引をした人の声であるため、実績やサービスの質、誠実さなどを知ることができます。会社が設立されてからどのくらい経っているのか、取り扱っている物件数、業績、会社が持つネットワークも調べることで会社に安心して依頼できるか検討する材料になるでしょう。また、投資をする目的や個人の状況によって適切な投資プランは異なります。メリットを強調するのではなく、リスクやデメリット、自分に合ったプランを一緒に検討してくれる不動産会社は信頼できる会社といえるでしょう。
不動産投資をおこなう際には、事前によく会社の事を調べてから安心して任せられるパートナーを見つけてから実行することをおすすめします。
不動産投資で騙される人についてよくある質問
不動産投資で騙される人に関するよくある質問をまとめました。
不動産投資で騙される人の特徴は?
不動産投資で騙される人は、知識不足が顕著です。基本的な仕組みやリスクを理解せずに投資を進め、甘い言葉に惑わされ、不利益を被る可能性があります。さらに、リスクを無視して都合のよい結果を想像し、楽観的に投資判断を下すことが失敗を招くことも。自分で調査せず他人任せにする人は、営業担当者に依存し、契約内容や物件情報を精査しない傾向があります。あとになって不利な条件に気付いても遅く、不動産投資で騙されてしまうでしょう。
不動産投資で騙されるケースと対処法は?
不動産投資で騙されないためには、注意すべき手口を知っておく点が大切です。例えば、手付金詐欺や満室偽装、サブリース詐欺、住宅ローンの不正利用などがあります。契約前には、会社の信頼性の確認や契約内容の精査を徹底し、第三者の意見を聞きましょう。節税効果やメリットばかり強調される場合には警戒し、リスクもしっかり理解しておくべきです。また、契約書の内容を十分に確認し、説明が不明瞭なら専門家に相談しましょう。
不動産投資で騙された場合の相談先は?
不動産投資で騙された場合、まずは消費生活センターに相談し、適切な助言を受けましょう。また、宅地建物取引業保証協会への相談は、オーナーが損害を受けて自主解決が難しい時に、保証金の弁済や契約解除のサポートを得られるでしょう。免許行政庁に連絡すると、不正行為に対する調査や是正措置が期待できます。
弁護士に相談すると、法的な手続きや損害賠償の対応を依頼できます。早めに専門機関に相談しましょう。
不動産投資で騙されないための心構えは?
不動産投資で騙されないためには、知識を身につけましょう。書籍やセミナーで学び、実務経験を積むとリスクを減らせます。物件の適正価格を見極め、収益性や修繕費用、売却価格の想定を考慮しましょう。返済計画も慎重に立て、リスクを回避する準備が大切です。また、収益は保証されていない点をよく理解し、自己責任のもとコストを考慮して慎重に投資をおこないましょう。
まとめ
本記事では、不動産投資で騙される人の特徴、そして騙されないための対策と心構えを解説しました。不動産投資では、知識不足やリスクを過信した投資判断が詐欺につながります。まずは事前に詐欺の手口を理解し、騙される人の傾向も理解して、予防策を講じましょう。そして、信頼できる情報源や相談できる専門家を見つけておきましょう。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ