不動産投資の固定資産税とは?計算方法や支払い方法を把握しておこう
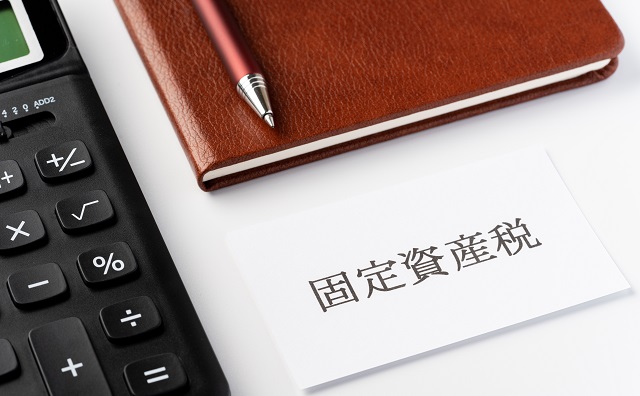
記事の目次
固定資産税とは
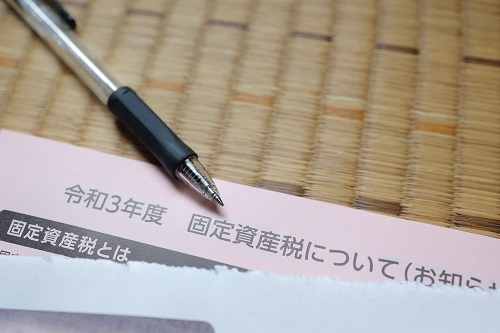
固定資産税は、土地や家屋(住宅や建物)を所有する個人や法人に課される地方税です。不動産投資ローンを完済しても、投資物件を所有する限り、毎年納付する義務があります。
不動産投資では、アパートや賃貸マンションなどの投資物件を購入することが多いでしょう。一棟丸ごと購入すれば、その建物と土地の全体に対して固定資産税が課されます。区分マンションを所有する場合は、専有部分(居室)と共用部分・土地の持分に応じた固定資産税を個別に納めなければなりません。
固定資産税評価額とは
固定資産税の計算の基礎となるのが「固定資産税評価額」です。固定資産税評価額とは市町村の長が決定する、土地や建物の評価額です。3年に1度、評価替えがおこなわれ、その際に新たな評価額が設定されます。
土地の評価額は、道路沿いの土地の1平方メートル単位面積あたりの価格である「路線価」や過去の売買事例を参考に算出されます。一方で、建物は同等の新築を想定した再建築価格から妥当な時価が算出されることが基本です。建物には耐用年数があり、年数の経過とともに資産価値が減少するため、固定資産税額も減額される仕組みになっています。
そのため、土地の評価額に大きな変動はありませんが、建物は建材の価格変動などにより、場合によっては中古物件のほうが新築より高い評価額になることもあります。
固定資産税評価額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されており、一定期間役所でも閲覧が可能です。
固定資産税を支払う人
固定資産税の納税義務がある人は、その年の1月1日時点で物件の所有者である個人や法人です。1月1日は「賦課期日(ふかきじつ)」と呼ばれ、それ以降に取得した物件であっても、その年の固定資産税は前所有者が支払う必要があります。
参考:総務省「 固定資産税制度の概要」
固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法は、主に以下の3通りがあります。
- 納税通知書による金融機関への振り込み
- 自治体窓口や納税コーナーでの現金払い
- コンビニでのクレジットカード・電子マネー払い
一般的な方法は、納税通知書による金融機関への振り込みです。市区町村から4〜6月頃に納税通知書が送付されてくるので、指定の期日までに払い込みを済ませなければなりません。
直接窓口で現金払いする方法もありますが、手続き上の手間がかかります。最近は便利なコンビニ納付が増えてきており、クレジットカードや電子マネーでもスムーズに払えます。ただし、クレジットカードには支払い上限額(通常100万円)があり、決済手数料もかかるため、注意が必要です。
固定資産税は分割払いも可能
固定資産税は年間の納税額が高額になる傾向があるため、4期に分けて納付するのが一般的です。納付時期は自治体により異なりますが、東京23区の場合は、6月、9月、12月、2月の年4回に分かれています。
一括払いを選べる自治体もあり、早期納付するとわずかですが、割引特典(前納報奨金制度)が設けられている場合もあります。ただし、この前納報奨金制度は徐々に廃止されつつあるため、自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
固定資産税を延滞するとどうなる?
固定資産税の支払いを忘れたり、滞納してしまうと、厳しい罰則を受ける可能性があります。具体的に内容を見ていきましょう。
延滞税が発生する
固定資産税の納付期限を過ぎると、地方税法に基づき延滞税(延滞金)が発生します。延滞税は、日割り計算で算出されるため、延滞期間が長引くほど高額になります。
2024年現在の延滞税率(年率)は、以下のとおりです。
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで原則として年「2.7%」
- 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後原則として年「8.7%」
ただし、2021年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます。具体的な数値は以下のとおりです。
- 2022年1月1日〜令和6年12月31日までは年2.4%
- 2023年1月1日〜12月31日までは年2.5%
参考:国税庁「延滞税について」
財産が差し押さえられる恐れがある
固定資産税の支払いが滞ると、まず市区町村や都道府県から督促状が送付されます。督促にも従わなければ、電話や自宅への直接訪問で支払いを促されることも。
固定資産税を滞納し続けた場合、最悪の事態として財産が差し押さえられる可能性があります。固定資産税の場合、差し押さえ対象になりやすいものが、土地や家屋(建物)です。
差し押さえ後も滞納が解消されない場合、その土地や家屋は競売にかけられ、滞納分の税金の支払いに充てられてしまいます。固定資産税を払わなかったことで、大切な不動産そのものを失ってしまう重大なリスクが生じてしまうため、確実に支払うようにしましょう。
固定資産税の計算方法と算出基準

前章では固定資産税の概要を説明しました。本章では固定資産税の計算方法や算出基準を解説します。
固定資産税の計算式
固定資産税は、公示価格をもとに算出された固定資産税評価額から課税標準額を求め、さらに1.4%の標準税率をかけて計算されます。課税標準額の算出には、小規模住宅用地の軽減措置や負担調整措置なども加味されたうえで計算されることが一般的です。
一般的な計算式は次のとおりです。
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%
新築住宅の場合、一定期間減額される特例措置が受けられます。
古い建物ほど固定資産税は低くなる傾向がありますが、新築で特例を受ける場合は逆転して税額が低くなることもあります。
固定資産税の算出基準

固定資産税の金額は、以下の4つの要素で変動します。
- 個人の保有資産
- 投資物件の構造や広さ
- 自治体ごとの税率
- 地価の変動状況
個人の保有資産
固定資産税は、個人が所有する不動産や減価償却資産の種類と数で税額が異なります。住宅や土地はもちろん、飛行機やボート、太陽光発電設備なども課税対象になります。保有資産が多いほど、総額でかかる固定資産税の負担は重くなるため、事前に自分が保有する資産を確認しておくことが大切です。
投資物件の構造や広さ
投資物件に課される固定資産税は、建物の構造、広さ、内外装の仕様、建材の等級などによって決まる「固定資産評価基準」にしたがって算出されます。評価基準の高い物件ほど、固定資産税の課税標準額が高く設定されているため、高額な税金を支払わなければならないことも。
広々とした高級住宅で、しかも経年劣化の少ない建材を使用している場合は、固定資産評価基準が高くなり、税金の負担も重くなります。
自治体ごとの税率
固定資産税の標準税率は1.4%と定められていますが、自治体ごとに異なることがあります。なかには1.5%など高めに設定している自治体もあるため、投資を検討している不動産の自治体の税率設定を事前に確認する必要があります。
また、都市計画税の課税有無も地域によって異なり、自治体によっては都市計画税が不要な場合もあるため、あわせて確認しておきましょう。
地価の変動状況
固定資産税のシミュレーションでは、特に土地部分への課税に注意が必要です。土地は経年劣化がないため、地価の変動に連動して評価額が変わります。
開発が進めば地価は上昇し、固定資産税の負担も重くなりますが、地価が下落すれば、固定資産税は減額されます。この仕組みを理解しておきましょう。
【建物別】不動産投資における固定資産税の目安

固定資産税は、毎年かかる税金です。不動産投資の収益にも大きく関わる支出なので、ある程度の目安を立てて収支計画を立てておくことが大切です。しかし、固定資産税は所有する不動産に合わせて税額が異なります。ここからは、建物別に不動産投資の固定資産税の目安を解説します。
ワンルームマンションの場合
ワンルームマンションへの投資では、年間の固定資産税は4〜8万円程度が目安です。
一般的にマンションは一戸建て住宅に比べて固定資産税が低い傾向にあります。その理由は、固定資産税が土地と建物に分けて課税されるから。
一戸建ては土地全体に対して課税されますが、マンションの場合は土地の持分面積に対してのみ課税されるため、負担が軽減されるのです。
さらにワンルームマンションは住居面積が小さいため、建物部分の課税額も抑えられます。そのため、他の不動産投資物件と比較しても固定資産税総額は低い傾向に。ただし、所在地や築年数によっても金額は変わってくるため、注意しましょう。
新築一戸建ての場合
木造新築の3,000万円物件の場合、固定資産税は年間10〜15万円程度が目安です。ただし、立地条件や建物の広さ、構造などでも変動するため、あくまでも目安の一つとして考えておきましょう。
新築住宅では一定期間、固定資産税の減額措置を受けられるメリットがあります。要件を満たせば大幅な節税が可能ですが、減額期間終了後に急に税額が上がるリスクもあります。長期的な収支シミュレーションをおこない、固定資産税の動向を踏まえた投資計画が重要となります。
中古一戸建ての場合
中古の一戸建て住宅の場合、土地部分の課税は新築・中古で変わりませんが、建物は経年劣化によって資産価値が低くなるため、築年数が古くなるほど固定資産税が低額になる傾向にあります。
ただし、新築住宅には減額措置が設けられていますが、中古住宅では適用されないため、注意が必要です。そのため、築年数によっては新築のほうが中古より固定資産税が安くなるケースもあります。
マンション一棟の場合
マンション一棟の場合、建物と土地全体に固定資産税が課されるため、負担額は高額になる傾向にあります。
ただし、マンション一棟投資には戸数に応じた大幅な減額措置があります。土地の固定資産税は「戸数×200平方メートル」の部分まで小規模住宅用地の軽減措置が適用されるため、税金の負担を大きく抑えられるでしょう。
マンションの一棟投資では、固定資産税を含めた詳細な収支シミュレーションが不可欠です。固定資産税の負担感は大きいものの、戸数による減額措置などのメリットも考慮に入れて検討してみましょう。
固定資産税における特例措置

繰り返しになりますが、固定資産税は、土地や家屋などの不動産に課される税金です。通常、土地の評価額は公示価格の70%程度、建物の評価額は購入金額の50〜70%程度が目安です。不動産の価格が高いため、標準税率が1.4%でも税額は決して安くありません。先述したように、固定資産税には特例措置が設けられています。具体的に、どういったものかを見ていきましょう。
新築の場合は固定資産税が減額される
2026年(令和8年)3月31までに新築された住宅の場合、一定の条件を満たせば3年間(マンションの場合は5年間)、固定資産税額が半額になります。具体的な条件は以下のとおりです。
- 居住割合が1棟全体の2分の1以上であること
※マンションなどの区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定 - 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下であること
上記をすべて満たす新築住宅であれば、建築後5年間は固定資産税が半額になります。
3階以上の耐火・準耐火住宅であれば、5年間減額されますが、それ以外の住宅でも3年間は特例措置が適用されます。
参考:名古屋市「新築住宅に対する固定資産税の減額について」
長期優良住宅の場合
長期優良住宅と認定された物件では、先述した特例措置の適用期間が5年間(マンションの場合7年間)に延長されます。長期優良住宅とは、以下の基準を満たす優良な住宅のことです。
- 長期にわたり建物や設備を良好な状態で維持できる構造
- 良好な居住水準を確保する十分な面積を有している
- 地域の居住環境の維持・向上に配慮されている
- 適切な維持保全の計画が立てられている
参考:国土交通省「長期優良住宅のページ」
長期優良住宅の特例措置の条件
長期優良住宅として特例措置を受けるための条件は、一般の住宅より厳しくなっています。
- 長期優良住宅の認定を受けていること
- 2026年3月31日までに新築された物件であること
- 一戸あたりの居住面積が50平方メートル以上(貸家の場合40平方メートル)280平方メートル以下
参考:国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」
小規模住宅用地の特例
人が住む目的で建物が建っている土地の場合も、固定資産税の軽減措置が設けられています。
土地の面積が200平方メートル以下の場合は「小規模住宅用地」、200平方メートルを超える部分は「一般住宅用地」と区分され、それぞれ以下のように課税標準額が減額されます。
- 小規模住宅用地:課税標準額の6分の1
- 一般住宅用地:課税標準額の3分の1
例えば、課税標準額が3,000万円の小規模住宅用地ならば、土地の固定資産税は以下のように計算できます。
課税標準額3,000万円 × 1/6分 × 標準税率1.4% = 7万円
このように、住宅用地でも特に小規模である場合には、固定資産税が大幅に軽減される仕組みになっています。
固定資産税が上がるのはどういう時?

最後に、固定資産税がどういう場合に上がるのかを解説します。
建物の場合
建物にかかる固定資産税は、建物自体の価値や建築費が高くなることで、税額が上がるケースがあります。
要因として考えられる1つ目の理由は、大規模なリフォームによる建物価値の上昇です。キッチンや内装の模様替えなど、小規模な内装リフォームでは影響はありませんが、増築や建物の骨組みを残してほぼ新築に近いリフォームをおこなうと、建物の評価額が大幅にアップします。
その結果、固定資産税額も増えてしまうのです。ただし、投資用の区分所有マンションでこうした大がかりな全面リフォームをおこなうケースは稀でしょう。
2つ目は、建築費の高騰により「再建築価格」が上昇した場合です。再建築価格とは、評価時点で同じ家屋を新築するのに必要な想定建築費用のことです。建築資材の値上がりや人件費高騰などで再建築価格が上がれば、それに連動して家屋の評価額や課税される固定資産税額も増えてしまいます。
ただし、前年度評価額を上回る場合は、前年度の税額に据え置かれます。「家屋の固定資産税は下がるもの」と考えていると、この据え置きで予想外の負担が増える可能性もあるため、注意が必要です。
土地の場合
一方で土地部分は、国税庁が算出する「路線価」(道路沿いの単位面積あたり地価)の変動に応じて、固定資産税評価額が増減します。
再開発や道路拡張などで路線価が上昇すれば、固定資産税も上がります。
しかし、住民への急激な負担を避けるため、増額幅には年間上限が設けられている点が特徴です。徐々に税額が引き上げられていく仕組みになっているため、急激に負担が大きくなる心配はありません。
また、区分マンションの場合、土地部分の固定資産税評価額は所有者全員に按分されます。路線価変動の影響で固定資産税が高くなっても、そこまで大きな負担にはならないでしょう。
年の半ばで不動産売買があった場合
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者に決まります。しかし実際には、年の途中で所有者が代わることも多々あるでしょう。
途中で所有者が変わった場合、旧所有者が全額支払うと、自身が所有していない期間の固定資産税まで負担することに。
以前の所有者の負担を減らすためにも、売主と買主で所有期間に応じて固定資産税を按分し、精算するのが一般的な手続きとなっています。
例えば、5月末に売買し名義変更があった場合、1月1日を起算日として売主が1〜5月分、買主が6〜12月分の固定資産税をそれぞれ負担することになります。
買主側の支払い分は「固定資産税清算金」と呼ばれ、売買契約書にその旨が明記されることがほとんど。適切な精算がなされているかを確認しておくことが重要です。
用途が変更された場合
住宅用地には固定資産税の減税措置がある一方で、住宅以外の用途に転用した場合は課税標準が引き上げられ、固定資産税額が増える可能性があります。
例えば、マンション経営から撤退して駐車場やコインランドリー経営に転用するとしましょう。上記のように用途を転用すると、これまでの住宅用地課税からは外れ、商業地や雑種地として評価替えされるため、固定資産税負担が大幅に増えるリスクがあります。
転用後に固定資産税が大幅に上がったなどのトラブルを避けるためにも、固定資産税のシミュレーションをしっかりおこないましょう。
タワーマンションは階層で税額が異なる
タワーマンションの一住戸あたりの固定資産税は、マンション全体の評価額をベースに、各世帯の専有面積をもとに算出されます。しかし、2017年度の税制改正により、高層階ほど資産価値が高いとみなされ、階層による補正がかけられるようになりました。
つまり、同じ専有面積でも高層階に位置する住戸ほど、固定資産税評価額が上乗せされて高額になる傾向にあります。制度変更は、2017年1月2日以降に新築されたタワーマンション(2017年3月31日までに売買契約が締結された者の専有部分を含むものは除く)が対象です。
特に高層階の物件を検討する際は、固定資産税負担が大きくなることを見込んでおく必要があります。
まとめ
今回は不動産投資の固定資産税を詳しく解説しました。ひとえに固定資産税といっても、建物や土地、自治体によってルールが異なります。固定資産税は毎年かかるものだからこそ、どのくらい発生するのかあらかじめ理解しておく必要があります。
建物によっては軽減措置が設けられている場合もあるため、自分が投資する物件が軽減措置の対象となるかも確認しておくとよいでしょう。
固定資産税は、支払いが遅れると延滞税がかかったり、最悪の場合は財産が差し押さえられたりなどのリスクもあります。支払い忘れがないようにしましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





