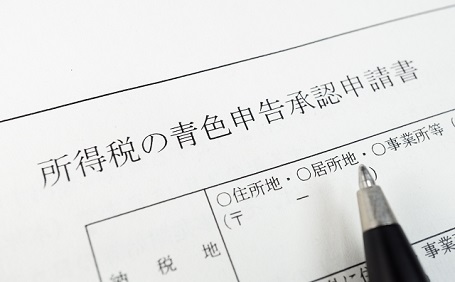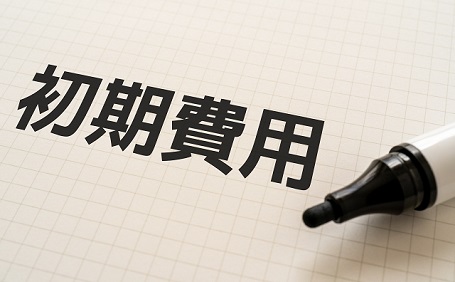アパート経営で確定申告が必要な人とは?申告の手順や注意点を徹底解説

本記事では、確定申告が必要となる人の基準や計算方法などを詳しく解説します。
記事の目次
確定申告が必要な人とは

税務上、以下のいずれかの条件に該当する場合、確定申告をおこなう必要があります。
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 1か所から給与を受け取り、給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円を超える人
- 複数の勤務先から給与を受け取り、年末調整をされなかった給与と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
- 公的年金の収入が400万円を超える人
- 公的年金の収入が400万円以下でも、公的年金以外の所得が20万円を超える人
※出典:国税庁「確定申告が必要な方」
アパート経営をしている場合、会社員や公的年金受給者でも、家賃収入が一定額を超えた場合は確定申告が必要です。特に、給与や年金とは別に年間20万円を超える不動産所得が発生している場合は、確定申告をおこなわなければなりません。
確定申告の義務を怠ると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。そのため、自分の所得がどの条件に該当するのかを確認し、早めの準備を心がけましょう。
不動産所得とは
確定申告の要否を判断するうえで重要となる基準が「不動産所得」です。不動産所得とは、アパート経営などで得た収入から、経営にかかった経費を差し引いた額のことを指します。不動産所得の計算式は以下のとおりです。
- 不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
ここで注意すべきことは、「収入」そのものではなく、「所得」が基準になる点です。つまり、家賃収入が20万円を超えても、必要経費を差し引いた結果、利益が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。
しかし、ローンを組んでアパートを購入した場合、元本返済分は経費として認められません。そのため、帳簿上は赤字であっても、不動産所得が20万円を超えれば確定申告が必要になります。
また、アパート経営では修繕費、管理費、固定資産税などが経費として計上できます。どの費用が経費として認められるのかを正確に把握しておくことが重要です。特に、確定申告の際に税務調査が入る可能性もあるため、領収書や請求書の保管を徹底し、適切に記録を残しておきましょう。
アパート経営で確定申告をしたほうが得をするケース

確定申告の義務がない場合でも、申告をすることでメリットを得られることがあります。その代表的な例が「損益通算」です。
損益通算とは、不動産所得と他の所得(給与所得など)を合算して税額を計算する仕組みのこと。仮にアパート経営で赤字が出た場合、その赤字分を給与所得と相殺することで、課税対象となる所得を減らせます。課税対象の所得が減ることで、所得税や住民税を軽減できる可能性があります。
例えば、アパートを新築した初年度や、大規模な修繕をおこなった年などは、減価償却費や修繕費が増えるため、赤字になることも珍しくありません。このような年に確定申告をして損益通算を活用すれば、本業の給与所得から引かれる税額を抑えられるため、税負担を軽減する効果が期待できます。
さらに、アパート経営を続けるうえで金融機関からの融資を受ける場合、確定申告の実績があると「事業の継続性」や「経営の透明性」を示す資料にもなります。実績があるとみなされれば、融資の審査がスムーズに進む可能性も。
そのため、「不動産所得が20万円以下だから確定申告は不要」と判断するのではなく、節税対策として確定申告を積極的に活用することをおすすめします。
アパート経営開始から確定申告までの流れ
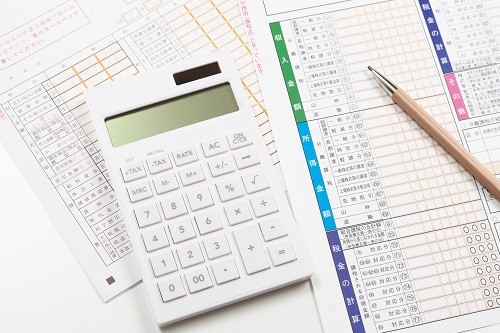
ここでは、アパート経営を始めてから確定申告を完了するまでの具体的な流れを解説します。経営をスタートしたあと、どのような準備を進めるべきか、1年間のスケジュール目安に沿って見ていきましょう。簡単な流れは次のとおりです。
- STEP 1毎月の収支を記録し帳簿をつける
- STEP 2毎年年末頃から確定申告に必要な書類を準備する
- STEP 3年が明けたら確定申告の準備をする
- STEP 4期限までに確定申告を済ませ、納税をおこなう
まずは確定申告の提出・納税期限を把握しておきましょう。
確定申告の提出・納税期限
確定申告の提出期間と納税期限は、原則として毎年2月16日から3月15日までの約1カ月間と定められています。この期間内に確定申告書を税務署へ提出し、税額を納付する必要があります。
ただし、この期間はあくまで「申告書の受付期間」のため、事前に準備を進めておくとよいです。
特に、青色申告か白色申告のどちらにするかは、事前に決めておきましょう。どちらを選択するかによって節税効果が変わるため、経営規模や収支を考慮しながら、よりメリットのある申告方法を選びましょう。
確定申告の準備は、想定以上に手間がかかるものです。直前になって慌てることのないよう、余裕を持ったスケジュールで、書類整理や帳簿管理を進めることをおすすめします。
STEP 1. 毎月の収支を記録し帳簿をつける
アパート経営を始めたら、最初にすべきことは毎月の収支を正確に記録することです。帳簿をつけることで、どれくらいの利益が出ているのか、どのような経費が発生しているのかを把握しやすくなります。
帳簿の形式は特に決まっていないため、手書きのノート、会計ソフト、スマホアプリなど、自分が管理しやすい方法を選びましょう。
帳簿作成のポイントは、完璧を求めすぎず、定期的に記録を続けることです。数カ月分をまとめて処理しようとすると、領収書やレシートの整理に手間がかかり、ミスの原因にもなります。最低でも1~2カ月ごとに帳簿を更新する習慣をつけましょう。
帳簿をしっかりつけておくことで、確定申告に向けた準備が格段に楽になります。また、税務調査などの際に経費の証明資料として役立つため、領収書や請求書もきちんと保管しておくことが大切です。
STEP 2. 年末頃から確定申告に必要な書類を準備する
確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの収支をもとにおこないます。そのため、年末の11月~12月頃には確定申告に必要な書類を揃え始めるとスムーズです。
確定申告で必要となる主な書類は、以下のとおりです。
| 必要書類 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| アパートローンの 明細書 |
銀行からの借入額や利息の明細 | 金融機関 |
| 不動産取得税の納付書 | 新築アパート取得時の税金(不動産取得税など)の支払い明細 | 税事務所や金融機関、郵便局の窓口 |
| 固定資産税の通知書 | 毎年5~6月頃に届く固定資産税の納付書 | 所有する土地・家屋の所在地のある市区町村 |
| 管理費や委託費の 明細書 |
管理会社に支払う費用の記録 | 管理会社 |
| 賃貸借契約書 | 敷金・礼金の金額が記載された書類 | オーナー自身が所持 |
| 修繕費や経費の領収書 | 事業経費の証明となる書類 | 取引先 |
| 火災保険・地震保険の 控除証明書 |
保険料の控除申請に必要 | 保険会社 |
| ふるさと納税の 控除証明書 |
控除対象となる寄付の証明 | 自治体 |
| 賃料入金明細書 | 家賃収入の証明となる記帳コピーなど | 管理会社 (管理会社を通さない場合はオーナー自身が所持) |
上記の書類は、確定申告時に提出が必要なものと保管しておくだけでよいものに分かれます。特に控除証明書は提出が求められるため、年末調整をおこなう会社員の方は早めに勤務先から受け取っておくようにしましょう。
STEP 3. 年が明けたら確定申告の準備をする
年が明けたら、確定申告の準備に本格的に取りかかります。この時点で、帳簿の記録がまだ終わっていない場合は、速やかに整理を完了させましょう。そのあと、確定申告をおこなうための手続きを進めていきます。
申告方法には、次の2つの方法があります。
-
手書きで申告書を作成し、税務署へ提出する
国税庁のホームページや税務署で申告書を入手し、手書きで記入します。その後、郵送または税務署窓口で提出します。
-
国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用する
インターネット上で入力すれば自動計算されます。印刷して郵送、または電子申告(e-Tax)が可能です。電子申告(e-Tax)の利用の際には、原則として、電子証明書の有効期限内であるマイナンバーカードが必要です。しかし、インターネット上で完結するため、税務署に出向けない方は利用するといいでしょう。
税務署や税理士への相談が必要な場合は、申告開始前に問い合わせると慌てずに済むでしょう。
STEP 4. 期限までに確定申告を済ませ、納税をおこなう
確定申告は期限内に完了させる必要があります。申告が完了したからといって税務署から納付案内が届くわけではないため、自分で納税手続きを進める必要があります。
納税方法には以下の選択肢があります。
- 振替納税
- e-Taxを使った口座振替
- インターネットバンキング
- クレジットカード払い
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード決済)
- 現金納付
納付期限を過ぎると延滞税が発生するため、期限内に確実に支払いを済ませましょう。上記の流れを毎年繰り返すことで、スムーズな確定申告が可能となります。
参照:国税庁「税金の納付」
アパート経営の確定申告で経費として認められる費用
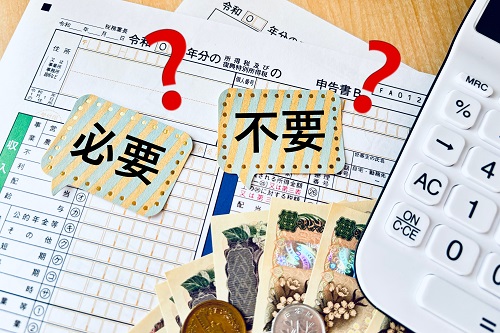
アパート経営をおこなう際、確定申告で経費として計上できる費用は多岐にわたります。経費を適切に申告することで、課税対象となる不動産所得を抑え、節税につなげることが可能です。
不動産所得の経費には、以下が挙げられます。
- 固定資産税や都市計画税などの「公租公課」
- 建物や設備の価値を年ごとに分割して計上する「減価償却費」
- 共用部分の修理や配管工事などの「修繕費」
- アパートローンの利息分の「借入金利子」
- 火災保険や地震保険の「損害保険料」
- 家族従業員に支払う「専従者給与」
- 入居者募集のための「広告宣伝費」
- インターネットや電話代の「通信費」
- 立ち退き時に発生した「雑損失」
- 関係者との接待費用の「接待交際費」
- 事務用品や設備購入費の「消耗品費」
- 移動にかかる「旅費交通費」
- 情報収集のための「新聞図書費」
さらに、不動産管理を外部委託する場合の「管理委託費」、不動産売買時の「仲介手数料」、税理士や弁護士への「報酬」など、追加で計上できる経費もあります。
ここからは、特に注意が必要な「公租公課」「減価償却費」「修繕費」「損害保険料」を詳しく解説します。
公租公課とは
「公租公課」とは、国や自治体に支払う税金の総称で、アパート経営に関連するものは経費として認められます。具体的には、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業税などが含まれます。
上記の税金は、不動産を所有・経営するために必要な支出のため、確定申告時に経費として計上が可能です。
一方で、所得税や住民税はアパート経営に直接関係する税金ではないため、経費として認められません。確定申告の際は、経費に含められる税金と含められない税金を正しく区別することが重要です。
固定資産税や都市計画税は、毎年課税されるため、年度ごとに確実に経費として申告しましょう。特に、不動産取得税や登録免許税などの単発の税金は忘れやすいため、支払った際に記録を残しておくとスムーズに申告できます。
減価償却費とは
アパートを取得する際、建築費や購入費、仲介手数料、固定資産税の日割り分、登記費用などの支出が発生します。上記の費用は高額なため、一度に経費として計上すると大きな赤字になってしまうでしょう。
そこで、会計基準では、上記の費用を「減価償却費」として、一定の年数にわたって分割計上するルールになっています。計算方法には3種類あり、2016年3月31日以降に取得した物件に対しては、定額法を使用します。計算式は次のとおり。
- 原価償却費 = 建物の購入価格 × 定額法の償却率
例えば、木造アパート(耐用年数22年:償却率0.046)を4,400万円で建築した場合。
4,400万円 × 0.046 = 202万4,000円
この場合、毎年の減価償却費として約202万円の経費計上が可能です。ただし、土地の購入費用は減価償却の対象外となるため、注意が必要です。
また、建物の構造によって耐用年数は異なります。例えば、鉄筋コンクリート造(RC造)は47年、鉄骨造は19~34年、木造は22年と定められています。
建物の構造や築年数に合わせて適切な減価償却をおこなうことで、税務上のメリットを最大限に活用できるでしょう。
損害保険料とは
火災保険や地震保険などの損害保険料は、確定申告で経費として計上が可能です。しかし、契約期間分を一括で支払う場合が多いため、契約年数に応じて分割計上する「期間按分」をおこなう必要があります。
例えば、5年間で25万円の火災保険に加入した場合。
25万円 ÷5年 =5万円
5万円を毎年の経費として計上します。上記のルールを守らなければ、税務調査で指摘される可能性があるため注意しましょう。
契約時に一括で支払った場合でも、契約が終了するまでは毎年按分して計上することを忘れないようにしなければなりません。
修繕費と資本的支出の違い
アパートを維持管理するためには、修繕費がかかります。しかし、修繕費として計上できるものと、資本的支出として減価償却しなければならないものがあるため、注意が必要です。
修繕費とは
修繕費は、建物をもとの状態に維持・管理するための費用のことで、その年の経費として一括計上できます。例えば、退去後の壁紙張替え、ガラスの交換、キッチンの修理、定期的な外壁塗装などが該当します。
資本的支出とは
資本的支出は、アパートの価値や耐久性を向上させるための費用で、一括経費計上はできず、減価償却が必要です。例えば、ブロックキッチンをシステムキッチンに変更する、外壁をより高品質な塗料で塗装するなどの支出が該当します。
基本的な区別として、支出額が20万円未満、または周期が3年以内であれば修繕費、それ以外は資本的支出として処理すると覚えておくとよいでしょう。
アパート経営の確定申告で経費にならない費用

アパート経営では、経営にかかるさまざまな支出を経費として申告できますが、すべての支出が経費として認められるわけではありません。確定申告の際に間違えて計上してしまうと、税務調査で指摘される可能性もあるため、事前に「経費として認められない項目」を理解しておくことが大切です。
一般的に、アパート経営で経費として計上できないものは、「借入金の元本部分」「所得税や住民税などの税金」「私的な支出」の3つが挙げられます。
上記は事業に直接関係しない、または二重計上のリスクがあるため、経費として認められません。ここからは、それぞれの項目をより詳しく解説します。
借入金の元本部分
アパート経営で金融機関から借り入れをおこなう場合、ローンの返済には「元本部分」と「利息部分」が含まれています。このうち、利息は経費として計上できますが、元本の返済額は経費にはなりません。その理由は、ローンの元本返済は「借りたお金をそのまま返しているだけ」の扱いになるためです。
例えば、1,000万円を借りて、そのまま1,000万円を返済する行為は、新たな支出ではなく、単に資金の移動にすぎません。そのため、経費として計上することは認められていません。
さらに、建物の取得費用は「減価償却費」として年ごとに分割して経費計上が可能です。つまり、ローンの元本部分を経費に含めてしまうと、建物の取得費用を減価償却と元本返済の両方で経費計上してしまうことになり、税務上のルールに反することになります。
このような二重計上を避けるためにも、ローンの元本部分は経費に含めることができないと理解しておきましょう。
所得税・住民税など個人に課される税金
アパート経営では、不動産に関連する税金の一部を経費として計上できますが、すべての税金が経費になるわけではありません。上記でも解説しましたが、「所得税」や「住民税」などの個人に課される税金は、経費として計上することはできません。
税金のなかには、事業の運営に直接関係するものと、個人の所得にかかるものがあり、後者は経費の対象外です。例えば、固定資産税や都市計画税は不動産の維持に必要な税金であり、経費として計上可能です。しかし、所得税や住民税、法人税はアパート経営とは関係がないため、経費として認められません。
また、事業税は一定の条件を満たした場合に限り、経費として計上できます。不動産賃貸業では、5棟10室基準(独立した家屋なら5棟以上、アパート、マンションなどなら10室以上を経営)を満たさなければ事業税は発生しません。小規模経営であれば事業税は発生しないため、確定申告でも記載は不要です。
税金は確定申告で間違いやすい項目の一つです。「支払った税金=経費」ではないため、不動産に関連する税金のみが経費計上できることを理解しましょう。
アパート経営に関係のない支出
アパート経営では、事業に関係のない支出を経費として申告することはできません。特に、個人的な食事代やプライベートな交際費などは、事業の経費として認められません。
例えば、オーナー仲間との会食や、不動産関係者との打ち合わせなどは、経費にできる場合があります。しかし、単なる友人との食事や、趣味で行った旅行の費用は経費にはできません。
もし、プライベートな費用を誤って経費として計上してしまうと、税務調査の際に指摘され、追加の税負担が発生する可能性があります。
ただし、アパート経営に関係する交際費や会議費は、正しく計上すれば経費として認められる場合も。そのため、経費として申告する際には、領収書をしっかり保管し、出納帳や会計ソフトに正確に記録することが重要です。
また、出張時の交通費や宿泊費も、業務上必要なものであれば経費にできますが、プライベートの旅行と区別するために、事前に経費の範囲を明確にしておくと安心です。税務署に不審に思われないよう、業務との関連性がわかるように証拠を残しておきましょう。
アパート経営で初めての確定申告に不安な場合どうすべき?

アパート経営を始めたばかりの方にとって、初めての確定申告は不安がつきものです。必要な書類の準備や経費の計上ルールなど、専門的な知識が求められるため、「自分で対応できるのか?」と心配になることもあるでしょう。
特に、複数の物件を所有している場合や、減価償却などの税務処理が絡む場合は、ミスのない申告をすることが難しくなります。確定申告が不安な方は、税理士に依頼する方法も一つの手です。
税理士に任せることで、手間が省けるだけでなく、正しい申告ができるため、税務リスクを軽減できるでしょう。ただし、税理士に依頼するには費用が発生するため、コストとメリットを天秤にかけて判断する必要があります。
ここでは、税理士に確定申告を依頼するメリットやデメリットなどを詳しく解説します。
税理士に依頼するメリット
税理士に確定申告を任せることで、多くのメリットが得られます。
時間と手間を削減できる
確定申告の作業には、領収書や帳簿の整理、申告書の作成など、多くの工程があります。上記をすべて自分でおこなうとなると、相当な時間と手間がかかります。特に、経費の計上ルールを正しく理解していなければ、調べる時間が増え、ミスするリスクも高まるでしょう。
税理士に依頼すれば、確定申告に関する作業をほぼ任せられるため、本業や他の業務に専念できます。物件数が多いオーナーや、副業としてアパート経営をしている方にとっては、大きなメリットとなります。
正しい申告ができる
税務の知識が不足していると、知らないうちに申告ミスをしてしまうことがあります。誤った申告をすると、税務調査の際に指摘され、追加の税金(追徴課税)を支払わなければならないケースも。
税理士に任せれば、専門知識を活かして正確な申告ができるため、ミスを減らすことが可能です。税法の変更にも対応してくれるため、最新のルールに基づいた適切な申告をおこなえるでしょう。
節税や経営アドバイスを受けられる
税理士に依頼することで、単なる申告作業だけでなく、節税対策のアドバイスを受けられます。例えば、修繕費の計上方法や減価償却の適用範囲など、税務の知識を活かして合法的に節税する方法を提案してくれるでしょう。
さらに、アパート経営の収益を最大化するためのアドバイスをしてくれる税理士もいます。物件の経営方法や資金計画など、長期的な視点で相談できる点も大きなメリットです。
税理士に依頼するデメリット
一方で、税理士に依頼することには、いくつかのデメリットもあります。
費用がかかる
税理士に確定申告を依頼する際のデメリットは、費用が発生することです。物件数が多いほど、経理処理が複雑になるため、費用も高額になる傾向があります。
特に、顧問契約を結ぶ場合は年間で数十万円かかることもあるため、手元の資金と相談したうえで慎重に判断する必要があります。
自身の税務知識が身につかない
すべて税理士に任せてしまうと、自身の税務知識が身につかない点もデメリットの一つです。将来的に自分で申告をしようと考えている場合は、税理士に依存しすぎないよう、ある程度の税務知識を学んでおくとよいでしょう。
税理士とのコミュニケーションが必要になる
税理士に正確な申告をしてもらうためには、自身の経営状況や経費に関する情報を正しく詳細に伝える必要があります。そのため、定期的な打ち合わせや連絡が欠かせません。
また、税理士にも得意分野と不得意分野があるため、相性のよい税理士を見つけることも重要です。信頼できる税理士でなければ、思うようなサポートを受けられない可能性があります。
税理士に依頼する際の費用相場
アパート経営での確定申告を税理士に依頼する場合、どの程度の費用がかかるのかを把握しておきましょう。税理士のサポート内容や契約形態によって料金は異なり、大きく分けて「単発の相談」「申告代行」「顧問契約」の3つのパターンが考えられます。
まず、税理士への単発相談のみを利用する場合、1回の面談費用は5,000円から5万円程度が目安です。この方法は、確定申告の基本的な手続きは自分でおこない、わからない点だけを専門家に確認したい方に適しています。
確定申告を1回ごとに依頼できる税理士もおり、この場合の費用相場は10万円〜30万円。アパート経営に関する収入や経費の計算をすべて任せるため、手間を省きたい方に向いています。
さらに、年間を通してサポートを受けられる顧問契約を結ぶケースもあります。顧問契約では、確定申告だけでなく、日常的な経理業務の相談や節税対策などを含めた総合的なアドバイスを受けられる点が特徴。顧問契約の費用は年間20万円〜50万円が一般的です。
なお、税理士の費用はアパートの規模によっても変動します。例えば、所有する部屋数が多い場合や複数のアパートを経営している場合、取引が増える分だけ税理士の作業量も増加するため、料金が高くなる傾向にあります。
依頼前に複数の税理士から見積もりを取り、比較判断することが大切です。
税理士に依頼する際の注意点
税理士に確定申告を依頼する際は、いくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。
最低3社に見積もりを取る
複数の税理士と話をして、比較検討することが重要です。税理士によって得意分野やサポート内容、料金体系が異なるため、事前にしっかりリサーチしましょう。複数の税理士と面談し、それぞれのサービス内容や費用を確認することで、自分に合った税理士を見つけられます。
契約内容と費用を確認する
契約内容と費用は事前にしっかり確認しましょう。顧問契約を結ぶ場合は、どこまでの業務が含まれるのか、追加料金が発生するケースはあるのかなど、細かい部分まで明確にしておくことが大切です。
確定申告の代行のみでなく、日々の帳簿作成や税務相談も含まれるのかどうかも確認し、契約内容と費用のバランスを見極めましょう。
実績を確認する
税理士には得意分野があるため、アパート経営の確定申告に詳しい税理士を選ぶことがポイントです。不動産関連の税務知識が豊富な税理士であれば、経費の計上方法や節税対策などに関しても的確なアドバイスを受けられるでしょう。
税理士と積極的にコミュニケーションを取る
税理士と積極的にコミュニケーションを取ることも、重要なポイントの一つです。自身のアパート経営の状況や経費に関する情報は、正確に伝える必要があります。
場合によっては話しにくいこともあるかもしれませんが、正確な申告をおこなうためには、税理士と信頼関係を築くことが欠かせません。そのため、相談しやすい税理士を選ぶことも、スムーズな確定申告を進めるうえで大切な要素の一つです。
まとめ
アパート経営で収益が出た場合は、基本的に確定申告をしなければなりません。場合によっては確定申告が不要なケースもありますが、その場合でも申告をすることで得られるメリットもあります。
また、確定申告には複雑な手続きが必要な場合もあるため、なかには自分でおこなうことが難しい方もいるでしょう。その場合は税理士に依頼することも一つの手です。費用はかかってしまいますが、節税のアドバイスも受けられ、正しく申告してもらえるメリットがあります。複数回の確定申告を経て、慣れてきたら自分でおこなうとよいでしょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ