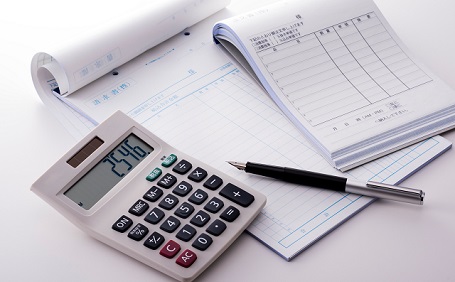不動産投資で不動産取得税がかからないケースとは?オーナーが活用できる軽減措置を解説

軽減措置を利用するためには確定申告が必要なことがほとんどで、不備があれば税務署とのやり取りが増える可能性もあります。適切な書類準備や手続きの知識を深めることで、余分な手間を避けられるでしょう。
今回は、不動産投資を目的として物件を購入した場合の不動産取得税の仕組みや計算方法、軽減制度などを詳しく解説します。
記事の目次
不動産取得税とは
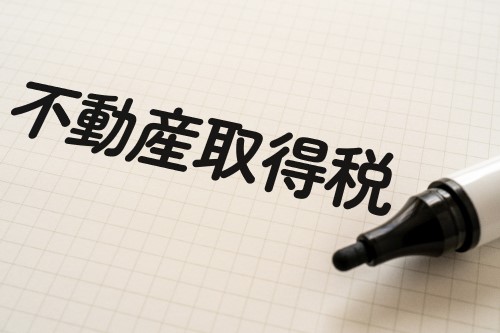
「不動産取得税」とは、土地や建物を購入または取得した際に自治体に納める地方税の一つです。住民税と同様、地域で課される税金であり、不動産取得後に確定申告をおこなうことで最終的な税額が決まります。取得後約1年以内に自治体から納税通知書が送られてくることが一般的です。そのため、自動的に口座から引き落とされるのではなく、自ら県税事務所やコンビニで納税手続きをおこなわなければなりません。
納付方法は自治体によって異なりますが、最近ではクレジットカードや電子マネーなどの支払いが可能な自治体も増えています。納税通知書が届いた際にスムーズに支払えるよう、準備を整えておくことが大切です。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は「取得金額×税率」で計算されますが、取得金額は購入価格ではなく固定資産税評価額が基準になります。たとえ市場価格が安くても、固定資産税評価額が高ければ不動産取得税も高額になるため、注意しましょう。
税率は通常4%ですが、2027年3月31日までに住宅用不動産を取得した場合、3%の軽減税率が適用されます。例えば、固定資産税評価額が500万円の不動産の場合、不動産取得税は15万円となります。
このように、投資用物件の購入を検討する段階で固定資産税評価額を不動産会社から事前に確認し、納税額を把握しておくことは重要なポイントです。
なお、不動産取得税が課される対象として、土地では田畑、住宅地、山林などが、家屋では住宅や店舗、工場、倉庫などが挙げられます。
不動産取得税が免除されるケース

物件価格が手頃であったり、相続で不動産を取得したりしても、予期せぬ税負担が生じれば総コストが想定以上に膨らんでしまいます。安定した不動産経営を始めるためにも、なるべく不動産取得税が発生しない方法を知っておくと便利です。一定の条件を満たすことで不動産取得税がかからない場合があるため、ぜひ参考にしてください。
相続による不動産取得の場合
「土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した場合」に不動産取得税が発生します。しかし、相続で不動産を取得した場合にはこの税金は課されません。つまり、相続による取得であれば納税通知書は届きません。
ただし「相続時精算課税制度」を利用した場合は「贈与」とみなされるため、課税対象となります。そのため、単純な相続でのみ非課税になることを理解しておかなければなりません。また、相続した不動産の評価額が高い場合は、別途相続税が課されるケースもあるため注意が必要です。
不動産取得税の軽減措置制度を利用する場合
国土交通省や総務省では、不動産取得税を軽減するための優遇措置を提供しています。軽減措置制度を活用して、課税標準額から控除額が上回った場合は不動産取得税がかからなくなるケースもあります。相続以外で不動産を取得する場合でも、条件を満たせば軽減措置を受けられるため、事前に制度内容を把握しておきましょう。
投資用物件を新築した場合にも不動産取得税は軽減できる?

不動産投資を始めるにあたって、新築物件の購入を検討される方もいるでしょう。新築物件を購入する際に算出される不動産取得税は、高額になりがちです。しかし、一定の条件を満たした場合には軽減措置が適用され、不動産取得税が0円になるケースもあります。
建物と土地、それぞれに適用される控除内容が異なるため、注意が必要です。まずは新築住宅の条件から見ていきましょう。
建物に対する控除
新築住宅で軽減措置を受けるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 賃貸住宅の場合、課税対象となる床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
- 居住目的で利用される個人住宅であること
上記の条件をクリアすれば、建物の固定資産税評価額から1,200万円の控除が可能です。そのため、建物の固定資産税評価額が1,200万円以下であれば、不動産取得税は発生しません。
評価額が1,200万円を超える場合でも、軽減措置の有無によって支払い額が大きく変わります。
例えば、固定資産税評価額が1,400万円の場合を考えてみましょう。
- 軽減措置を適用しない場合:
1,400万円×3%=42万円 - 軽減措置を適用した場合:
(1,400万円-1,200万円)×3%=6万円
上記のように軽減措置を利用すると、大幅な税負担軽減が可能です。
認定長期優良住宅の場合は1,300万円控除される
機能性や環境性能が優れている認定長期優良住宅の場合、控除額が1,300万円に引き上げられます。認定長期優良住宅は耐震性能や省エネ基準など、一定の条件をクリアした住宅のことを指します。
ただ、認定長期優良住宅として認めてもらうためには、申請手続きをおこなわなければなりません。しかし、認定長期優良住宅になると不動産取得税以外にも登録免許税や固定資産税の控除があるため、総合的な負担軽減につながります。
土地に対する控除
不動産取得税で土地に対する控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。土地を先に取得した場合、取得から3年以内にその土地上に住宅が新築されていることが条件です。 ただし、以下のいずれかに該当する場合に限られます。
- 土地を取得した本人が、新築されるまで継続してその土地を所有している場合
- 取得者が土地を譲渡し、その譲受人が住宅を新築した場合
上記の条件を満たしている場合に限り、特定の優遇措置が適用される可能性があります。
また、土地に適用される軽減措置には、以下の2つがあります。
- 固定資産税評価額が1/2に減額される
- 一定の金額が控除される
上記の軽減措置は併用可能です。ただし、固定資産税評価額が1/2になるのは2027年3月31日までに取得した土地に限られます。
土地に対する不動産取得税は、以下の計算式で算出できます。
(固定資産税評価額×1/2)×3%-軽減額
軽減額の計算には以下の2つの方法があり、高いほうが採用されます。
- 45,000円
- (土地1平方メートルあたりの評価額×1/2)×
(200平方メートルまでの課税床面積×2)×3%
例えば、以下のケースで見てみましょう。
- 土地面積が200平方メートル
- 住宅床面積が150平方メートル
- 固定資産税評価額が1,500万円
土地1平方メートルあたりの評価額は以下のように算出されます。
(1,500万円×1/2)÷200平方メートル
=3万7,000円
次に軽減額を計算しましょう。
3万7,000円×200平方メートル×3%
=22万2,000円
この場合、4万5,000円よりも高いため、22万2,000円が軽減額として適用されます。
- 軽減措置なし:1,500万円×1/2×3%
=22万5,000円 - 軽減措置あり:22万5,000円-22万2,000円
=3,000円
上記のように軽減措置を受けることで、税額が大幅に減ることがわかります。
不動産取得税の軽減措置の申請方法と必要書類

不動産取得後、軽減措置を適用するためには、期限以内に都道府県税事務所へ必要書類を提出する必要があります。申請時に用意する書類は以下のとおりです。
- 不動産取得税減額などの申請書
- 不動産取得を証明する書類(売買契約書や譲渡契約書など)
- 土地および建物の全部事項証明書(登記済みの場合)
- 登記されていない場合は建物の検査済証
- 取得した住所への移転を示す住民票
- 中古戸建住宅の場合は耐震基準適合証明書
- 長期優良認定住宅の場合は認定通知書など
- 建築確認済証や建築確認申請書、または建物請負契約書(猶予が必要な場合)
提出後、税額が軽減されたかどうかは郵送される納税通知書で確認できます。通知書が届いた場合は速やかに内容を確認し、税額に応じて納税をおこないましょう。
支払いは都道府県税事務所の窓口だけでなく、郵便局、銀行、コンビニエンスストア、自治体によってはクレジットカードや電子マネーも利用可能です。
なお、納付書が届かない場合は、税額が0円の可能性があります。しかし紛失も考えられるため、1年経っても通知が届かない場合は、念のため管轄の県税事務所に問い合わせましょう。
軽減措置がある場合の不動産取得税の計算例

以下は、条件別に不動産取得税の計算例を示したものです。軽減措置を適用すると、どの程度税額が変わるのかを確認してみましょう。
<条件>
宅地の購入日:2023年5月1日
宅地の面積:300平方メートル
宅地の評価額:5,000万円
宅地に賃貸用マンションを新築した日:
2023年10月5日
賃貸用マンションの総床面積:500平方メートル
賃貸用マンションの評価額:6,000万円
この建物は、以下のような区画に分かれています(共用部分を含む)
- Aタイプ(40平方メートル):5戸
- Bタイプ(25平方メートル):17戸
新築後1カ月以内に、全区画が賃貸用として利用開始されています。
<家屋に関する税額>
まずは、家屋の税額を計算してみましょう。新築物件における不動産取得税は、賃貸用の場合、床面積が40平方メートル以上なければなりません。そのため、Aタイプの区画は、軽減措置の対象となります。一方、Bタイプの区画は、要件を満たしていないため軽減の対象とはなりません。
まず、Aタイプにおける1戸あたりの評価額を計算します。
6,000万円 × 40平方メートル / 500平方メートル = 480万円
次に、Aタイプにおける1戸あたりの課税標準額を計算します。
480万円 - 1,200万円 ≦ 0円
Bタイプも同じように計算をおこないます。ただし、軽減措置を受けられないため、1,200万円の控除がありません。
6,000万円 × 25平方メートル / 500平方メートル = 300万円
AタイプとBタイプの課税標準額の合計
0円 × 5戸 + 300万円 × 17戸 = 5,100万円
新築物件に対する税額は次の式で求められます。
課税標準額 5,100万円 × 3% = 153万円
<土地に関する税額>
宅地に適用される軽減措置として、評価額の1/2を課税標準額とします。
また、取得から3年以内に新築した家屋が一定の要件を満たしているため、減額措置が適用されます。
課税標準額
5,000万円 ×1/2= 2,500万円
軽減措置を適用する前の税額
2,500万円 × 3% = 75万円
減額される額
※ 4万5,000円 または 以下の計算による額 のいずれか大きいほうが適用されます。
土地1平方メートルあたりの価格:2,500万円 ÷ 300平方メートル = 約8万3,000円
住宅の床面積の2倍(200平方メートルを上限として計算)
- Aタイプの床面積の2倍(40平方メートル × 2) × 5戸 = 400平方メートル
- 共同住宅などの場合、適用可能な面積は200平方メートルまで
したがって、
8万3,000円 × 200平方メートル × 3%
= 49万8,000円(減額額)
最終的な税額
75万円 - 49万8,000円 = 25万2,000円
最終税額は次のとおりです
- 家屋:153万円
- 土地:25.2万円
- 合計:178.2万円
上記のように、新築した賃貸用マンションに関する不動産取得税は、軽減措置を適用した結果、178.2万円となります。
投資用物件の不動産取得税に関する注意点

軽減措置の申請は、不動産取得税の申告と同時におこないます。不動産取得から地方自治体によって定められた期日以内に県税事務所で手続きをおこなうことが求められます。未登記の場合などは申告期限を延長できる場合もあるため、個別のケースに応じた対応が必要です。
ハウスメーカーや司法書士など専門家に相談し、必要書類を整えたうえで期限内に手続きを進めていきましょう。
申告期限は定められていますが、正当な理由がある場合、期限を過ぎても申告が認められることがあります。海外在住ややむをえない事情がある場合は、郵送での申請も可能です。
一方、正当な理由がない場合、申告漏れとして過料が科される場合もあるため、期限を意識した対応を心がけましょう。期限が過ぎてしまったことに気付いた場合は、速やかに各都道府県の所轄税事務所へ相談することが大切です。
まとめ
不動産投資で投資用物件や土地を購入する際には、さまざまな税金がかかります。そのなかの一つに「不動産取得税」がありますが、軽減措置を適用すれば、税金の負担が軽くなる場合があります。しかし、軽減措置を適用する際にはある一定の条件を満たさなければなりません。軽減措置を受けるかどうかで、不動産経営の収支計画に与える影響も大きく変わります。不動産投資を始める際には、事前によくシミュレーションしておきましょう。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ