家賃を値上げするための正当な理由とは?値上げ相場や交渉を成功させるためのポイントを押さえよう

そこで本記事では、家賃を値上げするための正当な理由として認められるものや、家賃の値上げ相場、交渉を成功させるためのポイントなどを解説します。家賃の値上げに対する入居者の理解を得られなければ、退去につながる可能性もあります。お互いが納得したうえで交渉を進められるよう、ポイントを押さえておきましょう。
記事の目次
家賃の値上げに関する法律
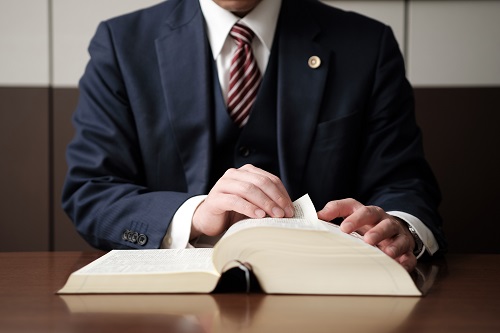
借地借家法の第32条では、家賃の値上げに関する「借賃増減請求権」が、次のように定められています。
第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
引用: 借地借家法第三十二条
どのような内容なのか、わかりやすく解説します。
一方的な家賃の値上げはできない
まず、オーナーから一方的に、家賃の値上げができない点を理解しておきましょう。借地借家法の第32条では、「将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」と定められています。つまり、家賃値上げの請求はできますが、変更ができるわけではありません。また、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」にも、「協議の上、賃料を改定することができる」と明記されており、オーナーからの一方的な値上げは想定されていません。入居者からの同意が得られなければ、家賃の値上げができないことを押さえておきましょう。
入居者を強制的に退去させることはできない
入居者が家賃の値上げを拒否したからといって、強制的に退去させることはできません。借地借家法では、入居者の権利が保護されており、正当な理由なく退去を求めることは難しくなっています。実際に借地借家法の第28条では、次のように定められています。
第二十八条
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
引用: 借地借家法第二十八条
オーナーから入居者に立ち退きを要求するためには、正当な理由が必要となります。正当な理由として認められるケースは、次のとおりです。
- 老朽化した物件を建て替える場合
- 行政による再開発計画がある場合
- 入居者に重大な契約違反がある場合
これらの場合は入居者に立ち退きを要求できます。家賃の値上げは入居者の同意がなければできないため、拒否したからといって、強制的に退去させることはできない点を理解しておきましょう。
家賃の値上げが認められる正当な理由

家賃の値上げが認められるためには、正当な理由が必要です。どのような理由が認められるのか、第32条で取り上げられていた3つの理由を見ていきましょう。
物件や土地の評価額が上昇した
賃貸用物件や土地の評価額が上昇した場合、家賃の値上げを請求する正当な理由として認められます。借地借家法の第32条で定められている借賃増減請求権でも「地価の上昇」と触れられていました。土地の価格が上昇する要因として、周辺地域の開発やインフラの整備などが挙げられます。
これらによって賃貸用物件の利便性や魅力が高まることで、物件や土地の評価額が上昇。これらの評価額が上昇すると、固定資産税や都市計画税などの税負担も増えることから、家賃の値上げも正当な理由として認められます。実際に、国土交通省の「令和6年地価公示の概要」によると、住宅地は全国で2%、東京圏では3.4%上昇しています。
物件の維持費用が増えた
賃貸用物件の維持費用が増えたことも、家賃の値上げが認められる正当な理由です。先ほど、土地の評価額の上昇によって、固定資産税や都市計画税が上がることが、値上げする正当な理由として認められることを解説しました。しかし、維持費用は税金だけではありません。他にも、不動産投資ローンや共用部分の光熱費、修繕費などさまざまな費用がかかります。2025年1月現在、物価の上昇により、資材価格や人件費が高騰。これにより物件の維持費用も増えていることから、家賃を値上げする正当な理由として認められるでしょう。
周辺物件の相場よりも安い
賃貸用物件の家賃が周辺物件の相場よりも安い場合、値上げする正当な理由として認められます。これまで見てきたように、地価の上昇や維持費用の高騰などが家賃を値上げする正当な理由として認められます。当初は周辺物件と同等の家賃を設定していても、周りが家賃を上げていた場合、いつの間にか相場より下回っている可能性も。賃貸需要が高いにも関わらず、見直しをしなかった場合は該当するかもしれません。今一度、周辺物件の相場はどれくらいなのかを調べてみましょう。
家賃の値上げが認められないケース

家賃の値上げが認められる正当な理由を3つ解説しました。しかし、あくまで例であり、紹介した理由以外でも正当な理由として認められる可能性があります。一方、値上げが認められないケースもあります。具体的に3つのケースを解説します。
オーナーの経済的な都合による場合
オーナーの経済的な都合を理由とした場合、値上げは認められません。第32条の条文を見ると、賃貸用物件を取り巻く客観的な状況の変化に基づいて、家賃の増減を認めていることがわかります。そのため、「生活費が不足している」「投資で損失を出した穴埋めをするため」などのオーナーの個人的な都合による値上げは、認められません。
相場とかけ離れた値上げをする場合
相場とかけ離れた値上げをする場合も、正当な理由として認められません。賃貸用物件の家賃が周辺の相場よりも下回っている場合、値上げをする正当な理由として認められます。しかし、相場以上に値上げをすることは認められておらず、入居者の理解も得られないでしょう。
2024年6月には大阪にあるマンションで、相場が10万円にも関わらず、18万円に値上げするという通知が入居者に届いたことがニュースになりました。これまでの家賃の2倍であったことから、多くの入居者から反感を買うことに。家賃の値上げをする際には、入居者の理解を得られるよう客観的なデータを示し、受け入れられる金額に設定することが重要です。
賃貸借契約書に値上げをしないことを明記している場合
賃貸借契約書に、「値上げをおこなわない」と明記している場合、契約期間中の値上げはできません。借地借家法の第32条1項にも「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」と定められています。もし、賃貸用物件の家賃が周辺物件より低くても、特約が記載されている場合は、家賃の値上げはできません。
家賃の値上げをした時に考えられるトラブル

家賃の値上げをする場合、さまざまなトラブルが考えられます。事前にトラブルを知っておけば、適切な対策を講じることができます。本章では、家賃の値上げをした時に考えられるトラブルを見ていきましょう。
値上げを拒否されてしまう
家賃の値上げをする時に考えられるトラブルの一つは、値上げを拒否されてしまうことです。家賃の値上げは入居者にとって、生活費の増加につながります。特に家賃は生活費のなかでも大きな割合を占めるため、値上げはできるだけ避けたいもの。値上げの理由が不明確であったり、相場とかけ離れている場合は、拒否される可能性が高くなるでしょう。
解約されてしまう
値上げを理由に賃貸借契約を解約されてしまうことも、考えられるトラブルの一つです。特に値上げ幅が大きい場合や周辺物件と比較して割高になる場合、入居者はよりいい条件の物件への住み替えを考えるでしょう。また、値上げに対する説明が不足していると、入居者は不安や不満を抱き、引越しを考えることも。空室が出れば、その分家賃収入は減少してしまいます。家賃の値上げは、入居者の理解を得られる範囲の金額で、理由とあわせて丁寧に説明することが大切です。
家賃の支払いを拒否されてしまう
家賃の値上げをする時に考えられるトラブルに、家賃の支払いを拒否されてしまうことが挙げられます。入居者が値上げに納得していない場合や、経済的な事情で支払いが困難になった場合、支払いを拒否されてしまう可能性があります。借地借家法の第32条では、借賃増減請求権が認められていますが、あくまで請求できる権利です。承諾を強制するわけではないため、値上げに同意しない場合、入居者が値上げした分の家賃を支払う義務はありません。
しかし、家賃そのものを支払わずに長期間滞納した場合は、入居者の契約違反となります。この場合は督促や法的な措置を取り、家賃の支払いを請求することが可能です。ただし、手間や費用がかかるため、できるだけ避けたいところでしょう。
連絡なく退去されてしまう
連絡なく退去されてしまうことも、家賃を値上げした時に考えられるトラブルです。特に、家賃の滞納を頻繁にしたり、経済的に困窮している場合、値上げによって生活が苦しくなり、連絡なく退去するおそれがあります。
入居者からの連絡なく退去された場合、家賃の回収は極めて困難になります。また、空室が発生するため家賃収入も減少。さらに、原状回復費用やクリーニング代など、さまざまな費用がかかります。トラブルを防ぐために、入居時の審査を慎重におこない、信頼できる入居者に入居してもらうことが重要です。
家賃の値上げ相場

家賃の値上げはどれくらいが適正なのか、悩まれることでしょう。周辺物件の相場に合わせても、値上げ幅が大きければ、入居者からの反感を買ってしまうかもしれません。
全国賃貸住宅新聞の調査によると、「家賃の値上げをおこなった」と回答した管理会社は51.7%。平均値上げ額は「1,000円〜3,000円未満」が63.6%、つづいて「3,000円〜5,000円未満」が28.6%となっています。入居者に負担を感じさせないよう、値上げ幅が設定されていることがわかるでしょう。
家賃の値上げを交渉する際の手順

家賃の値上げをしたい時、どのように進めればよいのでしょうか。まずは簡単な流れを見ていきましょう。
- STEP 1入居者に通知をする
- STEP 2入居者と交渉する
- STEP 3承諾を得られたら合意書を結ぶ
それぞれ詳しく解説します。
STEP 1. 入居者に通知をする
まず、入居者に値上げすることを通知しましょう。法律上では、通知時期について特に定められていません。しかし、急な通知は入居者にとって経済的や精神的な負担となるため、早めにおこないましょう。通知をする際は、内容証明郵便を利用します。内容証明郵便とは、「いつ、誰が、どのような内容で送ったか」を郵便局が証明するもの。通知した事実を確実に残し、入居者からの「知らない」「聞いていない」といったトラブルを防ぎましょう。
STEP 2. 入居者と交渉する
家賃の値上げは、入居者の同意がなければできません。おそらく、値上げに対して拒否感を示す入居者が多いでしょう。そこで、入居者と交渉をおこない、双方による合意を目指します。入居者からの理解が得られるよう、「なぜ値上げをするのか」理由を客観的に示すことが大切です。また、オーナーの意見のみを通すのではなく、入居者の意見にも耳を傾けましょう。
STEP 3. 承諾を得られたら合意書を結ぶ
家賃の値上げに対して承諾を得られたら、合意書を結びましょう。口頭だけではのちにトラブルになる可能性が高いため、書面で内容を明確にしておくことが重要です。合意書には、オーナーと入居者の住所、氏名、新しい家賃の適用開始日などを記載します。
承諾を得られない場合の対処法
入居者からの承諾を得られない場合は、法的な手続きを取らなければなりません。選択肢としては、「調停」と「訴訟」の2つがあります。調停とは、第三者である調停委員を挟んでおこなう話し合いのこと。第三者が入ることで、オーナーと入居者だけでは進まなかった話し合いも、スムーズに進むことがあります。「家賃の値上げをするか、しないか」よりも「どれくらいの値上げなら受け入れられるのか」という値上げ幅が話し合いの焦点になります。調停でもまとまらなかった場合、訴訟を起こすことに。訴訟となると、手間も費用もかかるため、できるだけ話し合いでの解決を目指したほうがいいでしょう。
家賃の値上げを成功させるためのポイント

家賃の値上げは入居者の家計に大きな影響を与えるため、慎重におこなわなければなりません。また、承諾を得られなければ値上げはできないため、丁寧に説明する必要があります。本章では、家賃の値上げを成功させるためのポイントを解説します。
値上げの理由を説明する
入居者の理解を得るためにも、値上げの理由を説明しましょう。「値上げします」と事実を伝えるだけでは、入居者からの反発を招きやすくなります。なかには不信感を抱き、退去を検討する入居者もいるかもしれません。入居者が納得できるよう、客観的な資料に基づいて、値上げが必要な理由を説明することが大切です。具体的なデータの例としては、周辺地域の家賃相場や土地の価格が上昇しているデータなどが挙げられます。
入居者にメリットがある条件を提示する
入居者にメリットがある条件を提示することも、家賃の値上げを成功させるためのポイントです。家賃を値上げするだけでは、入居者の経済的な負担が大きくなるデメリットのみになってしまいます。そこで、入居者にとってメリットがある条件を提示することで、家賃の値上げを受け入れてもらいやすくなります。例えば、次のような条件は、入居者にとってメリットがあるでしょう。
- エアコンやWi-Fi設備を新しくする
- 防犯カメラや宅配ボックスを設置する
- 更新料を無料にする
ただ値上げするよりも、入居者の満足度を高めることで、より長期的な入居が期待できます。新しい入居者を確保するよりも、現在の入居者に長く住んでもらうほうが、手間やコストの面でもメリットが大きくなります。家賃の値上げをする際は、入居者にメリットがある条件を提示しましょう。
入居者が受け入れやすい家賃に設定する
家賃の値上げを成功させるためには、入居者が受け入れやすい家賃に設定することが大切です。先ほども例に挙げた大阪のマンションでは、相場よりも大幅に高い家賃が設定され、入居者からの反感を招いていました。周辺地域の家賃相場や入居者の負担を考慮したうえで、適切な家賃設定をおこないましょう。
まとめ
本記事では、家賃の値上げをするための正当な理由を解説しました。家賃を値上げするためには、土地や賃貸用物件の評価額が上がっていること、物件の維持費用が増えていること、周辺物件の相場よりも安いことが正当な理由として認められます。法律で認められている権利は、あくまで家賃の値上げを請求できる権利であり、入居者からの承諾なしに変更できるわけではありません。客観的なデータを示したり、入居者にとってメリットのある条件を提示することで、値上げを受け入れてもらいやすくなるでしょう。オーナーから一方的に話すのではなく、入居者の意見にも耳を傾け、双方が納得できる条件で合意を目指しましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ



