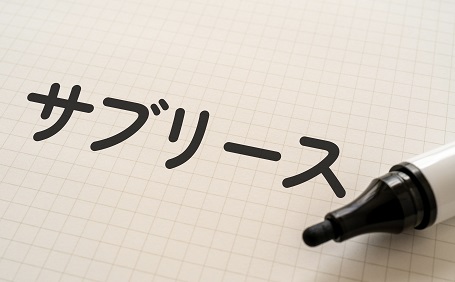不動産経営における委託管理とは?サブリースとの違いや費用相場を解説

そこで本記事では、委託できる業務や委託管理費用の相場、また委託するメリット・デメリットなどを解説します。不動産経営で安定した収益を得るためにも、適切な管理は欠かせません。ポイントを押さえ、効率よく安定した不動産経営をおこないましょう。
記事の目次
不動産経営における委託管理の種類

不動産経営において、管理会社に管理業務を委託することは一般的です。実際に、国土交通省の「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によると、すべて自ら管理しているオーナーは2割程度となっています。なお、このデータはサブリース以外の契約方法に限られます。それでは、具体的に委託管理には、どのような種類があるのか、サブリースとはどのような契約なのかも含めてみていきましょう。
一般管理契約
一般管理契約とは、不動産経営で必要な管理業務を、オーナーの代わりに管理会社がおこなう契約形態です。専門知識や経験が豊富な管理会社に委託することで、オーナーは安定した家賃収入を得ながら、手間をかけずに不動産経営が可能に。
なお、先ほど取り上げた国土交通省のデータによると、入居者募集から契約、それ以降の管理も委託しているオーナーの割合は28.2%となっており、3人に1人はすべての業務を委託していることがわかります。また、管理業務をすべて委託することを「全部委託管理」、一部の業務を委託することを「一部委託管理」といいます。
サブリース契約
サブリース契約とは、オーナーが所有する収益物件をサブリース会社が借り上げ、第三者に貸し出す契約のことです。サブリース契約には、「賃料保証型」と「パススルー型」の2種類があります。賃料保証型とは、空室や家賃滞納が発生しても、一定の家賃収入を得られるもの。一方、パススルー型とは、回収した家賃に応じてオーナーの得られる家賃収入が変動します。管理業務を委託できるだけでなく、一定の家賃収入を得られることから人気を集めています。
特に賃料保証型では、空室リスクが軽減されるため、注目が高くなっています。しかし、借地借家法によってサブリース会社の権利が守られるため、契約当初の家賃保証額が減額される可能性や、オーナーからの解約が難しいなどのデメリットがある点に注意しましょう。
一般管理契約とサブリース契約の違い
一般管理契約とサブリース契約をそれぞれ解説しました。管理業務を委託できる点は共通していますが、細かいところを比較すると違いがあります。より理解を深めるために、違いを押さえておきましょう。下表は一般管理契約とサブリース契約の違いをまとめたものです。
| 一般管理 | サブリース | |
|---|---|---|
| 入居者との契約 | オーナー | サブリース会社 |
| 家賃保証 | なし | あり |
| 更新料・礼金 | 受け取れる | 受け取れない |
| 契約期間 | 2年が多い | 2・10・20・30年など |
| 委託管理費用の相場 | 賃料の約5% | 賃料の10〜20% |
まずは、入居者との契約主体が異なります。一般管理契約では、オーナーが入居者と契約する一方、サブリース契約ではサブリース会社と契約します。また先述したように、サブリース会社との契約内容によっては家賃が保証されますが、一般管理契約では保証されません。そのため、入居者が決まらず空室になった場合、家賃収入が減少するおそれがあるでしょう。
更新料や礼金は、サブリース会社が入居者と契約しているため、オーナーは受け取れません。一方、一般管理契約ではオーナーが受け取れるため、家賃収入に含めることができます。さらに、一般管理契約とサブリース契約では契約期間も異なります。一般管理契約では2年ごとに更新することが一般的。しかし、サブリース契約では、2年・10年など、サブリース会社との契約内容によって異なります。
最後に、委託管理費用の相場も異なっており、一般管理契約のほうがサブリース契約より低くなっています。そのため、サブリース契約より手元に残せる収益が多くなる可能性も。
5つの観点で比較すると、2つの違いがよくわかるのではないでしょうか。違いをよく理解したうえで、検討しましょう。
管理会社に委託できる業務

管理会社に委託できる業務には、どのようなものがあるのでしょうか。本章では、入居者への対応業務と建物の管理業務の2種類に分けて解説します。
入居者への対応業務
入居者への対応業務とは、入居者と直接関わる業務のことです。具体的には次のようなものがあります。
- 入居者の募集・契約
- 家賃の回収
- トラブル・クレーム対応
それぞれ詳しく見ていきましょう。
入居者の募集・契約
安定した家賃収入を得るためには、入居者を確保し、高い入居率を維持しなければなりません。入居者を確保するために、不動産ポータルサイトに物件情報を掲載したり、入居希望者に対して内見対応などをおこないます。入居者の募集から契約までをスムーズに進められれば、空室期間を短縮でき、安定した家賃収入が見込めるでしょう。
家賃の回収
家賃の回収も業務の一つです。もし家賃滞納が起こった時には、督促や場合によっては法的な対応などをおこないます。知識や経験のないオーナーが対応するとなると、誤った対応をしてしまう可能性や、経済的・精神的な負担が大きくなるおそれがあります。専門知識や実績のある管理会社に委託することで、適切な対応が期待できるでしょう。
トラブル・クレーム対応
入居者のトラブルやクレーム対応も、入居者の満足度を高めるために欠かせません。例えば、トイレの水漏れや給湯器の故障など、迅速かつ適切に対応することで、入居者の満足度を向上できます。もし対応が遅れたり、誤った対応をしてしまうと、入居者が不満を募らせ、退去につながるおそれもあります。迅速かつ適切な対応によって、入居者の満足度を高められ、長期的な入居を見込めるでしょう。
これらの業務をオーナーが一人で負担するとなると、多くの時間や労力が必要です。信頼できる管理会社に委託することで、オーナーの負担を軽減しながら、安定した不動産経営の実現が可能となります。
建物の管理業務
収益物件の老朽化を遅らせ、資産価値を維持するために重要な建物の管理業務。例えば、次のような業務が該当しますが、これらも管理会社に委託できます。
- 定期的な清掃
- 建物の維持・管理
- 設備の維持・管理
- 修繕計画の策定
それぞれ詳しく解説します。
定期的な清掃
定期的な清掃は、入居者の満足度を高めるだけでなく、入居希望者からの印象をよくすることができます。具体的には、エントランスや廊下、階段など、共用部分の清掃をおこなうことで、清潔感を保てます。また、定期的に清掃をすると、建物や設備の劣化に早く気付ける可能性も。早期に発見し、適切な対応ができれば、故障などのトラブルも防げるでしょう。
建物の維持・管理
建物を適切に維持・管理することによって、老朽化を遅らせ、資産価値を維持しやすくなります。収益物件の価値を高く維持できれば、将来的に高い価格で売却できるかもしれません。また、不具合を放置したままにしていると、のちに大きなトラブルが発生するおそれがあります。
例えば、2020年には北海道の築古アパートで、2階の外廊下の床が崩落する事故が発生。女性4人と乳児1人が重軽傷を負いました。管理会社とオーナーの認識に差があり、管理会社は改修を勧めていたものの、オーナーはあと回しにしていたとのこと。このように、適切な管理をおこなわなければ、命に関わる事故が発生するおそれがあります。知識や実績の豊富な管理会社に委託し、適切な判断をすることで、入居者に安心な住環境を提供できるでしょう。
設備の維持・管理
電気設備や給排水管、消防設備などの設備の維持・管理も、入居者が安心・安全に暮らすために必要なものです。設備によっては、適切に維持・管理されているかを確認するために、法律によって点検が義務付けられている「法定点検」を実施しなければなりません。収益物件の規模や構造によって、必要な点検は異なります。国土交通省のホームページでは、築年数から必要な修繕や点検をチェックできる簡易診断が用意されています。ぜひ活用して、該当するものがないかを確認してみましょう。
修繕計画の策定
収益物件を長期的かつ良好に維持管理するために、修繕計画の策定も管理業務の一つです。建物は築年数が経つと、周辺に新しい物件ができたり、見た目が劣化したりなどで、競争力が低下してしまいます。競争力が低下すると、家賃を下げざるをえなかったり、空室が増加するおそれもあります。適切な時期に修繕をおこなうことで、建物の資産価値を維持しやすくなるでしょう。
国土交通省の「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」によると、階段や廊下の鉄部塗装は4〜10年目、給排水管の高圧洗浄は5年目からとされています。入居者にとって安心でき、満足度の高い住環境を提供するためにも、計画を策定し、適切な修繕をおこないましょう。
不動産経営において委託管理するメリット

不動産経営における管理業務を委託することで、どのようなメリットがあるのかを解説します。
管理の手間が省ける
委託管理するメリットの一つは、管理の手間が省けることです。これまで見てきたように、不動産経営における管理業務は多岐にわたります。これらの業務をすべてオーナーでおこなうには、時間と労力がかかり、専門的な知識も必要です。また、仕事が忙しい方や、所有している収益物件が遠方にある方などは、不動産経営に充てる時間を確保することが難しいでしょう。専門的な知識や経験のある管理会社に委託することで、オーナーの負担が軽減され、安定した不動産経営ができます。
遠方の物件も管理できる
管理業務を委託することで、遠方にある収益物件を管理できる点もメリットです。オーナー自身が管理業務をおこなう場合、清掃やトラブル・クレーム対応などで、所有する物件に定期的に出向かなければなりません。そのため、収益物件が遠方にある場合、なかなか足を運ぶことができず、適切な管理が難しくなります。
しかし、収益物件に近い管理会社に委託することで、トラブルやクレーム対応も迅速に対応でき、入居者の満足度を高められるでしょう。また、管理会社から定期的に収益物件の状況を報告してもらうことで、状況を把握しやすくなり、安定した不動産経営が可能となります。
入居者の満足度が向上する
入居者の満足度が向上する点も、管理業務を委託するメリットの一つです。先述したように、不動産経営における管理業務はさまざまです。法律などの専門知識や、取引先とのつながりが必要になることもあります。例えば、給湯器が故障した場合。管理会社であれば、これまでの経験からすでに取引のある会社に、修理の依頼がすぐにできるでしょう。
しかし、初めて不動産経営をするオーナーの場合、どのような会社があるのか、相場はどれくらいなのかなど、情報収集から始めなければなりません。設備の故障は、入居者の生活に影響を与えるため、迅速な対処が必要です。時間がかかってしまうと入居者の不満を募らせてしまい、退去につながる可能性もあります。専門的な知識や実績の豊富な管理会社に委託することで、入居者の満足度を高められ、長期的な入居につながり、安定した不動産経営ができるでしょう。
初心者でも不動産経営ができる
管理会社に管理業務を委託するメリットとして、初心者でも不動産経営ができる点が挙げられます。管理会社は、不動産経営に関する豊富な経験があり、知識を持っています。そのため、収益物件の選定や賃貸契約、家賃交渉など、さまざまな場面で的確なアドバイスを受けられるでしょう。また、不動産経営は不動産市場の動向や税制などにより、大きな影響を受けます。管理会社であれば最新情報を把握し、状況に応じたアドバイスをしてくれるでしょう。
ただし、管理会社に任せきりにするのではなく、オーナー自身でも知識を身に付け、判断することが大切です。不動産経営を始める際には、複数の管理会社を比較し、信頼できる会社を選ぶようにしましょう。
不動産経営において委託管理するデメリット

さまざまな管理業務を委託することで、オーナーの負担を軽減できる点はメリットといえるでしょう。しかし、メリットばかりではありません。本章では、不動産経営において委託管理をするデメリットを解説します。
委託管理費用がかかる
管理業務を管理会社に委託するデメリットとして、委託管理費用がかかる点が挙げられます。繰り返しになりますが、管理業務は入居者の募集や契約、建物の維持管理など幅広くなっています。これらの業務に対する対価として、委託管理費用がかかります。委託管理費用は毎月かかる費用であるため、コストを踏まえたうえで、収支計画を立てなければなりません。同じサービス内容でも、管理会社によって委託管理費用が異なる可能性があるため、複数の管理会社に見積もりを取るようにしましょう。
仲介手数料がかかる
仲介手数料がかかることも、管理会社に管理業務を委託するデメリットの一つです。仲介手数料は、入居者の募集から賃貸借契約の締結までのサポートに対する成功報酬のこと。集客力のないオーナーが自力で入居者を見つけることは難しいでしょう。必要経費ととらえ、集客力のある管理会社に委託することで、空室期間を短縮できる可能性が高まります。
管理会社の能力によって不動産経営が左右される
管理業務を管理会社に委託する場合、管理会社の能力によって、不動産経営の成功が左右されるというリスクがあります。管理会社によって、サービスの品質は異なります。また、得意とする地域や物件も異なるでしょう。
もし不適切な管理会社に委託した場合、入居者が集まらず空室が続き、不動産経営のキャッシュフローが悪化する可能性も。また、建物の管理が適切でなければ、入居者が退去してしまい、さらに経営状況が悪化するおそれもあります。このように、管理会社の能力は、不動産経営に大きな影響を与えるため、信頼できる管理会社を選ぶことが大切です。
物件の状況が把握しにくくなる
不動産経営において管理業務を委託すると、物件の状況が把握しにくくなる点がデメリットです。自主管理の場合、自ら収益物件に赴くため、入居者や建物、設備の状況が把握しやすくなります。しかし、委託する場合、管理会社からの報告が遅れたり、必要な情報が漏れてしまうおそれも。また、先ほど取り上げた事故のように、管理会社からアドバイスを受けていても、物件の状況を把握していないため、適切な対応ができない可能性もあります。
物件の状況を適切に把握することは、入居者の満足度を高め、安定した不動産経営をおこなうためにも欠かせません。また、収益物件の資産価値を維持するためにも重要です。管理会社に任せきりにするのではなく、オーナー自身もできるだけ足を運ぶようにしましょう。
自主管理に移行しづらくなる
管理会社に管理業務を委託すると、自主管理に移行しづらくなるデメリットがあります。長期間委託していると、オーナーの知識や経験が不足するおそれがあります。また、管理会社が独自のシステムを採用している場合、他の管理会社や自主管理への移行に手間がかかる可能性もあるでしょう。他にも、管理会社と入居者との間に良好な関係が築かれている場合、自主管理に移行することで、不安を抱く入居者もいるかもしれません。将来的に自主管理を考えている場合は、必要な知識やスキルを身に付けるようにしましょう。
不動産経営において委託管理する際にかかる費用と相場

管理業務を委託する際には、委託管理費用がかかります。毎月かかる費用のため、余裕を持った収支計画を立てる際に、把握しておかなければなりません。相場はどれくらいなのかを見ていきましょう。
委託管理費用の相場
管理業務を管理会社に委託する際には、委託管理費用が発生します。一般的に、委託管理費用の相場は家賃収入の5%程度とされています。例えば、家賃収入が20万円の場合には、1万円程度です。また、集金管理のみを委託することも可能。この場合の相場は、家賃収入の3%程度です。集金管理を委託できるため、家賃滞納が発生した場合、督促も代行してくれます。委託管理費用は管理会社や業務範囲によって異なるため、事前に見積もりを取るようにしましょう。
仲介手数料の相場
先述したように、仲介手数料とは、入居者の募集から賃貸借契約締結までの業務に対する成功報酬として支払うものです。宅地建物取引業法によって、下記のように上限が決められています。
仲介手数料の上限 = 家賃の1カ月分 + 消費税
入居者もしくはオーナーが全額負担するケース、入居者とオーナーが折半するケースがあります。折半する場合、それぞれの負担は家賃の0.5カ月分が上限となります。なお、上限は定められていますが、下限については特に定められていません。そのため、仲介手数料は交渉できる可能性があります。管理業務と仲介業務を兼務している管理会社の場合、交渉してみるとよいでしょう。
不動産経営で委託管理会社を選ぶ際のポイント

不動産経営において必要な業務は幅広く、安定した経営をおこなうためにも、管理の質は重要です。本章では、管理業務を委託する管理会社を選ぶ際のポイントを解説します。
複数の管理会社を比較検討する
管理会社を選ぶ際は、一社に絞らず、複数の管理会社を比較検討しましょう。それぞれの管理会社のサービス内容や費用を比較することで、最適な会社を見つけることができます。管理会社によって、得意とする業務内容や地域・物件の種類などは異なります。手間はかかりますができるだけ時間をかけ、複数の管理会社を訪問しましょう。また、これまでの実績や評判、対応のよさも確認しましょう。
委託管理費用が適切な会社を選ぶ
管理会社を選ぶ際には、委託管理費用が適切かを見極めましょう。先述したように、相場は家賃収入の5%程度。しかし、なかにはサービス内容に見合わない金額を設定している可能性もあります。費用が高すぎると、キャッシュフローが悪化するおそれも。複数の管理会社に見積もりを依頼し、サービス内容に見合った金額になっているか、比較検討しましょう。また、委託管理費用のなかに、どのような費用が含まれているのかも確認しましょう。
集客力がある管理会社を選ぶ
集客力がある管理会社を選ぶことも、チェックポイントの一つです。集客力が高い管理会社を選ぶことで、空室期間を短縮でき、安定した不動産経営が可能となります。具体的には、次のポイントをチェックしてみましょう。
- 築年数や立地が近い物件の入居率
- 不動産ポータルサイトの掲載情報
保有している物件と立地や築年数の近い物件が高い入居率を維持できていれば、安定した不動産経営を実現できる可能性が高いでしょう。また、不動産ポータルサイトに、物件情報がどのように掲載されているのかも確認しておきましょう。写真が多かったり、コメントがわかりやすいと、入居希望者から見ても印象がよく、入居者を確保しやすくなります。安定した不動産経営をおこなうために、集客力がある管理会社を選びましょう。
業務範囲が十分かを確認する
管理会社を選ぶ際には、業務範囲が十分かを確認するようにしましょう。先述したように管理には「全部委託管理」と「一部委託管理」の2種類があります。例えば、「家賃回収のみをおこなう」「修繕計画の策定はおこなっていない」など、管理会社によってサービス内容は異なります。自分が委託したい業務内容を明確にし、それらをカバーしてくれる管理会社を選びましょう。
管理物件の戸数が多い会社を選ぶ
管理物件の戸数が多い会社を選ぶことも、管理会社を選ぶ際のポイントです。管理物件が多ければ、豊富な経験があり、ノウハウも蓄積されていると考えられます。そのため、さまざまなケースに対応でき、安定した不動産経営がおこなえるでしょう。また、スタッフの多さも確認しておきましょう。スタッフの数と管理戸数が見合っていればトラブルやクレームの発生時にも迅速な対応ができ、入居者の満足度を高められます。
なお、管理物件の戸数が200以上の場合は、賃貸住宅管理業者の登録が義務付けられています。登録されている管理会社は国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索できるため、気になる管理会社があれば、調べてみるといいでしょう。
まとめ
本記事では、不動産経営における委託管理の種類を解説しました。委託管理契約には、一般管理契約とサブリース契約の2種類があります。一般管理契約は、管理会社がオーナーに代わってさまざまな管理業務をおこなうもの。しかし、管理会社によって、業務内容や委託管理費用は異なります。安定した不動産経営を実現させるためには、質の高い管理が不可欠です。信頼できる管理会社を選ぶために、複数社を比較検討し、最適な会社を見つけましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ