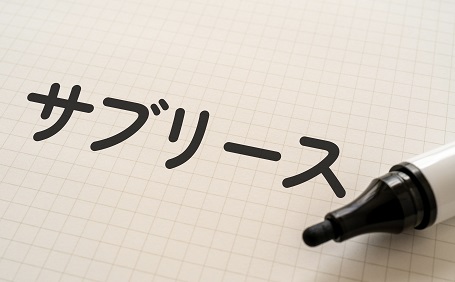家賃保証とサブリースの違いは?長所・短所と効果的な使い分けを徹底解説!

本記事では、家賃保証とサブリースの違いや、それぞれの長所と短所、使い分けのポイントと管理を委託する会社を選ぶポイントを解説します。毎月の家賃収入を安定的に得るための手法を検討している方は必見です。
記事の目次
家賃保証とサブリースの違いは?

家賃保証とサブリースと聞くと、どちらも空室になった時の家賃を保障してくれるものと思う方がいらっしゃるでしょう。本章では、家賃保証とサブリースの違いを、双方の仕組みから解説します。まずは、それぞれの違いを確認してみましょう。
| 家賃保証 | サブリース | |
|---|---|---|
| 家賃収入 | 滞納が発生した時に補填 | 空室有無に関わらず 一定の家賃収入あり |
| 契約 | 保証会社と締結 | サブリース会社 (不動産管理会社) と締結 |
| 物件管理・入居者募集 | オーナーが実施 | サブリース会社 (不動産管理会社) が代行 |
続いて、双方の仕組みを解説します。
家賃保証の概要
家賃保証とは、入居者が家賃を滞納した場合に備えて、家賃保証会社が代わりに家賃を支払う仕組みです。家賃を保証するための保証料は、入居者が支払います。家賃保証は、連帯保証人を立てる代わりとして利用されるケースや、不動産会社が入居者に対して、特定の保証会社の加入を入居条件として指定する場合もあります。
保証会社は入居者に対して、通常の入居審査と同等、またはそれ以上に厳しい審査をおこないます。これは、家賃を確実に回収するための対策です。家賃保証を利用する入居者に対し身分証や収入を証明できる書類等を求め入居者の信用力を審査します。審査に通過しなければ、入居者は家賃保証サービスを利用できず、不動産会社と賃貸契約を結べません。はじめからリスクの高い入居者は除外でき、家賃滞納のリスクを減らせます。
サブリースの概要
サブリースは、不動産管理会社がオーナーから賃貸物件を一括で借り上げ、それを入居者に転貸する仕組みです。このシステムでは、入居・退去の対応や物件管理などの業務はすべて管理会社がおこないます。オーナーは入居率や家賃滞納に関わることがなくなり、かつ安定した家賃収入を得られるでしょう。なお、サブリースには大きく分けて賃料保証型とパススルー型の2種類があります。
賃料保証型
賃料保証型のサブリースでは、管理会社がオーナーから賃貸物件を借り上げる点は同じですが、入居者の家賃滞納や空室が発生しても、家賃収入は下がりません。この仕組みにより、オーナーは空室リスクや家賃滞納リスクを負うことなく、安定した収益を確保できます。万が一、入居者が家賃を滞納したり、空室が続いたりしても、オーナーには毎月一定の家賃が支払われるため、家賃収入は変わりません。
パススルー型
パススルー型のサブリースでは、入居者の家賃滞納や空室が発生すると、集金した家賃に応じてオーナーの家賃収入が増減します。この場合、空室や家賃滞納が発生した場合のリスクは、オーナーが負わなければなりません。しかし、入居率が高まるほど家賃収入が増えるため、賃貸物件の魅力や管理会社の集客力が高い場合は、より高い収益になる可能性もあります。
家賃保証の長所・短所は?
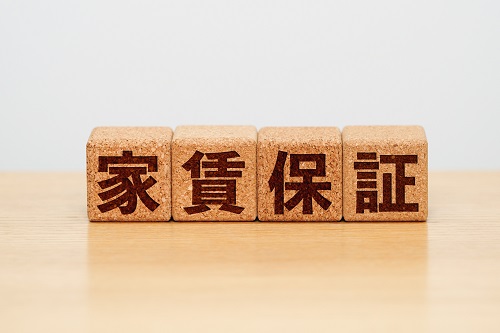
家賃保証とサブリースの違いはわかりましたが、どのような長所があるのでしょうか。本章では、家賃保証の長所と短所をみていきます。
家賃保証の長所
入居者が家賃を滞納した場合に備えて、家賃保証会社が代わりに家賃を支払う家賃保証の長所は以下のとおりです。
家賃滞納リスクを回避できる
家賃保証の主なメリットは、入居者が家賃を滞納した際に、保証会社が代わりに家賃を支払うため、オーナーが家賃滞納リスクを回避できる点です。オーナーは、家賃を回収する対策なども不要で、安定した家賃収入を確保できます。
経済的な負担がない
家賃保証にかかる保証料は入居者が負担するため、オーナーの経済的な負担は増えません。オーナーは初期費用を抑えつつ、賃貸経営をおこなえます。
信頼性の高い入居者を募集できる
保証会社が入居者の審査をおこなうため、はじめから信頼性の高い入居者を募集できます。これにより、入居者の質が向上するため、トラブルの発生リスクは低下するでしょう。
家賃保証の短所
次に、家賃保証の短所をみていきましょう。
入居者の負担が増える
家賃保証にかかる保証料は入居者の負担となるため、入居する際の初期費用が増加します。初期費用が高くなると、入居をためらう人が出てくるかもしれません。結果として、入居率が低下するリスクも考えられます。
物件を維持管理する必要がある
家賃保証は家賃の支払いに関する保証のみであり、賃貸物件の維持管理は別途おこなわなければなりません。オーナーは賃貸物件のメンテナンスや修繕を自分で手配しなければならず、手間と費用がかかります。
家賃は全額保証ではない
保証会社が保証する家賃は、必ずしも満額ではありません。契約内容によっては、一部しか保証されない場合もあります。そうなると、家賃保証をしていても、家賃収入の一部を損失してしまう可能性があります。
保証会社が倒産するリスクがある
保証会社が倒産した場合、オーナーは家賃を保証してもらえなくなります。この場合、自分で家賃を回収する手間と時間がかかり、賃貸経営に影響が出るでしょう。そのため、保証会社を選ぶ際には、経営状態が安定しているかの確認が不可欠です。
家賃保証は家賃滞納リスクの軽減や入居者の質の向上など、多くの長所がありますが、入居者の負担増加や賃貸物件管理の必要性が生じるなど、短所も存在します。オーナーはこれらの点を考慮し、家賃保証の利用を検討しなければなりません。
サブリースの長所・短所は?

サブリースは、サブリース会社(不動産管理会社)がオーナーから賃貸物件を借り上げ、入居者に転貸する仕組みです。このシステムには多くの利点がありますが、いくつかの注意点も存在します。以下に、サブリースの長所と短所を詳しく説明します。
サブリースの長所
サブリースはどのような点が長所でしょうか。長所を2つ解説します。
空室リスクを回避できる
サブリースの主な長所は、入居者がいなくても一定の家賃収入が得られる点です。空室リスクと家賃滞納リスクの両方をカバーできるのは、オーナーにとって心強いでしょう。賃料保証型のサブリース契約では、空室や家賃滞納が発生しても、オーナーには毎月一定の家賃が支払われ、家賃収入が安定します。
管理業務を軽減できる
サブリース契約を結ぶと、賃貸物件の管理や運営をサブリース会社に任せられます。入居者募集、契約手続き、トラブル対応などの煩雑な業務から解放され、オーナーの手間が大幅に軽減されるでしょう。
サブリースの短所
サブリースの短所はどのようなところでしょうか。6つの短所を解説します。
家賃収入が減少する
サブリース会社を経由するため、オーナーが受け取る家賃収入は満額ではありません。通常、家賃の10~20%が保証料として差し引かれるため、オーナーの手取り収入は80~90%に減少します。また、契約内容によっては入居状況が良好でも、家賃収入に反映されない可能性もある点が短所です。
賃料の見直しリスクがある
サブリース契約では、定期的に賃料の見直しがおこなわれます。近隣の家賃相場の下落や経済状況の変動により、賃料が減額されるかもしれません。また、契約更新時に条件が変更される可能性もあるため、長期的な家賃収入の見通しが立てにくい場合があります。
サブリース会社の倒産リスクがある
サブリース会社が倒産した場合、オーナーは家賃保証を受けられなくなります。倒産により、入居者との契約もオーナーに引き継がれるため、自分で家賃を回収しなければならず、手間と時間が発生するかもしれません。サブリース会社を選ぶ際には、経営状態が安定しているかを確認することが重要です。
オーナーからの契約解除が難しい
サブリース契約は借地借家法により、借主である不動産管理会社が保護されています。そのため、オーナーからの解約は難しく、特に契約内容によっては、簡単に契約を終了できないかもしれません。
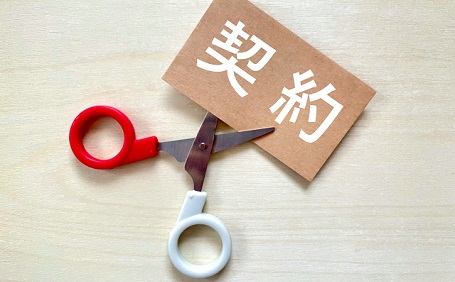
- サブリースは解約できない?難しい理由や解約が認められる正当事由を解説
- 「管理の手間が省ける」「家賃収入が保証される」などの理由から、所有する不動産でサブリース契約を結んだ方もいるでしょう。
続きを読む

収益が上がりにくい
サブリース契約では、満室になっても家賃収入が増える余地はありません。また、敷金や礼金、更新料はサブリース会社が受け取るため、オーナーの収益を最大化させることは難しいでしょう。賃料や入居者の決定権もサブリース会社にあるため、オーナーの意向が反映されにくい点も短所です。
免責期間が存在する
サブリースは、新築後や入居者の退去後に免責期間が設定されている場合があります。この期間中は家賃保証がされないため、家賃収入が一時的に減少するかもしれません。免責期間が適切かを確認し、契約内容を慎重に検討することが重要です。
サブリースのメリットは安定した家賃収入と管理業務の軽減にありますが、家賃収入の減少リスクや契約内容の見直し、サブリース会社の倒産リスクなども考慮する必要があります。オーナーはこれらの点を踏まえ、自身のリスク許容度や収益目標に応じてサブリースの利用を検討することが重要です。
家賃保証とサブリースを使い分けるポイント

家賃保証とサブリースは、それぞれ賃貸経営で重要な役割を果たす仕組みですが、それぞれ異なる特徴と利点がありました。オーナーの立場でどちらを選択するかは、賃貸物件の特性や自身の経営スタイル、リスク許容度によって決まります。では、どのように使い分ければよいのでしょうか。本章では、家賃保証とサブリースを使い分けるポイントを物件別に解説していきます。
新築物件の場合
新築物件では、初期の空室リスクが高いため、サブリースを利用して安定収入を確保する方法が有効です。一方、入居者が決まりやすい人気エリアの賃貸物件なら、家賃保証を利用してリスクを最小限にしつつ、高い家賃収入を目指す方法も効果的でしょう。
老朽化した物件の場合
老朽化した賃貸物件も、空室リスクが高いため、サブリースを利用して安定収入を確保する方法が適しています。また、管理会社に賃貸物件の維持管理を任せると、オーナーの負担を軽減できるでしょう。
複数物件を所有する場合
複数の賃貸物件を所有している場合、リスク分散の観点から、一部の賃貸物件には家賃保証を利用し、他の賃貸物件にはサブリースを利用する方法が有効です。そうすれば、収益の安定性と最大化を図れるでしょう。
経営スタイルによる選択
自身の経営スタイルやライフスタイルに合わせて適切な選択をおこなうことをおすすめします。物件管理に対して積極的に関与したいオーナーは家賃保証を選び、管理業務を一任したいオーナーはサブリースを選ぶとよいでしょう。
家賃保証とサブリースは、それぞれ異なる利点とリスクがあります。賃貸物件の特性や立地条件、オーナーのリスク許容度や経営スタイルに応じて、適切な選択をするよう心がけましょう。なお、家賃保証は家賃滞納リスクの回避や信用度の高い入居者の確保に適しており、サブリースは空室リスクの排除や管理業務の軽減に効果的です。両者の的確な使い分けが肝心になります。
家賃保証とサブリースを委託する会社を選ぶポイント

賃貸経営を安定させるには、信頼できる家賃保証会社やサブリース会社の選択が重要です。そこで、会社選びに重要な選択のポイントを解説します。
経営状況が安定しているか
経営状況が不安定な会社では、保証が不確かになり、最悪の場合、倒産して保証が受けられなくなるリスクがあります。確認するためには、会社の経営状況や財務情報を調査し、実績や業界内での評判を見ておきましょう。調査会社のレポートを利用するのも有効です。調査会社のレポートを利用して経営状況を確認し、業界内での評判や実績をチェックします。長期間にわたって安定したサービスを提供している会社を選びましょう。
透明性が高くコミュニケーションが円滑に取れるか
透明性が高く、コミュニケーションが円滑に取れる会社は信頼性が高いです。契約内容や費用を明確に説明してくれる会社を選びましょう。確認するためには、事前に契約書や料金体系を確認し、質問に対して丁寧に回答してくれるかをチェックします。定期的な報告や相談ができる体制が整っているかも確認しておきましょう。
サービスに柔軟性があるか
賃貸物件や経営スタイルに応じたカスタマイズ可能なサービスを提供している会社は柔軟性が高く、利便性があります。提供されるサービス内容やオプションを確認し、自身のニーズに合ったカスタマイズが可能かをチェックしましょう。
家賃の立替時期はいつか
滞納家賃の立替が遅れると、オーナーのキャッシュフローに悪影響を与えます。そのため契約前に、家賃滞納が発生した場合の報告タイミングや立替スケジュールを詳細に確認しておきましょう。迅速な対応を約束する会社を選ぶと安心です。
保証料や賃料設定は妥当か
家賃保証では、保証料が高すぎると入居率に悪影響を及ぼす可能性があります。また、妥当な保証料設定がないとオーナーの収益が減少してしまいます。適正な保証料の判断は、複数の保証会社から見積もりを取って比較検討しましょう。
サブリースでは、提示された家賃が周辺相場と乖離していると、入居率に悪影響を及ぼす可能性があります。適正な家賃設定には、複数のサブリース会社から見積もりを取り、提示された家賃が適切か比較検討しておきましょう。周辺相場と比較し、極端に高すぎたり、低すぎたりしないかの確認が必要です。
空室対策や入居者募集は適切か
賃貸経営では入居者募集が肝心で、空室が長期間続くと、収益に大きな影響を与えます。サブリース会社が効果的な空室対策と入居者募集をおこなっているかをチェックしましょう。空室対策の具体的な方法や入居者募集の取り組みに対し、詳細に確認しておきます。過去の空室解消実績や広告戦略なども参考にしましょう。
家賃保証とサブリースに関するよくある質問
家賃保証とサブリースに関するよくある質問をまとめました。
家賃保証とサブリースの違いは?
家賃保証とサブリースは、どちらも空室時の家賃を保証するものですが、その仕組みは異なります。家賃保証は、入居者が家賃を滞納した際、保証会社が代わりに支払う仕組みで、保証料を負担するのは主に入居者です。オーナーは賃貸物件の管理や入居者募集を担当し、家賃保証の契約には関わりません。
一方、サブリースはサブリース会社(不動産管理会社)がオーナーから賃貸物件を借り上げ、転貸する仕組みです。入居者の家賃滞納や空室に関わらず、オーナーは一定の家賃収入を得られます。賃貸物件の管理や入居者募集は管理会社に任せ、オーナーがおこなう業務は基本的にありません。なお、サブリースには賃料保証型とパススルー型があります。
家賃保証の長所と短所は?
家賃保証の長所は、次の3つです。
- 家賃滞納リスクを回避できる
- 経済的負担が少ない
- 信頼性の高い入居者を募集できる
入居者が家賃を滞納した場合でも、保証会社が代わりに支払うため、オーナーは安定した家賃収入を確保できます。また、保証料は入居者が負担するため、オーナーの経済的負担は増えず、保証会社の審査を通過した信頼性の高い入居者を迎えられます。
しかし短所は、入居者の初期費用が増加するため、入居率が低下する可能性がある点です。さらに、家賃保証は家賃支払いに関するものであり、賃貸物件の維持管理はオーナー自身がおこなう必要があるため、手間と費用がかかります。家賃全額が保証されない場合もあり、家賃収入の一部損失は避けられません。加えて、保証会社が倒産した場合、オーナーは家賃を保証してもらえなくなり、自ら回収する手間と時間が発生します。したがって、保証会社の経営状態を確認することが重要です。
サブリースの長所と短所は?
サブリースの主な長所は、空室リスクの回避と管理業務の軽減です。オーナーは入居者がいなくても一定の家賃収入を得られ、賃貸物件の管理や運営をサブリース会社に任せることで、手間を大幅に軽減できます。
しかし短所として、オーナーが受け取る賃料は通常、満額の80~90%であり、家賃収入の減少は避けられません。また、定期的な賃料の見直しによる減額リスク、サブリース会社の倒産リスク、契約解除の困難さがあります。さらに、収益の上がりにくさや免責期間の存在も短所です。満室でも家賃収入が増えず、敷金や礼金などはサブリース会社が受け取るため、収益を最大化しにくいでしょう。これらを考慮し、オーナーは自身のリスク許容度や収益目標に応じて、サブリースの利用を慎重に検討すべきです。
家賃保証とサブリースを使い分ける時のポイントは?
家賃保証とサブリースは、それぞれ異なる特徴と利点を持ちます。使い分けるには賃貸物件の特性やオーナーの経営スタイルに適用する点が重要です。新築物件では初期の空室リスクを避けるために、サブリースが有効ですが、人気エリアの賃貸物件なら家賃保証を利用して高い家賃収入を目指すのがおすすめです。老朽化した物件では、空室リスクを避けるためにサブリースが適しています。複数の賃貸物件を所有する場合は、リスク分散のために家賃保証とサブリースを併用するのが賢明でしょう。
また、賃貸物件の管理に積極的に関与したいオーナーには家賃保証が適し、管理業務を一任したいオーナーはサブリースが適しています。各方法の利点とリスクを考慮し、賃貸物件の特性や立地条件、オーナーのリスク許容度や経営スタイルに合わせた適切な選択が肝心です。
家賃保証とサブリースを委託する会社を選ぶポイントは?
まず経営状況が安定しているかを確認することが大切で、財務情報や業界での評判を調査して信頼性の高い会社を選びましょう。また、契約内容や費用の透明性が高く、コミュニケーションが円滑な会社が望ましいです。
さらに、サービスの柔軟性があり、自分のニーズに応じたカスタマイズが可能かも重要になります。家賃の立替時期、滞納発生時の対応スケジュールが迅速なことを確認しましょう。保証料や賃料設定の妥当性もチェックし、複数の会社から見積もりを取り、比較することが大切です。サブリース会社については、空室対策や入居者募集の取り組みが適切か、具体的な方法や過去の実績も忘れずに確認しましょう。
まとめ
本記事では、家賃保証とサブリースの違いや、それぞれの長所と短所、使い分けのポイントと委託する会社を選ぶポイントを解説しました。賃貸経営をする方にとって、安定的な家賃収入は必須です。もし家賃収入が不安定だと、キャッシュフローに悪影響を及ぼし、不動産投資の成功は難しくなるでしょう。細かい内容は違えど、どちらも家賃を安定的に得る手法のひとつです。今回紹介した情報を参考に、経営方針に合った方法をとり、賃貸経営を成功させるために役立ててください。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ