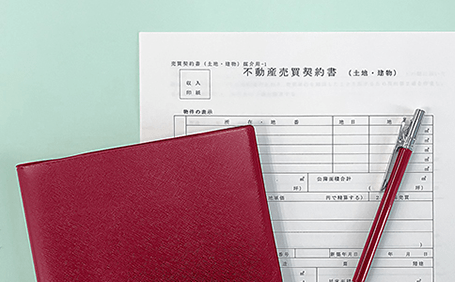信義則とは?意味や具体例、不動産の場合をわかりやすく解説

記事の目次
信義則(信義誠実の原則)とは

「信義則(信義誠実の原則)」とは、権利を行使したり義務を果たしたりする時には、信義に従って誠実に実行しなければならないという原則を意味します。内容をかみ砕いていうと、社会共同生活の一員として、お互いに相手の信頼を裏切らないよう誠意をもって行動することです。
契約における信義則とは
信義則は契約行為をおこなう時のほか、契約の交渉段階でも適用されます。契約行為も交渉段階も、関係のない人同士の決めごとではありません。そのため、信義則をもって実行する必要があります。
契約や交渉を進めるには、自分も取引相手も誠実に話し合いを進めていかなければ目的が達成できません。ですから、契約にも交渉にも信義則が適用されるのです。
契約書
契約時に、民法の基本原則である信義則に従って履行しなければならないことは当然であるため、契約書の条文に記載されていなくても信義則は適用されます。
信義則に違反すると契約不履行や、受領遅滞の責任を負わなければなりません。つまり、信義則に従わないで不動産の引渡しをおこなわなかった場合(契約不履行)や、引渡し時期が延長した場合(受領遅延)には、責任が発生します。
契約交渉時
契約交渉時には、信義則によって説明責任と情報提供義務が発生します。
契約交渉をする際には、正確な情報の提供がおこなわれないと目的を達成できません。そのため、信義則に従い、説明責任と情報提供義務が生じます。
信義則を守らず、嘘の情報で契約を誘導させると、損害賠償の対象になるでしょう。
信義則が適用される具体例
信義則が適用される事例は多く、例えば次のような行為は信義則に違反しています。
このような行為は、貸主の信義則違反です。賃料の支払いが滞ってからすぐ、連帯保証人に連絡するのが信義則に従った行動といえます。
信義則の原則の判例
信義則の原則について、有名な判例を一つご紹介しましょう。
有名な判例とは、「大豆粕深川渡し事件」です。大豆粕深川渡し事件は1925年にあった事件であり、信義則の行使について問題になりました。ここでは、大豆粕深川渡し事件の概要と判決をご紹介します。
●大豆粕深川渡し事件(1925年12月3日)
大豆粕深川渡し事件とは、取引の場所がわからなかったという理由で、取引場所に買い手が現れなかったという事件です。買い手は取引ができなかったことを理由に売り手に対し、損害賠償の請求と契約の解除を求めました。
しかし、裁判の判決では、取引場所を買い手に教えなかった売り手に責任があるのではなく、「買い手は誰かに場所を聞いて取引場所に行くべきだった」とし、買い手に「代金支払義務があることと契約遅延の責任を負うべき」としました。これは、裁判所が信義則に従わず、不誠実な行動を取った結果であるとした判決です。

信義誠実の原則に反する例
信義誠実の原則に反する例として、もう一つの事例をご紹介します。
2006年3月23日、最高裁判所で判決された「みなし道路に対する信義則違反」です。みなし道路とは、建築基準法が制定される前からあった4m以下の道で、特定行政庁が指定した公衆道路のこと。この事件の概要は、次のとおりです。
- みなし道路の所有者が道路上にブロック塀を設置し他の通行人の妨害をした
- みなし道路の所有者の家はこの道路に接している
- 通行を妨害された人もみなし道路に接している
- みなし道路は公衆用道路として非課税になっており妨害した人は道路という認識がある
つまり、妨害した人はブロック塀を設置した場所が道路という認識はあるにも関わらず、道路ではないと否定してモノを設置したわけです。
もちろん、この内容は矛盾しています。そのため、裁判では「ブロック塀を撤去し、道路として利用できるようにしなければならない」と判断しました。
信義則の基本原則
信義則は抽象的な内容であるため、具体的に表現するため以下4つの原則ができました。
- 禁反言(きんはんげん)の原則
- クリーンハンズの原則
- 事情変更の原則
- 権利失効の原則
上記の原則がどのようなものなのか、具体例を挙げつつご紹介します。
禁反言(きんはんげん)の原則
「禁反言の原則」とは、伝えた内容を信用しておこなわれた行為に対して、伝えた内容と矛盾した行為をおこなってはならないという原則です。例えば、不動産取引において買い手が「リフォームしてくれたら購入する」と約束し、それを信じた売主がリフォームしたのにも関わらず買い手が購入しなかった行為は、禁反言の原則に違反した行動となります。
クリーンハンズの原則
「クリーンハンズの原則」とは、法律を守った人しか法律では保護されないという原則です。例えば、人を騙して所有権を取得した不動産を譲り渡したあとに、その不動産の所有権を戻してほしいと言っても法律で助けてもらえないということです。
不法行為をおこなった人は信義則に反しているとみなされるため、保護する対象に値しません。
事情変更の原則
「事情変更の原則」とは、契約締結時に思いもよらない事情が発生した場合は契約の変更が認められるという原則です。しかし、契約を自由に変更できると弊害も大きいため、次の条件を満たす場合のみ変更できるとされています。
- 契約後に契約の内容を根底から覆すような出来事があったこと
- 契約締結時に変化が予測できないような内容であること
- 事情変更になった結果、締結した契約の内容で相手を拘束することが信義則に反してしまう状態であること
例えば、契約を進められないような疾患が発生して、相対して契約することが不可能になるなど。契約するという口頭上の約束をしたとしても、病気は予見不可能であり、契約を進めるのは信義則に反していると考えられるからです。
権利失効の原則
「権利失効の原則」とは、債権者がなかなか権利を行使せず、忘れた頃に権利を主張しても権利行使はできないという原則です。
権利失効の原則でわかりやすいのは時効です。時効は権利が失効する制度であり、権利失効の原則に従っています。
信義則の機能

信義則には、次の4つの機能があります。
- 規範を具体化する
- 正義・衡平を図る
- 規範を修正する
- 規範を創造する
信義則がもたらす機能を把握し、どのような影響をおよぼすのか理解を深めておきましょう。
規範を具体化する
「規範を具体化する機能」とは、抽象的な言葉で決められた法律の規範を、法律の枠内で内容を具現化する機能です。例えば、資金の提供方法を具体的に決めたとして、規定した方法を守ってはいるものの規定した金額に少し満たない金銭を提供した場合に、金銭の受領まで拒否するのは信義則に反しているとするケースが挙げられます。
正義・衡平を図る
「正義・衡平を図る機能」とは、法律で定められた枠外の根拠により、正義・衡平を実現できる機能です。例えば、時効により債務がなくなったにも関わらず、元債務者が消えたはずの債務を承認したあとに、時効を主張することはできないケースです。
この機能は先に述べた、伝えた内容と矛盾した行為をおこなってはならいという「禁反言の原則」に従っています。
規範を修正する
「規範を修正する機能」とは、制定された法律の内容を適用するのが妥当ではなくなった場合、制定されている法律の内容を修正する機能です。例えば、賃料の支払いが滞っても、借主と貸主の信頼関係を破壊する程度のものではないと判断された場合、法律の範囲外の判断として賃貸借契約の解除が信義則に反して許可されないケースがあります。
規範を創造する
「規範を想像する機能」とは、問題が発生した状態を正常な状態にするため、制定された法律に反した新たな規範を創造する機能です。先述した事情変更の原則は、規範を創造する機能となります。
信義則の判断基準
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
引用:e-Gov「民法」
上記のように、民法に記載されている信義則の内容は、たった2行であり非常に抽象的です。民法では、どのような行為が信義則に違反しているのか明らかになっていません。そのため、信義則に違反しているかは個々の状況によって判断するしかなく、判断するためのポイントを理解する必要があります。
判断するのは困難であるものの、着目すべきポイントがわかれば判断しやすくなります。具体的なポイントは次のとおりです。
- 「権利の行使」「義務の履行」に着目
- 前記の各機能に着目
- 信義則が適用される具体的法領域(契約法、親族法等)に着目
上記のポイントはあくまで着眼点であるため、信義則に違反するかは総合的に判断しなければなりません。裁判所も総合的な判断で判決を下しているため、基準を明確に表すのは困難といわれています。
信義則違反とその効果

信義則を規定した民法の条文は非常に抽象的であるため、違反の内容が記載されていません。どのような行為が信義則違反なのか、判断することは難しいのが実情です。そのため、個々の信義則違反ではなく、一般的な違反の内容とその効果を解説します。
義務の履行の場合
信義則違反の行為に該当する義務の履行とは、義務を果たさないことを指します。債権者が義務の不履行を起こすと債務を履行できなくなり、債権者に受領遅滞の責任が発生します。
例えば、引渡しの準備を整えたにも関わらず、買い手が資金の準備をせず引渡し日を過ぎてしまった場合、義務の不履行により買い手は損害賠償を受ける対象となるでしょう。
権利の行使の場合
信義則違反の行為に該当する権利の行使をしても、効果は生じません。不動産売買契約において契約内容に従っていない理由で解除したいと申し出ても、解除は認められないということです。
例えば、「気が変わってやっぱり不動産を売却したくなくなったから契約解除する」と売り手の一方的な言い分で解除権を行使しようとしても信義則違反で認められません。
権利の不行使の場合
信義則違反の行為に該当する場合、権利行使をしても効果が否定されます。例えば、時効を迎えた権利を主張しても、権利は実行できないというケースです。
不動産における信義則
信義則は不動産の契約や取引にも影響を与えており、守るべき原則です。
例えば、買い手の売買代金支払いと、売り手の所有権移転も信義則に従っておこないます。買い手が引渡し期日前までに売買代金を準備したとしても、売り手が期日までに所有権移転の準備をしなければ信義則違反・禁反言の原則違反です。契約締結し、所有権に移転を準備すると約束したにも関わらず、売り手の行動は契約書と違う動きをしているわけです。この場合、売り手は買い手に対し、受領遅滞の責任を負う必要があります。
信義則についてよくある質問

信義則についてよくある質問は、次のとおりです。
- 信義則と契約の関係とは?
- 信義則の基準とは?
- 「信義則に反する」とはどういう意味?
ここでは、信義則についてよくある質問とその回答をご紹介します。
信義則と契約の関係とは?
信義則と契約とは、密接な関係で結びついています。契約の目的を達成するには、自分と相手方が正確な情報を提供し、同じ方向へ動いていかなければいけません。
片方が相手に対して虚言を使い契約を妨害する行為など信義則に従った動きをしない場合、契約が達成できないため、信義則は契約に大きく影響するといえます。
信義則の基準とは?
信義則の基準は明確になっていません。信義則に従っているのか、違反しているのかは総合的に判断しなければいけません。判断する目安はあるものの、明確な基準ではないため、信義則違反と勝手に決めつけないようにしましょう。
「信義則に反する」とはどういう意味?
「信義則に反する」とは、相手の信頼を裏切るような行為です。例えば1,000万円なら土地を売却すると言いながら、実際に買い手が1,000万円用意したにも関わらず土地を売却しない行為は、信義則に反する行動です。
まとめ
信義則とは、社会生活をするにあたり相手を裏切らず、誠実な行動で対応することです。信義則は契約や交渉事にも大きな影響を及ぼすため、どのような行為が信義則に従っているのか理解しておくことが大切です。
しかし、信義則は民法に規定されているものの、どのような行為が信義則に当たるのか明記されていません。相手の行為が信義則に違反しているかは総合的に判断しなくてはならないため、違反をしているか慎重に判断しましょう。
物件を探す