2025年の建築基準法改正、変更点と影響は?重要なポイントを解説
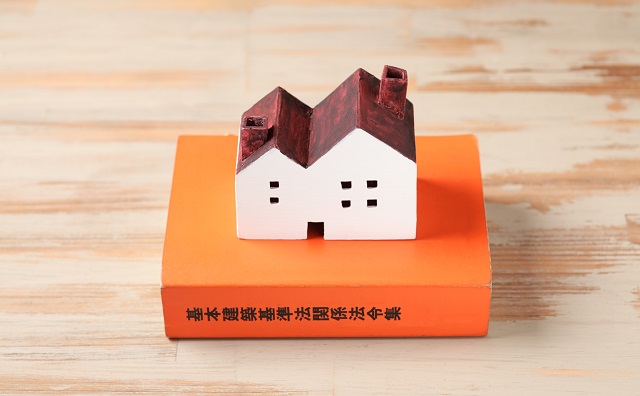
本記事では、2025年の建築基準法の改正点をわかりやすく、そして詳しく解説します。
記事の目次
建築基準法とは

建築基準法とは、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する基準を定め、国民の生命や健康、財産の保護を図る法律です。簡単にいうと、建物に関する内容をとりまとめた法律といえます。例えば、耐震性の低い家を建てられないようにして地震から生命と財産を守ったり、建物の高さや日照時間を決めて健康を守ってくれたりします。
なお、生命や財産などを守るため、建築基準法はたびたび改正されてきました。2025年にも、さまざまな内容が改正される予定です。
2025年の建築基準法改正、何が目的?

2025年の建築基準法改正の目的は、建物の省エネ性能を高めることです。2030年の温室効果ガス46%削減、2050年のカーボンニュートラル達成には、建物の省エネ化が不可欠です。建物を建築する際には多くの重機を利用し、温室効果ガスを発生させ、建築材料を作るにあたって環境を破壊します。建築時の温室効果ガス発生を抑制するのは難しいため、生活で発生する量を抑えるのが目的です。例えば、太陽光発電システムを搭載すれば電力消費が抑えられたり、断熱性の高い家ならエアコンの使用量を低下させたりして、温室効果ガスの発生を抑制できます。
このように、2025年の建築基準法改正で、環境問題の解決につながると考えられています。
2025年の建築基準法改正で何が変わる?
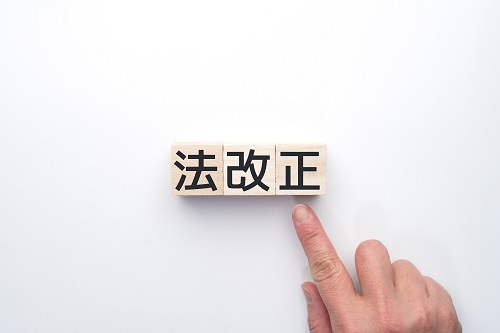
2025年の建築基準法改正では、次の8項目が変更されます。
- 1. 4号特例の縮小(建築確認・検査対象の見直し)
- 2. 構造計算が必要となる木造建築物の規模引き下げ
- 3. 大規模建築物の防火規定の変更
- 4. 別棟部における耐火性能の基準変更
- 5. 高さ制限・建ぺい率・容積率に関する特例制度の創設
- 6. 住宅の採光規定の見直し
- 7. 一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充
- 8. 既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除
項目のなかには今後家を建てる人に影響する内容もあるため、改正点の内容を理解しておくことが大切です。以下で詳しく解説します。
4号特例の縮小(建築確認・検査対象の見直し)
4号特例とは、一部の条件を満たした建物は、建築確認・構造等の安全性審査の対象から外すという制度です。検査の対象から外された建物は建築しやすい反面、欠陥住宅が生まれやすくなるおそれもあります。そのため、次の表のように現行制度が改正され、検査の対象となる住宅が多くなります。
| 現行 | 改正 | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 建築確認 | すべての建物 | すべての建物 |
| 構造等の 安全性審査 |
階数3以上 または 延べ面積500平方メートル以上 |
階数2以上 または 延べ面積200平方メートル以上 |
|
| 都市計画区域外 | 建築確認 | 階数3以上または 延べ面積500平方メートル以上 |
階数2以上または 延べ面積200平方メートル以上 |
| 構造等の 安全性審査 |
上記のように、改正後は2階建の建物を建築するだけで、構造等の安全性審査を受けなければならなくなります。この基準は新築だけでなく、大規模修繕にも適用される点に注意が必要です。
構造計算が必要となる木造建築物の規模引き下げ
一定以上の高さがある建物を建築する場合、一級建築士が丈夫な構造か計算しなければいけません。しかし、近年は建築技術の向上により、一定以上の高さの建物が多く建築され、構造計算する人に大きな負担がかかっています。特定の人に負担がかからないようにするため、二級建築士でも構造計算できる範囲が定められています。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 高さ13m以下かつ 軒高9m以下 |
階数3以下かつ 高さ16m以下 |
上記のように、二級建築士でも構造計算できる範囲が増えました。事務の負担が減れば、計算ミスや審査せずに処理するなどのケースが減ると期待されます。
しかし、構造計算について緩和される項目がある反面、厳しくなったものもあります。建物の面積が一定以上の場合、構造計算は一級建築士がおこなわなければなりません。その面積が改正により、次の表のように厳しくなりました。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 2階以下の木造建築物で構造計算が必要となる規模は、 延べ面積500平方メートル超 |
2階以下の木造建築物で構造計算が必要となる規模は、 延べ面積300平方メートル超 |
建物の高さの制限は緩くなり、面積の制限は厳しくなったのが2025年の建築基準法改正です。
大規模建築物の防火規定の変更
国内の森林資源を有効に活用するため大規模建築物の木造化を推進してきたものの、現状の法律のままでは木材のよさを活かしきれていない現状が問題となっています。現行法では木造で大規模建築物を建てる場合、石膏ボードといった不燃材料で木を覆わねばならず、見た目も機能もうまく活用できていませんでした。この状態を解決すべく、次のように規定が緩和されます。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 壁・柱等を耐火構造にし、3,000平方メートル毎に耐火構造体で区画しなければならない | 火災時に周囲に大規模な危害がおよぶことを防止でき、 木材の「あらわし」による設計が可能な構造方法を導入 |
改正後の文章にある「あらわし」とは、木材をそのままむき出しにする状態です。これにより、大規模建築物の内部でも木材をむき出しにできるようになり、デザイン性の向上、木の香りを漂わせるといった機能性も持ち合わせられるようになります。
別棟部における耐火性能の基準変更
大規模建築物が高層と低層の2つの建物からなっている場合、現行法の場合はどちらも耐火構造で建築しなければならず、低層の建物であっても木造化するのが難しいという課題があります。この課題を解決すべく、改正では次の表のような緩和が実施されます。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 低層についても高層と一体として扱われ、全体で防火規制を適用し建築物全体に耐火性能を要求される | 高い耐火性能の壁等や十分な離隔距離を有する渡り廊下で分棟的に区画された高層・低層をそれぞれ防火規定上の別棟として扱うことで、低層部分の木造化を可能とする |
改正のように延焼の防止策が取られていた場合、一体となった建物の低層部分については木造で建築できるようになります。
高さ制限・建ぺい率・容積率に関する特例制度の創設
建物には高さや面積の制限があり、現行法のままだと、省エネ設備を設置した際に制限に引っかかると法律違反となります。例えば、高さ制限ギリギリで建てられた建物の上に、太陽光パネルを設置すると制限を超えるといった場合です。このようなケースだと太陽光パネルを設置できないため、改正では次のような特例を設置します。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 特定の地域(※)では原則として、都市計画により定められた高さの制限を超えてはならない | 特定の地域(※)について屋外に面する部分の工事により高さ制限を超えることが構造上やむをえない建築物に対する特例許可制度を創設 |
※第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地区・高度地区
また、建物の高さと同時に、次の表のように面積の制限も緩和されます。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 都市計画区域等内では、原則、都市計画により定められた容積率や建ぺい率の制限を超えてはならない | 屋外に面する部分の工事により容積率や建ぺい率制限を超えることが構造上やむをえない建築物に対する特例許可制度を創設 |
上記の緩和により、すでに建っている建物についての省エネ化工事の増加が期待されます。
住宅の採光規定の見直し
コロナ禍によってホテルや旅館の経営状態が悪くなり、住宅に転用しようとする人がいたものの、採光規定が障壁となっていました。採光規定により住宅棟数の確保が難しくなっていたため、改正では次のように緩和されます。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 居室床面積の1/7以上の大きさの採光に有効な開口部面積の確保が必要 | 原則1/7以上としつつ、一定条件で1/10以上まで必要な開口部の大きさの緩和を可能にする |
緩和措置が設けられれば、ホテルや旅館だけでなく、事務所といったオフィスも住宅に変更できる可能性が高くなります。ただし、緩和の一定条件の内容は2024年8月11日現在決まっていません。
一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充
一団地の総合的設計制度等とは、複数建築物が同一敷地内にあるものとみなし、建築規制を適用する制度です。建物を建築するには道路に接している必要があるものの、一団地の総合的設計制度等を利用すれば接道していない土地でも建物が建てられます。しかし、この制度は建築だけが対象で大規模修繕が対象外となっており、無接道の建物だけの大規模修繕ができない状態でした。そこで今回の改正では、一団地の総合的設計制度等が次のように緩和されます。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 建築 (新築・増築・改築・移転) |
建築 (新築・増築・改築・移転) 大規模の修繕・大規模な模様替え |
大規模修繕・大規模な模様替えが追加されることで、一団地として工事する必要がなくなります。
既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除
既存不適格建築物とは、建築当時の法律に適合していたものの、現在の法律の内容では建てられなくなった建物です。例えば、建築当時は容積率100%だったのにもかかわらず、現在は80%まで下がってしまい面積が規定をオーバーしているといった状態です。このような状態を改善するには多額の金銭が必要となり、既存不適格建築物が減らない要因となっていました。そのため、改正により、次のように緩和されます。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 防火・避難規定や集団 規定については増改築時等において原則現行基準適合が求められる |
1.防火規定、防火区画規定等について、建築物の長寿命化・省エネ化等に伴う一定の改修工事は遡及適用対象外
2.接道義務、道路内建築制限について、建築物の長寿命化・省エネ化等に伴う一定の改修工事は遡及適用対象外
3.防火規定、防火区画規定について、分棟的に区画された建築物の一の分、当該分棟部分に限って遡及適用する
4.廊下等の避難関係規定、内装制限、建築材料品質規定について、増築等をする部分に限って遡及適用する。
|
既存不適格建築物の状態を適法にする場合、現行ではすべての内容を正さなければならないとしています。しかし、すべてを適法な状態にするのは困難であり、一定の条件を満たす工事なら、すべての内容を正さなくでもいいと変更するわけです。
2025年の建築基準法改正によるメリット
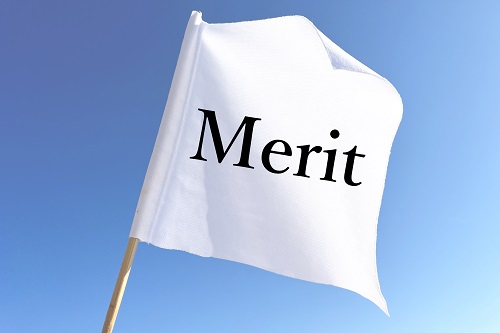
2025年の建築基準法改正による主なメリットは、次のとおりです。
- 行政が構造をチェックするため欠陥住宅が減る
- 断熱性の高い住宅が手に入る
- 耐震性の高さが一定以上になる
改正後はどのハウスメーカー・工務店に建築を依頼しても、一定水準の建物が手に入るようになります。断熱性が高ければエアコンの使用量が減って電気代が節約できますし、耐震性が高ければ大地震の発生の被害を抑えられます。
2025年の建築基準法改正によるデメリット・注意点

2025年の建築基準法改正による主なデメリット・注意点は、次のとおりです。
- 建築費用が増加する
- 建築に必要な工事期間が長くなる
- デザイン性の高い家が建てにくくなる
建築するにあたって構造計算といったチェック体制が厳しくなることで、手続きに関する費用の増加が懸念されています。計算するにあたっては時間が必要となり、建物完成までに時間がかかってしまいます。また、構造的に弱い建物を建築しにくくなるため、デザイン性の低下も発生するでしょう。
建築基準法改正に関するよくある質問

建築基準法改正に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 2025年の建築基準法改正の目的は?
- 2025年の建築基準法改正でどんな影響がある?
- 2025年の建築基準法改正で準備しておくことはある?
ここからは、各質問の回答を紹介します。
2025年の建築基準法改正の目的は?
2025年の建築基準法改正の目的は、省エネ住宅の増加が主な目的です。カーボンニュートラルや温室効果ガスの削減につながり、改正により政府が掲げる目標の達成への貢献が期待されています。また、高断熱や高耐震性、行政によるチェックなどにより、安心して住める家の取得が実現することでしょう。
2025年の建築基準法改正でどんな影響がある?
2025年の建築基準法改正では、次のような影響が考えられます。
【良い影響】
- 高性能住宅が取得しやすくなる
- 欠陥住宅をつかまされる可能性が減る
【悪い影響】
- 建築費用が上がる
- 建物完成までの時間が長くなる
2025年の建築基準法改正により、新居を建築する人にも影響が出ます。どのような影響が出るのか理解し、建築の手続きを進めていきましょう。
2025年の建築基準法改正で準備しておくことはある?
2025年の建築基準法改正後、新居を建築する前には次のような準備をしておきましょう。
- 建築費用に余裕をもっておく
- スケジュール管理をしっかりとおこなう
2階建の木造建物を建築する場合、どの場所に建築するにしても構造計算が必須となります。構造計算するには費用や時間がかかるため、注意しなければなりません。
構造計算の費用が追加されるのはもちろんのこと、建物完成までに時間がかかれば賃貸物件を借りる期間が長くなり賃料の負担も大きくなります。そのため、建築に関する費用、スケジュール管理をしっかりとおこない、どの程度の負担がかかるのか明確にしておくことが大切です。
まとめ
2025年の建築基準法改正では、建築会社だけでなく個人にも影響を与える変更点があります。今回の改正ではどのような改正がなされ、どのような影響を与えるのか理解しておくことが大切です。特に構造計算が必要になる建物の内容変更の影響が大きく、新居を建築する費用が高くなり、完成までに時間がかかるそれもあります。ハウスメーカー・工務店などに建築を相談する際には、2025年の建築基準法改正の影響を聞きつつ進めていくといいでしょう。
物件を探す



