取得時効とは?土地の時効取得についてわかりやすく解説

本記事では、取得時効とは何か、成立する条件などをわかりやすく解説します。記事の後半では取得時効に関する注意点も紹介しますので、不動産の時効取得を考えている人はぜひ参考にしてみてください。
記事の目次
取得時効とは

取得時効とは、「時効」のうちのひとつで時間経過とともに権利が取得できる制度です。そして、取得時効には「短期取得時効」と「長期取得時効」があり、時効が成立する年数に違いがあります。取得時効が成立すると、所有権や賃借権など権利の取得が可能です。
なお、時効には取得時効のほかに、「消滅時効」という権利を失う制度もあります。例えば、会社から退職金が出るにもかかわらず、それを知ってから5年を経過すると受け取る権利(債権)が消滅時効で失われます。
時効取得の対象となる権利
時効取得の対象となる権利は、以下のとおりです。
- 所有権
- 賃借権
- 地上権
- 永小作権
- 地役権
一方、「占有権」や「留置権」、「先取特権」は時効取得の対象となりません。権利によって時効が認められるもの、認められないものがある点には注意しましょう。
取得時効はなんのために存在する?
取得時効が存在する主な理由は、以下の3つであるといわれています。
- 一定期間経過した事実を尊重するから
- 占有されている事実に気付かない人を保護する必要はないから
- 数十年も前の事実を立証するのは困難だから
このように、取得時効は法的な権利関係を簡素化するために存在しています。
なお、占有とは自分のためにものを所有することを指します。例えば、他人が持っている雑誌を借りているのも占有です。ただし、占有したからといって取得時効できるわけではありません。取得時効するには、一定の条件を満たす必要があります。
時効取得のための要件

時効取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 【1】所有の意思をもって占有している
- 【2】平穏かつ公然の占有である
- 【3】一定期間占有を継続している
ここからは、各要件について詳しく解説します。
【1】所有の意思をもって占有している
取得時効は、所有の意思をもって占有していないと認められません。他人の物を所有する意思がない場合、時効で取得する意識がないものと判断されます。例えば、賃貸借契約をもとに賃料を払って部屋を借りている人は「他人の物を借りる」という意思があり時効取得できません。
なお、他人のものを所有する意思をもって占有することを「自主占有」、所有する意思を持たずに占有することを「他主占有」といいます。
【2】平穏かつ公然の占有である
取得時効を成立させるには、平穏かつ公然の占有が必要です。平穏かつ公然に反する例として、脅迫して物を奪いとった、所有者にわからない方法で物を取得したケースが該当します。常識の範囲内で物を取得した場合にのみ時効取得が認められ、罪になるような方法で取得しても認められません。
【3】一定期間占有を継続している
取得時効が認められるには、他人の物を10年もしくは20年占有する必要があります。占有期間が10年のものを「短期取得時効」、20年を「長期取得時効」と呼びます。それぞれの取得時効の違いは、以下のとおりです。
| 短期取得時効 | 長期取得時効 | |
|---|---|---|
| 必要経過年数 | 10年 | 20年 |
| 成立要件 | 占有を開始した時点において 善意無過失である |
占有を開始した時点において 悪意または有過失である |
短期と長期との差は善意無過失で占有しているか、悪意または有過失なのかによって変わります。
「善意無過失」とは?
善意無過失とは落ち度なく他人のものである事実を知らなかった場合、注意していても事実がわからなかった状態です。
例えば、本人ではない所有者が登記簿や権利証を偽造し土地を売却したとします。その事実を知らない人が土地を購入したとしても、売却に必要な書類をすべて偽造されている場合、本人ではないと見抜くのは難しいでしょう。相手を信用し(善意)、登記簿や権利証を確認して本人と判断(無過失)した事実があれば、善意無過失と認められる可能性があります。
なお、買主がきちんと登記簿や権利証を確認しなかった場合、調査しなかったとして有過失と判断されるかもしれません。
あとから設備や施設を設置した場合は?
建物を占有したあとに設備や施設を設置した場合、その設備・施設は設置したときから占有が開始されたとみなされます。あとから設置された物は占有開始時に存在せず、占有者が物理的支配できないため「占有が開始された」とはみなされません。実際に設備・施設が完成し、占有者が物理的支配できるようになってから取得時効の算定が始まります。
占有者が変わった場合、期間を合算できる?
占有者が変わった場合、時効取得までの期間は合算が可能です。例えば、悪意もしくは有過失で15年間に渡って建物を占有したAさんが、その建物をBさんに売却したとします。この場合は長期取得時効にあたり、本来の所有者から所有権を取得するには20年かかりますが、占有期間は前の占有期間と合算できるため、Bさんは5年間占有すれば取得時効が成立します。
土地や不動産を相続する場合、取得時効は認められる?

取得時効は相続でも認められますが、状況によります。認められるのは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。ここからは、なぜ相続で取得時効が認められにくいのか解説します。
相続人が複数いる場合は「自主占有」が認められにくい
相続人が複数いる場合は所有の意思を持っているとみなされにくく、認められないケースがほとんどです。相続人が複数いる不動産は所有者が亡くなった後、いったん相続人全員で共有する財産となります。そして、その後、相続人全員で話し合いをしてその不動産を誰が相続するか決定します。
相続財産はこのような流れで相続人を決定するため、占有していたとしても「自分の不動産ではなく相続人で共有している」という認識が生まれるはずです。この認識は自主占有ではなく他社占有であり、取得時効が成立する要件から外れます。
相続財産の自主占有が認められるケースの例
例外的に、相続財産の自主占有が認められるケースもあります。
例えば、父が祖父から贈与されていないにもかかわらず「祖父から贈与で土地を取得した」という言葉を息子に投げかけたとします。そして、相続人が本人ひとりだけである息子が、父の言葉を信じて土地を使っていたケースです。この場合、相続人がひとりしかいないため、相続財産を共有している認識は生まれず自主占有となります。
ただし、土地の所有者は登記簿を調査すればわかるため、有過失として長期取得時効である20年の占有が必要と判断されるでしょう。
取得時効に関する注意点

取得時効に関する注意点は、以下のとおりです。
- 賃貸(貸借)は所有権を時効取得できない
- 時効取得時に抵当権も消滅する
- 隣地からの越境の有無を確認しておく
- 不法な占拠でも取得時効が認められる場合がある
- 公有地は原則、取得時効の対象にならない
それでは、どのような注意点があるのか見ていきましょう。
賃貸(貸借)は所有権を時効取得できない
賃貸(貸借)は自主占有とはいえず、所有権を時効取得できません。土地や建物を借りるときに賃貸借契約を締結した場合、借りるという意思のもと契約することとなります。しかも、契約書という形で証拠も残るため、所有する意思があったと主張してもまず認められないでしょう。
時効取得時に抵当権も消滅する
時効取得した際の抵当権の取り扱いについては、以下のように民法に定められています。
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
e-Gov:民法 第397条
このように、抵当権の付いている不動産を取得時効で得た際に抵当権は消滅します。ただし、取得した人が債務者もしくは抵当権設定者だった場合、抵当権は消滅しません。
隣地からの越境の有無を確認しておく
越境が既成事実と化している場合、取得時効が認められるケースがあります。越境物があると、越境している部分を賃借したり、覚書で越境があることを証明したりします。このように、越境物の存在を認めさせておけば他主占有となり、取得時効は認められません。
しかし、賃貸借契約書も覚書も取得せずに越境を放置していると、相手側に自主占有を主張されやすくなります。隣地からの越境があるか確認し、もしあるならきちんと書類を作成し対処しておきましょう。
不法な占拠でも取得時効が認められる場合がある
不法占拠でも要件を満たせば、取得時効が認められるケースもあります。
取得時効は悪意もしくは過失があっても、所有する意思を持って20年占有すれば成立します。越境物のように不法な侵入物があったとしても同様であり、不法占拠に長い年月気付かない人までは保護されません。
公有地は原則、取得時効の対象にならない
国や自治体が所有する不動産は、原則的に取得時効の対象となりません。公有地は多くの国民の利益になる土地であり、ひとりの私人に対して利益を生む状態を避ける必要があります。そのため、公有地を20年以上占有しても、基本的に取得時効は成立しません。
しかし、例外的に「公用が廃止されたもの」「黙示的に公用が廃止されたと考えられるもの」については、時効取得が認められるケースもあります。公用が廃止されたとは、万人に利用されることがなくなったことです。また、公有地として維持する必要性がないようなもので、長年万人に使われていないものも廃止されたと推定されるケースがあります。
時効取得の手続きの流れ
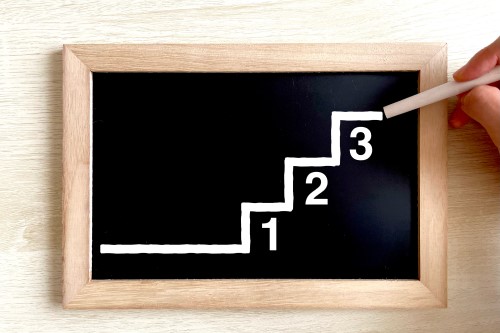
不動産を時効取得する際には、以下の手続きをおこないます。
- 要件を満たしているか確認する
- 相手に時効援用を意思表示する
- 登記の手続きを共同でおこなう
それでは、どのような手順で進めればよいのか詳しく解説します。
要件を満たしているか確認する
取得時効をおこなう場合、まずは要件を満たしているか専門家に確認します。取得時効を成立させるには、いくつもの要件をクリアしなければなりません。状況によっては要件を満たしているか判断しにくいものもあるため、自己判断はせずに弁護士といった専門家に相談しましょう。
相手に時効援用の意思表示をする
取得時効の要件を満たしていることがわかったら、相手に時効の援用をします。時効の援用とは、時効の完成によって利益を得る人が時効の完成を主張することです。
しかし、時効の援用は基本的に相手には受け入れられてもらえないため、どのように手続きを進めたらよいのか理解しておく必要があります。ここからは、以下のケースを想定した手続きについて説明します。
- 相手が登記手続きに協力しない場合
- 土地名義人が死亡している場合
- 土地名義人が所在不明の場合
相手が登記手続きに協力しない場合
取得時効で不動産の所有権を取得する場合、最終的に所有権移転登記をします。しかし、時効で権利を取得される人は、まず登記手続きに協力してくれません。
登記するには前の所有者と権利を取得する人と2人の署名・押印が必要であり、協力してくれない場合は民事裁判で裁判所の決定を仰ぎます。裁判所から取得時効の成立と登記手続きが認められれば、時効で権利を取得する人のみで登記できます。
土地名義人が死亡している場合
占有開始日から成立するまでに土地の名義人が死亡した場合、その土地の相続人と協力して所有権移転登記をおこないます。また、占有開始より前に土地名義人が死亡している場合は、いったん相続人の名義に変更してから、時効で土地を取得する人へ所有権移転登記をおこないます。こちらの場合も、まず相続人の協力は得らないため、裁判所を介して手続きを進める必要があると考えておきましょう。
土地名義人が所在不明の場合
土地名義人が所在不明の場合、不在者財産管理制度といった法的な手続きを進めます。不在者財産管理制度は、家庭裁判所が不在者の所有する財産について利害関係のある人の申し立てにより、財産の保全や売却をおこなう不在者財産管理人を選定する制度です。このような制度を利用すれば、名義人が不在でも土地の取得が可能です。
登記の手続きを共同でおこなう
土地の所有者に協力を得られたら、共同して登記手続きをおこないます。所有権移転登記は、以下の手順で進めます。
- STEP 1法務局などで登記申請書を取得する
- STEP 2取得した書類に必要事項を記載し押印する
- STEP 3登記申請書に必要な書類を添付する
- STEP 4法務局へ登記申請書を持参する(郵送やオンラインでも可能)
内容や添付書類に不備がなければ、申請から1~2週間後には所有権移転登記が完了します。なお、所有権移転登記の手続きは難しく、一般的には司法書士や弁護士に代行してもらいます。
自分が所有している土地の時効取得を阻止したい場合は?
ここまでは土地を「取得時効する側」からみた解説をしましたが、ここでは「される側」について解説します。自分の所有している土地が占有されているとき、取得時効を阻止したいと考える人もいるはずです。
取得時効を阻止するには、以下の方法を用いるとよいでしょう。
- 越境物がある場合は越境を是正してもらう
- 賃貸借契約書がない場合は契約書を作成し締結する
- 第三者に売却し占有者よりも先に登記する
いずれの行為も、取得時効の要件を満たさないようにする措置です。越境物がなくなれば占有の事実がなくなり、賃貸借契約書を締結すれば所有する意思を否定できたりします。どのような解決法が適切かはケースによって異なるため、実際に取得時効を主張されそうな場合は弁護士といった専門家に相談しましょう。
土地を時効取得するためにかかる費用

土地を時効取得するには、以下の費用・税金がかかります。
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 所得税・住民税
- 訴訟費用
- 弁護士・司法書士費用
なお、費用の金額と払うべき費用項目については、取得する土地の価格、取得方法によって異なります。詳細な費用が知りたいという人は、取得時効手続きの依頼先にご確認ください。
まとめ
取得時効の要件を満たせば、他人の土地の所有権が取得できます。しかし、取得時効の要件を満たすには、所有する意思を持って平穏かつ公然に10年もしくは20年占有しなければなりません。
また、要件を満たしても基本的に相手側は登記に協力してくれず、民事裁判の手続きを経て手続きを進めることとなります。そのため、取得時効で不動産を取得する場合は、成立する要件だけでなく手続きの方法まで理解しておく必要があります。取得時効に関連する知識を得ておけば、スムーズな所有権移転が実現するはずです。
物件を探す




