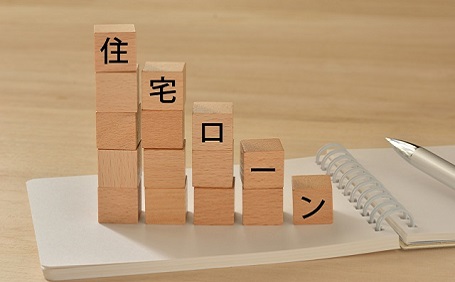残価設定型住宅ローンとは?仕組みから利用が向いている人まで徹底解説

そこで本記事では、残価設定型住宅ローンを初めて知った方や、聞いたことがあっても仕組みがよくわからない方に向けて、基本的な仕組みと特徴をわかりやすく解説します。残価設定型住宅ローンの仕組みやメリット・デメリット、どのような人に適しているかを理解すれば、自分に合った住宅ローン選びに役立つでしょう。
記事の目次
残価設定型住宅ローンとは?
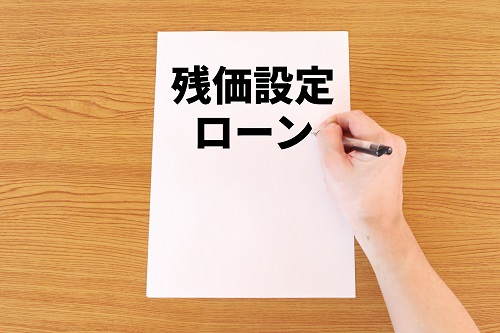
残価設定型住宅ローンとは、住宅購入時に住宅の残価(最終的な価値)をあらかじめ設定し、その残価を除いた金額を分割して返済していく仕組みの住宅ローンです。このタイプのローンは、車のローンでよく耳にするものですが、住宅ローンでは耳慣れない方も多いかもしれません。
なお、この制度は一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」が提供しており、各金融機関とともに運用されています。JTIとは、シニアや空き家所有者を支援するために設立された団体。主に、高齢者が所有する住宅の「マイホーム借上げ制度」を運営し、これによって空き家問題の解消や、住み替えを希望するシニアの生活支援をおこなっています。
残価設定型住宅ローンは、JTIが住宅の価値を見積もり、残価を設定してくれます。JTIが保証する将来における住宅の価値と、ローンの残高が同じ金額になる月の「残価設定月」以降、2つのオプションのどちらかを行使することができるもの。残価設定型住所ローンの仕組みと2つのオプションについて、それぞれ詳しく解説します。
残価設定型住宅ローンの仕組み
残価設定型住宅ローンは、基本的に普通の住宅ローンに加えて、特定のオプションが付随する独自の仕組みです。まず、この住宅ローンを組むためには、従来の住宅ローンとおなじく金融機関から融資を受けます。具体的には、金融機関や住宅金融支援機構が提供するフラット35を扱うモーゲージバンクを通じて借入がおこなわれます。
このローンが特徴的なのはJTIによる残価査定。住宅メーカーからの依頼を受け、将来の買取保証額を見積もります。実現可能な家賃をもとにした計算モデルを用いておこなわれ、将来的にその住宅がどれくらいの価値を持つのかを予測。残価査定が完了すると、残価設定月が設定され、借主は「返済額軽減オプション」を選択できるようになります。これにより残価設定型住宅ローンの借主は、月々の大幅な返済額圧縮ができ、負担軽減が可能です。
さらに、住宅が完成してから50年経過すると、借主は金利のみの支払いとなるので、月々の返済負担はさらに軽く感じられるでしょう。このようにして、借主は残価設定月以降も、通常の賃貸住宅に比べて低い負担で住宅に住み続けられます。もし借主本人とその配偶者が亡くなれば、自動的に買取オプションが発動し、JTIが住宅とそれに関連するローンを引き取ってくれるため安心です。
しかし、相続人がその住宅に住み続けたい場合や、ローンの残高が市場価格を上回る場合には、相続人がローンを引き継ぎ、返済すると住宅を手元に残せます。
このように、残価設定型住宅ローンは、借主に多様な選択肢を提供し、ライフスタイルや将来の変化に対応できる柔軟な住宅ローン。生活環境や経済状況の変化に応じて、返済方法や住宅の扱いを見直せるのが魅力です。
さらに、必要に応じたローンの借り換えや、「買取オプション」も選択できるため、状況に合った選択がポイントとなるでしょう。なお、買取オプションを選択すると、借主は残価設定月以降、住宅ローンの残高と同額でその住宅をJTIに売却できます。住宅の売却しようとすると売却価格が下がったり、そもそも買い手がつかないケースもありますが、買取オプションはそのリスクを軽減することができます。
「返済額軽減オプション」と「買取オプション」のどちらのオプションを行使するかは、任意のタイミングで変更が可能。ライフステージの変化に応じて、ローンの返済を続けるか、買い取ってもらうかの選択ができます。
残価設定型住宅ローンが提供された背景は?
残価設定型住宅ローンが提供される背景には、高齢化社会の進展や住宅資産の流動性の低下が挙げられます。日本では、定年後も住宅ローンを抱える高齢者が増加。定年して収入が減るなかでも、住宅ローンの返済をしなければなりません。そこで、住宅の価値を活かして返済負担を軽減し、老後の生活資金を確保できる残価設定型住宅ローンが提供されるようになりました。この仕組みは、老後の収入減少に備えつつ、住宅を資産として活用できる点で、高齢者や住宅を積極的に活用したい人々にとって大きなメリットがあります。
しかしこのローンを提供できる金融機関は日本住宅ローン、三菱UFJ銀行、楽天銀行の3行に限られるうえ、適用できる物件は基本的に長期優良住宅に限定されます。長期優良住宅とは、省エネルギー性能や耐震性能、バリアフリー性能が高く、長期間にわたって快適な居住が可能な住宅のこと。ご利用を検討される際は、お住いの住宅が対象であるか確認が必要です。
残価設定型住宅ローンのメリット

ここまでは残価設定型住宅ローンの概要を解説しました。ここからは、残価設定ローンの具体的なメリットを見ていきましょう。
残価設定月以降の返済負担が軽減できる
残価設定型住宅ローンのメリットの一つは、返済負担の軽減です。残価設定月以降、返済額軽減オプションを活用すれば、月々の返済額を大幅に削減できます。なお、軽減後の返済額は、近隣で似たような家を借りた場合の家賃相場の半分以下が目安。そのため、定年退職後に収入が減少した場合でも無理なく返済できるでしょう。
売却価格が保証される
売却価格が保証される点もメリットです。仮に、ローンの返済が困難な状況でも家を手放せば残りの返済がなくなるため、リスクを軽減できます。買取オプションにより売却価格が保証されるため、住宅の市場価値が下落した場合でも、損失を避けられる点が大きな利点になるでしょう。場合によっては、残価設定月以降に、設定された残価が住宅の売却価格を上回っている可能性も。そうなると、売却価格と残価の差額は手元に残るため、売却によって利益を得られるかもしれません。いずれの場合も、住宅の資産価値が維持されるのは、大きな安心材料になるでしょう。
老後の収入減に備えられる
老後の収入減に備えられる点もメリットです。住宅を購入する際、通常の住宅ローンでは返済が続く限り、毎月一定額の経済的な負担を負わなければなりません。しかし、残価設定型住宅ローンでは、残価設定月以降に返済額軽減オプションを行使すれば、定年退職後でも少ない負担で住宅に住み続けられます。もし住宅を売却する場合、住宅ローン残高より売却価格が上回っていれば、売却によって利益を得られ、その資金は老後の生活費にすることができます。
ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる
ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる点も残価設定型住宅ローンの重要なメリットの一つでしょう。残価設定月以降は、住宅の売却や再度ローンを組む選択肢が用意されています。このため、家族構成や仕事の都合、生活環境の変化に応じて、柔軟な住居の見直しができるでしょう。
売却価格が残価設定型住宅ローンの残高を上回っていた時、住宅を売却して得られた利益を新たな住居の購入資金として活用できるため、例えば、子どもが成長し独立したあと、広い家から小さい家に移り住みたいと考えている方などにもおすすめです。また住み替えだけでなく、返済額軽減オプションを行使して月々の返済負担額を抑えながら完済すれば、住宅を手元に残せるため、老後に向けた資産形成対策にも有効です。このように、残価設定型住宅ローンは、さまざまなライフスタイルの変化に対応できる柔軟性を持ち、住居の選択肢を広げる手段となるでしょう。
残価設定型住宅ローンのデメリット

さまざまなメリットがある残価設定型住宅ローンですが、もちろんデメリットも。本章では、残価設定型住宅ローンを利用するデメリットを解説します。
住み替え時に資金が必要になる
残価設定型住宅ローンのデメリットの一つは、住み替え時にさらに資金が必要になる点です。残価設定型住宅ローンの加入者が住み替えをする際は、返済額軽減オプションから買取オプションへの移行が可能です。しかし移行しない場合は、新しい住宅に住み替える場合でも残価設定型住宅ローンの返済が続きます。また、再ローンを組む際に金融情勢や自身の収入状況が悪化していると、借り入れ条件が厳しくなる可能性も。このように、住み替え時に必要な資金の確保が難しい場合、経済的なプレッシャーが増す点はデメリットです。
総返済額が多くなる可能性がある
総返済額が多くなる可能性がある点も、残価設定型住宅ローンのデメリットです。例えば、楽天銀行の残価設定型住宅ローンでは、返済額軽減オプションを行使したあとは終身ローンとなります。借り入れから50年経った頃から金利のみの支払いとなりますが、亡くなるまで支払いが続きます。つまり、長生きするほど、金利の支払いが続くことに。返済額軽減オプションを行使すると、総返済額は多くなる可能性がある点に注意しましょう。
住宅のメンテナンスにコストがかかる
住宅のメンテナンスにコストがかかる点もデメリットの一つです。残価設定型住宅ローンでは、将来の売却価格を見込んで住宅の残価を設定します。そのため、住宅の価値を保ち、建物の状態が悪化しないよう、定期的なメンテナンスや修繕が欠かせません。このメンテナンス費用は加入者が負担しなければならず、予期せぬ出費として重くのしかかる可能性があります。残価設定型住宅ローンが適用可能な長期優良住宅は10年に1回の点検が必須になるため、そのための手間や費用がかかります。特に、老朽化が進んでくると、外壁や屋根、給排水設備など大規模な修繕が必要となり、これが高額になるかもしれません。また、経年劣化によるリフォームが避けられない場合、その費用も考慮に入れる必要があります。結果として、通常の住宅ローンよりも資産価値維持のための支出が増える可能性がある点にも注意が必要です。
残価設定型住宅ローンの利用が向いている人とは?

メリットとデメリットが両方ある残価設定型住宅ローンですが、利用が向いている人はどのような人でしょうか。本章ではその特徴を紹介します。
自由なライフスタイルを希望する人
残価設定型住宅ローンは、特に自由なライフスタイルを希望する人に向いているでしょう。このローンの特徴は、残価設定月以降、返済額軽減オプションを行使するか、買取オプションを行使するかを選択できるため、将来的な住み替えやライフスタイルの変化に、柔軟な対応ができます。
例えば、転勤が多い職業に就いている人や、家族構成の変化に応じて住む場所を変更したいと考えている人におすすめです。通常、住宅ローンでは物件を長期間保有し続けるのが前提でしょう。しかし、残価設定型住宅ローンは、残価設定月以降に買取オプションを行使すれば、ローンの返済に縛られることなく、新しい住居に移行できます。そのため、長期間同じ場所に住み続ける必要はなく、ライフステージの変化に応じて住環境を調整する自由が得られる点が便利です。
また、住み替えが容易になるため、例えば定年後に都市から地方に移住したり、ライフスタイルの変化に応じてより小さな住宅に引越す選択もできるでしょう。この柔軟性は、ライフプランが固定されていない人や、生活の変化にともなって自由な選択をしたい人にとって大きな魅力です。
さらに、残価設定月以降、返済額軽減オプションを行使すれば、毎月の支払いが通常よりも軽減されます。そのため、教育費のピークを迎える頃でも経済的余裕を持てるでしょう。すると、浮いたお金を趣味などのほかのものに充てることもできます。結果、残価設定型住宅ローンは、自由なライフスタイルを求める人に対して理想的な選択肢になるでしょう。
現在の住宅の相続人がいない人
残価設定型住宅ローンは、現在の住宅の相続人がいない人にも向いています。相続人がいない場合、住宅を将来誰に引き継げばよいのかが問題になりがちです。通常の住宅ローンでは、住宅を資産として残す考えが前提になりますが、相続人がいない場合、その資産をどう処分するかが定まりません。しかし、残価設定型住宅ローンを利用すれば、残価設定月以降に住宅を買い取ってもらえます。売却価格が住宅ローンの残高を上回れば利益になるうえ、もし住宅の価値が下がっていた場合でも、再ローンを組むなどして対応も可能です。また、住宅を売却して住宅ローンの残高を精算できるため、相続の問題も解決しやすいでしょう。
定年後にも返済が続く設定になっている人
残価設定型住宅ローンは、定年後にも返済が続く人にも向いています。特に、退職後の収入が減少する可能性がある人にとっては、返済負担を軽くして老後の生活資金に余裕が持てるようになるでしょう。
通常の住宅ローンでは、定年後も返済が続くと、年金などの限られた収入で毎月の返済をおこなう必要があり、生活に圧迫を感じるかもしれません。しかし、残価設定型住宅ローンを利用すれば、残価設定月以降、返済額軽減オプションを行使して返済額が抑えられるため、老後の他の支出にも対応しやすくなります。加えて、買取オプションを行使すれば、住宅を売却して住み替えることも可能。このように、老後の状況に合わせた柔軟な対処が可能です。
例えば、売却価格が住宅ローン残高より高ければ、その売却益を老後の生活費に充てられるでしょう。住宅を手放さずに住み続けたい場合でも、返済額軽減オプションを行使すれば返済額を減らせ、一定期間を過ぎれば金利の支払いのみで済みます。これにより、定年後の生活に余裕を持ちながら、無理のない返済計画を継続できます。
残価設定型住宅ローンに関するよくある質問
残価設定型住宅ローンに関するよくある質問をまとめました。
残価設定型住宅ローンとは?
残価設定型住宅ローンとは、普通の住宅ローンに、返済額軽減オプションと買取オプションを行使できる権利が付加されたものです。JTIが提供するこのローンは、長期優良住宅に適用され、シニア層や高齢者の住み替えや生活資金確保を支援するのに役立っています。
残価設定型住宅ローンのメリットは?
残価設定型住宅ローンのメリットは、返済額軽減オプションを行使すると、毎月の返済額が少なくなり、経済的な負担が軽減される点です。また、買取オプションを行使した際には売却価格が保証され、住宅ローン残高と同じ金額で買い取ってくれるため、住宅を手放す際にも住宅ローンに縛られる必要がありません。売却価格が住宅ローン残高よりも高ければ、住宅を売却して資金を得る選択肢があるため、老後の生活費もカバーできるでしょう。ライフスタイルの変化に応じて住み替えがしやすい点も大きなメリットです。
残価設定型住宅ローンのデメリットは?
残価設定型住宅ローンのデメリットは、総返済額が多くなる可能性がある点です。返済額軽減オプションを行使すると、終身ローンとなり、契約者が亡くなるまで金利の支払いが続きます。また、買取オプションを行使せずに住み替えたい場合は、残価設定型住宅ローンの返済を続けなければなりません。この場合、残価設定型住宅ローンの返済に加え、住み替えたローンが必要になり、大きな資金負担が発生する可能性がある点が挙げられます。
新たにローンを組む場合、金利の上昇や返済期間の延長によって総返済額が増える点がリスクです。また、住宅の価値を維持するためには定期的なメンテナンスや修繕が欠かせません。これらのコストが予期せぬ出費となる可能性もあります。結果として、長期的な資金負担が増加するリスクがある点がデメリットです。
残価設定型住宅ローンに向いている人は?
残価設定型住宅ローンは、自由なライフスタイルを望む人や相続人がいない人、そして定年後も返済が続く人に向いています。このローンは、将来の住宅売却や住み替えが可能で、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる点が特徴です。また、相続人がいない場合、住宅を売却して老後の資金に充て、相続の問題を回避できるでしょう。さらに、返済額軽減オプションを行使すれば定年後の収入減少にも対応可能。毎月の返済額を抑えれば老後の生活費に余裕を持てるようになるでしょう。これらの特徴が、自由なライフスタイルを望む人、相続人がいない人、定年後も返済が続く人たちに利用しやすいローンになっています。
まとめ
本記事では、残価設定型住宅ローンの基本的な仕組みや特徴を解説し、毎月の返済額が軽減される点や売却時のリスクを軽減できるメリットを紹介しました。利点もある一方で、長生きするほど返済負担が続く点や住宅の価値維持のためにメンテナンス費用などがかかる点には注意が必要です。
本記事を通じて、残価設定型住宅ローンが、自由なライフスタイルを望む人や、老後の収入減少を見越した計画を立てたい人にとって有効な選択肢になることをご理解いただけたでしょうか。これから住宅ローンを選ぶ際に、最適な選択肢を見つけるための参考になれば幸いです。
物件を探す

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ