住宅ローンの返済期間の平均は?長期的に安定して返済する3つのポイントを紹介

ただし、返済期間を長期に設定する場合は、定年後に収入が減少したあとも返済を続けなければならない点が気になるところ。完済時年齢を意識して、返済計画を立てることをおすすめします。
この記事では、住宅ローンの返済期間の平均を紹介し、返済期間が長期化する理由、長期的に安定して返済するための3つのポイントを解説します。記事を読むことで、住宅ローンの適切な返済期間を決める方法がわかるようになるでしょう。
記事の目次
住宅ローンの返済期間の平均

住宅ローンの返済期間の平均は、国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によると以下のとおりです。
| 住宅の種類 | 返済期間 |
|---|---|
| 注文住宅(新築) | 32.7年 |
| 注文住宅(土地) | 34.4年 |
| 分譲戸建住宅 | 29.7年 |
| 分譲集合住宅 | 28.0年 |
| 既存戸建住宅 | 26.2年 |
| 既存集合住宅 | 29.0年 |
| リフォーム住宅 | 9.6年 |
上記の表からリフォーム住宅を除いて、住宅ローンの返済期間は30年前後であることがわかります。返済期間の平均値のみを示しても、具体的な返済のイメージがつかめないと考えられるため、平均値から住宅ローンを完済するタイミングも考えてみましょう。
完済時年齢は60代~70代
住宅ローンの完済時の年齢は、住宅を最初に取得した平均年齢に、平均返済期間を合わせると計算できます。
| 住宅の 種類 |
取得時の 年齢 |
返済期間 | 完済時の 年齢 |
|---|---|---|---|
| 注文住宅 | 40.1歳 | 32.7年 | 72.8歳 |
| 分譲戸建住宅 | 36.6歳 | 29.7年 | 66.3歳 |
| 分譲集合住宅 | 39.9歳 | 28.0年 | 67.9歳 |
| 既存戸建住宅 | 43.1歳 | 26.2年 | 69.3歳 |
| 既存集合住宅 | 44.2歳 | 29.0年 | 73.2歳 |
出典:国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」
上記の計算で導き出された完済時年齢の目安は、60代~70代。定年が65歳と仮定すると、定年後も住宅ローンの返済を続けている方が多いと考えられます。
以上をもって、住宅ローンの返済期間の平均値は約30年であり、定年後も返済を続ける方が多い結果に。多くの方が住宅ローンの返済期間を長期に設定しているといえるでしょう。
一見すれば、返済期間が長くなるほど利息がかさみやすいため、メリットがあるのか気になる方も多いことでしょう。次の章では、住宅ローンの平均返済期間が長い理由を解説します。
住宅ローンの平均返済期間が長い理由
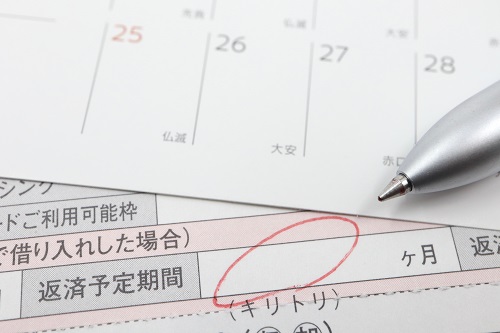
住宅ローンの平均返済期間が長い理由を紹介します。
- 毎月の返済負担を軽減できるから
- 借入可能額が増加するから
- 低金利で利息の負担が相対的に少ないから
- 繰り上げ返済であとから返済期間を短縮できるから
- 住宅ローン控除の期間が10年~13年であるから
- 金融機関が長期ローン商品を提供しているから
それぞれ詳しく見ていきましょう。
毎月の返済負担を軽減できるから
住宅ローンの返済期間を長く設定すると、毎月の返済負担を軽減しやすくなります。同額の借入金額で返済するケースを想定すると、返済期間の違いで返済負担は以下のように変化します。
- 借入金額:5,000万円
- 金利:1.5%
- 金利タイプ:固定金利
- 返済方法:元利均等返済
| 返済期間 | 毎月の返済額 | 利息負担 |
|---|---|---|
| 10年 | 44万8,957円 | 387万4,840円 |
| 15年 | 31万371円 | 586万6,780円 |
| 20年 | 24万1,272円 | 790万5,280円 |
| 25年 | 19万9,968円 | 999万400円 |
| 30年 | 17万2,560円 | 1,212万1,600円 |
| 35年 | 15万3,092円 | 1,429万8,640円 |
5,000万円を住宅ローンで借りたいと考えた場合、10年~20年の返済期間では、月々の負担が20万円を超えるため、返済が難しいと考えるかもしれません。しかし、35年であれば毎月の返済額を15万3,092円まで抑えられるため、借入金額が大きい場合も家計の負担が大きく軽減されます。
返済期間を長く設定すれば、収入を貯蓄に回しながら、無理なく返済を続けられるでしょう。一方で、利息負担は返済期間が長期化するほど重くなるため、注意が必要です。
借入可能額が増加するから
返済期間を長く設定するメリットは毎月の負担を減らすだけでなく、借入可能額が増加することが挙げられます。毎月の返済額の負担が10万円を超えないようにしたいと考えた場合に、返済期間によって変化する借入可能額を見ていきましょう。
- 毎月の返済額の上限:10万円
- 金利:1.5%
- 金利タイプ:固定金利
- 返済方法:元利均等返済
| 返済期間 | 借入可能額 |
|---|---|
| 10年 | 約1,100万円 |
| 15年 | 約1,600万円 |
| 20年 | 約2,000万円 |
| 25年 | 約2,500万円 |
| 30年 | 約2,800万円 |
| 35年 | 約3,200万円 |
返済期間10年の場合と35年の場合で比較すると、借入可能額が約3倍に増えることがわかります。返済期間を長く設定すれば、より高額な住宅を購入しやすいといえるでしょう。
低金利で利息の負担が相対的に少ないから
現在の住宅ローンの金利は、低金利環境にあります。リスクを避けるために長期固定金利の住宅ローンを選んだとしても、利息の負担は相対的に少ないといえるでしょう。よって、低金利環境では利息負担の増加よりも、毎月の返済負担の軽減と借入可能額の増加などのメリットが上回りやすいといえます。
ただし、住宅ローンの金利は経済情勢・政策金利の変動によって変化します。将来にわたってメリットが、利息負担増加のデメリットを上回るとは限りません。
繰り上げ返済であとから返済期間を短縮できるから
相対的に低金利であっても、返済期間が長期化するほど利息の負担が増加することは事実です。それでも、返済期間を長期に設定したほうがいいといわれる理由は、繰り上げ返済によって返済期間を短縮できるため。多くの金融機関では、毎月の返済とは別にまとまった金額を返済する繰り上げ返済を受け付けています。
繰り上げ返済の種類は2種類あります。返済期間を変えずに毎月の返済額の負担を減らす「返済額軽減型」、そして毎月の返済額を変えずに返済期間を短縮する「期間短縮型」です。期間短縮型の繰り上げ返済は、利息負担の軽減効果が高いことから多くの方に選ばれています。
最初に返済期間を長期に設定しても、あとから繰り上げ返済ができるほど貯蓄に余裕ができたのであれば、返済期間と利息の負担を柔軟に調整できます。最初に設定した返済期間を延ばすことは難しいですが、返済期間の短縮は繰り上げ返済を通じて簡単にできるため、繰り上げ返済を含めた返済期間を長期に設定するほうが有利といえるでしょう。
住宅ローン控除の期間が10年~13年であるから
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、一定の条件を満たすと税金の控除が受けられる住宅ローン控除があります。住宅ローンの控除期間は10年~13年であり、控除を最大限に活用して返済するためには、返済期間を控除期間よりも長く設定する必要があるでしょう。
住宅ローンの控除期間の終了と同時に完済する場合でも、返済期間は最低でも10年になります。つまり、返済期間が10年以下になるケースが少なくなるため、返済期間の平均が上がりやすいといえるでしょう。住宅ローンの返済期間を設定する際は、少なくとも住宅ローン控除の期間よりも長く設定することが基本です。
金融機関が長期ローン商品を提供しているから
多くの金融機関では、長期にわたって住宅ローンを返済できる商品が提供されています。住宅ローンの最長の借入期間は金融機関によって異なりますが、一般的に35年です。
しかし、近年ではより長期的に返済できるローン商品も増えており、最長で50年の商品も。金融機関にとっても長期にわたって返済が見込めることから、長期ローン商品が積極的に提供される現状があります。
ただし、返済期間が長期化するほど金利が高くなる傾向にあり、住宅ローンを借り始めた年齢によっては定年を迎えて収入が減少したあとも返済を続けることになるでしょう。個々の購入する物件の金額、設定されている金利、毎月の負担額、完済時年齢を考慮して適切に返済期間を設定する必要があります。必ずしも返済期間の長い住宅ローンがいい商品とは限りません。
住宅ローンを長期的に安定して返済するポイント

ここまでの内容を踏まえると、住宅ローンの返済期間の平均は長く、返済期間を長期に設定することにはさまざまなメリットがあることがわかりました。そのため、住宅ローンは長期的に返済したいと考えている方も多いでしょう。本章では、長期的に安定して返済するためのポイントを3つ紹介します。
- 定年と完済時年齢を意識して返済計画を立てる
- 固定金利の選択で将来的な金利上昇リスクを避ける
- 繰り上げ返済は余裕資金の範囲内でおこなう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
定年と完済時年齢を意識して返済計画を立てる
住宅ローンの返済計画を立てる際には、返済期間が長期化するほど完済時年齢の意識が重要です。返済が長期化するほど、完済のタイミングが定年に近づいたり、定年後になるでしょう。しかし、定年退職後は収入が減少するケースが多いため、住宅ローンの返済負担が現役時代と比較して大きく変化します。
仮に住宅ローンの返済期間が定年以降も続く場合は、在職中で収入が安定している時に繰り上げ返済で返済期間を短縮して、できるだけ定年前に完済することが理想といえるでしょう。一方で、どうしても完済時年齢が定年以降になることが予測される場合は、定年後の返済も考慮して計画を立てます。
先述したように、現在の住宅ローンの平均的な完済時年齢の目安は60代~70代であることから、定年後の返済を含めてシミュレーションを実施することはスタンダードになりつつあるといえます。
固定金利の選択で将来的な金利上昇リスクを避ける
住宅ローンの主な金利の種類には、変動金利と固定金利があります。変動金利は経済情勢の影響を受けて金利が上下するため、住宅ローンの返済中に返済額が変化することも。住宅ローンの返済期間の平均である30年にわたって返済すると考えると、将来的な金利上昇のリスクは無視できません。
固定金利を選ぶと政策金利の上下に左右されず、完済までの返済額が一定となります。固定金利は変動金利と比較して、初期の金利が高いデメリットがあります。その一方で、長期間にわたって住宅ローンを返済する前提であれば、返済期間中の予想外な返済額の増加を回避できるメリットもあります。また、返済額が最初から完済まで固定化されることから、家計に与える影響も安定してシミュレーションしやすいでしょう。長期の返済計画を組むなら、固定金利の採用も有効な戦略です。
繰り上げ返済は余裕資金の範囲内でおこなう
長期間にわたって住宅ローンを組む場合は、返済期間を短縮するために、繰り上げ返済を検討する方もいることでしょう。ただし、住宅ローンの繰り上げ返済は、あくまで余裕資金の範囲内でおこなうことが重要です。
子どもの教育費、医療費などの住宅ローン以外の突発的な出費も発生する可能性があるため、貯蓄を残しながら住宅ローンを返済することを心がけましょう。現在の住宅ローンは低金利の時代であるため、貯蓄に余裕がないのであれば、無理をして繰り上げ返済をおこなう必要はありません。
繰り上げ返済は、将来的な資金計画と突発的な出費に備えられる貯蓄を残したうえで、まとまった資金を返済できる場合におこなうことです。また、繰り上げ返済をする前に実際の効果をシミュレーションしておきましょう。
住宅ローンの繰り上げ返済に関するシミュレーションを以下にまとめました。
- 当初借入金額:4,000万円
- 当初返済期間:35年
- 返済済み期間:15年
- 残り返済期間:20年
- 金利:2.0%
- 繰り上げ返済の種類:期間短縮型
| 繰り上げ返済の額 | 減少する利息額 | 残り返済期間 |
|---|---|---|
| 100万円 | 47万6,280 円 | 19年1カ月 |
| 200万円 | 92万5,683 円 | 18年2カ月 |
| 500万円 | 212万1,906 円 | 15年7カ月 |
| 700万円 | 280万1,310 円 | 13年11カ月 |
| 1,000万円 | 365万8,431 円 | 11年5カ月 |
繰り上げ返済は、おこなうタイミングと返済額によって効果が変わります。基本的には早いタイミングほど有利になりますが、住宅ローン控除の控除期間中は住宅ローン残高が減少すると控除額に影響を及ぼすため、控除期間の終了後におこなうほうがよいでしょう。
上記のとおり、繰り上げ返済に用意できる金額から、減少する利息額と繰り上げ返済後の残り返済期間を算出できます。余裕資金の範囲内で十分な効果が見込めると考えた場合は、繰り上げ返済を実践してみましょう。
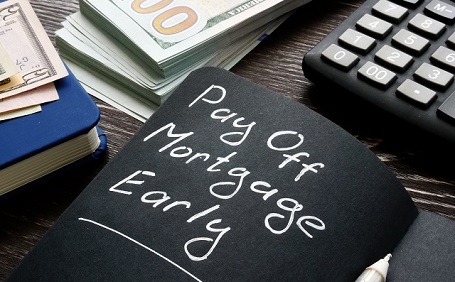
- 住宅ローンは早く返すべき?繰り上げ返済する前に知っておきたい優先事項とは
- 住宅ローンを借りている人の多くは、できるだけ早く住宅ローンを完済したいと考えているでしょう。借入期間が長くなれば、
続きを読む

まとめ
住宅ローンの返済期間は平均して30年前後とされ、長期返済を選ぶことで毎月の返済額を軽減し、より高額な借入が可能となるなどのメリットがあります。しかし、返済期間が長引くと完済時年齢が定年後にずれ込む可能性もあるため、定年以降の収入減少に注意が必要です。
返済計画を決定する場合は、定年と完済時の年齢を十分に考慮し、将来的な金利上昇を避けるために固定金利を選ぶなど、リスクに対する対策をしましょう。
余裕資金がある場合は、繰り上げ返済を活用できるため、無理のない範囲で返済期間を柔軟に短縮できます。返済が長期間にわたる住宅ローンは、計画的かつ安心して返済を進めることが可能です。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ




