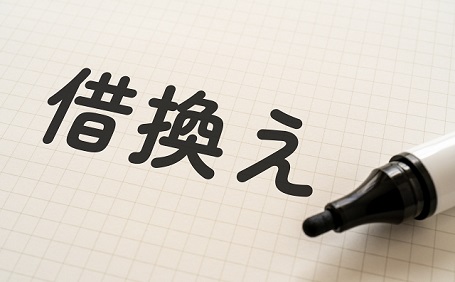住宅ローンの連帯債務は離婚すれば解消する?債務者から抜け出す方法を解説!

そこで本記事では、住宅ローンの連帯債務の概要や、どのようにしてその責任を解消するかを解説します。また、住宅ローンの名義変更など、対応にあたって知っておくべき情報もご紹介します。離婚後の住宅ローンの取り扱いや、連帯債務者としての責任をどう扱うべきか、具体的な対処方法の参考にしてみてください。
記事の目次
住宅ローンの連帯債務とは

連帯債務とは、夫婦が協力して返済をする住宅ローンの形態の一つです。本章では連帯債務型の住宅ローンを解説します。
連帯債務型の住宅ローンとは
住宅ローンの連帯債務とは、複数の人が共同で住宅ローンを借り入れ、その返済義務を分担する形態です。特に夫婦で利用されることが多く、夫婦がともに住宅ローンの債務者となり、それぞれが返済責任を負うことになります。つまり、ローン契約で債務者が複数人のため、もし一方が返済できなくなった場合、もう一方がその分を負担します。連帯債務では、各自の収入を合算して審査を受けるため、単独では借りられないような、高額なローンを組むことができる点が大きな特徴です。
連帯債務型の住宅ローンのメリット
連帯債務型の住宅ローンのメリットを3つ解説します。
- 収入合算で借入額が増加する
- 住宅ローン控除を夫婦で受けられる
- 共同で資産を所有できる
夫婦など複数人の収入を合算して借入可能額を上げることができるため、理想的な住宅を購入しやすくなります。例えば、夫婦で合算して年収700万円と審査されることで、単独では借りられない高額な住宅ローンを組むことが可能。
また、住宅ローンの返済負担に応じて、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため税金面での節税効果も期待できます。
さらに、連帯債務型では、購入した住宅の所有権も債務者が共同で所有するため、住宅に対する権利を夫婦平等に保つことができます。
連帯債務型の住宅ローンのデメリット
次に、連帯債務型のデメリットを見ていきましょう。
- 返済義務が重い
- 離婚時の調整が難しい
- 住宅ローン控除の申請が複雑になる
連帯債務型の住宅ローンでは、一方が返済不能になった場合、もう一方が全額を返済する責任を負うことになります。例えば、夫が失業した場合、妻がその分を全額返済する義務が発生し、経済的な負担が一気に増えるリスクも。
また、連帯債務者が離婚した場合、どちらかが住宅ローンの返済をし続ける必要があるため、財産分与や返済責任の分担でトラブルが生じる可能性があります。特に、住宅の売却額が住宅ローンの残高に満たない場合、残りの債務を夫婦で分担しなければなりません。
さらに、住宅ローン控除を受ける際には、負担割合に応じて申請が必要となり、手続きが煩雑になります。また、収入が多い方に多くの控除を集中させることが難しく、柔軟性に欠けることがあります。
以上のように、連帯債務型の住宅ローンは、住宅の購入を支援してくれる有効な手段ですが、返済責任やリスクの分担が重要なポイントとなります。
離婚する場合に住宅ローンにおける連帯債務者はどうなる?

離婚する場合、婚姻中に共同で築いてきた財産は分け合いますが、負債はどのように扱われるのでしょうか。特に、連帯債務型で住宅ローンを契約している場合、離婚になると自動的に連帯債務を外れるのでしょうか。そこで本章では、離婚時に連帯債務から外れられるのかを解説します。
離婚しただけでは連帯債務を抜けられない
離婚したら自動的に連帯債務者から外れるわけではありません。その理由は、住宅ローンの契約は、夫婦の共同責任のもとで結ばれており、離婚は個人的な事情に過ぎないためです。連帯債務型の住宅ローンでは、借り入れをした夫婦の両方が返済義務を負っているため、離婚で責任が自動的に解除される取り扱いはありません。金融機関が、事情に基づいてローン契約を変更したり、債務者を削除・変更するわけではありません。そのため、家に住まなくなっても、ローンの返済義務は残り、連帯債務者の責任を負い続けます。基本的に離婚してもなお、住宅ローンの返済は元妻・元夫の両方に請求されます。
もし、連帯債務者から外れたい場合は、金融機関の承認を得て契約内容を変更しなければなりません。そのためには再審査が必要で、引き継ぎ者が住宅ローンを負担できる経済状況が求められます。
主債務者が全額支払うと約束しただけでは連帯債務を抜けられない
離婚後、元妻が自宅を得る代わりに元夫が住宅ローンの全額を返済する合意があっても、元妻が自動的に連帯債務者でなくなるわけではありません。連帯債務者の責任は、金融機関との契約に基づくことから、個人的な合意や財産分与の内容だけでは変更できないためです。
元夫が住宅ローンの全額を返済するとした場合でも、元妻が連帯債務者としての責任を解除するためには、金融機関の承認を得て契約を変更しなければなりません。金融機関は、ローンの返済能力や条件を審査したうえで、新たな契約を結ぶため、元夫がローンを引き継ぐ場合でも再審査が必要です。この再審査が通れば、元妻は連帯債務者から外れる可能性がありますが、単に財産分与で合意しただけでは連帯債務者としての責任は消えません。
離婚を理由に住宅ローンの連帯債務を抜けるためには?

離婚する場合、通常ならもう住まない住宅のローンを返済し続ける連帯債務者はやめたいと思うでしょう。ではどのようにすれば、離婚後、住宅ローンの連帯債務者から外れるのでしょうか。本章では、離婚後に連帯債務者から外れる方法を解説します。
新しい連帯債務者と交代する
新しい債務者と交代できれば、連帯債務者から外れることができます。これは、既存の連帯債務者がローンの返済責任を他の人に引き継ぐ手続きです。この手続きをおこなうためには、まず金融機関と協議し、契約の変更を申し出なければなりません。金融機関は、新しい債務者の信用情報や返済能力を再審査し、その結果に基づいて承認を出します。新しい債務者が既存の債務を引き受ける条件が整えば、金融機関は契約変更をおこない、元の連帯債務者の責任は解消されます。
しかし、この方法を成功させるためには、いくつかの条件があります。新しい債務者が十分な返済能力を持っていなければ、金融機関は承認を出しません。また、引き継ぎの手続きには、時間と手間がかかり、すべての当事者(元債務者、新しい債務者、金融機関)の同意が必要です。新しい債務者と交代すれば連帯債務者から外れますが、金融機関の審査に通過することが前提になります。
住宅ローンを借り換える
住宅ローンを借り換えることも、連帯債務者から抜け出す方法の一つになります。借り換えとは、現在の住宅ローンを一度完済し、新たに住宅ローン契約を結ぶ手続きです。借り換えをおこなうには、まず金融機関に申し込んで新しい住宅ローンを借りなければなりません。新たな契約を結ぶ際、連帯債務者を外し、単独名義でローンを組むケースがあります。しかし、そうなると借り換え後、新しい債務者(通常は残る元夫婦の一方)が全額返済の義務を負います。
この方法のメリットは、連帯債務者から外れる点に加えて、金利の見直しや返済条件を有利に変更できる可能性がある点です。しかし、借り換えには審査が必要で、特に収入や信用状態に問題があると、承認されない可能性があるため注意しましょう。また、借り換えには手数料や事務費用がかかるため、これらのコストも考慮しなければなりません。
他の財産を担保にする
連帯債務者から外れるために、他の財産を担保にする方法もあります。その方法は、他の財産(他の不動産や貯金など)を担保にして、現在の住宅ローンの一部または全額を別のローンで返済する形式です。この手法を取ると、元々の住宅ローンに対する連帯債務者の責任を外せるでしょう。例えば、元妻が元夫と共同でローンを組んでいた場合、元妻が自分名義の別の不動産を担保にして新たなローンを組み、この新しいローンで元夫の返済負担をカバーします。この方法で、連帯債務者から外れるでしょう。
ただし、新しい担保を提供できる資産評価額や返済能力がないとこの方法はとれません。また、金融機関がこの方法を承認するためには、担保として提供する財産の価値を証明する必要もあります。さらに、財産を担保にして、新たなリスクや負担が生じる点も考慮しなければならないでしょう。
住宅ローンを完済する
住宅ローンを完済する方法も、連帯債務者から外れる方法の一つです。住宅ローンを完済すれば、連帯債務者は住宅ローンに対する責任がなくなり、返済義務から解放されるでしょう。例えば、連帯債務者が住宅を売却したり、他の資産を使ってローンを返済する方法が考えられます。
売却額がローン残高に足りる場合には、その全額を金融機関に支払えば完済できます。しかし、売却額がローン残高を下回る場合、差額にも責任を負わなければなりません。この方法は、確実な方法ですが、実現できる方は少ないかもしれません。相応の資金が必要になるため、慎重に計画を立て、必要な手続きをおこないましょう。
住宅ローンの連帯債務で離婚する場合に知っておくべき情報は?

連帯債務型の住宅ローンと離婚が絡むケースは、誰もが必ず経験するわけではありません。ただ、いざその状況に直面した際に、適切な対処法を知らなければ、大きなトラブルに発展する可能性があります。そこで今回は、連帯債務型の住宅ローンを契約していて、離婚する際に、知っておくべき情報を解説します。
連帯債務者には求償権が認められる
連帯債務型の住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚する際、求償権の存在を理解しておく点は重要です。求償権とは、連帯債務者の一方が全額または過剰な返済をした場合、他方の連帯債務者にその負担分を請求できる権利を指します。
例えば、夫と妻が連帯債務で3,000万円の住宅ローンを組んでいるケースで考えてみましょう。この場合、夫婦で1,500万円ずつの負担をしているとします。離婚後、夫が家に住み続ける一方で、妻が家を出てローンの返済をしなくなった場合、夫が月々の返済を全額負担しなければなりません。この時、夫は妻の負担分を求償権に基づいて請求できます。
しかし、実際に求償権を行使するためには、課題をクリアしなければなりません。例えば、妻が返済に応じない場合や、すでに経済的に困窮している場合、請求した額が回収できない可能性があります。また、求償権を主張すると、離婚後の関係が悪化し、法的トラブルに発展するリスクもあるでしょう。そのため、離婚時には住宅ローンの返済に十分に協議し、分担や負担の解消を書面で取り決めておく点も欠かせません。求償権は法律上の権利ですが、現実的には行使が難しい場合も多いため、事前に適切な対策を講じる必要があります。
住宅の名義変更を忘れないようにする
連帯債務型の住宅ローンを組んでいる場合、離婚後には名義変更を忘れないようにしましょう。名義変更を怠ると、実際に住まない側の元配偶者が不必要なリスクを負い続ける可能性があります。特に、住宅ローンの返済が滞った場合、名義が残っている限り、債務の責任を問われる可能性があり、信用情報にも影響が出る恐れがあるので注意が必要です。
例えば、夫婦で連帯債務型の住宅ローンを組み、離婚時に「住宅を夫が所有し、ローンも夫が返済を続ける」と取り決めをしたとしましょう。この場合、住宅ローンや住宅の名義が妻のまま残っていると、夫が返済を怠った際に、金融機関が妻にも返済を請求できてしまいます。また、住宅ローンの滞納情報が妻の信用情報に記録されると、のちに妻が別の住宅ローンを組む際や、クレジットカードの利用に支障が生じるかもしれません。
名義変更をおこなえば、実際に返済の責任を負う人に名義が統一され、不必要なトラブルやリスクを回避できます。ただし、名義変更には金融機関の審査や手続きが必要になり、場合によっては新しいローンの組み直しが求められるかもしれません。そのため、離婚時には、名義変更の重要性を認識し、早めに対処しましょう。
困ったら専門家に相談する
連帯債務型の住宅ローンを組んでいる場合、離婚にともなう問題を解決するなら、専門家に相談するようにしましょう。先述したように、連帯債務型は夫婦双方が住宅ローンの全額に対して同等の返済責任を負う仕組み。そのため、離婚による財産分与やローンの引き継ぎ、名義変更など複雑な問題が生じやすくなります。
例えば、離婚後にどちらか一方が家に住み続け、もう一方が連帯債務者から外れたい場合、新たなローン契約や金融機関の審査をしなければなりません。また、住宅を売却してローンを完済する場合でも、売却額がローン残高を下回れば、不足分の処理が課題になります。
こうした手続きは法律や税金、不動産取引の知識が関わるため、適切な判断を下すのが難しいです。そのような時、弁護士や司法書士に相談すれば、法的な問題や契約書の作成に関する適切なアドバイスが得られるでしょう。また、ファイナンシャルプランナーは、財産分与やローン再編成後の家計の見通しを立てる際に役立ちます。さらに、不動産会社や税理士に相談すれば、物件売却や税金の最適なプランを知ることができて便利です。専門家のアドバイスを受けると、予期せぬトラブルを回避し、安定した生活を築けるでしょう。
連帯債務の住宅ローン返済中に離婚する場合に関するよくある質問
連帯債務の住宅ローン返済中に離婚する場合に関するよくある質問をまとめました。
住宅ローンの連帯債務とは?
連帯債務型の住宅ローンは、複数の人(通常は夫婦)が共同で借り入れ、返済義務を分担する形態です。各自が返済責任を負うため、一方が返済不能になった場合、もう一方がその分を負担します。メリットは、収入合算で高額なローンを組める点、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる点、共同で資産を所有できる点の3つ。一方、デメリットは、一方が返済不能になった際の負担増加、離婚時の返済責任の分担問題、住宅ローン控除の申請手続きの煩雑さがあります。連帯債務型は住宅を購入する際の手助けとして有効ですが、返済責任やリスクの分担を慎重に考慮しなければなりません。
住宅ローンの連帯債務者で離婚する場合は?
離婚しても住宅ローンの連帯債務者からは自動的に外れません。連帯債務型の住宅ローンは、夫婦双方が借り入れに責任を負う契約です。離婚は個人的事情に過ぎないため、金融機関との契約内容が変更されない限り、返済義務が残ります。たとえ離婚後、元夫がローン全額を返済するという合意があっても、それだけで元妻が連帯債務者から外れるわけではありません。連帯債務者から外れるためには、金融機関の承認を得て契約内容を変更する必要があります。そのためには、新たな主債務者の返済能力で金融機関が再審査をおこない、承認を得る手続きが必要です。こうした手続きを経ずに、単なる合意や財産分与だけで連帯債務者から外れるわけではありません。
離婚後に住宅ローンの連帯債務から抜ける方法は?
まず、新しい連帯債務者を立てて交代する方法があります。ただし、金融機関の審査が必要です。また、借り換えで住宅ローンを単独名義に変更する方法もありますが、信用力や手数料が課題になるでしょう。他の財産を担保にしてローンを完済する方法や、住宅を売却して残高を返済する方法もありますが、売却額がローン残高を下回る場合、差額負担が必要です。確実な方法はローンを完済する方法ですが、多額の資金が必要になります。
住宅ローンの連帯債務で離婚する場合に知っておくべき情報は?
住宅ローンの連帯債務が絡む離婚では、適切な対応が重要です。まず、連帯債務者には求償権があり、一方が過剰に返済した場合、他方に負担分を請求できる点を把握しておきましょう。ただし、確実に回収できるわけではなく、法的トラブルのリスクがあるため、離婚時に返済負担を明確に協議し、書面で取り決めておく点に留意が必要です。次に、住宅やローンの名義変更を忘れないように注意しましょう。名義が残ると返済滞納時に責任がおよび、信用情報にも影響を与える恐れがあります。名義変更には手続きや新ローン契約が必要な場合もあるため、早めの対応が必要です。離婚の際には複雑な問題が生じやすいので、弁護士や司法書士、不動産会社など専門家に相談しましょう。
まとめ
本記事では、住宅ローンの連帯債務者から外れる方法や、離婚後に注意すべきポイントを具体的に解説しました。住宅ローンの連帯債務者が離婚する場合、責任は自動的に解消されず、金融機関の審査や契約変更手続きが必要になります。必要な手続きや解消の方法を理解して、対処に役立ててください。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ