住宅ローンの連帯保証人になれない人の特徴とは?3つのリスクも解説

どのようなケースに連帯保証人が必要で、どのような人が連帯保証人になれないのか気になる人もいるでしょう。
本記事では住宅ローンを組む際に、連帯保証人になれない人の特徴や連帯保証人になるリスクを解説します。
記事の目次
連帯保証人とは?保証人や連帯債務との違いを解説
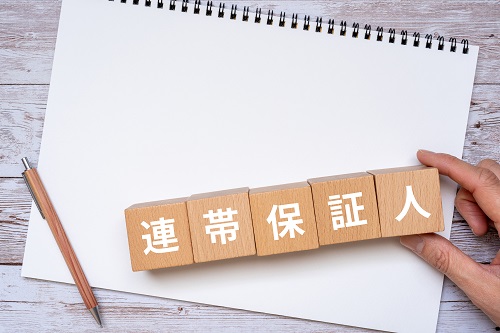
まず、連帯保証人の定義から解説します。
似た言葉に「保証人」と「連帯債務」があるため、一つずつ詳しく見ていきましょう。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者が債務の履行をしなかった際に、債務を代わりに履行する責任を負う人のことです。
住宅ローンの連帯保証人は、契約者が返済義務を果たさなかった際に、代わりに返済する責任を負います。
連帯保証人になるには、信用力や経済的な安定性が求められることが一般的です。
契約者の返済能力が不安定な際や信用力が低いと金融機関のリスクが高くなり、融資を受けられない可能性が高くなりますが、連帯保証人をつけることで融資を受けられる可能性が高くなります。
ただし、連帯保証人になることは重要な責任をともないます。
契約者が返済不能になると連帯保証人は代わりに住宅ローンの返済をしなければならないため、慎重に判断しリスクを理解したうえで連帯保証人になる必要があるでしょう。
保証人とは
保証人とは、債務者が債務の履行をしなかった際に、債務を代わりに履行する責任を負う人である点は、連帯保証人と共通しています。
連帯保証人と異なる点としては、以下の3点です。
| 連帯保証人 | 保証人 | |
|---|---|---|
| 貸金業者から返済の請求をされた時 | まず住宅ローンの契約者に請求することを主張できない | まず住宅ローンの契約者に請求することを主張できる |
| 契約者に返済義務があるにも関わらず返済をしなかった時 | 住宅ローンの契約者に対する強制執行を主張できない | 住宅ローンの契約者に対する強制執行を主張できる |
| 保証人が複数いる時 | 保証人が複数人いても全額負担する必要がある | 保証人の頭数で割った金額を負担すればよい |
保証人が連帯保証人よりも軽い責任となることがわかります。
連帯債務
連帯債務とは、二人の収入を合算して住宅ローンを組むことで、それぞれが主債務者と連帯債務者となるローンのことです。
連帯債務で住宅ローンを組む際には、主債務者と連帯債務者が同等の債務を負うことになるため、主債務者が返済できなくなった場合には連帯債務者に返済義務が発生します。
しかし、主債務者の年収だけでは希望の融資額まで到達できなくても、収入のある配偶者が連帯債務者となることで、希望の物件を購入できる可能性が高くなるでしょう。
配偶者以外にも連帯債務者になれる可能性がありますが、金融機関によって基準が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
一例として、全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」では以下の人が連帯債務者になれると定めています。
- 申込みご本人の親、子、配偶者等
- 申込時の年齢が70歳未満の方
- 申込みご本人と同居される方
引用:フラット35
連帯債務で住宅ローンを組めば、連帯債務者も主債務者と同様の住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローンを組む際に連帯保証人になれない人の4つの特徴
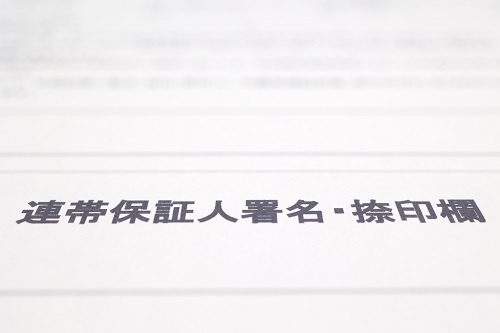
住宅ローンを組む際に連帯保証人になれない人の特徴は以下の4つです。
- 経営や収入が安定していない人
- 信用情報に傷がついている人
- 年金を受け取っている人
- 転職を繰り返している人
順番に見ていきましょう。
経営や収入が安定していない人
住宅ローンを組む際に連帯保証人になれない人の1つ目の特徴は、経営や収入が安定していない人です。
具体的には、自営業やフリーランスなどが挙げられます。
自営業は会社員や公務員とは異なり、経営や収入が不安定であると判断されるため、連帯保証人になれないことが多いです。
個人事業主の人は、一時的に高い収入を得られても、常に一定の収入を得られるわけではありません。
ただし、個人事業主でも収入が安定している人は審査に通る可能性があるため、連帯保証人になる際は数年分の収入証明書を保管しておきましょう。
信用情報に傷がついている人
住宅ローンを組む際に連帯保証人になれない人の2つ目の特徴は、信用情報に傷がついている人です。
連帯保証人に限らず、住宅ローンを組む際には信用情報に傷がついていると「返済能力がない」と判断される可能性があります。
借金の滞納があったり、過去に返済を遅延したりしている人は、金融機関にとってリスクがある人物であるため、連帯保証人にはなれません。
ただし、借金を全額返済し、一定期間が経過すれば信用情報が回復して連帯保証人になれる可能性がある点は、覚えておきましょう。
年金を受け取っている人
住宅ローンを組む際に連帯保証人になれない人の3つ目の特徴は、年金を受け取っている人です。
連帯保証人は、住宅ローンの契約者と同等の返済責任を負うことになるため、返済能力があるかが基準となります。
年金を受け取っている人は、自分で働いて収入を得ている給与所得者などと比較すると返済能力がないと判断されます。
また、年金受給者は高齢であるため、住宅ローンの契約者が返済しなかった際に責任を負う連帯保証人としては、十分な返済能力がないと判断される可能性が高いです。
転職を繰り返している人
住宅ローンを組む際に連帯保証人になれない人の4つ目の特徴は、転職を繰り返している人です。
転職を繰り返している人は、収入が何度も変化し、安定した収入が得られていないと判断されます。
先述した個人事業主と同様に、収入が安定していない人は連帯保証人になれません。
住宅ローンの審査を受ける際には、1度や2度の転職でも審査に影響が出る可能性があるため、3度以上転職を繰り返している人は審査に落ちる可能性が高いでしょう。
住宅ローンの連帯保証人がほとんどのケースで不要な2つの理由

住宅ローンの連帯保証人になれない人の特徴を解説しましたが、住宅ローンを組む際、ほとんどのケースで連帯保証人が不要となります。
連帯保証人が不要となる2つの理由を解説します。
不動産を担保にできるため
住宅ローンの連帯保証人が不要となる1つ目の理由は、不動産を担保にできるためです。
住宅ローンを組む際は、一般的には購入する不動産を担保にするため、連帯保証人をつけなくても不動産を売却して債権を回収できます。
不動産の価格は高額であることが多いため、連帯保証人が債務の責任を負わずに債権を回収できるでしょう。
金融機関は契約者が返済不能になった時に債権を回収できれば問題ないため、不動産を担保にすることで連帯保証人が不要となります。
原則保証会社を利用するため
住宅ローンの連帯保証人が不要となる2つ目の理由は、原則、保証会社を利用するためです。
多くの金融機関では、保証人ではなく保証会社を利用します。
保証会社を利用すれば一定の手数料を支払うことになりますが、身内の人や友人などに連帯保証人になってもらう必要がありません。
金融機関によって手数料の金額が異なるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となる6つのケース

住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となるケースは以下の6つです。
- ペアローンを組むケース
- 不動産が共有名義となるケース
- 金融機関から求められるケース
- 収入合算をするケース
- 契約名義人と担保の不動産名義人が異なるケース
- 好条件で融資を受けたいケース
順番に見ていきましょう。
ペアローンを組むケース
住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となる1つ目のケースは、ペアローンを組むケースです。
ペアローンは、夫婦や親子関係にある二人が一つの物件に対してそれぞれで住宅ローンを契約することで、共同で借入ができるローンのことで、双方が連帯保証人になる必要があります。
希望の借入金額に対して契約者の収入が不足している際に、配偶者や親の年収を合算し希望金額を借りられる可能性が高くなります。
ただし、ペアローンは2本の契約をすることになるため、事務手数料が2倍になることや一方の返済能力がなくなった際のリスクを負う点には、注意が必要です。
不動産が共有名義となるケース
住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となる2つ目のケースは、不動産が共有名義となるケースです。
不動産が共有名義で契約者が単独で住宅ローンを組む際には、共有名義人が連帯保証人となる必要があります。
本来であれば、住宅ローンの負担割合と不動産の持分割合は同等にする必要があるため、割合が異なると連帯保証人が必要となるため、覚えておきましょう。
金融機関から求められるケース
住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となる3つ目のケースは、金融機関から求められるケースです。
住宅ローンを組む際には、金融機関の審査に通過する必要があります。
住宅ローンの審査では、年収や勤続年数、年齢などが基準となりますが、契約者の返済能力が低いと判断されると、連帯保証人を要求されることがあります。
連帯保証人をつけることで希望する金額の住宅ローンを組める可能性が高くなるでしょう。
収入合算をするケース
住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となる4つ目のケースは、収入合算をするケースです。
収入合算とは、夫婦の収入を合算して融資を受けるローンのことです。
先述したペアローンと似ていますが、収入合算は1本の契約で、契約者ではない人が連帯保証人となります。
ペアローンと収入合算には双方にメリットやデメリットがあるため、金融機関に相談するのがおすすめです。
契約名義人と担保の不動産名義人が異なるケース
住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となる5つ目のケースは、契約名義人と担保の不動産名義人が異なるケースです。
住宅ローンを組む際には、一般的に土地と建物を担保にしますが、土地と建物の名義人が異なるケースがあります。
具体的には、親が所有している土地に子が家を建てるケースです。
子が家を建てるため、住宅ローンの契約者は子となりますが、土地の名義人である親が連帯保証人になる必要があります。
好条件で融資を受けたいケース
住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要となる6つ目のケースは、好条件で融資を受けたいケースです。
追加の保証を提供することで、金融機関は借り手によりよい貸付条件を提供できることがあります。
連帯保証人をつけることで、金利の引き下げや返済期間の延長など、より有利な条件を実現する一因となることがあります。
事前に金融機関に確認しておくよいでしょう。
住宅ローンの連帯保証人になる際の3つのリスク

住宅ローンの連帯保証人になる際のリスクは以下の3つです。
- 住宅ローンの契約者が自己破産や滞納するリスク
- 離婚をした時のリスク
- 住宅ローンの契約者が死亡した時のリスク
順番に見ていきましょう。
住宅ローンの契約者が自己破産や滞納するリスク
住宅ローンの連帯保証人になる際の1つ目のリスクは、住宅ローンの契約者が自己破産や滞納するリスクです。
住宅ローンの契約者が返済を滞納すると、連帯保証人に返済の請求が来るようになり、保証人とは異なりさまざまな主張ができずに支払いに応じるしかありません。
また、契約者が自己破産すると契約者の支払い義務は免除されますが、代わりに連帯保証人が債務の責任を負うことになります。
連帯保証人も、返済ができないと自己破産に追い込まれてしまう可能性があるため、注意しましょう。
離婚をした時のリスク
住宅ローンの連帯保証人になる際の2つ目のリスクは、離婚をした時のリスクです。
住宅ローンの契約者の配偶者が連帯保証人になると、離婚をしても連帯保証人の責任が免除されることはありません。
離婚をして購入した住宅に住まなくても連帯保証人としての責任を負い続けることになります。
借り換えや一括で繰り上げ返済をするなど、連帯保証人の責任を解除する方法はありますが、手続きや資金が必要となります。
住宅ローンの契約者が死亡した時のリスク
住宅ローンの連帯保証人になる際の3つ目のリスクは、住宅ローンの契約者が死亡した時のリスクです。
住宅ローンの契約者が死亡して不動産の名義が相続人に移転されても、連帯保証人の債務の責任は免除されません。
ただし、契約者が団体信用生命保険に加入して住宅ローンを組んでいる場合には、死亡時に住宅ローンの返済が0になります。
多くの金融機関では、住宅ローンを組む際に団体信用生命保険の加入が義務付けられていますが、一部の金融機関では加入せずに契約ができるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
住宅ローンを組む際に、ほとんどのケースで連帯保証人は不要となりますが、6つのケースでは連帯保証人が必要となります。
収入が不安定な人は住宅ローンの契約者だけではなく、連帯保証人になれないでしょう。
連帯保証人になるにはリスクを負うことにもなるため、不安な人は金融機関に相談することをおすすめします。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





