住宅ローンの保証料の返金はある?返金されるタイミングや保証料の考え方を解説

そこで本記事では、住宅ローンの保証料とは何か、保証料を決める要素にはどのようなものがあるのかを解説します。また、保証料の計算方法にはどのようなものがあり、どのようなケースでいつ返金されるのかも解説するため、ぜひご参考ください。
記事の目次
住宅ローンの保証料とは?

住宅ローンの保証料とは、借主が住宅ローンの契約時に金融機関が提携している保証会社に対して支払う費用です。住宅ローンで借り入れをするために、借主は各金融機関と契約を交わしますが、融資にあたって返済が滞る可能性を考慮して、貸主である金融機関は保証会社を利用します。
もし借主が返済不能になった場合、金融機関は保証会社から住宅ローンの残債を回収するでしょう。そうすることで、金融機関は貸し倒れを防いでいます。場合によっては、抵当権の付いている住宅を競売にかけて現金化し回収を実行する時もあります。
住宅ローンをはじめとした融資を利用する際には、連帯保証人を立てるケースが一般的でした。ただ、連帯保証人を用意したり、その人の審査にも工数がかかるため、借主・貸主両方の負担になってしまいます。そこで近年では、連帯保証人のかわりに保証会社を利用する金融機関が多くみられるようになりました。
保証料を決める要素は?
保証料を決める要素になるものは4つあります。以下、それぞれ説明します。
借入金額
保証料を計算するには、借入金額に対して保証料が何割と決めるケースが多いです。そのため、保証料の金額は借入金額に左右され、借入金額が多いほど高額になる傾向があります。保証会社から考えれば、借入金額が多いほどリスクが高くなるので、その分保証料も高くなるでしょう。
支払方法
支払方法の違いも、保証料を決める要素になります。後ほど説明しますが、保証料の支払いは、一括と分割の2種類があります。一括払いをすれば事務手数料は1回きりですが、分割払いにすれば支払いのたびに事務手数料が必要です。結果的に、一括払いよりも分割払いのほうが総額が高くなるなど、支払方法の違いによっても保証料が異なります。
返済期間
住宅ローンの返済期間が長くなるほど、保証料の金額は増えます。なぜなら、返済期間が長いほど住宅ローンを全額回収できないリスクが上がり、保証をすべき期間が長くなるからです。反対に返済期間が短ければリスクも下がるので、返済期間は短いほうが保証料は安くなるでしょう。
利用する金融機関
利用する金融機関によって保証会社が異なり、それぞれに独自の基準で保証料を設定しています。そのため利用する金融機関によって、保証料は大きく異なります。保証料は高かったり安かったり、あるいは保証料は不要など金融機関によってさまざまです。
保証料はこれまでに述べた要素によって決まり、数十万円から100万円程度の金額になる場合も。保証料は住宅ローン関連費用のなかでも、大きな割合を占める可能性があります。大手の金融機関を利用して住宅ローンを組む場合は、保証会社を利用する傾向が高いです。住宅ローンの比較で保証料なども検討する時は、内容をよく確認して選びましょう。
保証料の支払い方法は?
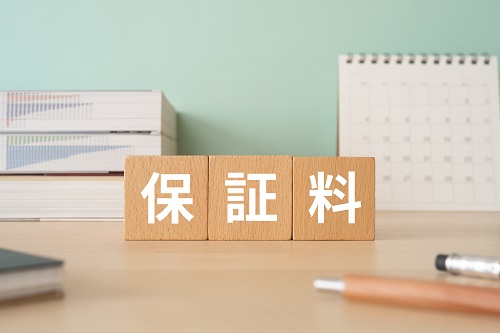
保証料の支払い方法には、「外枠方式」と「内枠方式」があります。以下、それぞれの違いと特徴や相場、計算の仕方を解説します。
外枠方式
外枠方式とは、住宅ローンの契約当初に保証料を一括で支払う方法です。保証料は全額前払いになるので、住宅ローンの返済期間中に追加で保証料を支払うことはありません。
保証料の相場は、住宅ローンの借入金額の2.2%が一般的です。例えば、住宅ローンの借入金額が4,000万円で保証料が2.2.%の場合、4,000万円×2.2%=88万円になります。
外枠方式で支払った保証料は、繰り上げ返済をすると一部返金される場合があります。例えば、外枠方式で返済期間が35年の住宅ローンを組み、25年目に繰り上げ返済をしたとします。すると、残った10年の返済期間に対して支払っている保証料が、規定に応じて一部返金されます。なお、計算方法などは金融期間によって異なるので、詳細は利用している金融機関に確認しましょう。
外枠方式を利用すると、保証料を一括で支払うので、一時的に手元から大きな自己資金が出ていきます。住宅ローンの返済を始めた当初の支出はありますが、それ以降保証料の支払いは必要ありません。最終的に、住宅ローンの返済期間が同じであれば、後述の内枠方式よりも保証料の支払総額は少なくなります。住宅ローンの契約時にまとまった一時金を用意できて、総支出を抑えたいと考えるのであれば、外枠方式を選択するのがいいでしょう。
内枠方式
内枠方式とは、保証料を分割し住宅ローンの返済に上乗せして毎月支払っていく方法です。
保証料の相場は、住宅ローンの借入総額の金利に0.2%程度上乗せして計算されるのが一般的です。例えば、住宅ローンの金利が年0.4%の場合だと、保証料として0.2%の金利上乗せ、合計で0.6%の金利になるイメージです。
内枠方式は外枠方式と異なり、契約時にまとまった費用を支払う必要がなく、毎回の保証料の支払いは少額で済みます。ただし、保証料の支払いは住宅ローン完済まで続くため、支払総額だと内枠方式のほうが高くなるでしょう。さらに、内枠方式で支払う保証料は、繰り上げ返済をしても返済されないのが外枠方式との違いです。
住宅ローンの保証料は、契約内容や具体的な住宅ローンの審査結果によって異なります。本章で紹介した金額はあくまで目安と考えてください。外枠方式と内枠方式どちらがあっているかは、それぞれの特性をよく理解し、毎月の返済額の許容範囲と家計の状況によって適切に選択しましょう。
住宅ローンの保証金が返金されるのはどのような時?

住宅ローンの保証金の内容について見てきましたが、住宅ローンの保証金が返金される時はどのような時でしょうか。住宅ローンの保証金が返金されるケースは以下の2つです。
- 1. 外枠方式を選択していて繰り上げ返済をする場合
- 2. 住宅ローンの借り換えをする場合
ではそれぞれの内容を解説していきます。
外枠方式を選択していて繰り上げ返済をする場合
保証料の支払い方法には、先述のとおり一括で保証料を支払う外枠方式と、保証料を按分(あんぶん)して毎月の住宅ローン返済と一緒に支払う内枠方式があります。
保証料が返金されるのは、住宅ローンの契約当初に保証料を一括払いする外枠方式を選択していて、途中で全額繰り上げ返済をおこなった場合です。この場合、未経過分の保証料が返金されます。
借り換えをおこなった場合
住宅ローンの借り入れ当初に外枠方式で保証料の支払いをし、その後借り換えをおこなった場合も、保証料が返金されます。他の金融機関に借り換え、元の金融機関からの借り入れがなくなれば保証の必要もなくなるためです。
保証料はいつ、いくら返ってくる?

住宅ローン保証金の返金はいつ頃受けることができるのでしょうか?また、いくら返金されるのでしょうか。住宅ローンの保証金が返金されるタイミングは、金融機関によって異なります。本章では、大手銀行と地方銀行に分けて解説します。
大手銀行
大手銀行の場合は、手続き後1カ月以内で返金される目安です。このペースは比較的早いほうといえます。大手銀行は、手数料や金利などが比較的高い可能性もありますが、その分対応が早い場合もあるため、利用の選択肢になるかもしれません。
地方銀行
地方銀行の場合は、繰り上げ返済や借り換えが完了した日の翌々月で返金される目安です。大手銀行に比べると、時間がかかるケースが多いようです。そのため、利用する場合は、事前にスケジュールを確認しておきましょう。
保証料はいくら返金される?
返済されるまでの期間について見てきましたが、実際にどのくらい保証料が返金されるか気になるかと思います。結論からいうと、各金融機関によって規定が異なるため、正確な金額については利用している金融機関の規定を確認するか、直接問い合わせをしましょう。
保証料の返金で用いられる計算は、単純に按分して出すものではありません。例えば、外枠方式で返済期間が35年の住宅ローンを組み、保証料が35万円だったとします。25年目に繰り上げ返済をすると、住宅ローンの残りは10年間です。35年で35万円の保証料なら、繰り上げた10年分の10万円が返金されるのではないかと予想されます。
しかし、保証会社に支払う事務手数料が5,000円~2万円程度必要だったり、振込手数料も借り主負担になるなど、返金金額は10万円以下になる可能性があります。
住宅ローンの完済までに数年だった場合など、返金金額が少なければ事務手数料を差し引くことによって返金が0円にもなりかねません。詳しい計算方法やどのくらい返金があるのかを金融機関に確認することが大切です。
この記事のQ&A
Q:住宅ローンの保証料とは?
A:住宅ローンの保証料とは、借主が金融機関が提携している保証会社に対して支払う費用です。これまで、ローンなどの融資を利用するには、連帯保証人を立てるケースが多くみられました。ただ、連帯保証人をたてるのが難しいケースなどを考慮して近年では、連帯保証人のかわりに保証会社を利用する金融機関が多くみられます。
Q:保証料の支払い方法は?
A:保証料の支払い方法には、外枠方式と内枠方式があります。外枠方式とは、保証料を住宅ローン契約時に一括で支払う方法です。保証料は全額前払いになるので、住宅ローンの返済期間中に追加の保証料を支払うことはありません。保証料の相場は、住宅ローンの借入金額の2.2%位が一般的です。
内枠方式とは、保証料を分割し毎月の住宅ローンの返済に上乗せして支払っていく方法です。保証料の相場は、金利に0.2%程度上乗せして計算されるのが一般的です。内枠方式は外枠方式と異なり、契約時にまとまった費用を支払う必要がなく、毎回の保証料の支払いは少額で済みます。
ただし、保証料の支払いは住宅ローン完済まで続くため、支払総額だと内枠方式のほうが高くなります。さらに、内枠方式で支払う保証料は、繰り上げ返済をしても返金はないなど、違いをよく理解しておきましょう。
Q:住宅ローンの保証金が返金されるのはどのような時?
A:住宅ローンの保証金が返金されるケースは、外枠方式を選択していて、繰り上げ返済をする場合と住宅ローンの借り換えをする場合です。
Q:保証料はいつ、いくら返ってくる?
A:住宅ローンの保証金が返金されるタイミングは、金融機関により異なります。大手銀行の場合は、手続き後1カ月以内で返金、地方銀行の場合は、繰り上げ返済や借り換えが完了した日の翌々月を目安に返金される傾向です。利用する金融機関の特性を理解し、利用する場合は事前にスケジュールを確認しておきましょう。
なお、保証料はいくら返金されるのかも、各金融機関によって異なるため、正確なことは利用している金融機関の規定を確認するか、直接問い合わせをしましょう。保証料の返金には各種手数料がかかるため、思ったよりも少ない場合があります。保証料の返金で用いられる計算は、単純に按分して出すものではありません。単純計算で考えている分より減るものと考えておきましょう。
まとめ
本記事では、住宅ローンの保証料とは何か、保証料を決める要素にはどのようなものがあるのかを解説しました。また、保証料の計算方法と返金されるケース、タイミングを解説しました。保証料に関する知識を先に持っておけば、さまざまな状況に柔軟に対応できます。住宅ローン関連の知識を幅広く持って、スムーズな住宅購入に役立ててください。
物件を探す

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







